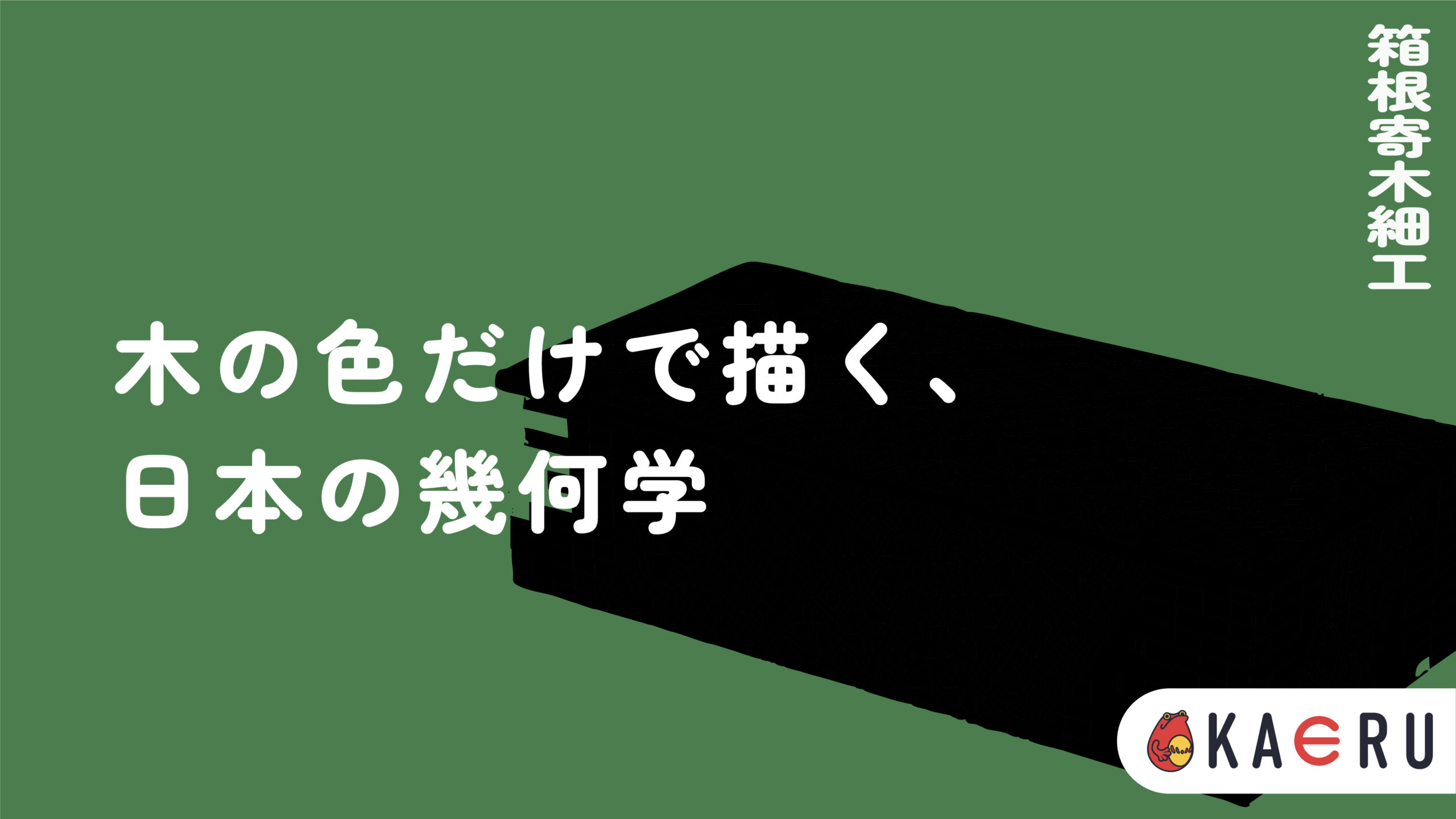箱根寄木細工とは?
箱根寄木細工(はこね よせぎざいく)は、神奈川県の箱根町および小田原市でつくられる伝統的工芸品で、木材の自然な色合いと木目を活かした幾何学模様が特徴の木工品です。50種類以上にもおよぶ国産・外国産の広葉樹を、染色せずにそのまま組み合わせて模様を描くため、一つひとつが異なる表情を持ち、温かみと精緻さを併せ持つ仕上がりになります。
技法には、薄く削った装飾板を貼る「ズク貼り」と、装飾材そのものを成形して仕上げる「ムクづくり」があり、小箱や茶托、盆、秘密箱など幅広い製品が作られています。日用品から贈答品、工芸アート作品まで、多様なニーズに応える表現の幅広さも魅力のひとつです。
| 品目名 | 箱根寄木細工(はこねよせぎざいく) |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 1984(昭和59)年5月31日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 6(17)名 |
| その他の神奈川県の伝統的工芸品 | 鎌倉彫、小田原漆器(全3品目) |

箱根寄木細工の産地
山の恵みと文化が交差する箱根・小田原

主要製造地域
箱根寄木細工の主な産地である箱根町畑宿は、箱根山系の豊富な樹種に恵まれた地域で、古くから木工文化が根付いていました。戦国時代には挽物細工(ろくろを使って椀などを作る技術)が盛んで、江戸時代には東海道の整備によって湯治や観光の客でにぎわいを見せるようになります。
また、小田原も木工と漆工の町として発展しており、これらの文化圏が交差することで、木地づくり・指物・寄木といった技法が融合・発展する素地となりました。現在も多くの工房が点在し、技術の伝承と革新が日々行われています。
箱根寄木細工の歴史
木工の伝統に寄木の技法が加わり進化
箱根寄木細工のルーツは、江戸時代の箱根・小田原地域に根づいた木工文化にあります。箱根山系に広がる豊かな森林資源と、東海道の宿場町として栄えた交通の要衝という地の利が、職人たちの技術と創意を育んできました。幾何学模様の美を木の自然な色味だけで描き出す技法は、江戸時代に生まれ、明治以降に大きく発展していきます。
- 16世紀(戦国時代):箱根町畑宿では挽物(ひきもの)細工が盛んに行われ、椀や盆といった木工品がつくられていました。
- 18世紀〜19世紀初頭(江戸時代中期〜後期):東海道の整備により、箱根は湯治客や旅人で賑わいを見せ、宿場町のお土産品として木工品の需要が増加。箱根細工の名が徐々に広まります。
- 19世紀初頭(江戸後期):畑宿の石川仁兵衛が、静岡で学んだ寄木技術を応用して、独自の寄木細工を創出。これが「箱根寄木細工」の始まりとされます。
- 19世紀後半(明治時代):1873年のウィーン万国博覧会をはじめとする国際博覧会で注目を集め、「秘密箱(ひみつばこ)」などの高度な加工技術とデザイン性が国内外で高い評価を受けました。
- 20世紀(昭和〜平成時代):観光地としての箱根とともに発展し、贈答品や民芸品としての需要が高まります。技術の継承とともに新たな意匠も模索されました。
- 1984年(昭和59年):箱根寄木細工が経済産業省により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:伝統文様を継承しつつも、現代的なデザインやプロダクトとの融合が進み、インテリアやアクセサリーなど用途の幅も広がっています。
箱根寄木細工の特徴
自然のままの色彩が描く幾何学の美
箱根寄木細工の最大の魅力は、木そのものの色味を活かして作られる幾何学模様です。赤、黄、茶、白、黒など、木材本来の色を用いて複雑な文様を構成し、化学的な染色や着色を一切行わない点が他に類を見ない特色です。
文様には、「亀甲」「麻の葉」「鱗」「市松」など、古くから縁起の良いとされる和柄が多く用いられます。これらは単なる装飾ではなく、日本の美意識や思想を背景に持つ意匠であり、寄木細工の中に伝統文化が宿っています。
また、「ズク貼り」では紙のように薄く削った模様板(ズク)を製品に貼り、「ムクづくり」では模様そのものを活かした立体的な造形が可能です。さらに、秘密箱などの仕掛けを施した遊び心のある作品も多く、工芸品でありながら機能美と娯楽性を兼ね備えています。

箱根寄木細工の材料と道具
50種以上の木が織りなす自然の色
箱根寄木細工の美しさは、素材そのものの色や木目を最大限に活かして生まれる文様の妙にあります。そのため、素材選びは製作工程の要であり、50種以上におよぶ国産・外国産の広葉樹の中から、色味・硬さ・木目の方向・乾燥状態などを総合的に見極めて使用されます。また、数ミリ単位での調整を要する工程には、専用の道具や治具も欠かせません。自然と技術の両面に配慮した緻密なものづくりが、箱根寄木細工のクオリティを支えているのです。
箱根寄木細工の主な材料類
- カツラ(黄白):柔らかく加工しやすい。基礎構造材にも使用される。
- ニガキ(黄):鮮やかな黄色が特徴。アクセントとして使われる。
- ホオノキ(淡緑):落ち着いた緑みを帯びた色で、柔らかく安定した素材。
- クスノキ(茶):香りがあり、やや硬め。深みのある茶色が特徴。
- ケヤキ(黄褐):美しい木目と堅牢性を兼ね備える。
- エンジュ(赤褐):やや赤みを帯びた濃い茶色で、文様の締め色に使われる。
- パドック(朱赤):アフリカ原産の木材で、華やかな朱色を持つ。
- 神代カツラ(墨黒):長期間地中に埋まっていた木材で、自然な黒みを帯びた希少材。
箱根寄木細工の主な道具類
- 大型かんな:寄木ブロックを平らに削るための手動道具。均一な厚みに整えるのに用いられる。
- 定規・直角定規・分度器:正確な角度と直線を保つために不可欠。幾何学模様の組み立てに使用。
- 糸鋸:種木やブロックを細かく切り出すための鋸。曲線や複雑なパーツの切断にも対応。
- アイロン・プレス機:ズク貼りの際に、薄く削った模様板(ズク)を製品に圧着するために使用。
- 接着道具(はけ・ローラー):接合面に均一に接着剤を塗布するための道具。はみ出し防止にも配慮。
- 研磨用具(サンドペーパー・布・バフ):仕上げ工程で使用。表面の平滑化や光沢の調整に欠かせない。
- 型・治具:文様の再現性や部品の精度を保つための補助器具。世代を超えて受け継がれるものもある。
これらの素材と道具があってこそ、自然素材だけで構成された精緻な幾何学模様が生まれます。木の持つ美しさを損なうことなく、細部まで統一された美意識で仕上げられる箱根寄木細工は、職人の手技と素材の力が融合した「木の芸術」と呼ぶにふさわしい工芸品です。
箱根寄木細工の製作工程
精密な組み木から削り出しへ
箱根寄木細工は、木材選びから模様づくり、仕上げまで緻密な工程を経て完成します。自然の色と木目を活かし、精密に組み上げられた模様が、唯一無二の木の芸術を形づくります。
- 木材の選定・接着:模様に必要な色や木目を考慮して材を選び、接着して模様の単位となる「種木」を作る。
- 種木の切断・成形:種木を一定の形に切り出し、複数の単位模様を組み合わせて「寄木ブロック」を構成。
- 種板づくり:寄木ブロックを一定の厚みとサイズに加工し、連続模様となる「種板」に仕上げる。
- ズク貼り(またはムクづくり):
- ズク貼り:種板を薄く削った「ズク」を作り、アイロンなどで平らにして製品に貼り付ける。
- ムクづくり:種板そのものを削らず成形して仕上げる。
- 仕上げ:製品表面を磨き、必要に応じてコーティング処理を施し、美しさと耐久性を両立させる。
各工程は職人が木の性質を見極めながら進めていくため、手間と時間がかかるものの、その分だけ完成品には深い味わいと精度が宿ります。
箱根寄木細工は、木の生命力と職人の構成力が融合した、まさに「木のモザイク」ともいえる存在です。幾何学的でありながらも温かみを感じさせるこの工芸品は、日本の自然と知恵が織りなす芸術といえるでしょう。