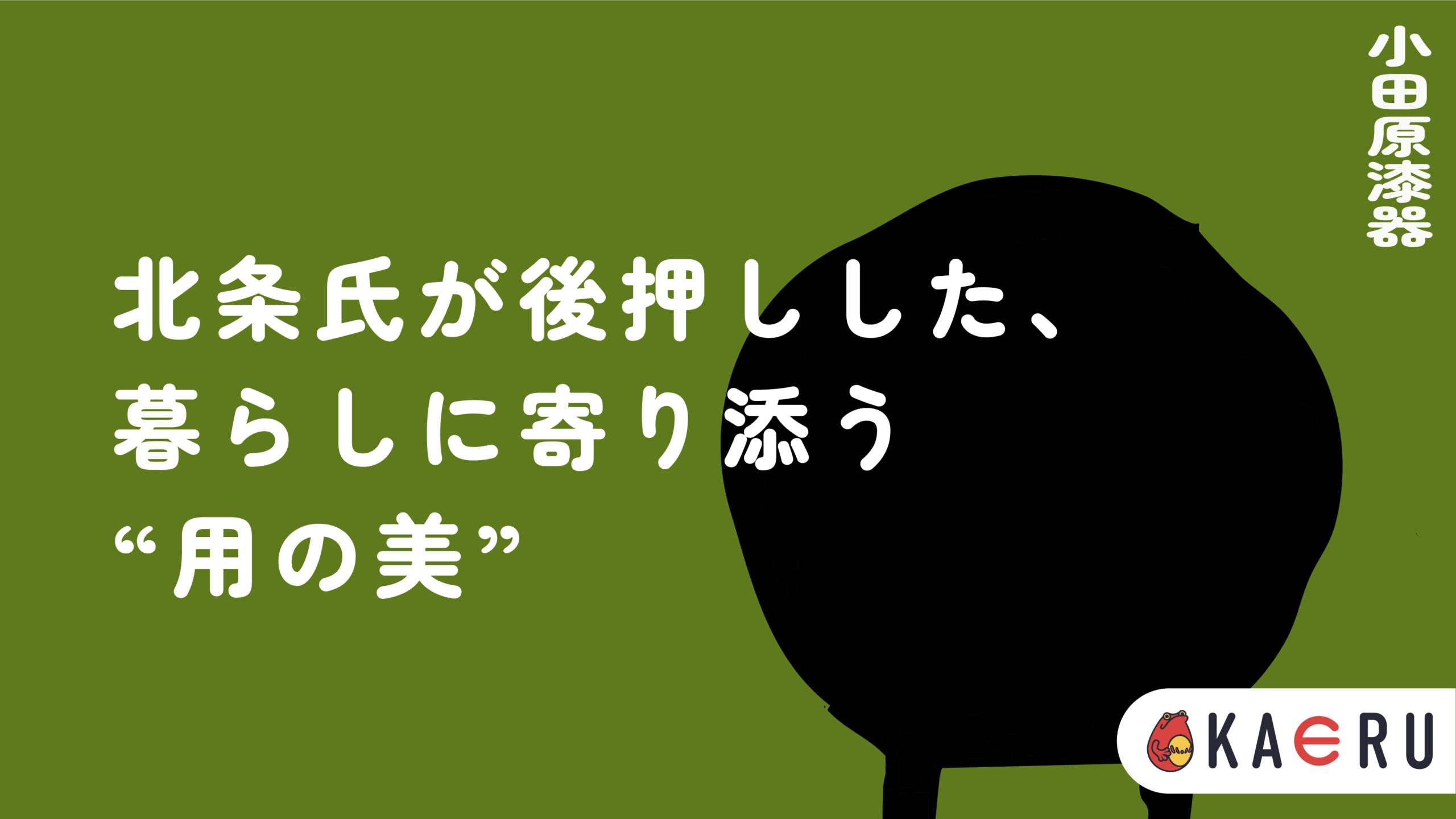小田原漆器とは?
小田原漆器(おだわらしっき)は、神奈川県小田原市を中心に生産される伝統的工芸品です。室町時代中期、豊かな自然資源を背景に箱根山系の木材を用いた木地作りと、漆を塗る技術が結びつき誕生しました。最大の特徴は、木目を活かす透明感ある漆仕上げと、堅牢で歪みの少ない木地加工にあります。日用品としての実用性を持ちながらも、自然美と手仕事の精緻さが同居する小田原漆器は、「使って美しい」漆器として長年親しまれてきました。
| 品目名 | 小田原漆器(おだわらしっき) |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1984(昭和59)年5月31日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(13)名 |
| その他の神奈川県の伝統的工芸品 | 鎌倉彫、箱根寄木細工(全3品目) |

小田原漆器の産地
箱根山系の恵みを受け継ぐ城下町・小田原

主要製造地域
小田原は、戦国時代に後北条氏(関東一円を支配した戦国大名・北条早雲を祖とする一族を指す呼称)の本拠地として栄えた歴史ある城下町です。相模湾に面し、箱根山系の森林に恵まれたこの地は、木工や漆工に適した環境を有していました。特にケヤキをはじめとする硬質な広葉樹が豊富に産出され、ろくろ技術による木地加工が発展しました。箱根細工と並び、木工文化の拠点としての小田原の風土が、小田原漆器の品質を支えています。
小田原漆器の歴史
室町から江戸、そして現代へ受け継がれる技
小田原漆器は、戦国時代から江戸、明治を経て現代にいたるまで、城下町・小田原の武家文化とともに歩んできた漆器です。堅牢で美しい木地づくりと、木目を活かす透漆の塗りの技術は、時代とともに改良され、日用品としての実用性と風格を併せ持つ漆器として進化を続けてきました。
- 15世紀中頃(室町時代中期):箱根山系の良質な木材を利用した木地加工と漆塗りが始まる。小田原地域での漆器生産の起源とされる。
- 16世紀(戦国〜安土桃山時代):後北条氏が小田原城を拠点とし、漆工を保護。塗師を招聘し、調度品や武具の制作を通じて技術が発展。
- 17〜19世紀(江戸時代):東海道の宿場町として栄え、庶民の間でも椀や膳などの実用漆器が普及。江戸への物流の拠点としても需要が増加。
- 19世紀後半〜20世紀初頭(明治〜大正時代):職人組合が結成され、品質向上と販路拡大に取り組む。小田原・箱根の観光発展と連動し、土産物としても定着。
- 1950年代〜(昭和戦後):戦後の民芸運動や郷土工芸品ブームにより、伝統産業として再評価される。
- 1984年(昭和59年):小田原漆器が経済産業省により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:家具や現代インテリアへの展開が進み、木目を活かすモダンな器やデザイン製品が人気。若手職人の参入やデジタル販路の活用も見られる。
小田原漆器の特徴
木の風合いを活かす、洗練された日常の器
小田原漆器は、華美な装飾を控えつつも、素材と技術の美しさが際立つ工芸品です。なかでも透き漆と呼ばれる技法が代表的で、木目の美しさをそのまま見せる塗りが特徴です。漆が木にしっかりと染み込み、時間とともに艶を増していくその様は、自然と人の技が交わる静かな調和を感じさせます。
また、使用されるケヤキ材は堅牢で狂いが少なく、椀や盆といった日常使いに適しています。軽量かつ扱いやすいため、現代のライフスタイルにもなじみやすく、長年にわたり使い込むほどに味わいを深めてくれる点も魅力のひとつです。素朴ながらも品格を感じさせる佇まいは、まさに「用の美」を体現しています。

小田原漆器の材料と道具
木目の美と堅牢さを引き出す素材と道具
小田原漆器の魅力は、木目を透かす漆の美しさと、長く使い続けられる堅牢な作りにあります。その背景には、厳選された木材と漆、そして伝統的な技法に最適化された道具の存在があります。職人たちは、素材の性質を見極めながら、用途や意匠に応じて最良の組み合わせを用い、ひとつひとつの器を丁寧に仕上げていきます。
小田原漆器の主な材料類
- 木材:主にケヤキを使用。堅牢で木目が美しく、漆との相性も良い。他にトチ、サクラ、ホオノキなども用途に応じて用いられる。
- 漆:透漆(すきうるし)や朱漆を用い、木目を活かしながら塗膜を形成。経年で艶を増す性質がある。
- 下地材:必要に応じて和紙や布を素地に貼り、下地を補強。天然糊や炭粉なども用いられる。
小田原漆器の主な道具類
- ろくろ(電動・手動):椀や盆などを成形するための基本工具。木地の回転加工に使用。
- 彫刻刀・のみ:細部の成形や彫り装飾を施すための手工具。
- 刷毛(はけ)・へら:漆を均一に塗るための道具。塗りの厚みや仕上がりを左右する。
- 砥石・炭粉:中塗りや上塗り後の研磨作業で用い、漆面に滑らかな艶を出す。
- 布・和紙:下地処理や乾拭き仕上げに用いられ、素材ごとの吸湿性や風合いも活かされる。
これらの材料と道具は、木と漆という自然素材が本来持つ魅力を最大限に引き出し、使い手の暮らしに寄り添う器へと昇華させるために欠かせない存在です。職人の繊細な手仕事と相まって、小田原漆器の「用の美」はいまもなお健やかに息づいています。
小田原漆器の製作工程
木地と漆が響き合う伝統の手仕事
小田原漆器の製作は、厳選した木材を成形する木地作りから始まり、漆を塗っては研ぐ工程を幾度も重ねて仕上げます。木目を活かす透漆の艶やかな表情は、この丁寧な手仕事の積み重ねによって生まれます。
- 木地作り:乾燥させた木材をろくろや手工具で成形。
- 下地処理:素地の凹凸を整え、漆の吸い込みを均一にする。
- 漆塗り(中塗・上塗):透漆を数回に分けて塗布し、都度乾燥と研磨。
- 磨き:仕上げに炭粉や砥石を用いて磨き上げ、艶を出す。
製品によっては彫りや装飾を加えることもあり、用途や意匠に応じて工程が柔軟に変化します。
小田原漆器は、実用性と芸術性を兼ね備えた、暮らしの中の工芸です。木の力強さと職人の技が融合した器には、使うたびに深まる魅力があります。