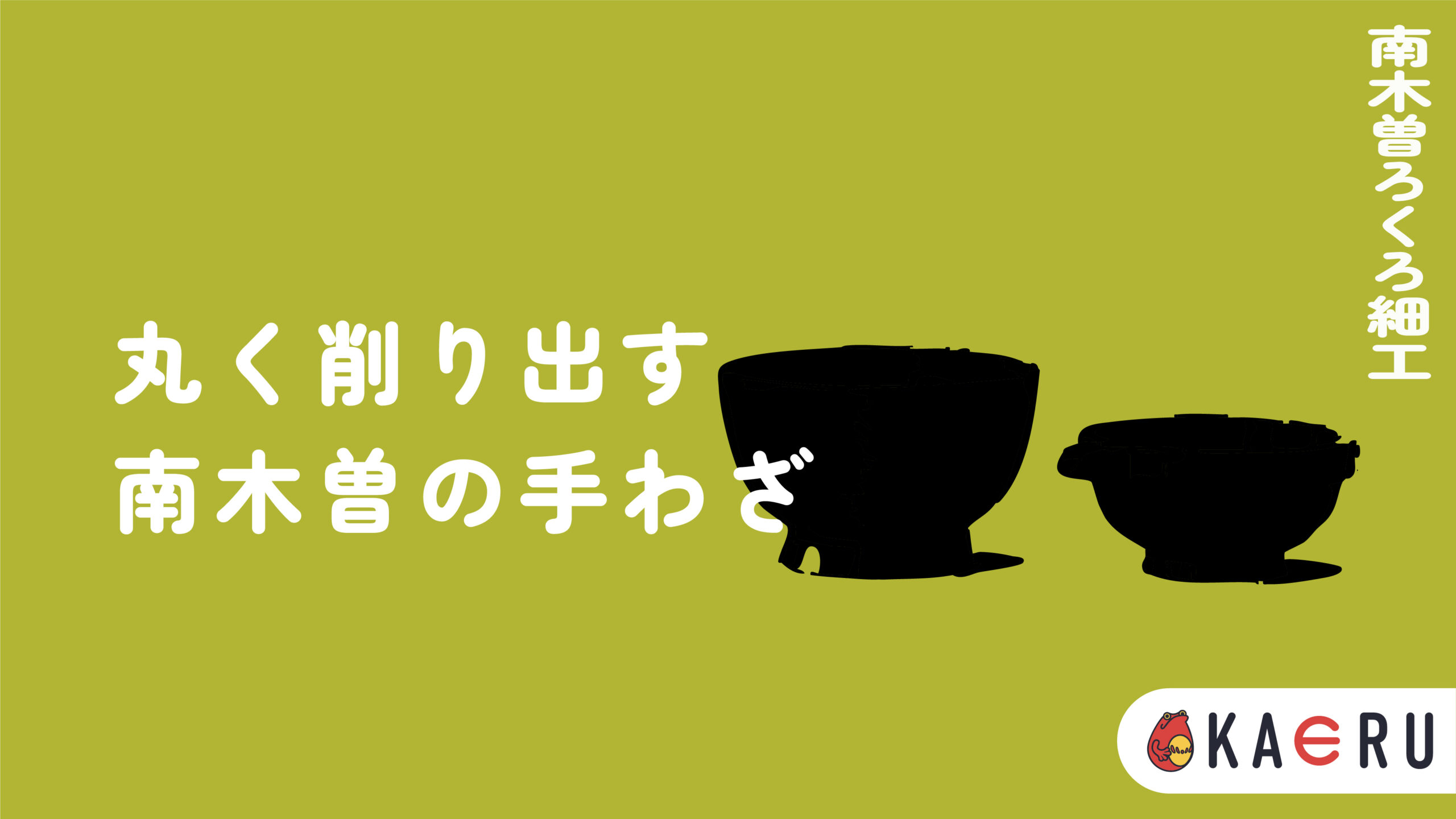南木曽ろくろ細工とは?
南木曽ろくろ細工(なぎそろくろざいく)は、長野県南木曽町を主産地とする木工品で、木地をろくろで回しながら刃物で削る挽物(ひきもの)技術によって作られます。主に茶びつやお盆、菓子鉢、椀など、日常の生活道具として長く親しまれてきました。
木材にはトチ、セン、ケヤキ、クリなどが使われ、それぞれの木目や質感に応じて最適な仕上げが施されます。漆を使った仕上げが多く、実用性と美しさを兼ね備えた製品として高く評価されています。
| 品目名 | 南木曽ろくろ細工(なぎそろくろざいく) |
| 都道府県 | 長野県 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 1980(昭和55)年3月3日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(18)名 |
| その他の長野県の伝統的工芸品 | 信州紬、飯山仏壇、内山紙、木曽漆器、松本家具、信州打刃物(全7品目) |

南木曽ろくろ細工の産地
木曽谷の恵みを活かす、南木曽町のろくろ文化

主要製造地域
南木曽ろくろ細工の産地は、木曽谷の最南端に位置する長野県南木曽町。ヒノキや広葉樹に恵まれた森林地帯で、古くから木工が盛んな地域です。近隣には木曽漆器や木曽ヒノキ細工といった木の工芸文化が根付き、木材加工に対する深い知見と経験が蓄積されています。
ここでは、職人自ら山に入り、木の選定から乾燥、加工、販売まで一貫して行うスタイルが根付いています。製品はかつて木曽路を通る旅人にも愛され、名古屋や大阪方面にも盛んに出荷されました。
南木曽ろくろ細工の歴史
暮らしの道具から、木の美を伝える工芸品へ
南木曽ろくろ細工では、長野県周辺で採れる広葉樹を中心に、木の性質に応じて適切な加工が施されてきました。木目や色味を活かすため、乾燥や仕上げにも高度な技術が求められ、これらの知見は長い歴史の中で培われてきました。
- 18世紀前半(江戸時代中期): 木曽谷の豊かな森林資源を背景に、南木曽周辺で挽物技術が発展。
- 1801〜1804年(享和年間):村々で木地師が増え、碗や皿の生産が活発化。
- 1818〜1830年(文政年間):ろくろ細工が木曽路を通じて旅人に普及し、実用品として広く定着。
- 1844〜1848年(弘化年間): 地元産のトチやセンの使用が増え、木の美しさを活かす工夫が深化。
- 幕末〜明治時代:茶びつや菓子器が旅人の土産として評判を得て、名古屋・大阪方面への出荷が拡大。
- 明治時代中期:電動ろくろの前身となる簡易機械が導入され、生産効率が向上。
- 昭和初期:電動ろくろの導入が進み、より複雑な形状への対応が可能に。
- 1980年(昭和55年):南木曽ろくろ細工が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:木の温もりとろくろ加工の美しさが再評価され、現代のライフスタイルに合う商品開発が進む。
南木曽ろくろ細工の特徴
回転が削り出す、暮らしに根ざした曲線美
南木曽ろくろ細工の最大の魅力は、木の質感を活かしながら滑らかに仕上げる挽物の美しさにあります。トチやセンなどの広葉樹は、柔らかく緻密な木質で、ろくろ加工に適しています。職人は木材ごとの癖を読み取りながら、刃物一本で美しい曲線を削り出していきます。
また、丁寧に塗り重ねられた漆は、木の呼吸を妨げず、使い込むほどに艶を深めていきます。器としての機能性はもちろん、経年変化によって味わいを増す点も、南木曽ろくろ細工が愛される理由のひとつです。

南木曽ろくろ細工の材料と道具
木の声を聴き、形にするための素材と手道具
南木曽ろくろ細工では、長野県周辺で採れる広葉樹を中心に、木の性質に応じて適切な加工が施されます。木目や色味を活かすため、乾燥や仕上げにも高度な技術が求められます。
南木曽ろくろ細工の主な材料類
- トチノキ: 木目が美しく、適度な硬さがあり、ろくろ加工に適する。
- セン: 軽く柔らかい。白く滑らかな仕上がりが特徴。
- ケヤキ: 木目が鮮やかで耐久性に優れる。
- クリ: 水分に強く、器物に適する。
- 漆: 防腐・防水性を高め、使うほどに艶を増す。
南木曽ろくろ細工の主な道具類
- 電動ろくろ: 木材を回転させながら削る主力機材。
- 木工用刃物: 丸刃・平刃などの各種ノミやカンナ。
- 乾燥棚: 長期間かけて自然乾燥させるための設備。
- 漆刷毛: 仕上げに漆を塗るための道具。
これらの素材と道具は、木と向き合うために洗練されてきたものであり、暮らしの中で育まれたものづくりの文化そのものといえるでしょう。
南木曽ろくろ細工の製作工程
木を選び、挽き、仕上げるまでの丁寧な手しごと
南木曽ろくろ細工の製作は、木の選定から始まり、乾燥、粗挽き、成形、漆仕上げまで、すべての工程が職人の手で丁寧に行われます。木の個性を生かしながら回転と刃物で削り出すことで、暮らしに寄り添う滑らかな曲線美が生まれます。
- 木材選定・伐採
熟練の職人が山に入り、適した木を選んで伐採。 - 乾燥
木材を数ヶ月〜数年かけて自然乾燥させ、割れや歪みを防ぐ。 - 粗取り(荒挽き)
大まかな形に削る工程。ろくろや旋盤を使って基本形をつくる。 - 成形(仕上げ挽き)
刃物を用いて精緻な曲線を整え、最終的な形状に仕上げる。 - 研磨
紙やすりなどで表面を滑らかに仕上げる。 - 漆塗り
器に漆を丁寧に塗り重ね、乾燥と研磨を繰り返して仕上げる。 - 検品・仕上げ
製品の品質を確認し、最終仕上げを施して完成。
南木曽ろくろ細工は、木の個性を見極めながら、人の手と技によって一つひとつ形づくられていきます。木曽の自然と共に歩んできた職人の感性と経験が宿る、まさに「暮らしの中の芸術品」です。