高岡銅器とは?
高岡銅器(たかおかどうき)は、富山県高岡市で生産される金属工芸品で、主に銅合金を用いた鋳物によって作られます。江戸時代初期から続く伝統を有し、仏具、花器、茶道具から大仏像まで、大小さまざまな作品が生み出されてきました。
高岡銅器の真髄は、「鋳造・彫金・着色」という三位一体の技にあります。銅という素材の美しさを引き出すため、職人たちは土や蝋、和紙、植物など多彩な素材と技法を駆使し、金属とは思えない繊細さと深みを与えます。現在では、全国の銅器生産量の9割以上を高岡銅器が占め、国内外の寺社仏閣や美術館でも高く評価されています。
| 品目名 | 高岡銅器(たかおかどうき) |
| 都道府県 | 富山県 |
| 分類 | 金工品 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 33(81)名 |
| その他の富山県の伝統的工芸品 | 高岡漆器、越中和紙、井波彫刻、庄川挽物木地、越中福岡の菅笠(全6品目) |


高岡銅器の産地
鋳物と共に歩む城下町、高岡の地理と文化が育んだ銅器の都
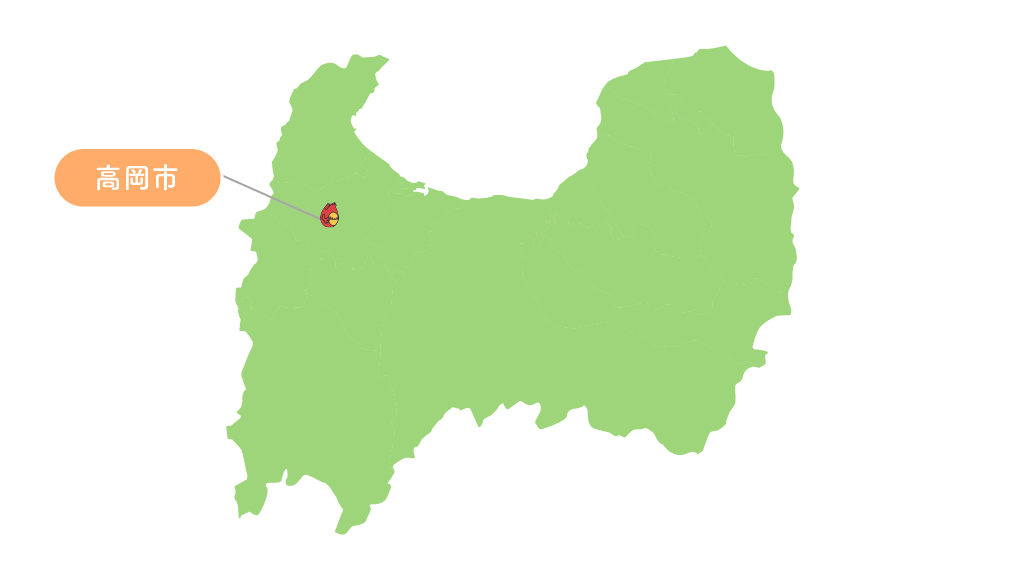
主要製造地域
高岡銅器の産地は、富山県西部に位置する高岡市です。1609年に加賀藩二代藩主・前田利長が築いた城下町として開かれ、以来400年以上にわたり鋳物と共に発展してきました。
藩政期、武器や農具の内製化を進める中で、鋳物師たちは高岡へ移住させられ、産業としての鋳物業が根付きました。江戸中期以降、仏具や花器といった美術鋳物の需要が高まり、精巧な技術が蓄積されていきます。
また、金沢文化の影響を受けた高岡では、茶の湯や仏教文化、美術工芸が庶民層にも浸透し、鋳物も単なる道具から芸術性の高い品へと変貌。町人文化が成熟し、彫金や着色など、装飾性の高い技法が発展していきました。
さらに、高岡周辺は湿潤で粘土層が豊富な地質を有し、生型や焼型に必要な粘土や鋳物砂の入手が容易でした。また、北陸の冬は作業が屋内で進むため、分業制での鋳物制作に適していたとも言われます。加えて、伏木港から銅や錫などの原料が運ばれ、鋳造産業の集積が進みました。
こうした歴史・文化・自然条件が重なり合い、高岡は現在に至るまで「日本の銅器の都」としての地位を築いてきたのです。
高岡銅器の歴史
藩政の鋳物振興から万博受賞まで、進化し続ける銅の芸術
高岡銅器の歴史は、加賀藩の殖産興業政策と共に始まり、やがて日本を代表する美術鋳物へと発展しました。
- 1609年:加賀藩主・前田利長、高岡城を築城。西部金屋村より鋳物師7人を招き、鉄製の鍋や釜の生産を開始。
- 1611年:金屋町に鋳物工場が形成され、鋳物産業が高岡に根付く。
- 1700年代中頃:「唐金(からかね)鋳物」が誕生。仏具や花器の表面に彫金を施す技法が登場。
- 1780年代:蝋型鋳造が広まり、細密で複雑な造形が可能となる。
- 1835年:高岡で日本初の銅製仏像の鋳造に成功。大型鋳物への技術転換が進む。
- 1873年:ウィーン万国博覧会で高岡銅器が受賞。国際的な注目を集める。
- 1878年:パリ万博に出品。彫金技術と着色技法が高く評価される。
- 1910年代:機械化が進み、大量生産と並行して美術鋳物の分業体制が確立。
- 1975年(昭和50年):高岡銅器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:現代アートやホテル装飾、企業モニュメントなど新分野へ展開。海外展開も加速。
高岡銅器の特徴
彫る・流す・染める、金属に宿る表情の多様性
高岡銅器の魅力は、その多様な鋳造技術と、金属でありながらも有機的な“表情”を持つ仕上がりにあります。蝋型鋳造では、彫刻家が蝋で細かい原型を作り、そのまま焼いて型を取るため、毛並みや衣のひだといった繊細な造形がそのまま金属に置き換わります。一方、生型鋳造では、日用品や文鎮など小型で繰り返し製造されるものに向き、耐久性のある形を効率的に作れます。
また着色では、「おはぐろでつやを消す」「草で煎じたカリヤス液で下色を入れる」など、驚くほど自然素材が活用されています。これにより、同じ銅でも黒褐色、緑青、金色、赤銅色など多彩な色味が生まれ、時と共に変化する“育つ器”としての美も楽しめます。
高岡銅器の材料と道具
銅の声を聴き、火と土を操る熟練の眼と手
高岡銅器の製作には、金属と自然素材の融合が欠かせません。鋳型づくりから着色まで、すべてが素材選びと道具の使い方に支えられています。
高岡銅器の主な材料類
- 銅合金(青銅・真鍮など):加工性と耐久性に優れる高岡銅器の主原料。
- 鋳物砂・粘土・和紙:鋳型の素材として使用。
- 蜜蝋・木蝋・松脂:蝋型鋳造に用いる自然由来の材料。
- 天然着色剤(カリヤス・おはぐろ・うるし等):金属表面の発色に使用。
高岡銅器の主な道具類
- 彫金タガネ:細部を彫るための精密道具。
- 鋳型枠・双型機械:鋳造のための型成形機器。
- 火炉・るつぼ:銅合金を溶解するための炉具。
- 色焼き炉:着色後の安定処理に使用。
自然の素材と伝統道具を自在に操ることが、高岡銅器の美しさを支える原点です。
高岡銅器の製作工程
銅に命を吹き込む、技の連なり
高岡銅器の製作には、数十にも及ぶ工程が存在します。そのすべてに専門の職人が関わり、分業体制のもとで一品一品が完成します。
- 原型づくり(造形)
木や粘土、蝋を使って原型を作成。立体構成力が求められる。 - 鋳型製作
生型・双型・焼型・蝋型など、用途や形状に応じて鋳型を選び、形成。 - 鋳造
るつぼで1,100度以上に熱した銅合金を鋳型へ流し、冷却・脱型。 - 仕上げ(研磨・彫金)
鋳肌を整え、彫金で装飾や陰影を加える。 - 着色
天然成分で下地・中塗・つや出しを行い、深みある色彩に仕上げる。 - 完成・検品
全体の均整・重量・色調などを職人が目視で最終確認。
完成した銅器は、金属でありながら温もりをたたえた造形美を放ちます。
高岡銅器は、火と金属、自然素材、職人の手仕事が織りなす400年の技の結晶です。仏具や花器はもちろん、現代アートや建築装飾にも広がり続けるその表現力は、用と美の理想を体現する日本の誇る伝統工芸です。










