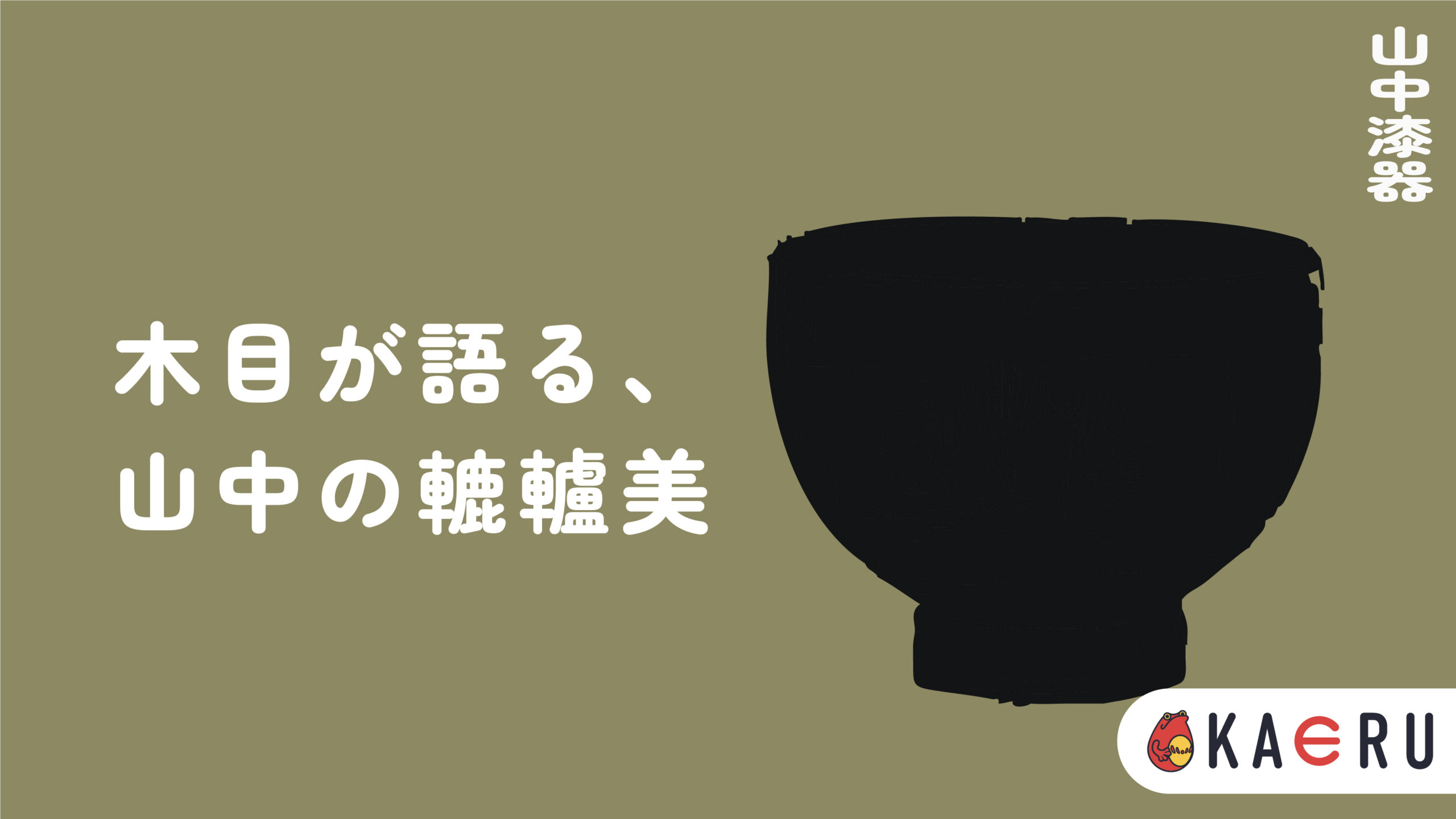山中漆器とは?

山中漆器(やまなかしっき)は、石川県加賀市山中温泉地区で作られる伝統的な挽物漆器です。16世紀後半に移住した木地師集団によって始まり、轆轤(ろくろ)を駆使した木地加工と、精緻な塗り・蒔絵技術により発展してきました。
木の育った向きに沿って木を割り出す「縦木取り」や、木地に細かな筋を彫って装飾する「加飾挽き」といった高度な技法が特徴で、椀・盆・茶道具などの日用品から芸術性の高い作品まで多彩な品が生まれています。近年では、異素材との融合やモダンデザインにも挑戦し、伝統と革新が共存する漆器文化として国内外で注目されています。
| 品目名 | 山中漆器(やまなかしっき) |
| 都道府県 | 石川県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 31(91)名 |
| その他の石川県の伝統的工芸品 | 牛首紬、加賀友禅、加賀繍、九谷焼、輪島塗、七尾仏壇、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔(全10品目) |

山中漆器の産地
温泉と山林が育んだ、木地の里
山中漆器の主産地である加賀市山中温泉は、白山山系の清らかな水と広大な森林に囲まれた地です。歴史的には、滋賀県から福井県を経て移住した木地師たちが、この地に豊富なケヤキやトチの材を求めて定住し、挽物技術を基盤に漆器作りを始めました。
文化的背景としては、加賀藩の庇護と、金沢を中心に栄えた加賀文化の影響が色濃く反映されています。茶道や香道といった伝統文化が生活に根付き、漆器の需要と美的洗練を高めました。特に山中は温泉地としても知られ、江戸期には湯治客に向けた土産物の需要から、椀や盆などの日用品の製作が発展。商業と観光が融合する土地柄が、職人の創意と技術を後押ししました。
気候的にも、湿潤で雪深いこの地域では、木の乾燥に適した環境が整っており、ゆっくりと材を寝かせることで反りや割れの少ない木地が得られるとされています。こうした歴史・文化・気候が三位一体となり、山中漆器独自の発展を支えてきました。
山中漆器の歴史
木地師の移住から始まった、挽物漆器の道
山中漆器は、移住してきた木地師たちの手により16世紀後半にその歴史を刻み始めました。
- 1570年代:滋賀県蛭谷から越前(福井)を経て、木地師たちが加賀国山中温泉真砂に移住。轆轤を用いた木地加工を開始。
- 1600年代初頭:山中温泉の湯治客向けに椀や盆、玩具などを製作・販売。温泉町ならではの土産文化が始まる。
- 1700年代中期:輪島・金沢から塗師や蒔絵師の技術が伝来し、分業体制が徐々に整う。
- 1800年代初頭:茶道の隆盛とともに棗や茶筒などの茶道具製作が本格化。「木地の山中」と称される。
- 1880年代:商業資本による問屋制度が確立。木地屋・塗師屋・蒔絵屋による分業が定着。
- 昭和初期:都市化と機械化の影響で一時衰退するも、美術工芸品としての再評価が進む。
- 1975年(昭和50年):山中漆器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:異素材漆器やデザイン漆器が登場。国内外で新たな市場を獲得しつつある。
山中漆器の特徴
挽物技術が生む、木と漆の新たな表情
山中漆器の核心を成すのは、職人が轆轤を使って木材を削り出す挽物技術です。この技術により、極めて薄く、均一な厚みの器を作る「薄挽き」も可能となり、軽量で使いやすい漆器が生み出されます。木材は「縦木取り」と呼ばれる山中独自の手法で加工されます。これは、木が立っていたときと同じ方向に沿って切り出す方法で、歪みにくく、衝撃にも強いという利点があります。そのため、棗や茶筒、コップなど、気密性や耐久性が求められる製品に適しています。
もうひとつの魅力が「加飾挽き」です。千筋、稲穂筋、渦巻き模様など、木地に細かい筋をつける装飾技法で、木の表面に立体感と陰影を生み出します。これらは職人が自作する専用の刃物で挽き上げられ、同じ模様でも職人ごとに微妙に表情が異なるのも魅力の一つです。
さらに、山中漆器の仕上げには、何度も漆を塗り拭き取る「拭き漆」や、蒔絵を立体的に盛り上げる「高蒔絵」などの技法が駆使されます。光の加減や手の角度で表情を変える漆の艶と、木地の文様が織りなす造形美は、まさに実用と芸術の融合です。

山中漆器の材料と道具
木の命を生かす、精緻な轆轤と刃物の世界
山中漆器では、木地の加工から塗りまで多くの工程が分業で行われ、各段階で専門の職人が高度な道具と感性を駆使します。
山中漆器の主な材料類
- ケヤキ:硬く美しい木目が特徴で、茶道具などに用いられる。
- トチ:柔らかく加工しやすい木材で、椀や盆に多用される。
- ミズメザクラ:滑らかな木肌と堅牢性を兼ね備える。
山中漆器の主な道具類
- 挽物轆轤:木地を回転させながら成形する伝統的な機械。
- 加飾刃(筋引き刃):木地に模様をつけるための特殊な刃物。
- 漆刷毛・拭き布:漆の塗布と拭き取りに用いられる。
- 彫刻刀・蒔絵筆:高蒔絵や装飾に使われる精密道具。
こうした材料と道具を操る木地師・塗師・蒔絵師の連携によって、山中漆器の豊かな表現力が支えられています。
山中漆器の製作工程
木を挽き、漆を重ね、器に命を吹き込む
山中漆器の製作は、素材選びから木地加工、塗り、蒔絵に至るまで、緻密な分業体制によって成り立っています。
- 製材・荒挽き
原木を目的に応じた大きさにカットし、ろくろを用いて荒挽き。乾燥工程で歪みを防ぐ。 - 仕上挽き
乾燥後、職人自作の刃物で精緻に成形。ここで「加飾挽き」を加える。 - 拭き漆
漆を木地に摺り込み・拭き取りを数回~20回以上繰り返し、耐久性と美しさを高める。 - 髹漆(下地~上塗り)
布着せ・地付けを経て、下塗り・中塗り・上塗りを施す。 - 蒔絵・加飾
蒔絵師により高蒔絵などが施され、完成度を高める。
山中漆器の製作は、400年以上にわたり培われた技術と分業の美の結晶です。
山中漆器は、挽物の技術と漆の美が融合した、石川県が誇る伝統的工芸品です。縦木取りや加飾挽きによる堅牢性と意匠性、そして分業制に支えられた美しい漆器の数々は、現代の食卓や茶の湯の場でも愛され続けています。