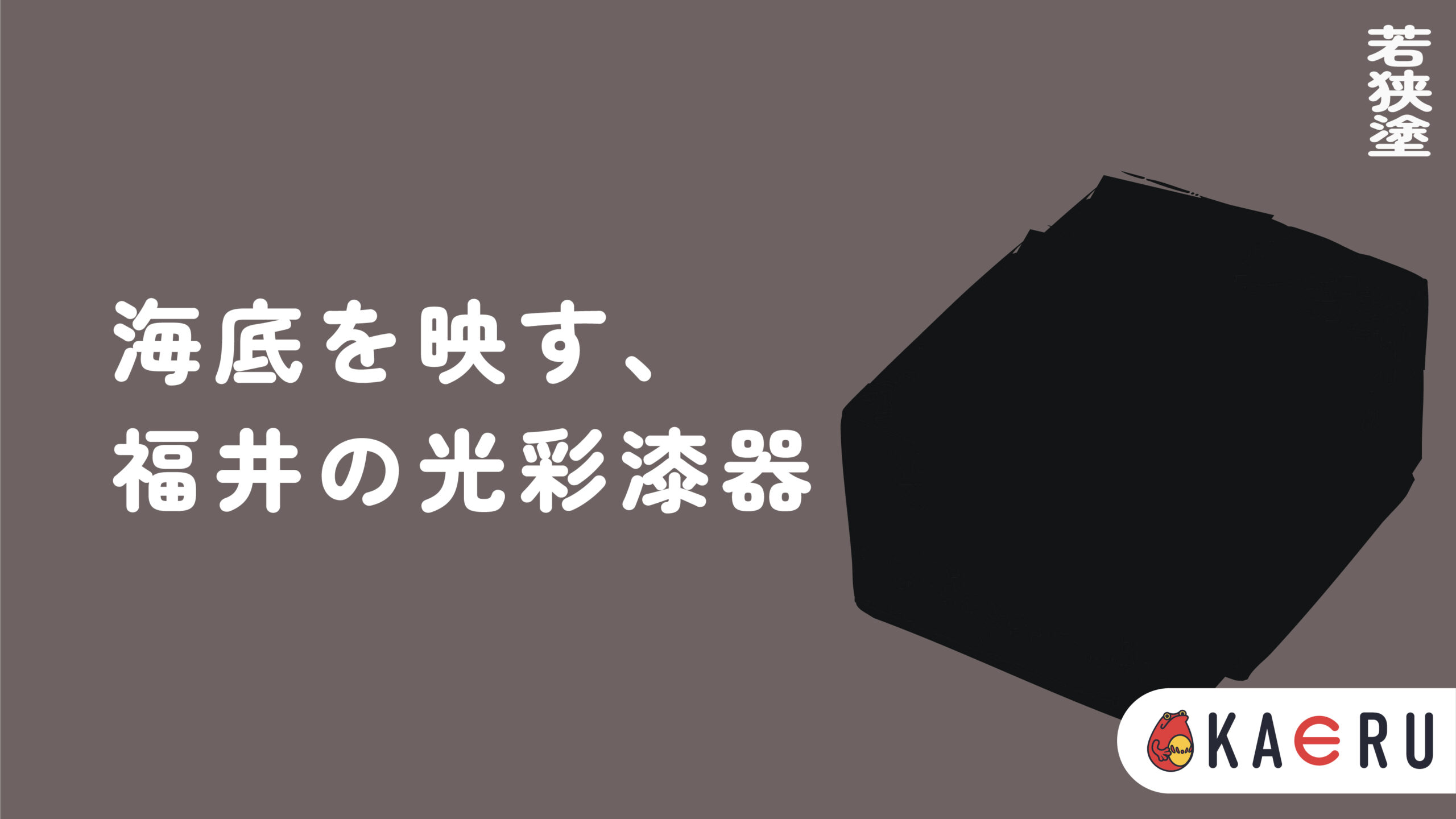若狭塗とは?

若狭塗(わかさぬり)は、福井県小浜市で作られている伝統的な漆器です。江戸時代初期より続く400年の歴史を持ち、螺鈿や卵殻、松葉などを用いた装飾技法により、きらめく海底のような幻想的な模様を漆の層から研ぎ出す独特の技術が特徴です。
その深みある表情は、美術品としての評価はもちろん、熱や水にも強く、箸や椀などの日用品としても広く親しまれています。中でも「若狭塗のぬりばし」は全国シェアの8割を占め、現代の暮らしにも息づく工芸品として進化を続けています。
| 品目名 | 若狭塗(わかさぬり) |
| 都道府県 | 福井県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1978(昭和53)年2月6日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(8)名 |
| その他の福井県の伝統的工芸品 | 越前焼、越前漆器、越前打刃物、越前和紙、若狭めのう細工、越前箪笥(全7品目) |

若狭塗の産地
海と都を結んだ交易拠点、小浜の風土が育んだ漆の芸術
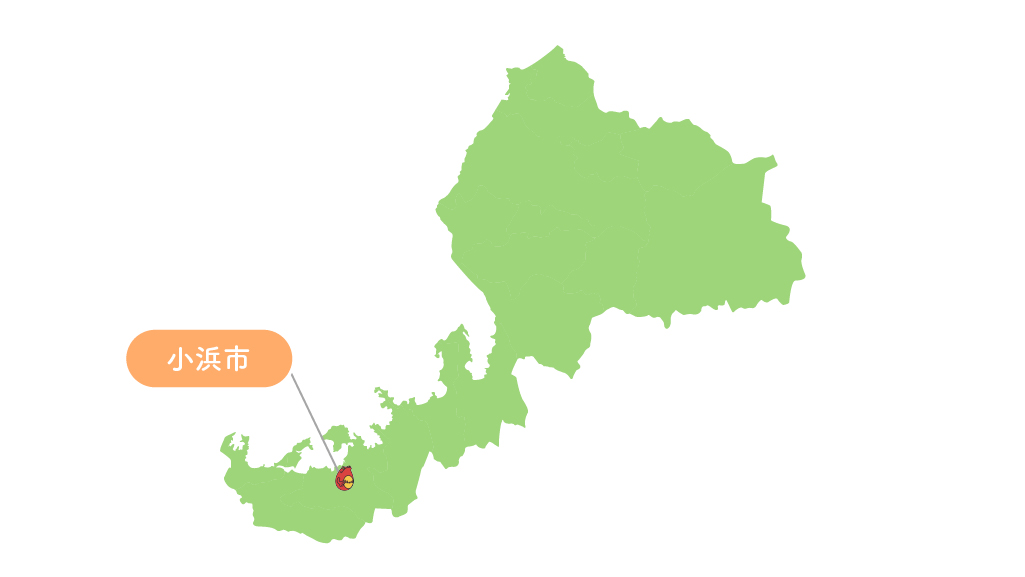
主要製造地域
若狭塗の産地である小浜市は、福井県南西部に位置し、古来より「若狭国」と呼ばれた地域に含まれます。日本海に面した港町として、古代から大陸や都との交易拠点として発展してきました。
奈良・平安時代に仏教伝来とともに中国文化の影響を受け、寺院建築や仏具制作を通じて漆芸の素地が培われました。中世には熊川宿をはじめとした宿場町が栄え、江戸時代には小浜藩の城下町として政治・文化・経済の中心地となります。若狭湾から水揚げされた海産物は「鯖街道」を通じて京都・奈良へ運ばれ、海と都を結ぶ経済・文化ルートの起点として機能していました。
また、上方文化との結びつきが強く、京都の美意識や技法が小浜に流入したことで、洗練された工芸文化が育まれました。仏教行事や年中行事も豊富で、漆器は祭礼用具や贈答品としての需要も高く、漆工技術は町人や武家層に支えられて継承されていきました。
気候的には、漆の乾燥と発色に適した湿潤な日本海側の環境が揃っており、安定した製作条件が確保できる土地でもあります。また、若狭湾の澄んだ海底や季節ごとに変わる海の色彩が、若狭塗に見られる模様の着想源ともなっています。
こうした歴史・文化・気候の三位一体が、若狭塗という独創的な漆芸を生み出したのです。
若狭塗の歴史
城下町文化とともに育まれた、加飾漆器の系譜
若狭塗は、江戸初期の城下町・小浜において独自に発展した加飾漆器です。
- 1600年代初頭: 小浜藩の御用塗師・松浦三十郎が、若狭湾の海底風景を漆で表現した「菊塵塗(きくじんぬり)」を考案。貝殻や松葉、卵殻を加飾に用いた新技法を確立。
- 1634年: 酒井忠勝が小浜藩主に就任。「若狭塗」と命名し、藩の秘技として他藩への技術流出を禁止。若狭塗は小浜藩の保護産業として地位を固める。
- 1700年代中頃: 松浦三十郎の弟子たちにより「磯草塗」などの新技法が考案され、装飾性がさらに高まる。
- 1800年代初頭: 若狭塗が京都や江戸でも美術工芸品として高く評価され、贈答品や調度品として流通が広がる。
- 1868年(明治維新): 藩政の廃止により保護産業としての体制が消滅。武家需要が激減し、一時衰退。
- 1890年代(明治中期): 庶民向けの日用品漆器として再興。箸や椀を中心に生産される。
- 1930年代(昭和初期): 装飾技法の芸術性が再評価され、美術工芸品として国内外に販路を拡大。
- 1978年(昭和53年): 若狭塗が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
若狭塗の特徴
色と光を閉じ込め、削り出す。唯一無二の「研ぎ出し模様」
若狭塗の最大の特徴は、加飾→塗布→研磨という工程を通じて、多層構造の漆の中から幻想的な模様を“掘り起こす”ように表現する点にあります。アワビ貝や卵の殻、松葉など自然由来の素材がランダムに散りばめられた後、何層もの色漆で覆われ、砥石や炭で慎重に研がれることで、隠れていた模様が徐々に浮かび上がってくるのです。まるで、宝石を原石から磨き出すかのような工程です。
模様は完全に偶然性に任される部分もあり、一つとして同じ仕上がりにはなりません。ときには波のうねり、貝のきらめき、深海の底のような色の重なりなど、見る者の想像力を刺激します。
また、「螺鈿(らでん)」と呼ばれる貝殻の光沢を漆に封じ込める技法は、奈良時代に中国から伝来したもので、日本の工芸史にも深いルーツがあります。若狭塗はこの技法を現代の実用漆器にまで昇華させた、まさに進化形といえる存在です。

若狭塗の材料と道具
素材の個性を生かす、重ねと研ぎの道具たち
若狭塗の製作は、木地以外のすべての工程を一人の職人が担う「一貫製作」が基本です。複雑な技法を支えるのは、多様な自然素材と、繊細な塗り・研ぎ・磨きの道具たちです。
若狭塗の主な材料類
- アワビ貝(真珠層):螺鈿の加飾に使用。輝きと硬度を併せ持つ。
- 卵殻:白色の細かな文様に使われる。繊細で割れやすく扱いに熟練を要する。
- 松葉・ヒノキ葉:線的な意匠として、構図のアクセントに。
- 色漆(青・赤・黄など):層ごとの色彩表現を可能にする。
- 金箔:仕上げに添えて華やかさを演出する。
若狭塗の主な道具類
- 漆刷毛:均一な塗布のための筆状工具。毛の質が仕上がりを左右する。
- 砥石:模様を研ぎ出す初期研磨用。粗さの種類を使い分ける。
- 炭(炭研ぎ用):表面をなめらかに整える仕上げ研磨に使用。
- 磨き粉(砥の粉+なたね油):最終仕上げの艶出し用。
これらを使いこなす熟練の感覚が、若狭塗の美しさを支えています。
若狭塗の製作工程
重ね、閉じ込め、そして研ぎ出す、漆芸の精華
若狭塗の製作工程は、すべてが手作業であり、1点の完成に数ヶ月から1年を要することもあります。
- 下地つけ
生漆に地の粉とのりを混ぜたものを木地に塗布し、乾燥させる。 - 中塗り
下地を研磨後、中塗りを行い、表面を整える。 - 模様付け
卵殻・貝片・松葉などをランダムに貼り付ける。 - 合塗り
青・赤・黄などの色漆を2色以上重ねて塗布。 - 箔置き
金箔や銀箔をアクセントとして配置する。 - 塗り込み
色漆を6~7回塗り重ねて模様を閉じ込める。 - 石研ぎ・炭研ぎ
砥石で模様を研ぎ出し、炭で滑らかに整える。 - 磨き
砥の粉と菜種油を使って最終仕上げの艶出しを行う。
この工程を一貫して担う職人は、塗師であり、意匠家であり、研磨職人でもあるのです。
若狭塗は、福井・小浜の海と文化、自然素材と職人技が織りなす漆芸の逸品です。螺鈿や卵殻、色漆を幾層にも重ね、研ぎ出すことで浮かび上がる唯一無二の模様は、まさに“使える芸術”。日常と美が調和する若狭塗は、今も進化を続けています。