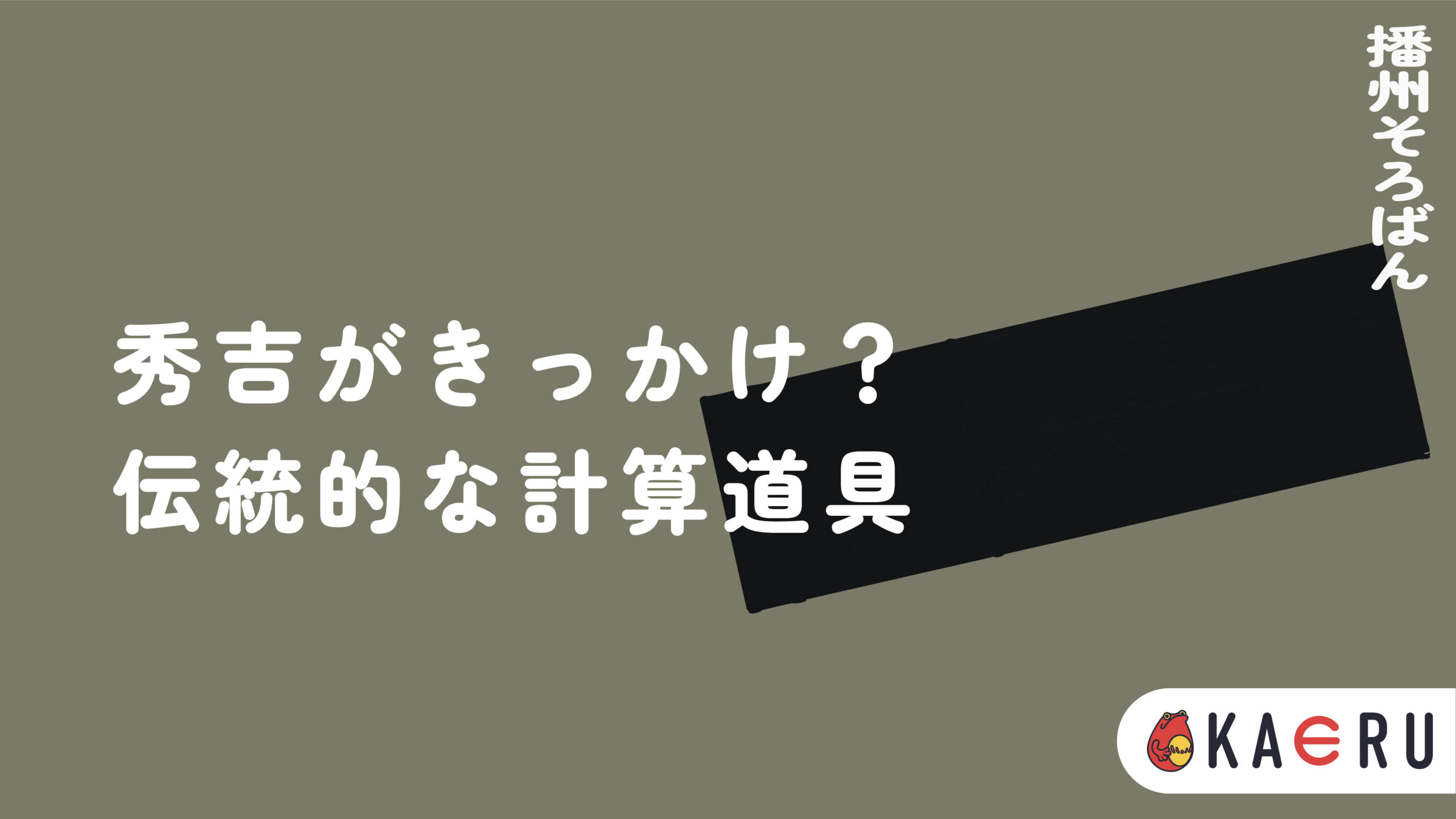播州そろばんとは?
播州そろばん(ばんしゅうそろばん)は、兵庫県小野市や三木市などを中心に製作されている、木製の伝統的な計算道具です。その特徴は、玉の動きが極めて滑らかで、弾いたときに澄んだ音が響き、止めたい位置でぴたりと止まるという操作性の高さにあります。さらに、玉の形状は独特の菱形で大きさが整い、軸との精密な嵌合を可能にする穴あけ技術や、緻密な分業体制による製作が、その品質を支えています。
単なる文具の域を超え、木工技術の粋を集めた「工芸品」としての価値を今もなお保ち続けています。
| 品目名 | 播州そろばん(ばんしゅうそろばん) |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 分類 | 文具 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(24)名 |
| その他の兵庫県の伝統的工芸品 | 丹波立杭焼、出石焼、豊岡杞柳細工、播州毛鉤、播州三木打刃物(全6品目) |


播州そろばんの産地
播磨平野が育んだ、分業と技の集積地

主要製造地域
播州そろばんの主産地は、兵庫県南部の小野市・三木市を中心とする旧・播磨国の地域です。この地は古くから刃物・木工・和紙などの手工業が盛んな土地であり、そろばん製作もまた、そうした工芸文化の中で自然と育まれてきました。
江戸時代を通じて小野では農閑期の副業としてそろばんづくりが広まり、明治以降には分業制による量産体制が確立されました。また、三木市は鍛冶職人の町として知られ、同地域では木工・金工が高度に共存していたことが、そろばん枠や工具の製造にも有利に働いたとされます。
また、計算能力や几帳面さを重視する商人文化や、読み書きそろばんが基礎教養とされた教育熱心な地域性が、産業としてのそろばん製作を支えました。そろばんが単なる道具でなく、暮らしの中に根ざした“学びの象徴”として愛されてきた背景があります。
播州そろばんの歴史
戦乱を越えて伝わった、計算具の知と技
播州そろばんの歴史は、室町時代の末期に中国から伝来した「算盤(そろばん)」に端を発します。
- 16世紀後半(室町時代末期):中国から長崎を経由して、日本に「算盤(そろばん)」が伝来。最初の定着地は滋賀県大津とされる。
- 1580年(三木城の戦い):羽柴秀吉による三木城攻めの際、小野・三木の住民が戦火を避けて大津へ避難。避難中にそろばん製作技術を習得。
- 1590年代(安土桃山時代末):小野に戻った避難民らが地元でそろばん製造を開始。木工技術と農閑期の副業文化が融合し、播州地域に普及。
- 18世紀(江戸中期):農民や職人が冬季にそろばん製作を行う「分業制」の萌芽。そろばんの品質と生産量が徐々に向上。
- 1870年代(明治10年代):西洋教育の導入とともに「読み・書き・そろばん」が義務教育の基礎に。播州そろばんの需要が一気に拡大。
- 1960年(昭和35年):年間360万丁を生産。播州そろばんが全国のそろばんの約9割を占め、日本一の生産地として頂点を迎える。
- 1976年(昭和51年):播州そろばんが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:電卓・デジタル機器の普及により実用性は低下するも、教育効果や工芸的価値が再評価され、観光資源・文化財としての価値が高まる。
播州そろばんは、まさに時代の波を越えながら、人々の暮らしとともに歩んできた“道具と教育と技術の記録”です。
播州そろばんの特徴
精緻な機能美と、五感に響く使い心地
播州そろばんの魅力は、その操作性・精密性・美しさがすべて調和している点にあります。第一の特徴は操作感覚の良さ。玉を弾いたときの「カツン」という澄んだ音は、熟練の職人が均一な厚みと重さで仕上げた証拠。さらに、玉がなめらかに滑りつつ、必要な場所でぴたりと止まるのは、玉と軸の精密な嵌合によって実現されています。
また、播州そろばんの玉は、ややふくらみのある菱形をしており、視覚的にも指先にもやさしくなじみます。高級モデルではツゲや黒檀を用いた深い艶のある仕上げがなされ、工芸品としての鑑賞価値も高まります。
教育用・高級文具用・記念品やインテリア向けまで、用途とデザインに応じた多様なモデルが揃っており、なかには名入れやカラフルな玉を配した「見せるそろばん」もあります。
播州そろばんの材料と道具
指先に応える、木と竹のこだわり素材
播州そろばんの製作には、木の硬度・竹のしなやかさ・道具の精度、すべてが高次元で要求されます。
播州そろばんの主な材料類
- オノオレカンバ(玉):その名の通り「斧が折れるほど硬い」木で、密度と耐久性に優れる。
- ツゲ・コクタン(玉・枠):細工性と強度に富む高級木材。
- コクタン(枠):黒く光沢があり、高級感と堅牢性を兼ね備える。
- マダケ・煤竹(軸):繊維が緻密でしなやか。経年で赤黒く変色した煤竹は希少。
播州そろばんの主な道具類
- 玉切り抜き器:玉を打ち抜く専用刃物。
- 面取り鉋:玉の縁をなめらかに仕上げる道具。
- 穴あけ機:高精度な芯通し用の穴を開ける。
- 組立冶具:枠や軸を正確に固定しながら組み立てるための台。
これらの素材と道具を、4人の専門職人が分業で担当することにより、100以上の工程を経て、播州そろばんは完成します。
播州そろばんの製作工程
百の工程が生む、手に馴染むそろばん
播州そろばんの製作は、大きく「ひご職人」「玉削り職人」「玉仕上げ職人」「組立職人」の4人による分業体制により行われます。それぞれの職人が専門の工程を担い、数ミリ単位の精度を維持しながら完成へと導いていきます。
- 軸づくり
マダケや煤竹を割ってひごに加工し、滑らかに磨き上げる。強度と柔軟性が命。 - 玉づくり
オノオレカンバを輪切りにして、型抜き・面取り・研磨・穴あけなどを行い、美しい菱形の玉を形成する。 - 枠づくり
コクタンやツゲを用いて枠材・はりを加工。軸が通る穴の位置もミリ単位で調整。 - 仮組み・通し
枠に軸を通し、箱状にした中で玉を左右に揺らしながら丁寧に通す。玉の摩擦具合を調整。 - 組立・仕上げ
裏板や固定部品を取り付けて形を整え、紙やすりやムクの葉で全体を磨き上げる。
播州そろばんは、使うたびに木の温もりと職人の精緻な技が伝わってくる、日本の工芸精神が息づく文具です。百を超える工程と分業体制が支えるその技術は、電卓やデジタル機器では決して代替できない“手と音の道具”として、今も世界中で愛されています。