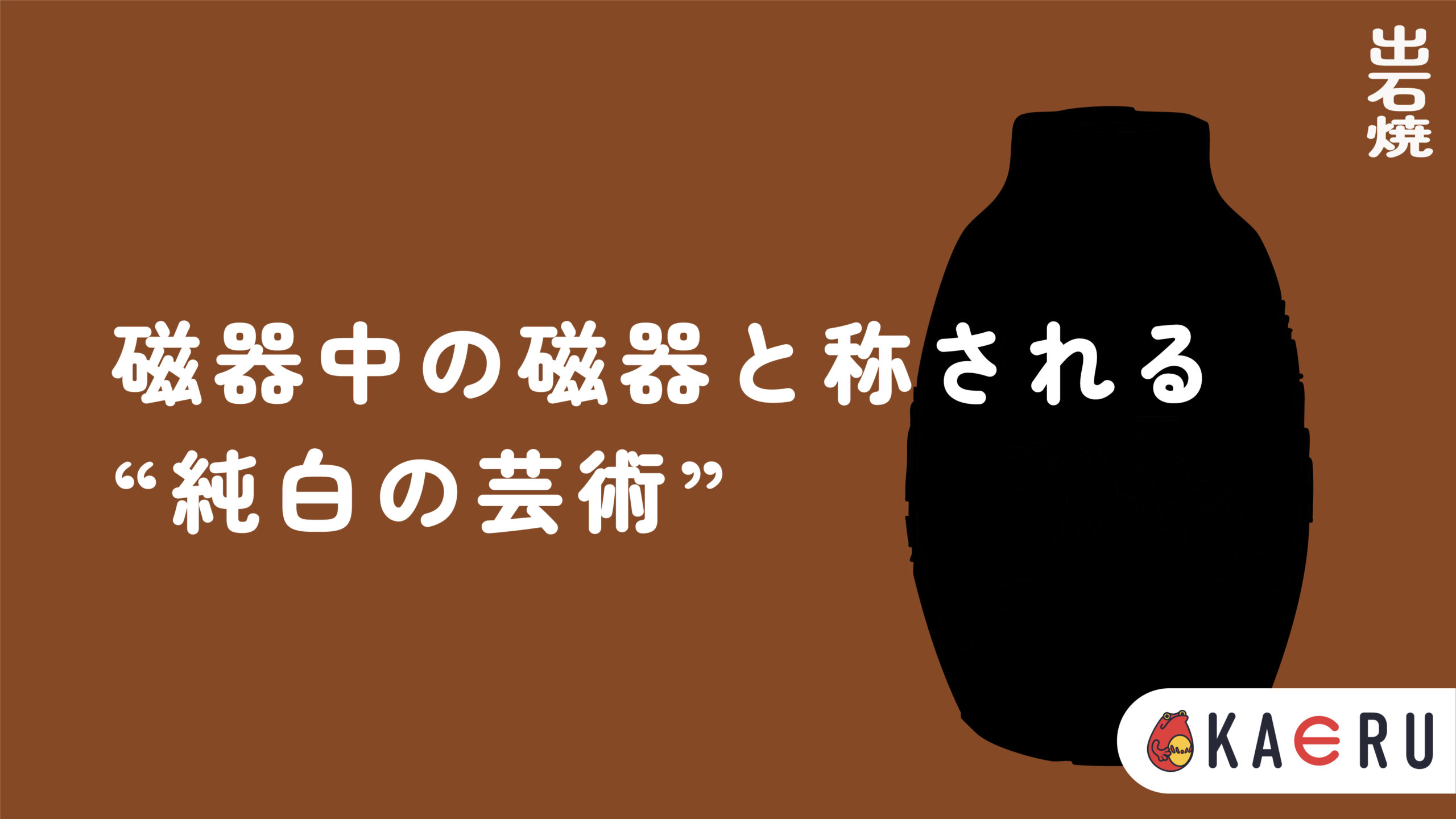出石焼とは?
出石焼(いずしやき)は、兵庫県豊岡市出石町で生産される磁器の伝統工芸品です。江戸時代中期に磁器原料が地元で発見され、出石藩の後押しを受けて始まったこの焼きものは、白磁の中でも際立った純白さと繊細な彫刻・絵付で高く評価されています。
特に、「冷たいほどに白い」と称される磁肌は、伊万里焼の青白さとも、京焼の柔らかな白とも異なり、まさに“磁器の中の磁器”と呼ぶにふさわしい気品を湛えています。西日本では珍しい本格磁器として、明治時代には国内外の博覧会でも高い評価を受け、現在もその精緻な技術が受け継がれています。
| 品目名 | 出石焼(いずしやき) |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1980(昭和55)年3月3日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(6)名 |
| その他の兵庫県の伝統的工芸品 | 丹波立杭焼、豊岡杞柳細工、播州そろばん、播州毛鉤、播州三木打刃物(全6品目) |

出石焼の産地
但馬の山里が育んだ、白磁工芸の聖地
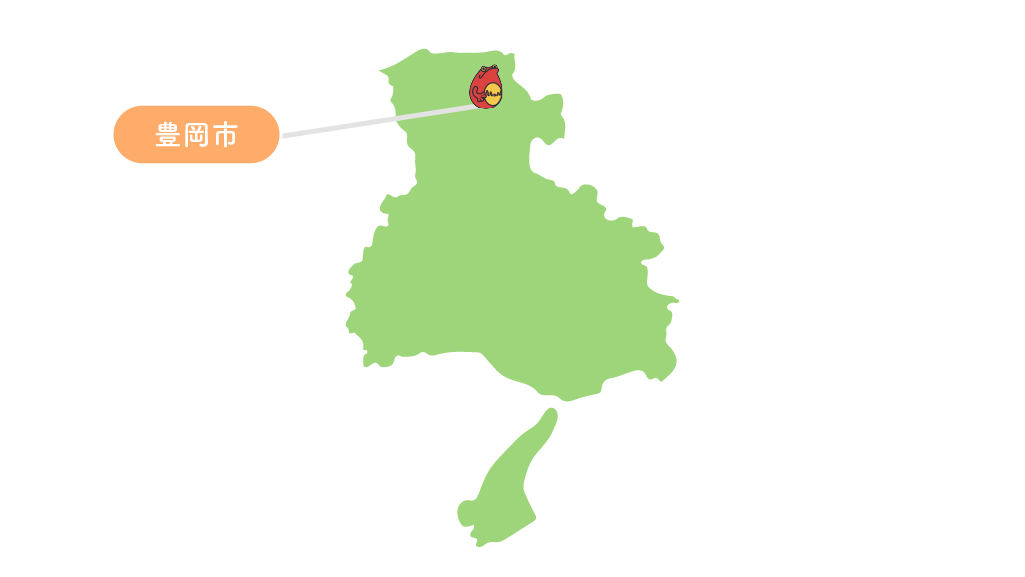
主要製造地域
出石焼の産地は、兵庫県豊岡市出石町。城下町として知られるこの地は、但馬地方の自然と歴史、文化が色濃く息づく場所です。出石は、江戸時代に五万八千石の出石藩が置かれた政治と文化の中心地であり、出石城の城下町として町屋や寺社、茶屋が整然と築かれました。出石焼の誕生も、この町人文化と藩の保護政策が深く関係しています。藩主の支援により有田から陶工が招かれ、藩営として磁器生産が始められたのです。
また、出石町は古来より和歌・茶道・文人文化が盛んで、繊細で洗練された美意識が住民の間に根づいていました。こうした風土のなかで、装飾性よりも静かな気品を尊ぶ出石焼の美学が育まれていきます。今でも「小京都」と称される町並みに、白磁の器がしっくりと馴染むのはその文化的背景ゆえでしょう。
但馬地方は冬に積雪が多く、夏は湿潤で寒暖差が大きい気候です。このため、出石焼の登窯では、湿度管理や乾燥時間に細やかな工夫が求められ、焼き上がりの安定と白磁の透明感を生み出す職人技が発展しました。また、冬場に仕事が少なくなる農村部での副業としても焼き物づくりが広まり、地域の産業基盤として定着していきました。
こうした歴史・文化・気候の三拍子が揃う出石という土地が、日本でも屈指の白磁芸術を育て上げたのです。
出石焼の歴史
静謐な白の芸術、出石焼の系譜
出石焼のルーツは古代にさかのぼる伝承を持ちながらも、現代に通じる磁器技術は江戸後期に確立されました。その発展の過程は、工芸と政治、そして国際博覧会の舞台へと連なります。
- 紀元前1世紀頃(垂仁天皇時代):天日槍命(あめのひぼこのみこと)が但馬に来訪し、陶工を伴って生活の器を焼いたという伝承が出石焼の起源とされる。
- 1789年(寛政元年):二八屋陳(珍)左衛門が出石藩の命で有田へ赴き、磁器製造技術を習得。陶工を出石に招き、本格的な白磁づくりが始まる。
- 1804〜1818年(文化年間):藩営窯が安定的に稼働し、藩財政の一助として磁器生産が制度化される。
- 1830〜1844年(天保年間):一般町人による磁器製作が始まり、民間窯元も登場。技術の多様化が進む。
- 1877年(明治10年):第1回内国勧業博覧会に出品。純白の白磁に精緻な絵付けが評価される。
- 1899年(明治32年):兵庫県立陶磁器試験所が開設され、彫刻や色絵など高度な装飾技術が体系化される。
- 1904年(明治37年):米国セントルイス万国博覧会にて金賞を受賞し、国際的な評価を得る。
- 1980年(昭和55年):出石焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」として指定される。
こうした歴史を経て、出石焼は日本の白磁を代表する工芸として不動の地位を築きました。
出石焼の特徴
透きとおる白に宿る精緻な美と静けさ
出石焼最大の魅力は、その比類なき白磁の「白さ」にあります。一般的な白磁よりも青みが少なく、「冷たいほど白い」と形容されるその肌合いは、出石の陶石と職人の焼成技術が生み出す独自の美です。伊万里焼の白はやや青みを帯び、京焼は乳白色の柔らかさが特徴ですが、出石焼はそのどちらとも異なる硬質でシャープな印象を与える白です。この冷ややかさが、絵付や彫刻の精密さを際立たせます。
さらに特徴的なのが「彫刻磁器」という側面。器の表面に花鳥風月の文様を手彫りで施し、陰影が立つように焼き上げられます。絵付と併用されることもあり、「夜学式染付赤絵盃洗」や「赤青五彩花弁名花十友図花瓶」など、意匠性の高い作品は、工芸と美術の融合を体現しています。
まさに出石焼は、白という“無彩”にこそ、最も多彩な表現が宿ることを教えてくれる磁器芸術です。

出石焼の材料と道具
白磁を極める、選び抜かれた素材と道具の妙技
出石焼の製作には、地元で採れる陶石を主とした素材と、細やかな表現を可能にする繊細な道具が用いられます。素材の純度と職人の手業が融合し、唯一無二の白磁を生み出します。
出石焼の主な材料類
- 出石陶石:出石地域で採掘される白色度の高い陶石。磁器焼成に最適。
- 長石・珪石:焼成温度や透明感を調整するために使用。
- 絵付顔料:鉄・銅・コバルトなどをベースにした酸化金属顔料。
出石焼の主な道具類
- ロクロ:成形に使用する回転式の台。手ロクロが主流。
- 彫刻刀:花鳥や文様を刻むための細身の刃物。
- 絵筆・絵具皿:筆による絵付に用いる伝統的な筆と陶製の絵具皿。
- 登窯・電気窯:焼成に用いる。伝統的な登窯も一部で継承される。
こうした素材と道具の選定・使いこなしが、出石焼ならではの透明感と緻密な装飾性を生み出しているのです。
出石焼の製作工程
白に語らせる、美と技の結晶
出石焼の製作工程は、原料精製から焼成、彫刻・絵付に至るまで、すべてが高度な技術と美意識のもとに行われます。
- 原料精製
出石陶石を粉砕・精製し、成形に適した粘土を作る。 - 成形
手ロクロで器の形を整える。均一な厚みと形状が求められる。 - 素焼き
成形後の作品を低温で一度焼く。強度を持たせる工程。 - 彫刻・絵付
素焼き後、文様を彫ったり絵付を施す。手彫りや筆描きなど複数の技法がある。 - 本焼き
高温で本焼きを行い、磁器としての硬さと白さを引き出す。 - 上絵焼成
赤絵・五彩などの場合はさらに低温で再焼成を行う。
すべての工程を通じて、職人たちは“白”という色の中に、奥行きと感情を宿らせていくのです。
出石焼は、白磁の魅力を極限まで引き出すことで、静けさと気品を空間に届ける芸術磁器です。冷たさを感じさせるほどの白、緻密な彫刻と絵付、そして歴史に裏打ちされた技術。日本の磁器文化において確かな存在感を放つ出石焼は、現代においてもなお、その静謐な美を通して私たちの暮らしに豊かな余白を添えてくれます。