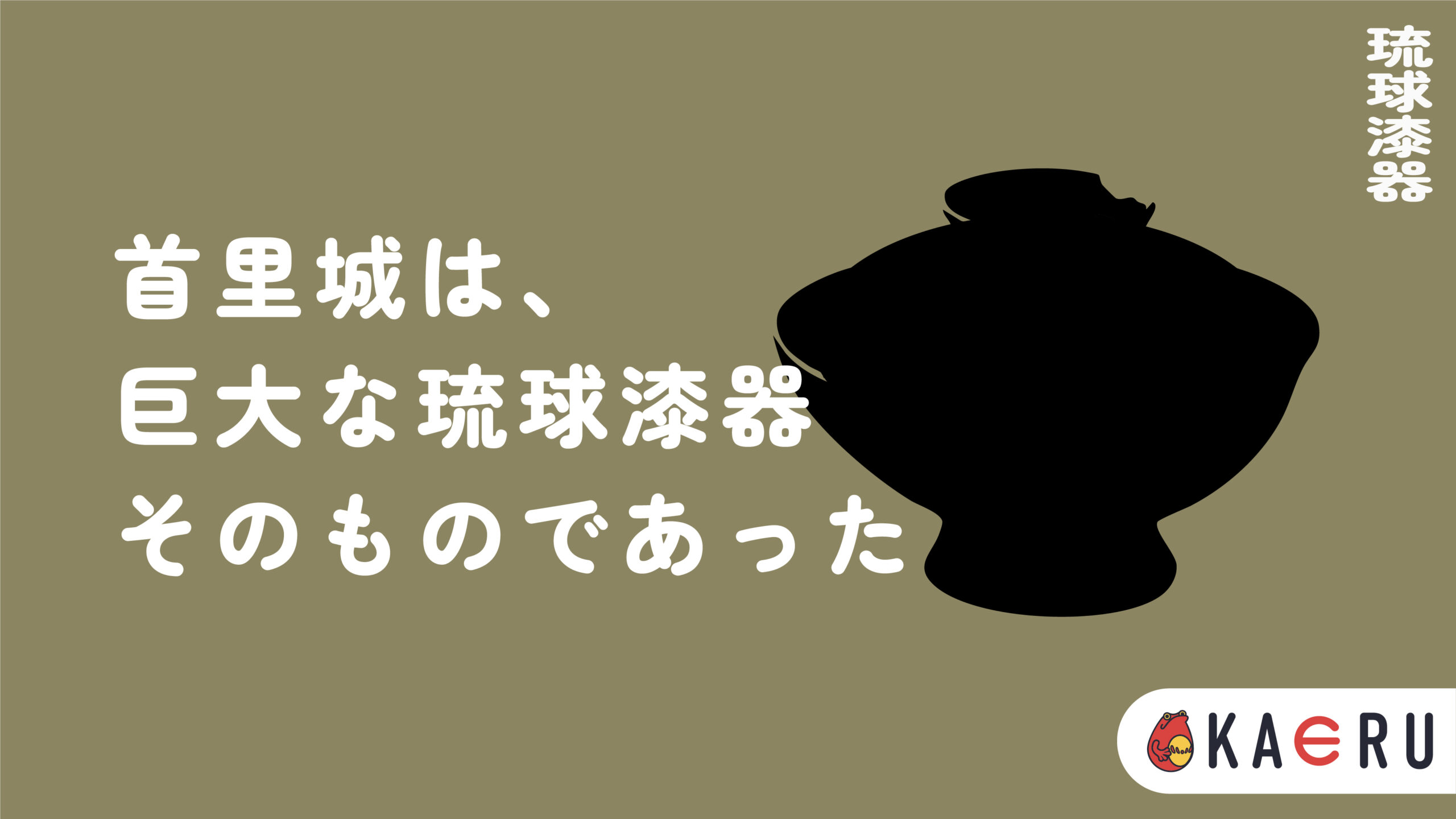宮島細工とは?
宮島細工(みやじまざいく)は、広島県廿日市市の宮島周辺で作られている伝統的な木工品です。厳島神社の門前町として栄えた宮島では、参拝客向けの土産物として発展した背景を持ち、特に木地の美しさを活かした無塗装仕上げが特徴とされます。
その技法は、鎌倉時代に神社建築のため招かれた宮大工や指物師の流れをくむもので、木の目利き、精緻な彫刻、ろくろ挽きなど、多彩な木工技術が融合しています。なかでも「宮島杓子(しゃもじ)」は全国的にも有名で、現在ではろくろ細工、宮島彫り、くりもの細工といった多様な製品が作られています。
| 品目名 | 宮島細工(みやじまざいく) |
| 都道府県 | 広島県 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 1982(昭和57)年11月1日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 6(11)名 |
| その他の広島県の伝統的工芸品 | 広島仏壇、熊野筆、福山琴、川尻筆(全5品目) |

宮島細工の産地
世界遺産と木工の町が織りなす、自然美の舞台
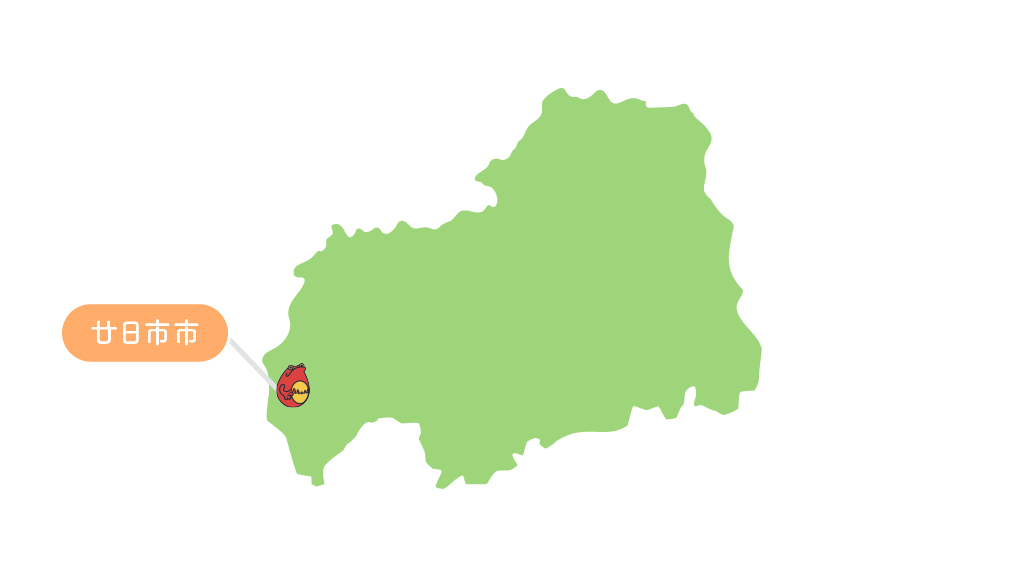
主要製造地域
宮島細工の産地は、広島県廿日市市および宮島(厳島)周辺です。宮島細工の産地は、広島県西部に位置する廿日市市およびその沖合に浮かぶ宮島(厳島)です。広島湾に浮かぶ宮島は、「日本三景」の一つに数えられ、厳島神社が鎮座する“神の島”として古来より崇敬されてきました。
歴史的に見れば、廿日市はかつて「二十日ごとに市が立つ町」として名を馳せ、物流と人の往来が盛んな港町でした。鎌倉時代には厳島神社の修築のため、全国から優れた宮大工や指物師が集められ、木工技術が地域に根づいていきました。こうした寺社建築の文化的蓄積が、やがて日用品や土産物の木工品へと派生していったのです。
また、厳島神社を中心とする門前町文化の存在が欠かせません。古来より参拝客の往来が絶えなかった宮島では、縁起物や奉納品としての工芸品需要が高く、土産物としての木工細工が発展する土壌が整っていました。とくに江戸後期以降、町人文化の中で「使える美」「贈る美」が重視されるようになると、宮島の木工芸もその潮流に応えるかたちで多様化していきました。
気候的には、温暖で比較的湿度の安定した瀬戸内気候が、木材の乾燥や保管に適しており、木工品の品質維持にも理想的な環境でした。さらに背後には中国山地の豊かな森林が広がり、クワやケヤキ、トチなどの優良な広葉樹が近隣から供給される立地も、技術と素材の融合を後押ししました。
こうした歴史・文化・気候の三要素が折り重なることで、宮島細工は観光土産の枠を超えた、確かな技術と感性をもつ工芸品へと成長を遂げてきたのです。
宮島細工の歴史
信仰と観光のなかで育まれた、木工の記憶
宮島細工は、厳島神社とともに歩んできた木工の伝統を背景に持ちます。その技術は時代とともに変化しながらも、土地の文化と結びつき、今日まで連綿と受け継がれています。
- 1185年頃(鎌倉時代初期):平家滅亡後、厳島神社の修築が進む中で、各地から宮大工・指物師が集められ、木工技術が地域に根づく。
- 14世紀後半〜(室町時代):神社修繕の恒常化により、廿日市周辺で木工の常住職人が増加。
- 17世紀(江戸時代前期):宮島参詣の一般化により、神社門前での土産文化が定着し始める。
- 1790年頃(江戸時代中期):僧・誓真が琵琶の形に着想を得て「宮島杓子」を考案。縁起物として人気を博し、島内に製造技術が広まる。
- 1850年頃(江戸時代末期):中国地方よりろくろ技術が伝わり、木地盆や器の生産が本格化。
- 1868年〜(明治期):参詣と観光が両立するようになり、木工品が全国への土産品として定着。
- 1930年代(昭和初期):彫刻技法の導入により、宮島彫りやくりもの細工の製品が多様化。
- 1982年(昭和57年):宮島細工が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:伝統技術を活かしつつ、アクセサリー・食器・漆塗りなど現代的製品が登場し、用途の拡張が進む。
宮島細工の特徴
素地の美を伝える、木と暮らしの共演
宮島細工の魅力は、木の素地の美しさをそのまま伝える「木地仕上げ」にあります。表面に塗装を施さず、木目や色合いを生かす仕上げは、素材への深い理解がなければ成立しない技法です。そのため、素材選びや乾燥、成形に至るまで、極めて高い精度が求められます。
製品の種類も多岐にわたり、なかでも最も知られるのが「宮島杓子」です。江戸時代の僧・誓真が考案したとされ、琵琶の形を模したその姿には、仏具的な静けさと、食卓の道具としての実用性が共存しています。現在でも受験合格や商売繁盛などを願う縁起物として全国に流通しており、「幸せをすくう」という語呂合わせから贈答品にも用いられます。
一方で、「ろくろ細工」は円形の木地をろくろで回転させながら成形する伝統技法で、茶盆や菓子器、酒器などが中心。木の年輪や木目が同心円状に浮かび上がる姿は、まさに自然が描いた模様とも言える美しさがあります。
また「宮島彫り」は、下絵を描いた木地に彫刻刀で図柄を彫り出す手仕事で、草花や動物文様など、温かみある意匠が人気です。彫りの深さや線の流れは職人の個性が強く反映され、同じ図柄でもひとつとして同じものはありません。

宮島細工の材料と道具
木の声を聴き、素肌を活かす選材と技術
宮島細工では、木目の美しさと乾燥性に優れた広葉樹を中心に使用します。加えて、用途や技法に応じた専用の道具も多数使い分けられます。
宮島細工の主な材料類
- クワ:軽くて強く、杓子や細工全般に適する。
- ケヤキ:木目が明瞭で、くりものや高級盆に使用。
- トチノキ:柔らかく加工しやすい。彫刻やろくろ細工に最適。
- サクラ:手触りがよく、色合いも上品で人気。
宮島細工の主な道具類
- のこぎり:木取り・型取りに使用。
- ろくろ:円形製品の成形に不可欠。
- かんな(10種類以上):粗挽き〜仕上げまで使い分け。
- 彫刻刀:宮島彫りにおいて精緻な文様を刻む。
- 紙やすり・布:仕上げ磨きに使用。水やけを防ぐ技術も必要。
自然乾燥と道具の使い分けによって、木目の魅力が最も美しく現れる製品が生まれます。
宮島細工の製作工程
木と呼吸を合わせる、静かな制作の連なり
ここでは、代表的な「ろくろ細工」の工程を紹介します。どの工程も自然素材と向き合うため、時間と技術が不可欠です。
- 木どり
原木を製材し、用途に応じた厚みに整える。2〜3ヶ月自然乾燥。 - 型どり
製品の円形を木材に描き、木目の向きを考慮して切り出す。 - 荒挽き
ろくろで回しながらかんなで形を整える。 - 割れ止め
木材表面に蝋を塗り、割れを防止。 - 長期乾燥
1年以上、自然通風で静置乾燥。 - 粗仕上げ挽き
形を整え再度蝋処理。さらに乾燥。 - 仕上げ挽き
かんなを使い分け、丁寧に成形。 - 磨き
水拭き・布磨きを4〜5回繰り返し、つやを出す。
いずれの細工も、木を「削る」のではなく「整える」感覚が求められ、時間をかけて木が本来持つ美を引き出していきます。
宮島細工は観光土産として親しまれてきた歴史の裏に、宮大工の系譜を継ぐ本格的な木工技術があります。伝統を受け継ぎながらも、現代の暮らしに寄り添うデザイン開発にも力を注ぐ宮島細工は、今なお進化を続ける“神の島”の工芸文化そのものなのです。