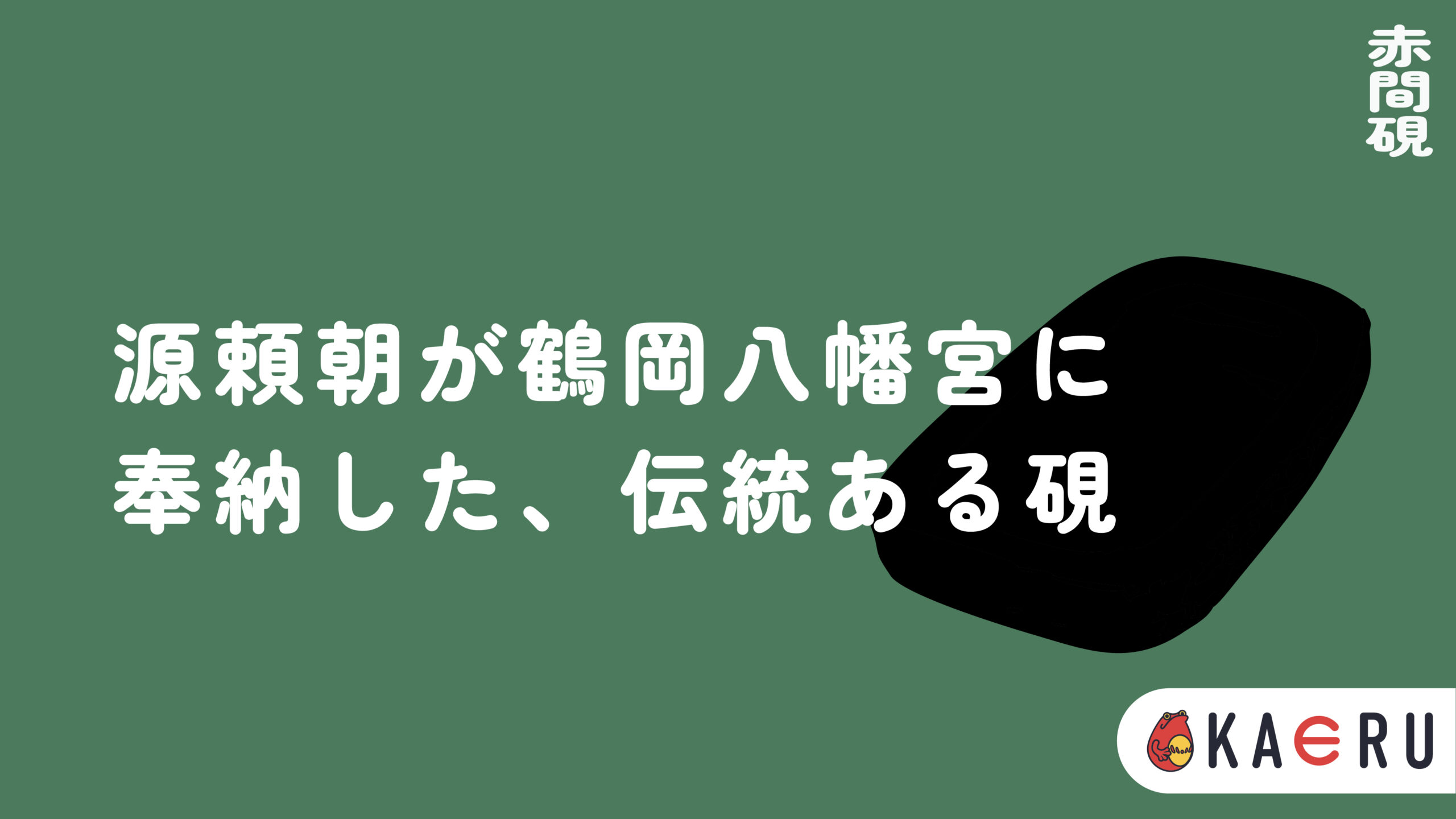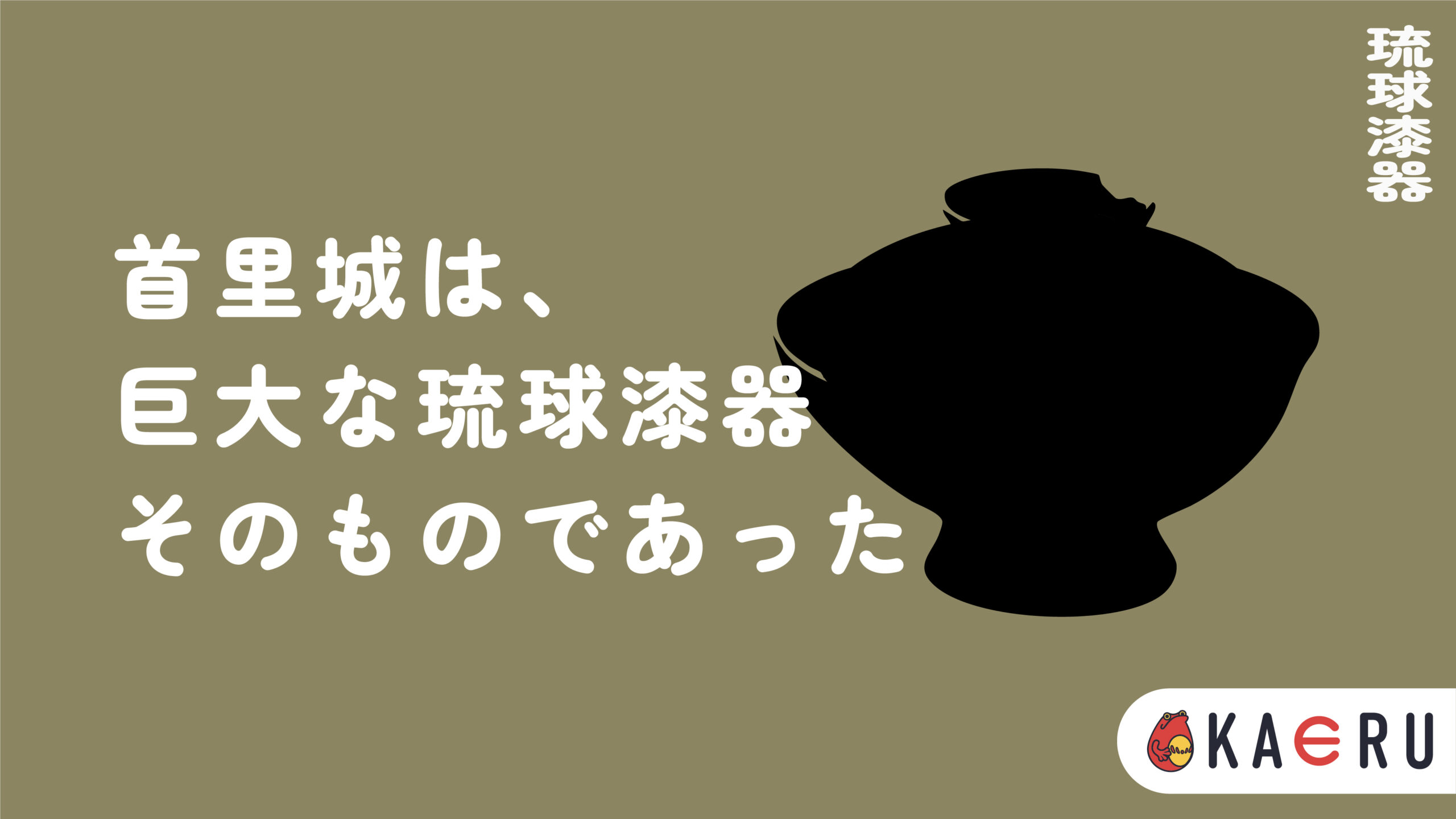赤間硯とは?
赤間硯(あかますずり)は、山口県下関市および宇部市で作られている伝統的な硯で、硯材として最適な「赤間石」を原料に用いた工芸品です。赤紫がかった美しい石肌と、墨を滑らかに擦り下ろす「鋒鋩(ほうぼう)」の緻密さが特徴で、書道家をはじめとする多くの愛好家から高い評価を受けています。800年以上の歴史を持ち、鎌倉時代にはすでに鶴岡八幡宮への奉納記録が残され、江戸時代には長州藩の献上品としても珍重されました。
今日では、伝統を受け継ぐ職人がすべての工程を一貫して行うことで、赤間石の特性を最大限に生かした硯が作り続けられています。
| 品目名 | 赤間硯(あかますずり) |
| 都道府県 | 山口県 |
| 分類 | 文具 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(5)名 |
| その他の山口県の伝統的工芸品 | 萩焼、大内塗(全3品目) |

赤間硯の産地
石と書の伝統が息づく、海と山の工芸のまち

主要製造地域
赤間硯の産地である山口県下関市と宇部市は、歴史・文化・地勢のいずれにも恵まれた地域です。下関市は古くから「赤間関」と呼ばれ、関門海峡に面した港町として中世より栄えてきました。交易と文化交流の拠点であったこの地では、筆や墨などの文房文化も早くから浸透し、硯の需要が高かったことがうかがえます。
宇部市は、赤間石の採石地として知られ、下関から続く山地に広がる鉱山では、石の質が特に良好な「御止山(おとめやま)」が長州藩の管理下に置かれるなど、赤間硯の重要性が制度的にも認められていました。赤間石は6000万年前の火山活動によって生成された赤紫色の頁岩で、特有の硬さと粘り、滑らかさを兼ね備えた硯材として重宝されてきました。
気候的にも、温暖多湿な瀬戸内の気候が石の風化を緩やかに保ち、また港湾からの石材輸送が容易であったことから、採石・加工・流通の全てに適した立地条件に恵まれていたといえます。こうした歴史・文化・自然条件が結びつき、赤間硯は日本有数の伝統硯として育まれてきたのです。
赤間硯の歴史
800年の風雪を超えて刻まれる、書と石の物語
赤間硯は、鎌倉時代より続く日本有数の硯の名産地として知られています。その歴史は、墨とともに書の文化を支えてきた歩みにほかなりません。
- 1191年(建久2年):鎌倉の鶴岡八幡宮に赤間硯が奉納されたとされる。現存する記録としては最古。
- 15世紀頃(室町時代):九州・中国地方の禅寺や学僧の間で愛用され、知識人文化に浸透。
- 1600年代前半(江戸初期):長州藩により赤間石の山が藩の管理下に置かれ、献上品・贈答品として使用。
- 18世紀後半(江戸中期):御用硯として格式が定着し、赤間硯の名が全国に広まる。
- 1850〜1860年代(幕末期):吉田松陰や高杉晋作らが使用。思想家・志士の愛用品として語られるようになる。
- 1880年代(明治20年代):書道の普及とともに赤間硯の生産が活発化。職人は200人を超える規模に。
- 1950年代(昭和30年代):文具の変化により需要減少。赤間石の新たな用途開拓が始まる。
- 1976年(昭和51年):赤間硯が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:若手職人が赤間石の端材を用いた現代製品の開発に取り組む。
今日では数少ない職人によって、伝統技術を守りながら、新しい赤間石製品の開発も進められています。
赤間硯の特徴
墨ののびと艶を引き出す、石の芸術品
赤間硯の最大の特徴は、その墨おりの良さにあります。赤間石は鋒鋩(ほうぼう)と呼ばれる微細な硬質成分を多く含み、この突起が墨を細かく滑らかに擦り下ろす役目を果たしています。その結果、墨は非常に伸びが良く、深く豊かな黒を表現できるため、書道家の間で長年にわたり支持されてきました。
また、石に適度な粘りがあるため、彫刻にも適しており、硯の縁や側面に施される装飾彫刻は、実用性と芸術性を兼ね備えています。浮かし彫りによる立体的な龍や松竹梅、細やかな毛彫りによる波文様などは、まるで絵画のような存在感を放ちます。
赤間硯の鋒鋩(細かな突起)は、新端渓硯より粒が小さいため、煤の粒が細かい松煙墨と相性が良く、墨色に艶と濃淡の深みを引き出す性質があります。逆に、膠(にかわ)を多く含む油煙墨や特大筆にはやや磨りにくい傾向があるため、筆の種類に応じた使い分けが推奨されます。
近年では、加工時に出た端材を活用し、箸置きやおちょこ、文鎮やアクセサリーといった新たな赤間石製品が開発されています。伝統を守るだけでなく、日常に寄り添うかたちで進化し続ける赤間硯。その背景には、素材への敬意と、技術への信念が息づいています。
赤間硯の材料と道具
墨と彫の美を生む、6000万年の石と精緻な彫刻具
赤間硯の製作に用いられる赤間石は、非常に限られた地層からのみ採石される希少な天然石です。石材の選定から彫刻・研磨まで、高度な目利きと熟練技術が求められます。
赤間硯の主な材料類
- 赤間石(赤色頁岩):6000万年前の火山堆積物。赤紫色で硬く粘りがあり、鋒鋩に富む。
赤間硯の主な道具類
- 大のみ:石を厚さ一定に整える粗削り用の工具。
- 彫刻用のみ:浮かし彫りや毛彫りなどに用いる多種の彫刻刀。
- ピックハンマー:石の切り出しに使用する先端鋭利なハンマー。
- 砥石・紙やすり:表面研磨用の仕上げ道具。
- 漆刷毛:艶出し・防水・防劣化処理に使用。
硬質で繊細な赤間石を、これらの道具と技で「墨を育てる器」へと昇華させます。
赤間硯の製作工程
石に魂を込める、書の器が生まれるまで
石の選定から細部の仕上げまで、すべてに職人の経験と感性が込められています。
- 採石
赤間石の良質な層を見極め、火薬やピックハンマーで石を切り出す。 - じぎり
石を大のみで厚さを整え、表面を水と砂で滑らかに加工。 - 縁立て
硯の大きさ・形状を決定し、縁部分を約3mm深さで成形。 - 荒彫り
墨をためる「海」、墨をする「丘」の部分を粗削り。装飾彫刻もここで下彫り。 - 仕上げ彫り
彫刻部分を整え、滑らかな面を整形して完成形へ。 - 磨き・漆塗り
砥石・紙やすりで磨き上げ、海と丘以外の部分に漆を塗って艶と耐久性を付加。
完成した赤間硯は、墨の美しさを引き出す道具であると同時に、赤間石の自然美と職人の技が融合した芸術品でもあります。
赤間硯は、6000万年の時を経て生まれた赤間石の魅力と、職人の一貫した手仕事が融合した伝統的工芸品です。墨の発色を引き出す実用性に加え、繊細な彫刻による芸術性を兼ね備えたその硯は、今なお書の世界に寄り添い続けています。