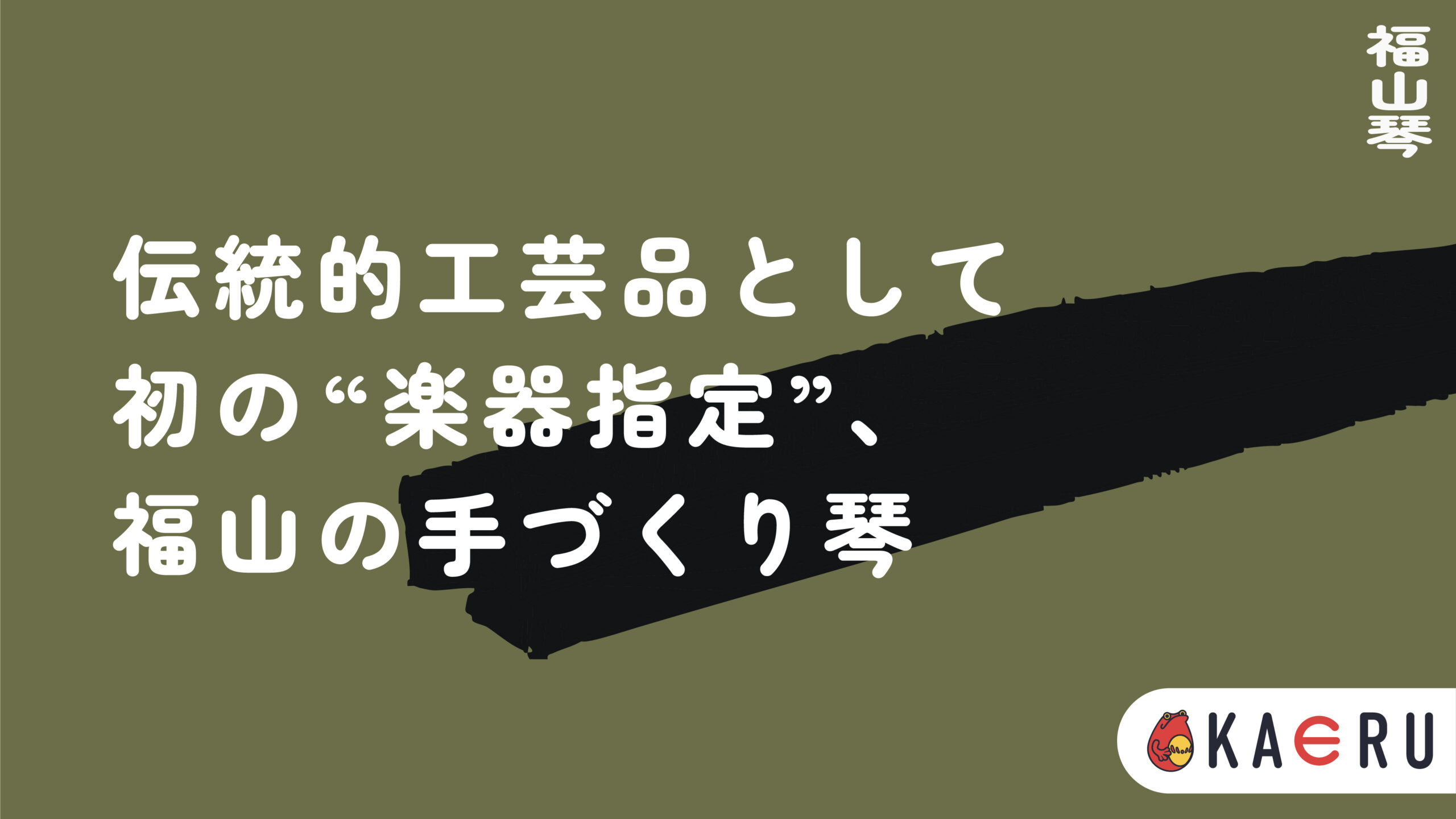福山琴とは?
福山琴(ふくやまごと)は、広島県福山市で製作される伝統的な和楽器で、最高級の桐材を用い、ほぼすべての工程を手作業で仕上げることで知られています。江戸時代初期から続く長い歴史を持ち、音の美しさと装飾の華麗さが特徴です。
木目の美しさを活かした意匠と、豊かな音色、そして長年の使用にも耐える堅牢な構造が評価され、昭和から平成にかけては全国有数の琴の産地として名を馳せました。現在も品質へのこだわりを貫きながら、小ぶりで扱いやすい普及型の琴を製作するなど、新たな需要開拓にも取り組んでいます。
| 品目名 | 福山琴(ふくやまごと) |
| 都道府県 | 広島県 |
| 分類 | その他の工芸品 |
| 指定年月日 | 1985(昭和60)年5月22日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 3(14)名 |
| その他の広島県の伝統的工芸品 | 宮島細工、広島仏壇、熊野筆、川尻筆(全5品目) |

福山琴の産地
城下町が育んだ、音と工芸の融合文化
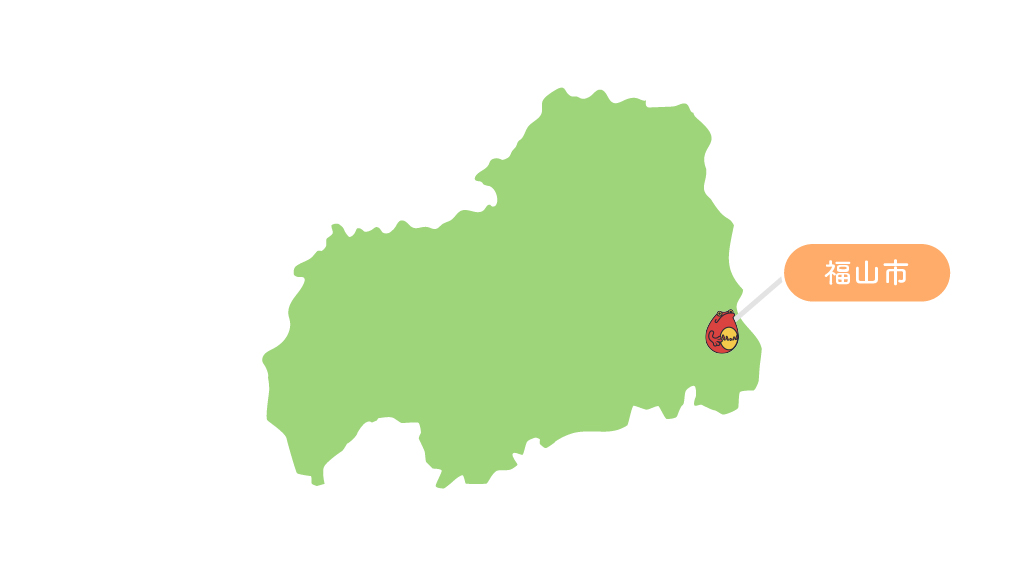
主要製造地域
福山琴の産地は、広島県福山市。瀬戸内海に面し、中国山地を背に持つこの地は、古来より交通の要衝として栄え、豊かな自然と文化が交差する地域です。
福山は1622年、水野勝成が築いた福山城を中心に城下町として整備されました。商人や職人が集い、工芸や音楽、茶道や華道といった諸芸も育まれた文化都市へと発展。こうした背景のなかで、琴づくりも自然に定着していきました。
また、福山は京都・大阪から箏曲や書画、漆芸などの上方文化が流入しやすく、特に幕末には葛原勾当をはじめとした箏の名手が当地に文化を持ち帰り、福山琴の芸術性を高める契機となりました。地元の人々の間でも琴は日常に根ざし、家庭での演奏や地域の催しで親しまれる存在となっていきました。
福山琴の歴史
江戸から全国へ、琴の音がつないだ伝承の系譜
福山琴は、400年以上にわたり地域の文化とともに発展してきた伝統工芸です。その歩みには、土地の人々と音楽への深い愛情が刻まれています。
- 1622年(元和8年):水野勝成が福山城を築城。城下町の整備とともに、琴づくりが始まる。
- 1700年代中頃:地元の神社仏閣や武家の嗜みとして琴の需要が広がり、職人が定着。
- 1800年代初頭:箏曲の流行とともに、地元の作曲家や演奏家が登場。文化として根付く。
- 1860年代(幕末):葛原勾当が京都から帰郷し、備後・備中で箏の演奏と指導を開始。門弟が増え、琴の文化と製作が広まる。
- 1870年代(明治初期):本格的な琴工房が設立され、産業としての琴づくりが軌道に乗る。
- 1910年代(大正時代):学校教育にも和楽器が導入され、需要が増加。
- 1970年代:最盛期を迎え、年間約3万面を製造。全国トップの生産地となる。
- 1985年(昭和60年):福山琴が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:生産数は減少するも、小型・軽量化、普及活動に注力し、日本一の座を維持。
福山琴の特徴
音に、意匠に、心を宿す桐の楽器
福山琴の魅力は、音色の深さ、工芸的な美しさ、そして手仕事の温かみにあります。最も特徴的なのは、用いられる素材とその加工法です。福山では、音響性に優れた最高級の桐材だけを使用し、製材から仕上げまでの大半を熟練職人の手で行います。
胴体部分「甲(こう)」の加工では、焼きと磨きで独特の艶を出し、木の目が際立つよう仕上げられます。また、「龍舌(りゅうぜつ)」や「磯(いそ)」と呼ばれる部位には、金蒔絵や焼印、真鍮製の金具が施され、美術品としての品格も備えています。
福山では軽量で扱いやすい小型琴も製作しており、学校教育や初心者向けとしても人気を集めています。地域ではコンクールや演奏会も開かれ、暮らしの中に琴の音が自然に溶け込んでいます。
福山琴の材料と道具
桐の目利きと磨きが生む、音の完成度
福山琴の製作には、原木選びから装飾に至るまで、熟練の目と手が求められます。木の音響特性と工芸的美しさを引き出すための、厳選された材料と道具が使われます。
福山琴の主な材料類
- 桐(キリ):軽量で反響性に優れた国産材。とくに会津・福島産の高級桐が使われる。
- 金具類:糸巻きや装飾部に用いる真鍮や銅合金製の細工金具。
- 蒔絵素材:金粉・銀粉などの加飾材。
福山琴の主な道具類
- 鋸(のこぎり):木材の荒取りに使用。
- 彫刻刀・鑿:龍舌や装飾部分を彫るための道具。
- ヤスリ・鉋(かんな):面取りや磨きに用いる。
- 蒔絵筆・焼きごて:装飾作業に使用。
こうした道具と材料を用い、五感と経験を頼りに、音の工芸品としての完成度を高めています。
福山琴の製作工程
音を育てる、五つの手仕事工程
福山琴の製作工程は、大きく五つに分かれ、それぞれが手仕事によって丁寧に行われます。1年〜3年という長い時間をかけて、音を育てるようにして一面の琴が生み出されます。
- 製材工程
原木の桐を選び、琴の形状に大まかに切り出す。 - 乾燥工程
1〜3年かけて自然乾燥。音の響きに大きく影響する重要な工程。 - 甲造工程
琴の胴体である「甲」を整形し、磨きや焼き加工を施す。 - 装飾工程
蒔絵や金具、焼き印を施し、美術工芸品としての品格を整える。 - 仕上げ工程
組み立て・検査を経て、音の調整と最終確認を行い完成。
完成した琴は、音楽的な品質のみならず、見た目の美しさや耐久性にも優れ、芸術品として長く愛される一品となります。
福山琴は、素材・技術・意匠のすべてにおいて高い完成度を誇る日本の伝統楽器です。城下町の文化と自然の恵みが生んだその音色は、今も人々の暮らしの中で静かに響き続けています。次世代への継承とともに、手仕事の温もりを未来へとつないでいく工芸品です。