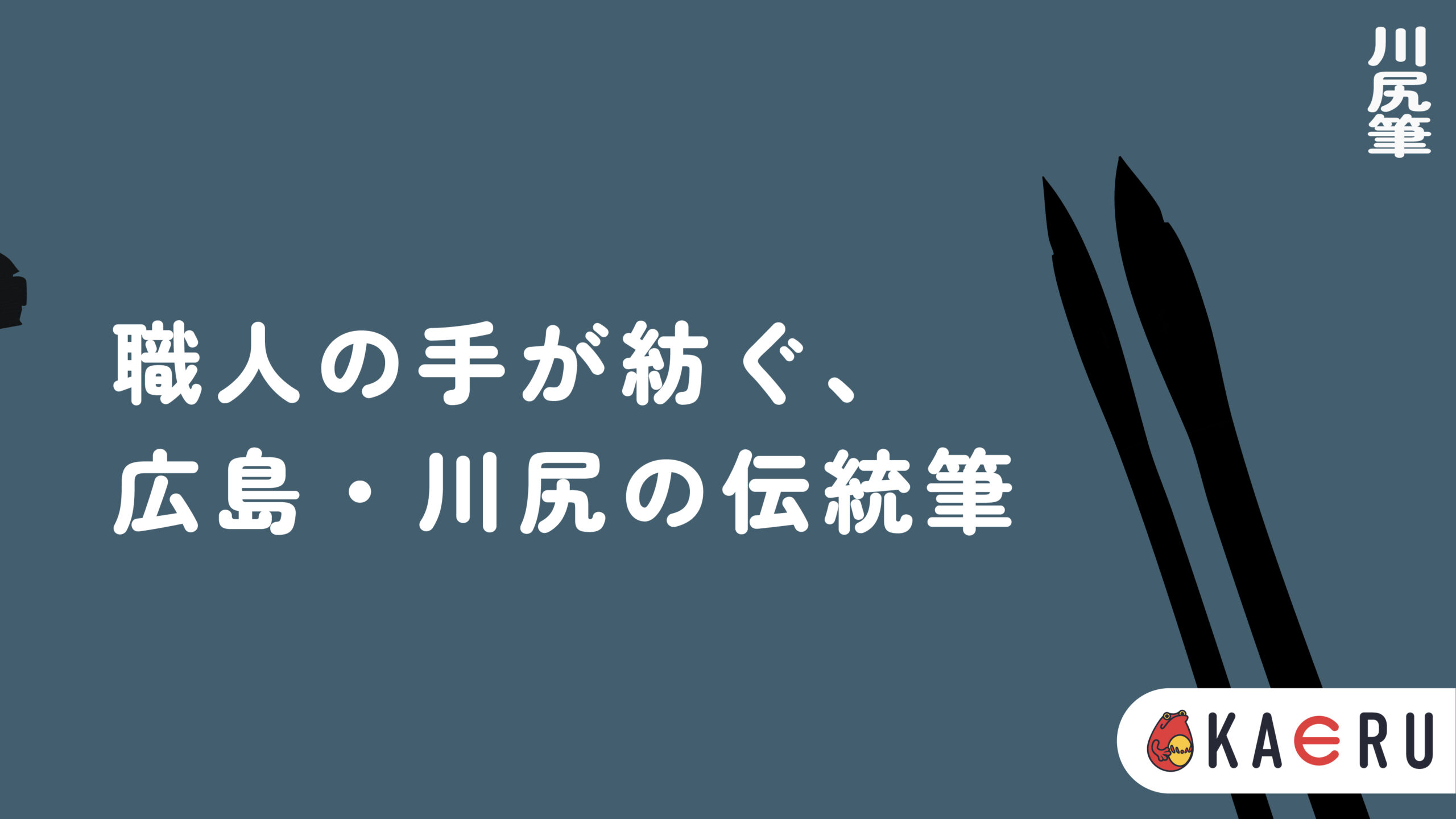川尻筆とは?
川尻筆(かわじりふで)は、広島県呉市川尻町で作られている高級筆です。江戸時代末期に上野八重吉(うえの やえきち)によって製法が伝えられたとされ、現在も「ねりまぜ」と呼ばれる独自技法を用いた一本筆の製造が受け継がれています。
川尻筆最大の特徴は、穂先の材料を複数種類混ぜ合わせ、あたかも一本の毛から成るかのように均一で滑らかな穂先をつくる「ねりまぜ」技法にあります。この精緻な技術によって、墨含み・穂先の弾力・筆運びのバランスに優れた逸品が生まれます。
工程のすべてを一人の職人が担うのも川尻筆の特徴。穂首づくりから軸付け、仕上げに至るまで、筆一本一本に職人の技術と美意識が凝縮されています。
| 品目名 | 川尻筆(かわじりふで) |
| 都道府県 | 広島県 |
| 分類 | 文具 |
| 指定年月日 | 2004(平成16)年8月31日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 4(5)名 |
| その他の広島県の伝統的工芸品 | 宮島細工、広島仏壇、熊野筆、福山琴(全5品目) |

川尻筆の産地
瀬戸内の恵みと筆文化が息づく、広島・川尻町
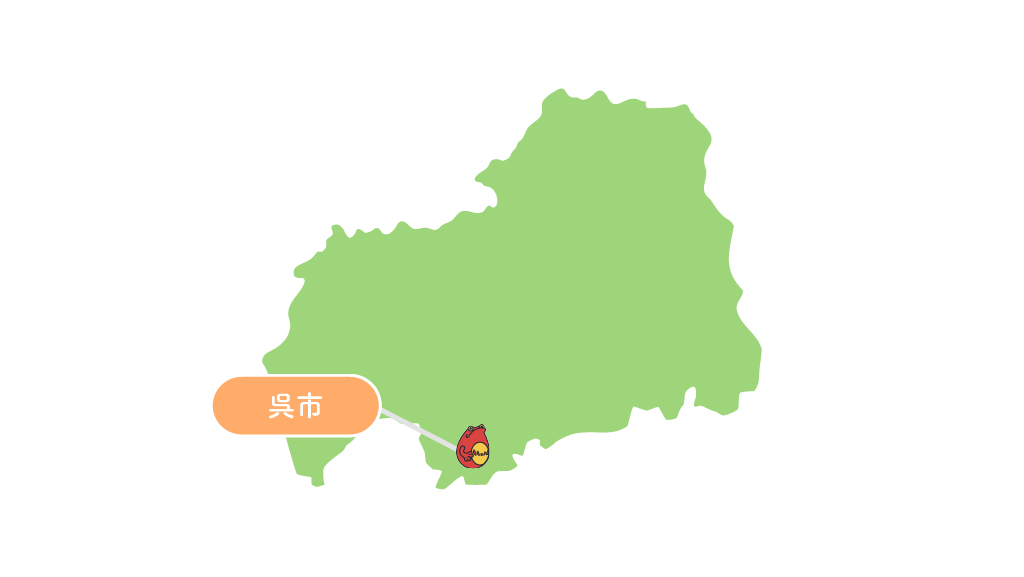
主要製造地域
川尻筆の主産地である広島県呉市川尻町は、瀬戸内海沿いに位置する温暖で湿潤な気候を持つ地域です。この穏やかな気候は、動物毛や竹といった筆の素材の保管・乾燥に適しており、筆製作に理想的な環境を提供しています。
江戸時代後期から明治にかけて、広島藩の商業・流通の拠点として発展した町であり、製筆業もその中で育まれました。近隣には熊野筆で知られる熊野町があり、筆づくりの技術や文化が交流しながら広がっていった背景も見逃せません。
さらに、町には筆に関する神社や資料館も存在し、筆づくりの歴史と精神性を地域全体で守る姿勢が色濃く見られます。まさに川尻町は、筆という道具を単なる消耗品ではなく、工芸と文化の象徴として扱うまちであり、そのことが川尻筆の品質と精神性に深く結びついています。
川尻筆の歴史
筆とともに歩んだ、川尻町の職人精神
川尻筆は、およそ150年以上の歴史を持つ伝統工芸です。その技術と文化は、時代の流れとともに磨かれ、受け継がれてきました。
- 1865年頃(江戸時代末期):上野八重吉が川尻で筆づくりを始める。熊野筆の技術をもとに独自の製法を模索。
- 1877年(明治10年):地域内で製筆業が広がり、家内制手工業として発展。
- 1890年代(明治後期):ねりまぜ技法の技術が確立し、品質の高い筆として評価が高まる。
- 1926年(大正15年):川尻町内に複数の筆工房が誕生。出荷量が拡大。
- 1955年(昭和30年):全国的な書道ブームにより、需要が急増。学校用筆の製造も本格化。
- 2004年(平成16年):川尻筆が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:書道筆に加え、化粧筆や絵筆などへの応用も進む。若手職人の育成も強化されている。
川尻筆の特徴
ねりまぜが極める、一本筆の真価と美しさ
川尻筆の最大の特徴は、穂先の内部に複数の毛を練り合わせて配列する「ねりまぜ技法」にあります。一見すると一本の毛のように見える穂先は、実は太さや性質の異なる毛を職人が手で緻密に揃えた集合体であり、筆の“芯”ともいえる構造が巧みに作られています。
たとえば、中心には弾力のあるイタチ毛を用いて筆のコシを保ち、外側に柔らかな羊毛を配することで墨の含みをよくする、といった設計が可能です。この「芯のある穂先」は、筆運びの安定性と筆勢の表現力を両立させ、初心者から書家に至るまで高い信頼を得ています。
完成した筆は「立てて置く」のが正式とされています。穂先を下にして保管することで、毛が整い、次回の使用時も心地よい書き味を保つことができるのです。
川尻筆の材料と道具
毛と竹が響き合う、筆づくりの緻密な手仕事
川尻筆の製作には、毛の選定から軸材、接着までに高度な知識と感覚が必要とされます。素材はすべて天然由来で、機能と美観を両立させる素材が選ばれます。
川尻筆の主な材料類
- イタチ毛:コシが強く、墨含みも良好。細字用に適する。
- 羊毛:柔らかく墨を多く含む。行書・草書に向く。
- 鹿毛:張りがあり耐久性に優れる。中太筆などに使用。
- 竹:国産の真竹を使用。節の美しさや手触りの良さが求められる。
川尻筆の主な道具類
- 櫛(くし):毛を揃えながら異物を取り除くための道具。
- 糸掛け台:毛を束ね、穂先を整形するための専用台。
- 火入れ器:根元を固めるために接着剤を加熱する装置。
- 接着剤(にかわ):天然の膠(にかわ)を使用し、毛を固定する。
これらの道具と材料を駆使し、一本の筆に命を吹き込むのが川尻の職人たちです。
川尻筆の製作工程
ねりまぜの妙技、全工程を一貫して一人で担う匠の道
川尻筆の製作は、その一つひとつが、筆の性能と美しさを左右する重要な要素です。
- 毛の選別・洗浄
イタチ・羊・鹿などの毛を産地・個体ごとに分類し、不純物を洗い落とす。 - ねりまぜ
異なる毛質を混ぜて最適な筆質を作る。川尻筆特有の工程。 - 毛揃え・櫛通し
穂先の太さと長さを均一に整える。 - 糸掛け・成形
毛束に糸を巻いて形を整える。 - 火入れ・膠付け
毛束の根元ににかわを入れ、接着固定する。 - 乾燥
自然乾燥させて固める。 - 軸付け
乾いた穂首を竹軸に装着する。 - 仕上げ・検品
穂先の形状を最終調整し、筆全体のバランスを整える。
一本の筆にかけられる時間は数日〜数週間。まさに筆一本が“作品”とも言える、川尻ならではの職人芸の極みです。
完成した川尻筆は、書道家の手に渡って文字に命を与え、画家の筆先で情景を描き出す。伝統に裏打ちされた技術と、筆一本に込められた誠実な手仕事は、今もなお静かな輝きを放ち続けています。