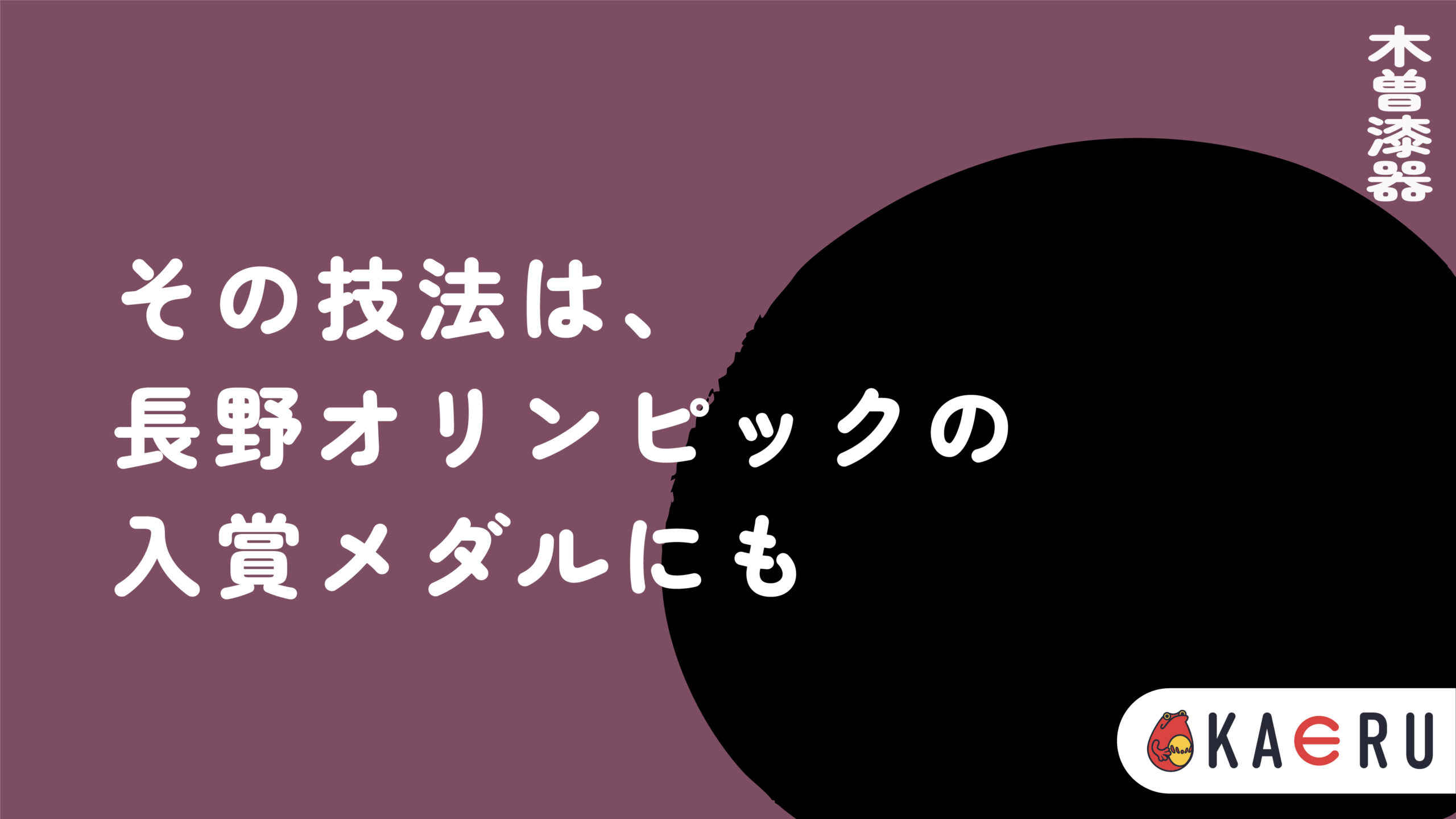木曽漆器とは?
木曽漆器(きそしっき)は、長野県南西部の木曽地方を中心に生産される伝統的な漆器で、その起源は約400年前の江戸時代初期にさかのぼります。地元産の木曽ヒノキやカツラ、トチなどを用いて木地を作り、漆を何度も塗り重ねて仕上げるのが特徴です。
代表的な技法として、木目の美しさを活かす「木曽春慶」、漆を幾重にも重ねて模様を浮かび上がらせる「木曽堆朱」、異なる色の漆を塗り分ける「塗分呂色塗」などがあり、用途や美意識に応じた多彩な仕上がりを見せます。近年では家具やインテリアにも展開され、環境にやさしい天然素材による製品としても注目されています。
| 品目名 | 木曽漆器(きそしっき) |
| 都道府県 | 長野県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 22(90)名 |
| その他の長野県の伝統的工芸品 | 信州紬、飯山仏壇、内山紙、南木曽ろくろ細工、松本家具、信州打刃物(全7品目) |

木曽漆器の産地
ヒノキに恵まれた信州・木曽の山あいの地域

主要製造地域
木曽漆器の産地は、長野県南西部の塩尻市、木曽町、松本市など、高地に位置する木曽地方に広がっています。この地域は、木曽ヒノキなど良質な木材の産地であるとともに、うるし塗りに適した涼しい夏と厳しい冬の気候条件を備えています。
古くから中山道の宿場町として人の往来が多く、木曽漆器は土産品としても人気を集め、日本各地に広まりました。現在も木曽平沢をはじめとする職人の町で、伝統を守りながら制作が続けられています。
木曽漆器の歴史
土と木が育んだ、丈夫で美しい漆器の歩み
木曽漆器の歴史は、信州・木曽の自然と職人たちの知恵が織りなす営みの積み重ねでもあります。良質な木材と漆、さらに土の資源を活かして生まれたこの漆器は、地域の暮らしに根ざしながら発展してきました。
- 17世紀(江戸時代初期):尾張徳川藩の保護を受け、木曽地方で漆器づくりが盛んになる。
- 江戸時代中期:中山道の発展とともに、木曽漆器が土産物として全国に知られる。
- 明治時代初期:塩尻市楢川地区で鉄分を多く含む「錆土(さびつち)」が発見され、下地強度が飛躍的に向上。
- 昭和初期:家具や建具などの大型製品にも応用され、塗装技術が高度化。
- 1975年(昭和50年):木曽漆器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:三種の伝統技法を継承しつつ、テーブルウェアや現代建築向けの漆塗装など新たな展開が進む。
木曽漆器は、自然の資源と地域の知恵が融合した生活工芸品として、時代を超えて人々の暮らしに彩りを添えています。
木曽漆器の特徴
自然素材と伝統技法が生む、暮らしに根ざす美
木曽漆器の魅力は、天然木の温もりを活かした木地と、使い込むほどに艶を増す漆塗りにあります。特に、以下の3つの伝統技法がその魅力を際立たせています。
- 木曽春慶:透明な漆を摺り込むことで木目を際立たせ、軽やかで明るい印象に仕上げる。
- 木曽堆朱:朱や黒などの色漆を12回以上重ね塗りし、磨き出してまだら模様を浮かび上がらせる。
- 塗分呂色塗:異なる色の漆を幾何学模様などで塗り分け、シャープで現代的な印象を与える。
いずれの技法にも共通するのは、自然素材のみを使い、環境に配慮した製法であることです。使用される顔料や筆、布、粉類に至るまで、すべてが自然由来。木曽の山々の恵みと職人の手しごとが融合した、美と実用性を兼ね備えた漆器です。

木曽漆器の材料と道具
木曽の森と土から生まれた、漆器づくりの素材と道具
木曽漆器の製作には、豊かな木曽の自然がもたらす素材と、繊細な作業を支える伝統の道具が用いられます。
木曽漆器の主な材料類
- 木曽ヒノキ・カツラ・トチ:器の木地に使われる高品質な木材。
- 生漆(きうるし):木の樹液から採取される塗料。
- 錆土(さびつち):下地に使われる鉄分を含んだ土。
- 顔料・油・炭粉・米粉:漆の調合や着色、下地強化に用いられる。
木曽漆器の主な道具類
- 木地師の道具:ノコギリ・カンナ・木工旋盤など。
- 塗師の道具:刷毛・タンポ(布団のような塗布具)・ヘラなど。
- 研磨具:炭粉・砥石・研磨紙など。
- 蒔絵や沈金の道具:細筆・彫刻刀・金粉振り器など。
これらの素材と道具によって、手間を惜しまず仕上げられる木曽漆器は、まさに“使う芸術品”としての価値を体現しています。
木曽漆器の製作工程
30以上の工程を積み重ね、木と漆が一体となるものづくり
木曽漆器は、木地づくりから塗り、磨きまで30以上の工程を重ねて完成します。木と漆、それぞれの持ち味を最大限に引き出すため、一つひとつの作業が丁寧に行われ、使うほどに艶と味わいが増す器が生まれます。
- 木地づくり
よく乾燥させた木材を選び、器の形状に加工する。 - 下地塗り
木地を研磨し、生漆と錆土を混ぜた下地を塗る。乾燥後に研磨する。 - 中塗り
複数回に分けて漆を塗布・乾燥させる。ホコリの付着を防ぎながら丁寧に塗る。 - 上塗り(仕上げ)
色漆を塗り重ね、模様や艶を調整しながら最終仕上げを行う。
工程の多くは高度な手仕事に支えられており、一品一品に職人の感性と熟練が込められています。
こうして仕上げられる木曽漆器は、自然素材の温もりと職人の技が融合した“用の美”の結晶です。日常の食卓から特別な場面まで、長く寄り添い続ける器として、その価値は時を経ても色あせません。