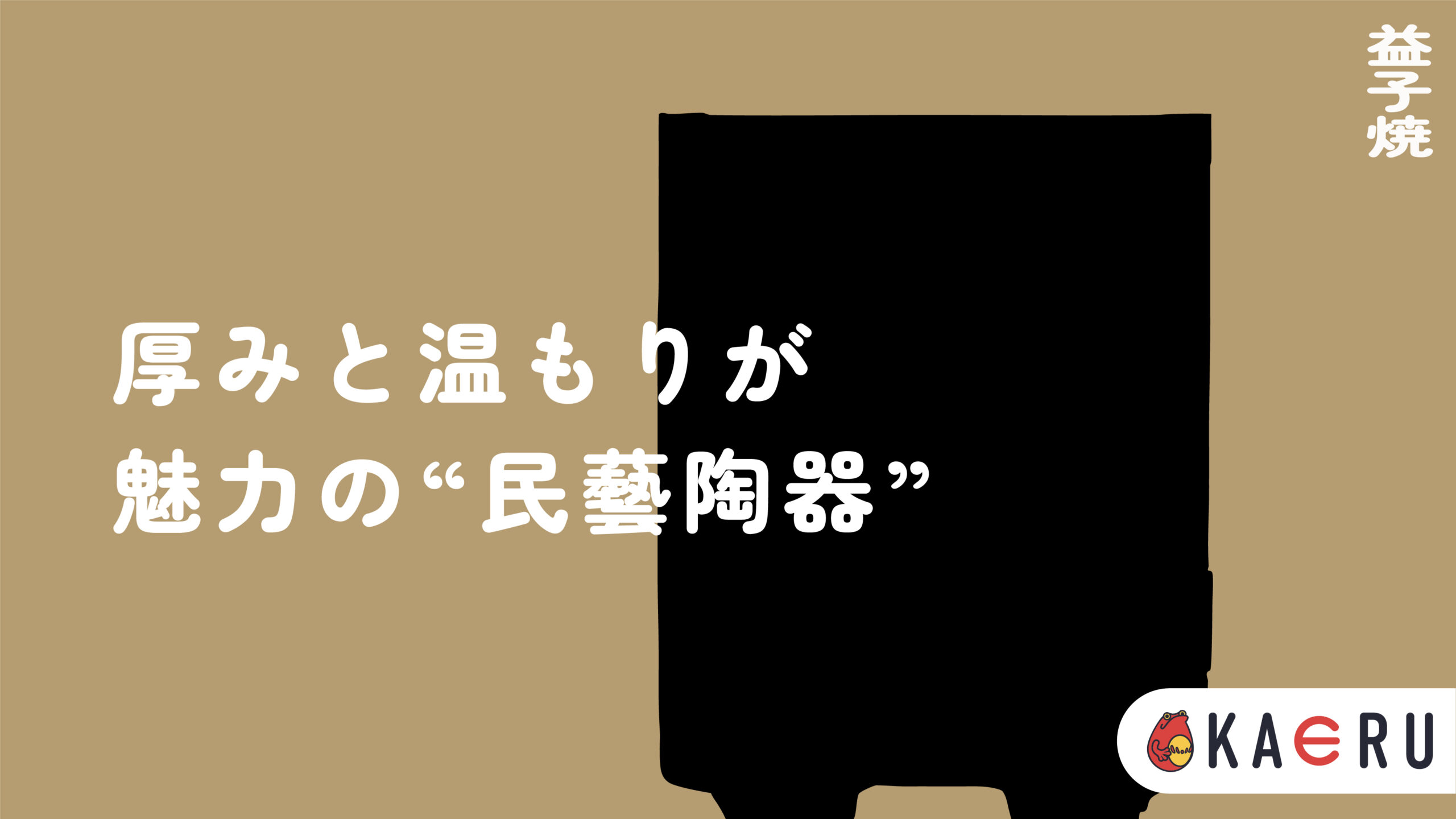益子焼とは?
益子焼(ましこやき)は、栃木県益子町を中心に生産されている伝統的な陶器です。江戸時代末期に笠間焼から技術を受け継いで始まったとされ、素朴で厚みのある形と、落ち着いた色彩をもつ日常使いの器として親しまれてきました。
そして1920年代、濱田庄司がこの地に移住し、民藝運動の旗手として益子焼の美を世界に知らしめたことで、実用性と芸術性をあわせ持つ“使う美術”として新たな価値を獲得します。今日では、伝統の中に現代の感性を取り入れた多様な作家たちの作品が集い、民藝の精神を未来へと受け継いでいます。
| 品目名 | 益子焼(ましこやき) |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1979(昭和54)年8月3日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 14(27)名 |
| その他の栃木県の伝統的工芸品 | 結城紬(全2品目) |

益子焼の産地
山間の自然と共に生きる

益子町は栃木県南東部に位置し、緑豊かな里山と肥沃な土壌に恵まれた土地です。この地域には陶器に適した新福寺粘土と呼ばれる良質な陶土が多く分布しており、古くから窯業に適した環境が整っていました。また、登り窯の燃料として用いられる松林が近くにあるなど、自然資源との共生のなかで発展してきた背景もあります。
益子は、今も多くの陶芸家や工房が点在し、「益子陶器市」などを通じて来訪者と直接触れ合える陶の町として親しまれています。
益子焼の歴史
笠間から伝わり、民藝が育てた陶の文化
益子焼のはじまりは、江戸時代末期、笠間焼で修行を積んだ陶工・大塚啓三郎が、益子の地に窯を築いたことにさかのぼります。彼は笠間焼の技術に加え、信楽焼や相馬焼の技法も取り入れ、地域に根ざした焼き物文化の礎を築きました。
- 19世紀中頃(江戸時代末期):大塚啓三郎が益子に窯を構え、焼き物の生産を開始。水がめやすり鉢などの日用品が中心。
- 明治時代:黒羽藩による保護を受け、関東一円へと販路を拡大。
- 1924年(大正時代):民藝運動の提唱者・濱田庄司が益子に移住。民藝陶器としての価値が見直され、全国から若い陶芸家が集まる。
- 1979年(昭和54年):益子焼が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:地元住民と陶芸家の連携によって、春・秋の「益子陶器市」が開催され、全国的な人気を誇る産地へと成長。
濱田庄司の活動は特に大きく、民藝という美意識を国内外に紹介し、益子焼の名声を高めた立役者となりました。
益子焼の特徴
厚みと素朴さが生み出す“用の美”
益子焼は、やや分厚く、丸みを帯びた素朴なフォルムが特徴で、ろくろによる成形を基本としつつも、石膏型を用いた量産技法なども取り入れています。その魅力は、どこか不揃いで人間味のある仕上がりにあり、生活に溶け込む器として根強い人気を誇ります。
装飾には、白化粧・刷毛目・イッチン描きなどの手法が用いられ、釉薬には柿釉・糠白釉・青磁釉・並白釉・本黒釉といった伝統色が流し掛けや浸し掛けによって施されます。これにより、一つひとつ表情の異なる器が生み出されます。その結果、益子焼は、実用性と美術性を兼ね備えた“民藝陶器”として、暮らしの中に自然な彩りをもたらしてくれるのです。

益子焼の材料と道具
自然素材が息づく民藝陶器
益子焼の魅力は、素朴な風合いの背後にある、自然素材と職人技の融合にあります。地元の粘土と釉薬、そして昔ながらの手道具が、益子焼独特の温かさを支えています。
益子焼の主な材料類
- 陶土:新福寺粘土を中心とした、益子町周辺で採れる粘り気のある土。成形しやすく、分厚い成形に適している。
- 釉薬:柿釉、糠白釉、青磁釉、並白釉、本黒釉など。天然の灰や赤粉を用いた独自の色合いが特徴。
- 化粧土:白化粧用の白土。器の表面に刷毛で塗ることで風合いを演出する。
益子焼の主な工具類
- 手ろくろ・電動ろくろ:成形の中心をなす道具。用途に応じて使い分けられる。
- 石膏型:量産型成形に用いられる型枠。皿や鉢などで活用。
- はけ・スポイト:白化粧や釉薬の塗布に使う。
- のみ・カンナ:表面装飾や形の整形に用いられる。
- 登り窯・電気窯・ガス窯:焼成方法に応じて使い分けられる。
素材の力を引き出すこれらの材料と道具の存在が、益子焼の手仕事としての魅力を際立たせています。
益子焼の製作工程
民藝の精神を継ぐ丁寧なものづくり
- 土練り(荒練り・菊練り)
益子焼協同組合で精製された陶土を荒練りし、手作業で菊練りして空気を抜く。 - 成形
主に電動ろくろを使用し、形をつくる。型成形や手びねりも併用。 - 乾燥
成形後は室内で陰干ししたのち、天日でさらに乾燥させる。 - 素焼き
700〜800度で一度焼き、強度を高める。 - 装飾・釉掛け
刷毛目、白化粧、イッチンなどの装飾を施し、釉薬をかける。 - 本焼き
1200〜1300度で焼成。焼き上がった器は2日ほどかけて冷まし、窯から取り出す。
焼成方法や釉薬の選択、装飾の有無により、一つとして同じものはない個性的な作品が生まれます。
益子焼は、豪華さや技巧を競うのではなく、使い手の暮らしに馴染む器であり続けることを美としています。濱田庄司が見出した「用の美」の精神は、現在の作り手たちにも受け継がれ、多くの若手陶芸家が自由な発想で新たな表現を生み出しています。自然素材と人の手による素朴な温もり。それが、益子焼という器に息づく、日本の美のひとつのかたちなのです。