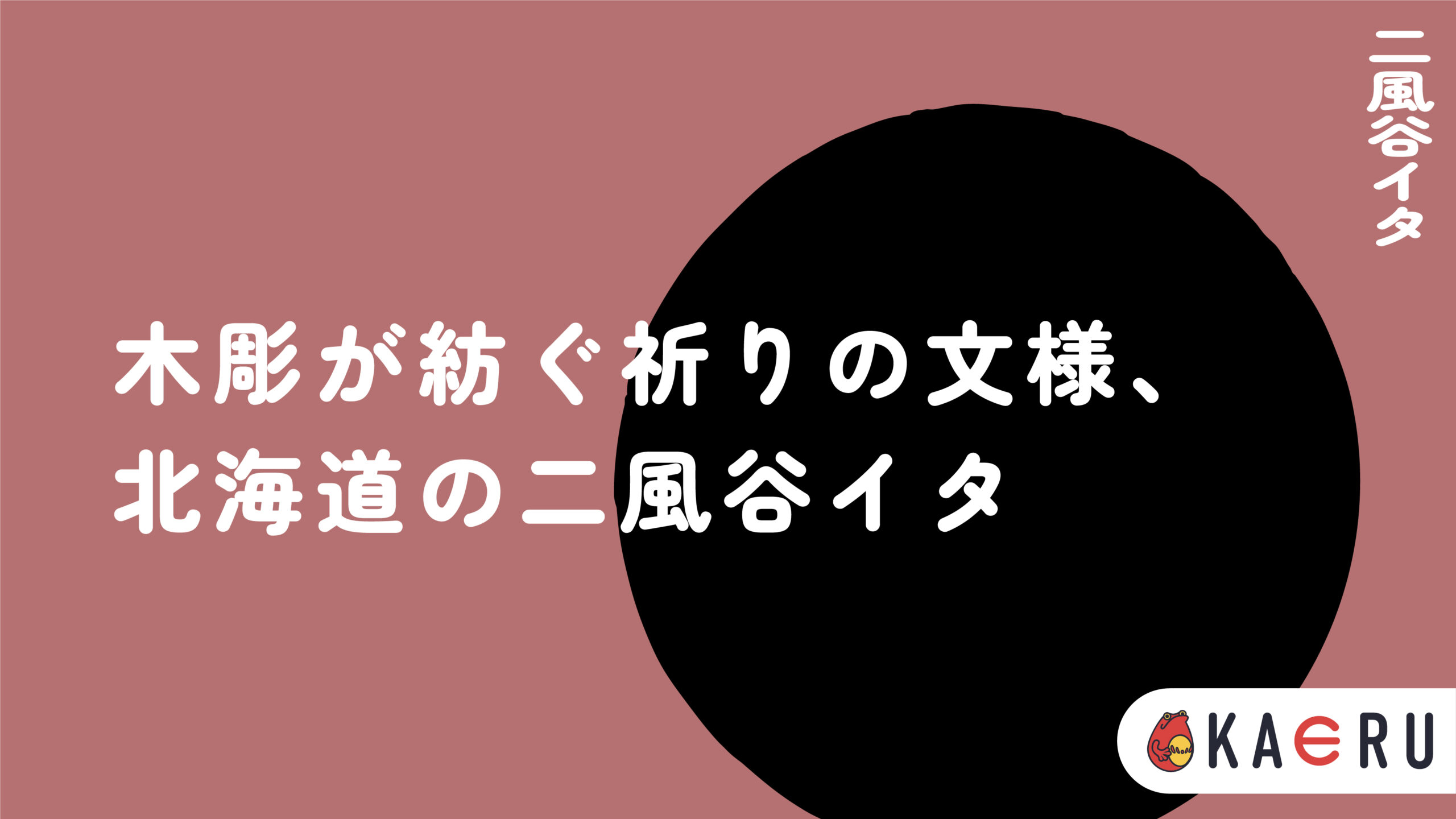二風谷イタとは?
二風谷イタ(にぶたにいた)は、北海道沙流郡平取町の二風谷地区を中心に伝承されてきた、アイヌ民族の木工芸品です。「イタ」とはアイヌ語で「盆」を意味し、主にクルミやカツラといった北海道産の広葉樹から作られる平たい木盆を指します。
その最大の特徴は、盆の表面に彫刻されるアイヌ伝統の抽象文様にあります。幾何学的な形状の中に自然観や精神性が込められた意匠は、かつて祭具や贈答品としても用いられ、単なる日用品を超えた「祈りの器」としての役割を果たしてきました。
| 品目名 | 二風谷イタ(にぶたにいた) |
| 都道府県 | 北海道 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 2013(平成25)年3月8日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(1)名 |
| その他の北海道の伝統的工芸品 | 二風谷アットゥㇱ(全2品目) |

二風谷イタの産地
自然と精神が共鳴する、アイヌ文化のふるさと

二風谷イタの産地である北海道平取町・二風谷地区は、北海道南西部、日高地方の内陸に位置し、沙流川(さるがわ)の清流が流れる風光明媚な地域です。この「二風谷(にぶたに)」という地名は、アイヌ語の「ニプタイ(木の生い茂るところ)」に由来し、その名のとおり、古来より豊かな森林資源に恵まれてきました。
アイヌ民族が自給自足の生活を営んできた地であり、木工や織物、漆器などの技術が生活と密接に結びついて発展しました。特に沙流川流域は、儀礼具や贈答品に用いられる工芸品の産地としても知られ、アイヌ文化の精神的・物質的中心地のひとつとされています。
また、口承文芸や舞踊、歌、衣装文様などと並び、木彫の文様文化が深く根付いています。盆に刻まれる抽象的な模様には、自然への畏敬や霊的な信仰が込められており、これはアイヌの世界観そのものが可視化された造形だと言えるでしょう。
気候的には、冷涼で積雪も多く、木材の伐採・乾燥にとって時間をかけた管理が必要な環境です。しかしそのぶん、ゆっくりと自然乾燥させることで木目の美しさや安定性が高まり、精緻な彫刻に適した木材が得られます。こうした自然条件と精神文化が交差する場でこそ、二風谷イタのような独自の工芸が育まれてきたのです。
二風谷イタの歴史
100年を超えて継承される、交流のかたち
二風谷イタの歴史は、地域に根ざした生活文化と、外部との交流を通じて磨かれてきました。
- 18世紀後半(江戸中期):沙流川流域で木彫盆の使用が一般化。日常食器や儀礼具として普及。
- 1853年(嘉永6年):平取の半月盆・丸盆が幕府に献上された記録が残る。工芸品としての認知が高まる。
- 1873年(明治6年):ウィーン万国博覧会に出品。国際舞台でアイヌ文化が紹介される契機に。
- 1930年代(昭和初期):農耕定住化が進み、儀礼用具としての使用が減少。工芸としての転換点を迎える。
- 1970年代(昭和中期):アイヌ文化再評価の動きの中で、工芸の技術継承が地域で始まる。
- 1992年(平成4年):二風谷アイヌ文化博物館が開館。地域文化の復興と伝承が本格化。
- 2013年(平成25年):二風谷イタが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。北海道初の指定品目となる。
- 2020年代以降:国内外の民芸展・アートフェアで再評価が進み、現代的な表現にも挑戦が見られる。
こうした動きのなかで、地域の教育機関やアイヌ文化振興施設による後継者育成が進み、近年では国内外の工芸展や民俗学的研究でも注目されています。
二風谷イタの特徴
文様が映し出す、自然との共生と精神性
二風谷イタの魅力は、その表面に刻まれるアイヌ文様に凝縮されています。文様は装飾であると同時に、祈り、護符、物語の象徴でもあります。幾何学的で抽象的なそれらの模様は、ただ美しいだけでなく、アイヌの精神性や自然観を表現するための“言語”のような役割を果たしているのです。
「モレウノカ」は渦巻き状の曲線で、川の流れや時間の循環を表し、「アイウシノカ」は棘のような形で、邪気を祓う意味があります。「シクノカ」は目を表し、神々の視線や見守りを意味し、「ラムラムノカ」は魚の鱗や葉の重なりを想起させる繰り返し文様で、命の連なりや豊穣を象徴します。
これらの文様は、職人が下描きなしに彫ることも多く、まさに“手が覚えた祈り”とも言えるもの。さらに、「模様の読み方」によってその解釈や意味が変わることもあり、使用者が感じるままに読み取る自由さも持ち合わせています。
また、二風谷イタは必ず「底面」から彫り始めます。これは“支え”を整えてから“装い”に移るという、生活哲学の表れとも言われています。

二風谷イタの材料と道具
木と文様の声を聴く、繊細な素材と彫刻技法
二風谷イタの製作は、木の選定と乾燥から始まり、彫刻に至るまでの全工程において、自然への理解と職人の感性が求められます。
二風谷イタの主な材料類
- クルミ:滑らかな木肌と適度な硬さをもつ、代表的な木材。
- カツラ:木目が緻密で加工しやすく、文様彫刻に適する。
二風谷イタの主な工具類
- 包丁:底彫り用に使う先平の刃物。力加減と均一さが求められる。
- 三角刀:文様の輪郭線を彫る際に用いる。精密な線彫りに必須。
- 丸のみ:文様に立体感を加えるための面彫り用工具。
木材は3〜4年かけて乾燥させたものを使用し、含水率や反りを抑えたうえで加工します。工具の使い分けと力のコントロールにより、滑らかで美しい彫刻面が生まれます。
二風谷イタの製作工程
木に文様を宿す、祈りの造形工程
二風谷イタの制作は、素材の吟味から彫刻、仕上げまで一貫して手仕事で行われます。各工程において木と文様に向き合う丁寧な作業が重ねられます。
- 木地の乾燥・板取り
3〜4年自然乾燥させたクルミやカツラを板状に加工。 - 荒彫り・整形
包丁で盆の底を彫り、裏面の角を面取りして滑らかに整える。 - 図案構成
モレウノカ・アイウシノカ・シクノカ・ラムラムノカの4種を組み合わせて構図を決定。 - 輪郭彫り
三角刀で文様の外枠を線彫りする。緊張感のある一手一手が要求される。 - 立体彫り
丸のみで模様を立体的に彫り出し、細部に陰影と奥行きを加える。 - 仕上げ・調整
全体の彫りの深さや連続性を調整し、手触りと陰影のバランスを整える。
こうして完成した二風谷イタは、光を浴びる角度や手に取る感触で表情が変わり、使うほどに味わいを深めていく“生きた盆”として、今も人々の暮らしに息づいています。
二風谷イタは、北海道平取町の自然とアイヌ文化が融合して生まれた祈りの工芸品です。繊細な彫刻文様には、自然への畏敬や精神性が込められ、使う人それぞれの手で物語が刻まれていきます。暮らしと信仰が共鳴する器として、今もなお静かに受け継がれています。