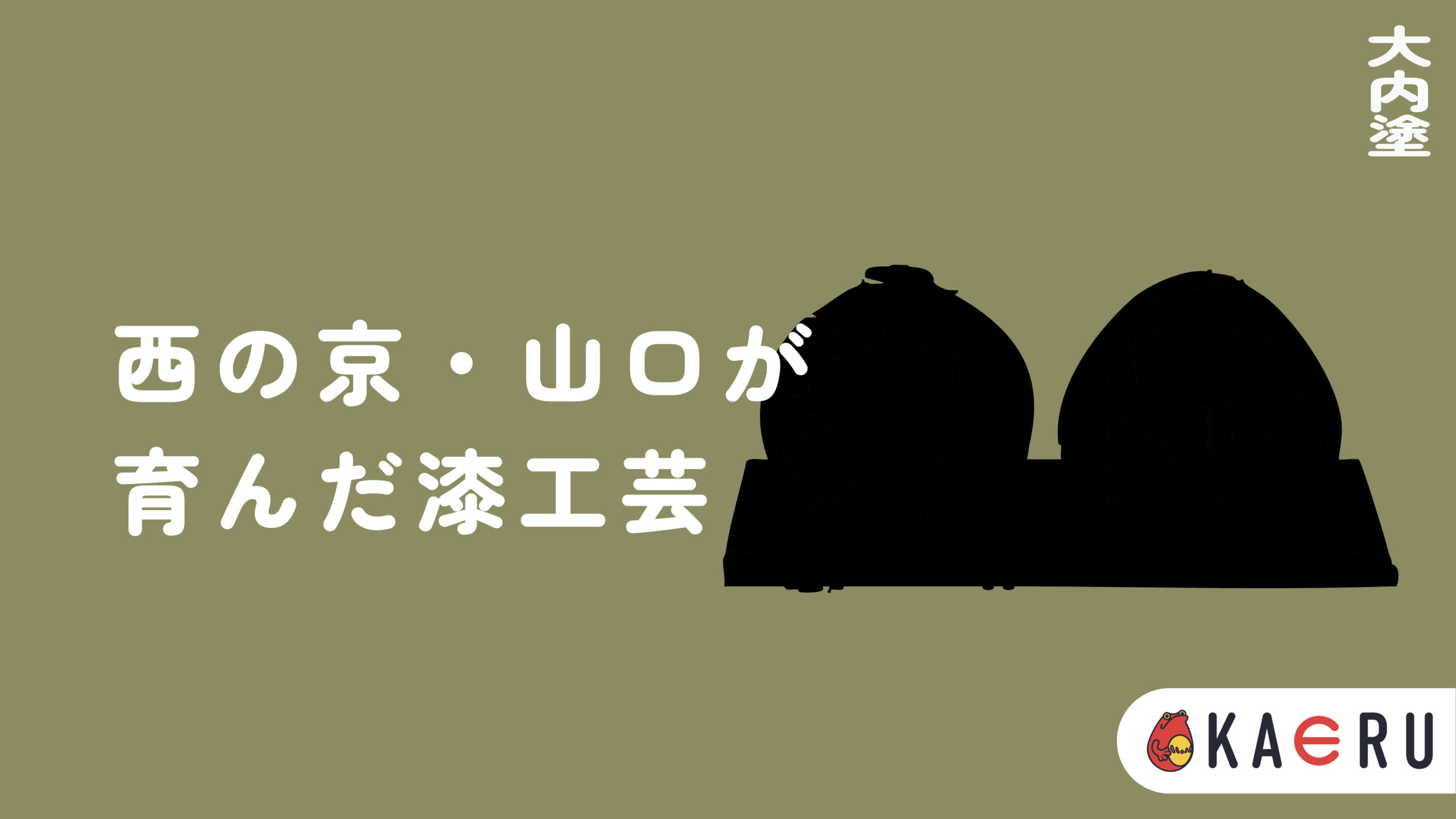大内塗とは?
大内塗(おおうちぬり)は、山口県山口市を中心に作られている伝統的な漆器工芸です。起源は室町時代にさかのぼり、当時西国の雄として栄華を極めた大内氏の保護のもと、貿易品や献上品として発展しました。その最大の魅力は、漆黒の下地に重ねられる赤や金、螺鈿などの装飾技法が織りなす、華やかで気品ある意匠にあります。特に、男女一対の人形を漆で仕上げた「大内人形」は全国的にも有名で、大内塗の象徴的存在といえるでしょう。
現在では、盆や椀、重箱といった実用漆器のほか、飾り人形や工芸品としても高い芸術性を誇り、贈答品や観光土産としても親しまれています。
| 品目名 | 大内塗(おおうちぬり) |
| 都道府県 | 山口県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1989(平成元)年4月11日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(1)名 |
| その他の山口県の伝統的工芸品 | 萩焼、赤間硯(全3品目) |

大内塗の産地
西の京・山口が育んだ、漆工芸の雅
大内塗の主産地である山口県山口市は、かつて「西の京」と称されるほどに京都文化が色濃く反映された町です。室町時代、大内氏は京都との交流を活発にし、京の宮廷文化や唐物文化を積極的に取り入れてきました。能・茶の湯・連歌・水墨画などの文化がこの地に根づき、漆工芸もその中で発展しました。特に、大内氏当主の大内義興・義隆らは文化庇護に熱心で、都から蒔絵師や彫金師を招聘していたと伝えられています。
気候的にも、山口市は比較的温暖で湿潤な気候に恵まれており、漆の硬化に不可欠な「むろ(乾漆棚)」での乾燥作業が安定して行いやすい環境にあります。これは、漆器産地として非常に有利な条件であり、漆塗り文化の根づきを後押しする要因となってきました。
さらに、近隣に良質な木材を供給できる地域があったことや、日本海側と瀬戸内海側を結ぶ地理的立地から、交易と情報の要衝としての役割も果たしており、文化と物資の流入が漆器文化の成熟を支えたと考えられます。
大内塗の歴史
大内文化に育まれた、漆芸と人形の物語
大内塗は、室町時代から山口の地で連綿と受け継がれてきた伝統の漆器です。その歩みは、歴代の大内氏の文化政策と密接に関わっています。
- 1370年代(南北朝期):大内弘世が山口に本拠を移し、京風都市整備を進める。
- 1400年代初頭(応永年間):大内盛見の時代、日明貿易が盛んになり、漆器が貿易品・献上品として重用される。
- 1440年代(嘉吉年間):大内教弘が京都の蒔絵師・絵師を山口に招き、工芸振興を図る。
- 1500年代前半(永正〜大永年間):大内義興・義隆による文化保護が最高潮に達し、大内塗の装飾性が高度に発展。人形漆器の原型が現れる。
- 1551年(天文20年):大寧寺の変で大内義隆が討たれ、大内氏滅亡。職人たちは民間に移り、庶民の間に技術が継承される。
- 1700年代(江戸中期):婚礼道具・祝い品として大内塗が山口地域で定着。人形漆器が「大内人形」として定型化。
- 明治時代:観光・土産品として注目され、販路が拡大。
- 1930年代(昭和初期):意匠の多様化が進み、実用漆器と人形工芸が二軸で展開。
- 1989年(平成元年):大内塗が経済産業大臣より「伝統的工芸品」として指定される。
- 現代:現代のライフスタイルや海外需要に応じた作品も登場し、漆器の芸術性が再評価されている。
大内塗の特徴
紅と黒が紡ぐ、優雅な色彩と文様の調和
大内塗の魅力は、何層にも塗り重ねられた漆の艶やかさと、赤・黒・金・螺鈿といった多彩な装飾の調和にあります。漆黒の下地に朱漆が浮かび上がるような技法は、見る角度や光の加減によって表情が変化し、静謐な華やかさを演出します。意匠には、松竹梅・鶴亀・桐紋・雲鶴・宝尽くしなどの縁起物が用いられ、装飾の随所に吉祥の意味が込められています。これらは婚礼や長寿祝いなど、人々の人生の節目を彩るものとして重用されてきました。
象徴的な存在である「大内人形」は、古来より山口で嫁入り道具のひとつとして扱われており、夫婦円満や家内安全の祈願が込められた品です。その姿は、男性が束帯姿、女性が十二単風で、顔の穏やかな微笑みや衣装の金彩が、見た者の心に和やかさをもたらします。

大内塗の材料と道具
漆と木が織りなす、精緻な手技と色彩の世界
大内塗は、木地作りから漆塗り、加飾に至るまで、複数の職人の手を経て完成します。各工程に応じた素材と道具の選定が、美しい漆器を支えています。
大内塗の主な材料類
- 木地材(トチ・ホオなど):軽くて加工しやすい木材が主流。
- 漆(天然漆):下地・中塗・上塗に使い分けられる。
- 顔料(朱・黒・金粉):色漆や蒔絵用。
- 螺鈿材:アワビや夜光貝などの貝殻を使用。
大内塗の主な道具類
- 漆刷毛:均一に塗膜を形成するための専用刷毛。
- ヘラ・木ベラ:下地や粉固めに使用。
- 蒔絵筆・沈金刀:加飾用の精密な筆や彫刻刀。
- 乾漆棚(むろ):一定の湿度・温度で漆を硬化させる設備。
熟練の職人は、漆の性質や乾燥状態を読み取りながら、塗り・加飾・研ぎを重ね、色と文様が調和する漆器を生み出していきます。
大内塗の製作工程
塗り重ねに宿る、時間と技の美意識
大内塗は、多層的な工程を経て仕上げられる工芸品です。ひとつひとつの段階に、時間と精緻な手技が込められています。
- 木地製作
器や人形の形に合わせ、トチやホオなどの木材を成形。歪みのない滑らかな土台を作る。 - 下地塗り
砥の粉と漆を練り合わせた下地を塗り、乾燥と研磨を繰り返すことで丈夫な塗膜を形成。 - 中塗り・上塗り
色漆(朱・黒)を塗り重ね、艶やかで深みのある表面に仕上げる。 - 加飾
金粉を用いた蒔絵、細い彫りに金泥を埋め込む沈金、貝片を用いる螺鈿など、装飾の要となる工程。 - 研磨・磨き
最終的な表面を磨き上げ、光沢と滑らかさを出す。 - 乾燥・検品
「むろ」で湿度管理をしながら乾燥させ、細部を点検して完成へ。
これらの工程はすべて手作業で行われ、完成までに数週間から数ヶ月を要します。大内塗は、伝統と手間が凝縮された“雅の器”。現代の暮らしに彩りを添える、山口が誇る漆芸の結晶です。
大内塗は、山口の文化と歴史に根ざした気品ある漆器です。幾重にも重ねられた漆と、赤・黒・金彩による華やかな装飾が織りなす雅な世界は、実用品としても芸術品としても高い評価を受けています。時代を越えて愛されるその魅力は、今も静かに、そして確かに息づいています。