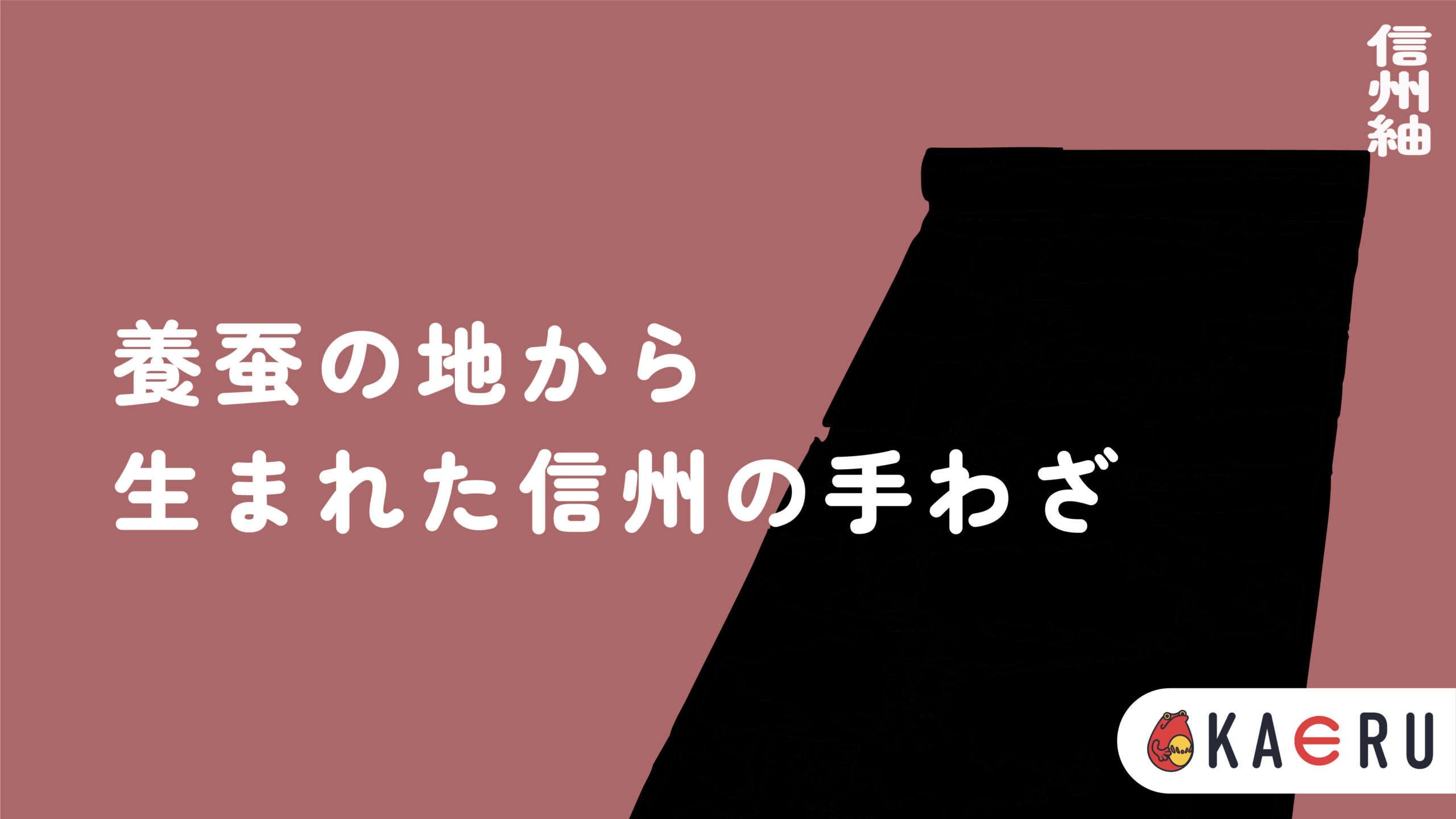信州紬とは?
信州紬(しんしゅうつむぎ)は、長野県の上田市、松本市、飯田市、伊那市など各地で製作される紬織物の総称です。かつて養蚕農家が、生糸にできないくず繭から紬糸(真綿糸)を紡ぎ、家族の衣類として織ったことに由来します。自然由来の染料を用いた縞模様や絣模様が特徴で、素朴でありながらどこか上品な趣を感じさせます。
信州紬は、地域ごとに個性を持つ織物が多数存在し、上田紬、松本紬、飯田紬、伊那紬などがそれに含まれます。なかでも上田紬は、大島紬・結城紬と並び「日本三大紬」のひとつに数えられており、信州紬を代表する存在です。その起源は戦国時代、真田幸村の父・真田昌幸が農民に織らせたことに始まるとされており、古くから地域に根ざした生産が行われてきました。
| 品目名 | 信州紬(しんしゅうつむぎ) |
| 都道府県 | 長野県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(33)名 |
| その他の長野県の伝統的工芸品 | 飯山仏壇、内山紙、南木曽ろくろ細工、木曽漆器、松本家具、信州打刃物(全7品目) |

信州紬の産地
信州の風土とともに歩んできた、地域に根ざす織の文化

主要製造地域
信州紬の主な産地は、長野県の上田市、長野市、松本市、飯田市、岡谷市、駒ヶ根市など、かつて養蚕が盛んであった地域に広がっています。これらの土地では、蚕を飼う家庭が多く、真綿を自家製の糸にして織物を作る文化が育まれてきました。
各地域にはそれぞれの特徴的な紬があり、上田紬はシャリ感のある風合い、松本紬は繊細な縞柄、飯田紬は絹糸の艶と堅牢性、伊那紬は素朴な風合いといった特色を持ちます。いずれも信州の自然と人の営みに根ざした、温かみのある織物です。
信州紬の歴史
暮らしの織物から、美術工芸品としての道へ
信州の自然とともに暮らす人々の手によって受け継がれてきた紬は、時代の移り変わりとともに進化を遂げ、今も生活に寄り添う織物として愛されています。
- 8世紀(奈良時代):信濃国でも養蚕が行われ、絹の産出地として知られる。
- 16世紀(戦国時代):上田地方で真田昌幸が農民に紬を織らせたのが上田紬の始まりとされる。
- 江戸時代:農家の副業として紬が広まり、真綿から手紡ぎ糸をつくり自家用に織られる。
- 明治時代:上田紬などが商品化。都市部へ出荷されるようになる。
- 昭和初期:草木染と手織による個性的な作品が注目され、工芸的価値が見直される。
- 1975年(昭和50年):信州紬が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:現代のライフスタイルに合う製品開発が進み、和装だけでなく洋服地やインテリアにも展開。
信州紬の特徴
自然の色、手のぬくもり、風土が織りなす布の詩
信州紬の最大の魅力は、草木染によるやさしい色合いと、真綿から手で紡がれる糸が生み出す素朴な風合いにあります。化学染料では表現できない深みのある色味が、四季折々の風景や山々の自然を映し出し、絹特有の光沢とともに独自の味わいを添えます。
また、しっかりとした打ち込みで織られるため丈夫で長持ちし、日常着としての実用性も兼ね備えています。縞模様や絣模様を中心とした控えめで上品な柄行は、飽きが来ず、時代を超えて愛され続ける理由のひとつです。

信州紬の材料と道具
信州の自然と共に生きる、草木と絹の恵み
信州紬の製作には、地元の自然資源を活かした素材と、繊細な手作業を支える道具が用いられます。真綿から紡ぐ糸や草木染の色合いには、山里の風景や人の手の温もりが宿っています。
信州紬の主な材料類
- 真綿(まわた):蚕の繭を手で広げて綿状にしたもの。紬糸の原料。
- 紬糸(手紡ぎ糸・撚糸):真綿から紡がれた太めの糸。独特の風合いを持つ。
- 草木染料:クルミ・ヤシャブシ・藍・コブナグサなど地域で採れる植物。
- 絹糸(精練糸):絣や細かな模様を織り出す際に使用される。
信州紬の主な道具類
- 座繰り機:真綿や繭から糸を手で紡ぐ装置。
- 手織機(高機・地機):織りの種類や工程によって使い分けられる。
- 框(かまち):糸を巻く枠。整経に用いる。
- 杼(ひ):糸を通して布を織るための道具。
信州紬の材料や道具は、いずれも自然の摂理と人の知恵が合わさって生まれたものであり、そこには暮らしとともにあった織物文化の記憶が色濃く息づいています。
信州紬の製作工程
糸を紡ぎ、色を重ね、布へと織り上げる手しごと
信州紬の製作は、真綿づくりから糸紡ぎ、草木染、そして手織りまで、すべてが職人の手作業で進められます。自然の色を重ね、糸を整え、丹念に織り上げることで、素朴であたたかな風合いと丈夫さを併せ持つ一反が生まれます。
- 真綿づくり
繭を蒸して広げ、綿状にして真綿を作る。繊維の方向を揃えながら乾燥させる。 - 紡ぎ(糸づくり)
真綿から指先で少しずつ糸を引き出し、撚りをかけて紬糸にする。撚糸機を用いることもある。 - 精練・草木染
不純物を取り除いて絹を精練し、クルミや藍などの草木染料で染める。染め重ねにより深みのある色を出す。 - 絣括り(模様準備)
絣模様をつくる場合は、糸に防染の括りを施し、模様位置を調整する。 - 整経・経糸張り
経糸の長さや模様に応じて糸を並べ、手織機に設置する。 - 手織り
高機や地機で、杼を通して緯糸を打ち込みながら、布を丁寧に織り上げる。
信州紬の製作は、自然と向き合い、時間と手間をかけて丁寧に積み重ねられる仕事です。一反一反に込められた職人の感覚と手の技は、まさに織られた風景そのものといえるでしょう。