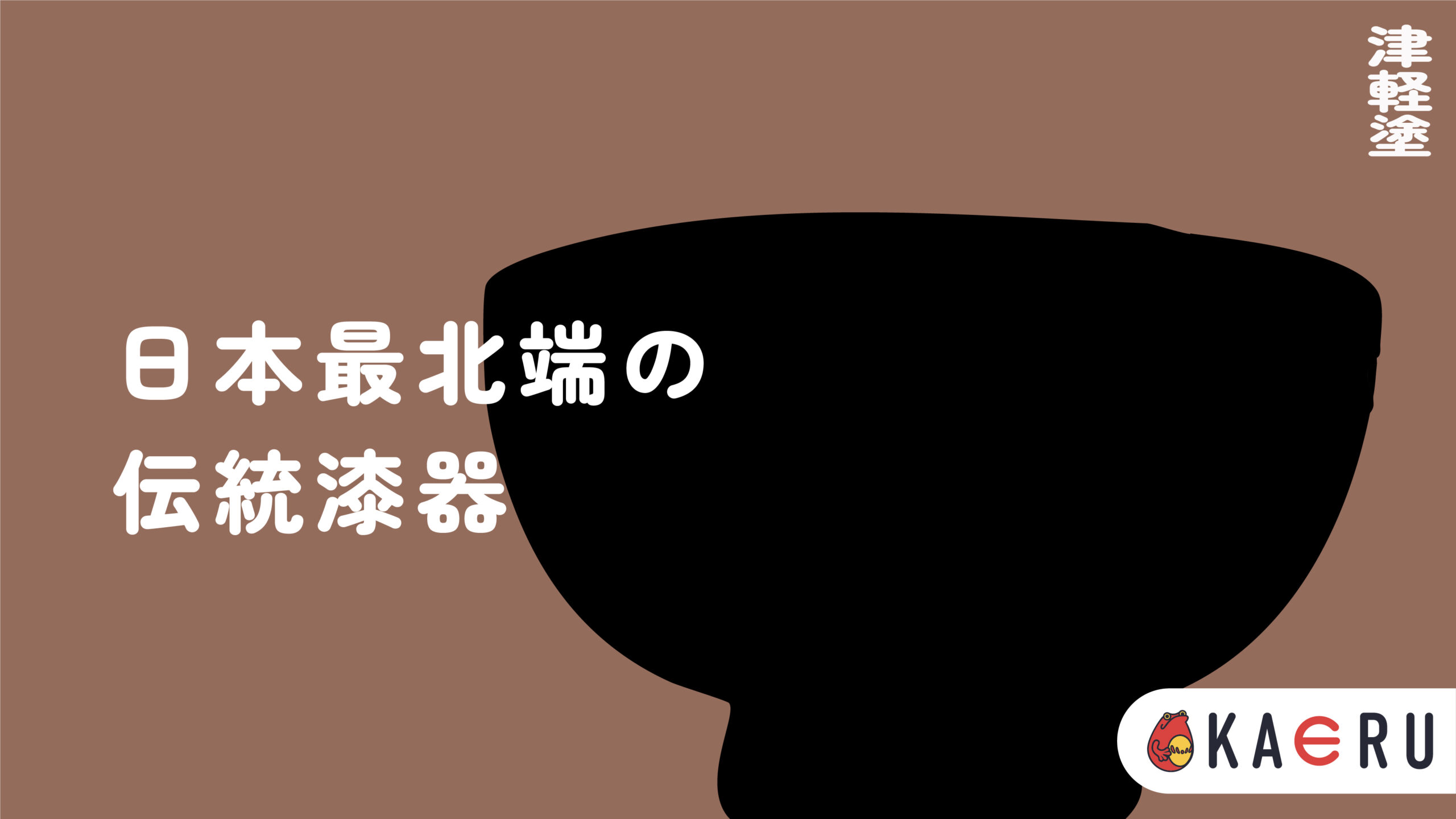津軽塗とは?

津軽塗(つがるぬり)は、青森県西部・津軽地方で350年以上にわたって受け継がれてきた伝統的工芸品です。その最大の特徴は、漆を幾重にも塗り重ね、乾燥と研磨を繰り返す「研ぎ出し変わり塗り」と呼ばれる技法によって生まれる、美しく奥行きのある文様にあります。唐塗、七々子塗、錦塗、紋紗塗といった複数の技法があり、製品ごとに異なる表情を持つため、「二つとして同じものがない」と言われる唯一無二の美を誇ります。
| 品目名 | 津軽塗(つがるぬり) |
| 都道府県 | 青森県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 12(43)名 |
| その他の青森県の伝統的工芸品 | なし(全1品目) |

津軽塗の産地
青森・弘前に根ざした工芸文化

津軽塗の主産地は、かつて弘前藩の城下町として栄えた青森県弘前市です。今も武家屋敷や弘前城などの歴史的建築物が残るこの地では、江戸時代から続く漆器文化が育まれてきました。木地には青森ヒバをはじめとする地域産の木材が使われ、防虫性や耐久性に優れる素材として高く評価されています。漆や研磨素材も地元で調達されており、「土地に根ざしたものづくり」が津軽塗の根幹を支えています。
津軽塗の歴史
藩政時代の奨励から世界へ
津軽塗の起源は17世紀後半、弘前藩第4代藩主・津軽信政が殖産興業を奨励し、若狭(現・福井県)から塗師の池品源兵衛を招いたことに始まります。仏具や武士の調度品に用いられていたこの技法は、江戸中期以降、文箱や重箱などの民間日用品へと広がっていきました。
- 17世紀後半(江戸時代中期):弘前藩第4代藩主・津軽信政が若狭国から塗師・池品源兵衛を招き、藩内に漆工技術を導入。仏具や武具、調度品の制作から始まりました。
- 18〜19世紀(江戸後期):民間にも技術が広がり、文箱や膳などの日用品へと展開。藩の保護政策により技術が体系化され、産地としての基盤が固まります。
- 19世紀後半(明治時代):1873年のウィーン万国博覧会で初出展し、「津軽塗」の名で国際的に知られるようになります。
- 1920〜50年代(昭和戦前〜戦後):第二次世界大戦による中断を経て、戦後は再評価され伝統工芸の再興が進みます。1958年には青森県が「郷土工芸品」として認定。
- 1975年(昭和50年):津軽塗が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 1990年代以降(現代):ファッション雑貨やインテリア、アート作品などへの応用も進み、若手職人やデザイナーとの協業が新たな展開を生んでいます。
津軽塗の特徴
美しさと実用性を兼ね備えた漆芸の極み
津軽塗は、視覚的な美しさとともに、強度や防水性といった実用性も兼ね備える漆器です。40以上の工程を経て完成する漆器は、重厚でありながら扱いやすく、日用品としての利便性にも優れています。
- 唐塗(からぬり):しかけべらで凹凸をつけ、複数の色漆を重ねて研ぎ出すことで、斑紋のような模様が現れます。
- 七々子塗(ななこぬり):菜種を撒いて文様の型を作り、透明感ある艶やかな表情に。
- 錦塗(にしきぬり):七々子塗の上に錫粉で文様を描いた華やかな技法。
- 紋紗塗(もんしゃぬり):炭粉を使って艶を抑えた上品な仕上がり。
これらの技法はすべて職人の手技によるもので、一つひとつに異なる味わいと物語があります。

津軽塗の材料と道具
自然素材と職人技が織りなす、津軽の美意識
津軽塗の魅力は、目を奪う模様の美しさだけでなく、その源となる自然素材と、それらを活かすために工夫された道具の数々にもあります。青森の風土が育んだ木材や漆、そして伝統的な塗り道具や研磨用具が揃うことで、繊細かつ丈夫な漆器が生まれます。すべての工程において手作業が重視されており、道具の使い方ひとつが仕上がりを大きく左右します。
津軽塗の主な材料類
- 木材(素地):青森ヒバを中心に、ホオノキ、カツラ、ケヤキなど。軽量で防虫性に優れ、加工もしやすい。
- 漆:国産の天然漆を使用。特に透明度が高く、美しい光沢と高い耐久性を持つ。
下地材:珪藻土や砥の粉、米糊を漆に混ぜた「地の粉」、砥石粉と水・漆を合わせた「錆漆」。強度と密着性を高める。 - 研磨材・仕上げ材:炭粉や砥石、菜種油など。磨きの工程で文様を浮き上がらせ、光沢と滑らかさを引き出す。
津軽塗の主な工具類
- しかけべら:唐塗などの模様づけに使用する専用の金属製ヘラ。漆の凹凸をつけるために不可欠。
- 刷毛・へら:漆を均一に塗布するための基本道具。用途により大きさや素材が異なる。
- 布貼り用具:縁や継ぎ目の補強に使う布を貼るための器具や台。強度を保つ重要な工程。
- 研磨用具(砥石・炭粉仕上げ用道具):下地〜仕上げに至るまで、各段階で使い分ける。文様の「研ぎ出し」を担う。
- 乾燥棚・塗台:湿度管理をしながら漆を乾かすための専用棚。塗りムラを防ぎ、発色を安定させる。
これらの素材と道具が、津軽の地に根ざした職人の手に渡ることで、重厚感と繊細さを兼ね備えた漆器が生み出されます。単なる「道具」ではなく、長年にわたる試行錯誤と技術の積み重ねが込められたそれぞれの工程が、津軽塗の奥深い魅力を支えているのです。
津軽塗の製作工程
40以上の段階を経て生まれる芸術品
津軽塗は以下のような工程を、約2か月以上かけて行います。
- 木地作り
天然木を用いて器の形状を整える。 - 下地塗り
生漆に地の粉を混ぜて塗布し、乾燥と研磨を繰り返す。 - 布着せ
器の縁など補強が必要な部分に布を貼る。 - 錆付け・中塗り
凹凸を整える錆漆を塗布し、研磨する。 - 模様付け
しかけべらや種子などを使って技法ごとの模様を施す。 - 色漆塗布・乾燥
多色の漆を塗り重ね、乾燥させる。 - 研磨・上塗り・仕上げ
透明漆でコーティングし、最終仕上げとして磨き上げる。
これらの工程すべてが手作業で行われるため、一点ごとに表情が異なるのも津軽塗の大きな魅力です。
津軽塗は、地域に根ざした素材と技が結びついた、まさに「用の美」の結晶です。器としての実用性はもちろん、日常に芸術を取り込む豊かさを私たちに教えてくれる存在でもあります。