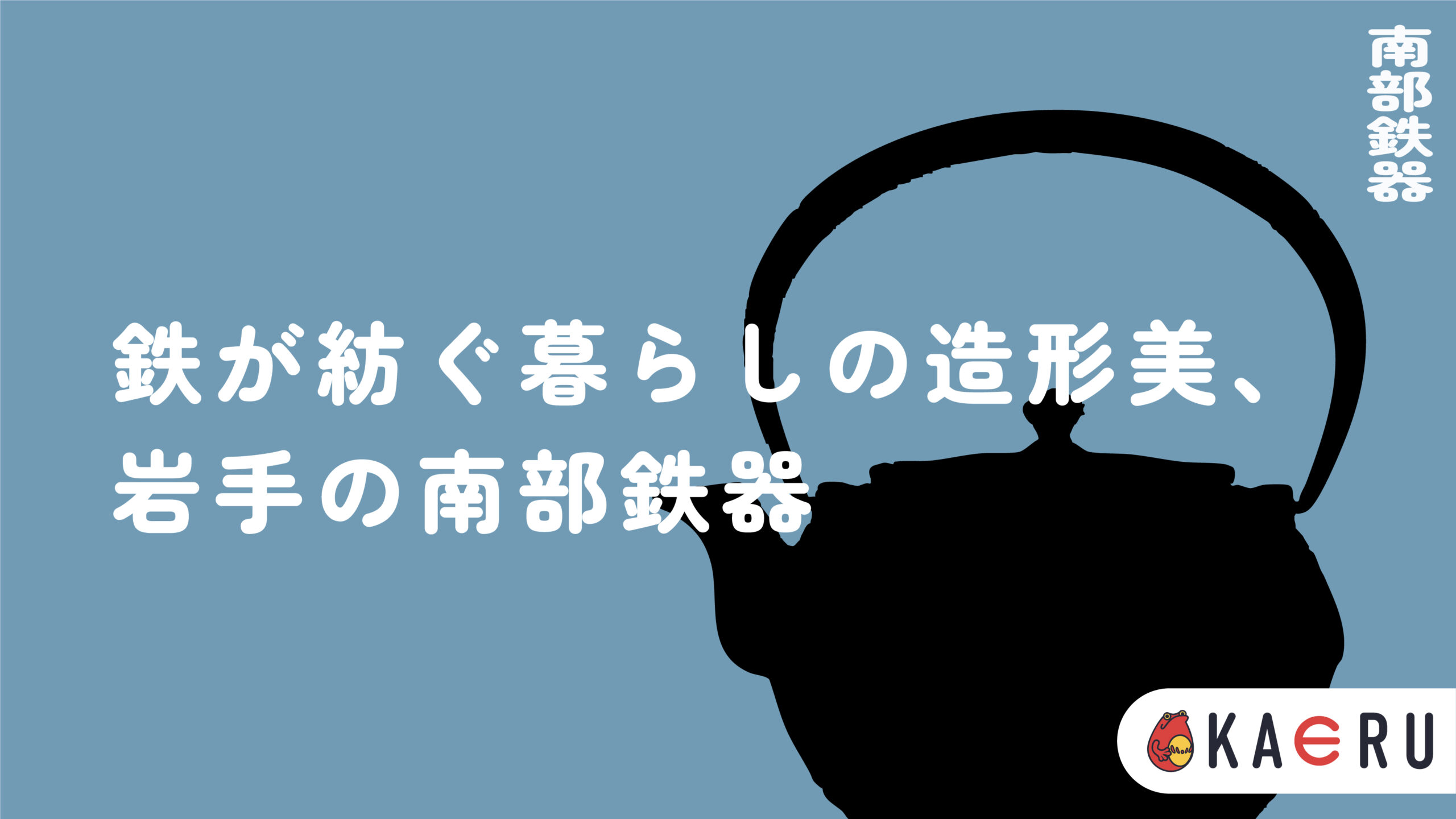南部鉄器とは?

南部鉄器(なんぶてっき)は、岩手県の盛岡市および奥州市を中心に製作される、伝統的な鋳金工芸品です。17世紀に南部藩が京都から茶釜職人を招いたことを契機に始まり、江戸から明治、大正、昭和へと受け継がれながら、多様な鋳物製品へと発展しました。
鉄ならではの重厚な存在感と、繊細な意匠が共存する南部鉄器。その魅力は、ただの道具を超え、暮らしの中に芸術性を宿す実用品として、現代でも高く評価されています。中でも鉄瓶に施される「あられ」模様や、金気止め(さび止め)などの独自技法は、日本独自の鋳物文化の結晶といえるでしょう。
| 品目名 | 南部鉄器(なんぶてっき) |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 分類 | 金工品 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 23(41)名 |
| その他の岩手県の伝統的工芸品 | 秀衡塗、浄法寺塗、岩谷堂箪笥(全4品目) |

南部鉄器の産地
北上川流域が育んだ、鉄と民のものづくり文化

南部鉄器の主産地である盛岡市と奥州市は、北上山地と奥羽山脈に挟まれた北上盆地に位置しています。この地域は、古くから上質な砂鉄や鉄鉱石に恵まれた鉱山地帯であり、鋳物に欠かせない材料が揃っていました。鋳型に使われる川砂や粘土は、北上川とその支流の河川から採取され、木炭や漆といった副資材も周辺の森林から確保できました。鉄を精錬するための燃料、水、素材がすべてこの地で賄えたことが、鋳物業の発展の土台を築いたのです。
また、戦国期から江戸初期にかけて武家の拠点となった盛岡と、奥州藤原氏や仙台藩の影響を受けた奥州市水沢で、それぞれ異なる文化圏に根ざした鋳物づくりが展開されました。茶道文化の浸透とともに茶釜の需要が高まる中、茶の湯釜の名工や鋳物師がこの地に集まり、優れた金工技術が確立していきます。特に南部藩の保護を受けた盛岡は、「茶の湯文化の北限」とも言える地域として知られました。
南部鉄器の歴史
鋳物の名産地が歩んだ、400年の系譜
南部鉄器は、盛岡と奥州、それぞれに異なるルーツを持ち、やがて一つのブランドとして結実した伝統工芸です。
- 1090年頃(平安後期):奥州藤原氏の藤原清衡が、近江国から鋳物師を水沢(現・奥州市)に招き、仏具や鐘の鋳造を始める。東北最古の鋳物産地の起源とされる。
- 1600年代初頭(江戸初期):盛岡藩(南部藩)主が京都から茶釜職人を召致。盛岡にて茶の湯釜・鍋などの鋳造を開始。
- 1659年頃(万治2年頃):盛岡藩士・村田宗正が鋳物場を設け、南部鉄器の基礎を築く。
- 1700年代中頃(江戸中期):日常使いの鉄瓶が盛岡で鋳造され始め、「南部鉄瓶」として名声を得る。
- 1820年頃(文政年間):水沢でも鉄瓶の製造が本格化。伊達家の庇護のもと鋳物技術が洗練される。
- 1870年代〜(明治時代):水沢と盛岡間で職人の技術交流が活発化し、製品が全国に流通。
- 1959年(昭和34年):盛岡鋳物と水沢鋳物が統一され、「南部鉄器」の名称で総称されるようになる。
- 1975年(昭和50年):南部鉄器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 2000年代以降:鉄瓶ブームの再来とともに健康効果やデザイン性が再評価され、海外需要も拡大。
南部鉄器の特徴
暮らしに寄り添い、時を超えて愛される鉄器の魅力
南部鉄器の魅力は、まず何よりも“用の美”にあります。鉄器は熱伝導率に優れ、一度温まると冷めにくいため、お湯をまろやかにし、茶葉の旨みを引き出すとも言われています。とくに冬の寒さが厳しい東北地方では、保温性の高い鉄器は生活の知恵として受け入れられてきました。
装飾性の面では、鉄瓶に施される「あられ文様」が代表的です。小粒の突起が一面に押し出されるこの意匠は、単なるデザインではなく、滑り止めや熱の均一な分散といった実用性も兼ね備えています。文様は職人があられ棒で一粒ずつ押していく手作業で、同じ型でも職人のクセや力加減で微妙な違いが生まれます。これにより、一つひとつが“世界に一つだけの鉄器”としての個性を持つのです。
また、「金気止め」と呼ばれる南部鉄器独特のさび止め処理も注目すべき技法です。器を高温で焼成し、酸化皮膜をつくることで内部から発生する赤さびを防ぎます。これは科学的な防錆ではなく、自然素材と火の力を活かした処理であり、鉄と人との知恵の結晶とも言えます。
近年では、カラフルな鉄瓶や、モダンなフォルムの調理器具、インテリアとしての風鈴や文鎮なども登場し、若い世代や海外の人々にも親しまれています。鉄分補給の面でも注目されており、実用と健康、そして美しさを兼ね備えた工芸としての魅力が再認識されています。
南部鉄器の材料と道具
鉄と型が生み出す、確かなかたち
南部鉄器の制作は、鉄と鋳型を中心に、繊細な工程と専門の道具によって支えられています。地場の自然資源と熟練の技が融合し、ひとつひとつが丁寧に作り上げられていきます。
南部鉄器の主な材料類
- 銑鉄(せんてつ):鉄鉱石から生成された鋳物用の原料。粘りと強度を持つ。
- 砂鉄:地元産の高純度素材。古来からの重要な原料。
- 川砂・粘土:鋳型や中子の成形に用いられる。
- 木炭:鉄の溶解時に使用される高温燃料。
- 漆:仕上げの着色やさび止めに使用。
南部鉄器の主な工具類
- 挽型板(ひきがたいた):鋳型の原形をつくるための図案板。
- あられ棒:鉄瓶に文様を押す専用道具。
- 中子型:中空部分を形成する内部型。
- 溶解炉:鉄を1400〜1500℃で溶かす大型設備。
- 金気止め用焼成台:鉄瓶の表面に酸化皮膜を形成させるための装置。
南部鉄器は、素材の選定から仕上げまで、一貫して「鋳造ならではの手仕事」で支えられています。
南部鉄器の製作工程
手業がつなぐ80の工程、日々に寄り添う道具の誕生
南部鉄器の制作は、鉄瓶一つで80工程以上。職人の経験と感覚が試される、緻密な仕事の積み重ねです。
- デザイン設計
鉄瓶の図案を設計し、鉄板に図面を写して挽型板を作成。 - 鋳型づくり
粘土と砂を混ぜた素材で、胴型・尻型・蓋型の3種類の鋳型を成形。 - 文様押し
胴型が乾く前に、あられ棒で一粒ずつ文様を手作業で刻印。 - 中子づくりと組み立て
川砂と粘土で作った中子(なかご)を胴型にセットし、尻型をかぶせて鋳型を組み立てる。 - 鋳込み
溶解炉で鉄を1500℃まで加熱し、ひしゃくで鋳型に流し込む。 - 型出し・整形
鉄が固まったら鋳型を壊して取り出し、バリを削り整形。 - 釜焼き・金気止め・着色
表面を高温で焼成し、酸化皮膜を形成。さらに漆焼き付けなどで仕上げを施す。 - 最終仕上げ
磨き、つる付けを行い、品質を確認して完成。
南部鉄器は、鉄という素材の可能性を極限まで引き出した、日本の鋳金工芸の真髄です。400年以上の歴史を受け継ぎながら、現代の暮らしにもなじむ“用の美”を体現し、国内外で愛され続けています。鋳型に込めた職人の想いが、ひとつひとつの器に温もりを宿し、日々の暮らしを静かに豊かに彩ります。