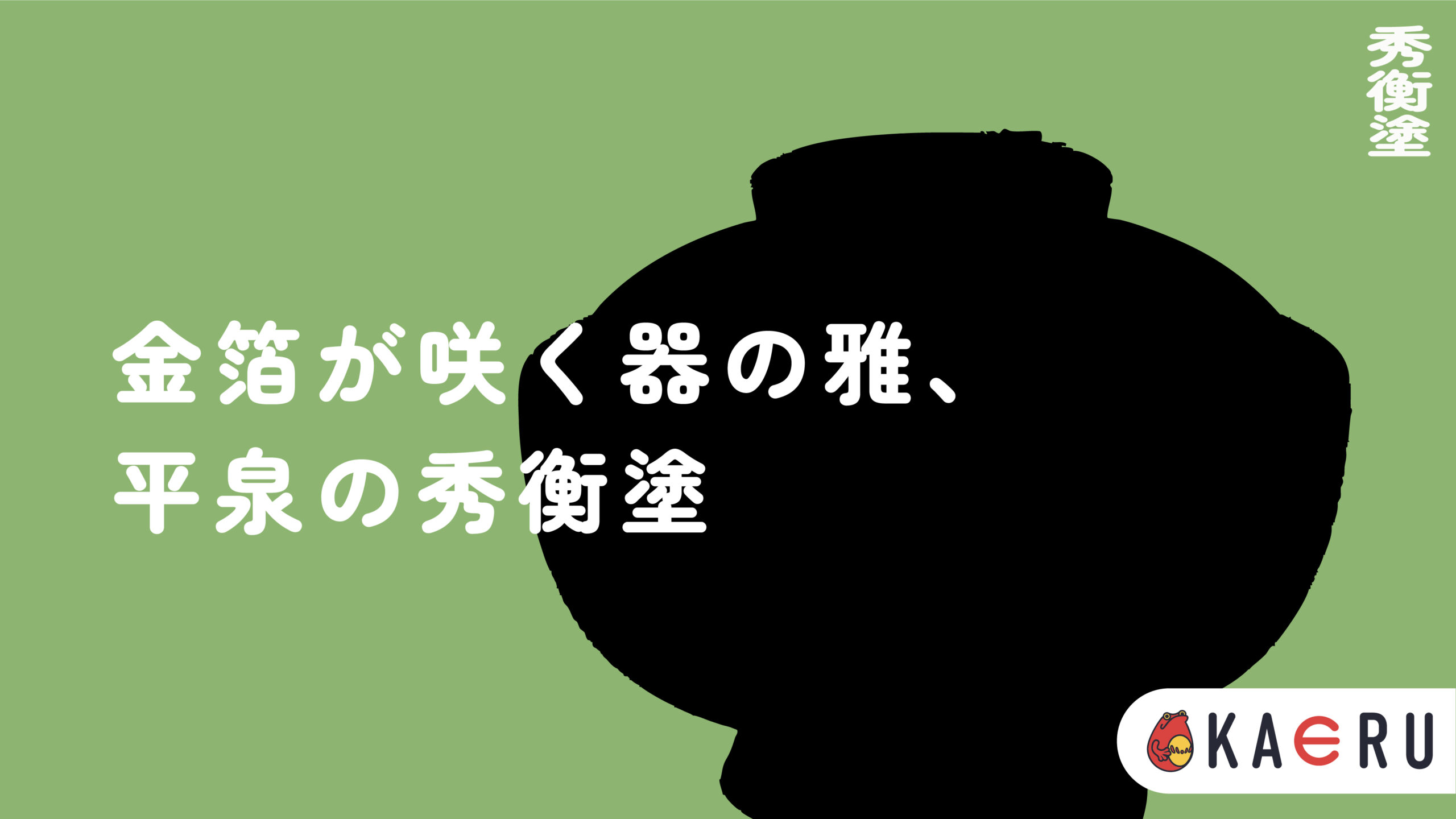秀衡塗とは?

秀衡塗(ひでひらぬり)は、岩手県南部の平泉町や一関市を中心に作られている伝統的な漆器です。丸みを帯びた手なじみのよい器形に、金箔と伝統文様による華麗な装飾が施され、実用性と美術性を兼ね備えた漆芸品として親しまれています。
最大の特徴は、金箔で表現される「源氏雲」と「有職菱文(ゆうそくひしもん)」と呼ばれる文様装飾。貴族文化の流れを汲む優雅なデザインと、東北の風土に根ざした堅牢な塗り技術が融合し、独自の美を築き上げています。
| 品目名 | 秀衡塗(ひでひらぬり) |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1985(昭和60)年5月22日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 4(9)名 |
| その他の岩手県の伝統的工芸品 | 浄法寺塗、岩谷堂簞笥、南部鉄器(全4品目) |

秀衡塗の産地
黄金と漆の恵みが出会う、みちのくの美のふるさと

秀衡塗の主な産地は、岩手県南部の平泉町と一関市です。特に平泉町は、12世紀に奥州藤原氏が築いた理想郷として知られ、中尊寺金色堂や毛越寺などの仏教建築が今も残る“文化遺産の町”です。これらの建築には、漆と金をふんだんに用いた装飾が施され、秀衡塗の原点ともいえる美意識が息づいています。
平泉は平安貴族文化の影響を色濃く受けながらも、東北の実用性や堅牢さを重視する風土と融合し、独特の漆芸様式が育まれてきました。特に有職文様や金箔の装飾技法は、貴族的でありながらも日常使いに適応した点で、他地域の漆器とは一線を画しています。
気候的にも、この地域は北上川流域の湿潤な気候と、四季の寒暖差が大きな盆地環境であることから、漆の栽培に適しており、国産漆の一大産地として発展してきました。加えて、周辺山地にはかつて良質な金鉱が存在し、「黄金の国ジパング」と称された日本像を支える要因のひとつとも言われています。
このように、歴史・文化・自然環境の三位一体が、秀衡塗という芸術的かつ実用的な漆器文化を生み出し、今に受け継がれているのです。
秀衡塗の歴史
藤原秀衡の美意識を受け継ぐ漆芸の系譜
秀衡塗の起源は、平安時代末期に奥州藤原氏三代目・藤原秀衡が京から職人を招き、地元で採れた金とうるしを用いて器を作らせたことにあると伝わります。その雅な加飾技法に由来し、後にこの塗物が「秀衡塗」と呼ばれるようになりました。
- 12世紀後半(平安末期):奥州藤原氏三代・藤原秀衡が京から漆器職人を招き、地元産の漆と金を使った器の制作を奨励。これが「秀衡塗」の起源とされる。
- 1189年(文治5年):源頼朝の軍勢により奥州藤原氏が滅亡。秀衡塗の伝統も一時断絶。
- 18世紀末〜19世紀前半(江戸時代後期):平泉町周辺の農村部で漆器製造が復活。日常雑器から加飾器まで幅広く生産。
- 1868年(明治元年)前後:明治維新後、装飾性の高い漆器が「秀衡塗」として再評価され始める。
- 1900年代前半(大正〜昭和初期):贈答品・婚礼用として需要が高まり、意匠の統一や技法の継承が進む。
- 1985年(昭和60年):経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 2000年代以降:現代のライフスタイルに合う新たな製品展開とともに、美術工芸品としての評価も確立。加飾や図案の伝統を守りつつ、色漆やモダンデザインの導入も進む。
秀衡塗の特徴
金と漆、雅と用の絶妙なバランス
秀衡塗の最大の魅力は、実用品でありながら芸術品としての風格を併せ持つ点にあります。ふっくらと丸みを帯びた器形は、手になじみやすく、持ったときにほっとする柔らかな感触があります。これは寒冷な東北の風土で育まれた“ぬくもりのデザイン”とも言えるでしょう。
表面を飾る「源氏雲」は、流れる雲の形を写したもので、空間の動きを感じさせる象徴的なモチーフです。そして「有職菱文」は、古代中国から伝来し、日本の宮廷文化で洗練された格式ある文様。その菱形の中に金箔を細かく貼ることで、華やかで奥行きある意匠が生まれます。
見て美しく、使って心地よい。そんな「機能する芸術」としての秀衡塗は、まさに日常に溶け込む雅の象徴です。

秀衡塗の材料と道具
漆と金が奏でる雅、素材の力を引き出す匠の手
秀衡塗では、木地から加飾に至るまで、すべての工程において厳選された素材と専門の道具が用いられます。分業制を採ることで、それぞれの職人が高度な専門性を発揮しています。
秀衡塗の主な材料類
- うるし(漆):岩手県産の国産漆を使用。粘りと艶に優れ、塗膜が堅牢。
- 金箔:文様装飾に使用。ひし形に裁断されたものが用いられる。
- 木地材:ホオノキ、ケヤキ、トチなど、長期間乾燥させた良質な広葉樹が中心。
秀衡塗の主な工具類
- 彫刻刀・線描筆:文様下描きや色漆による装飾に用いる。
- 箔ばさみ・箔押し具:金箔を細かく配置するための専用道具。
- 刷毛・ぬりへら:花塗(油入り漆塗り)や上塗り作業に使用。
- 研磨用砥石・炭:下地や仕上げ面の調整に用いる。
素材選びと道具使いの巧みさが、秀衡塗の美しさと耐久性を支えているのです。
秀衡塗の製作工程工程
漆と金が紡ぐ美、分業が磨く伝統技
秀衡塗は、「木地」「下地」「塗り」「加飾」の4工程を、専門の職人が分業で手がけます。それぞれの段階で緻密な技術と感性が求められ、完成までに数ヶ月を要することもあります。
- 木地づくり
2~10年乾燥させた広葉樹から木地師が器を成形。歪みのない形に削り出す。 - 下地
漆を染み込ませた布を貼るなどして強固な下地を形成。乾燥と研磨を繰り返す。 - 塗り(花塗)
下塗り・中塗り・上塗りの3工程で漆を重ねる。油を混ぜた「花塗」で滑らかな艶を出す。 - 加飾
源氏雲と有職菱文を下描きし、ひし形の金箔を貼る。色漆で草花を描き、仕上げる。
完成した秀衡塗は、手にしたときの温もりと、目にしたときの華やぎを兼ね備えた逸品となります。
秀衡塗は、奥州藤原氏の黄金文化を今に伝える東北の名品です。金箔と漆の美しさ、手に馴染む形、そして有職文様の雅やかさが調和した器は、実用の中に芸術を感じさせてくれます。歴史と文化、自然素材が融合した逸品として、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。