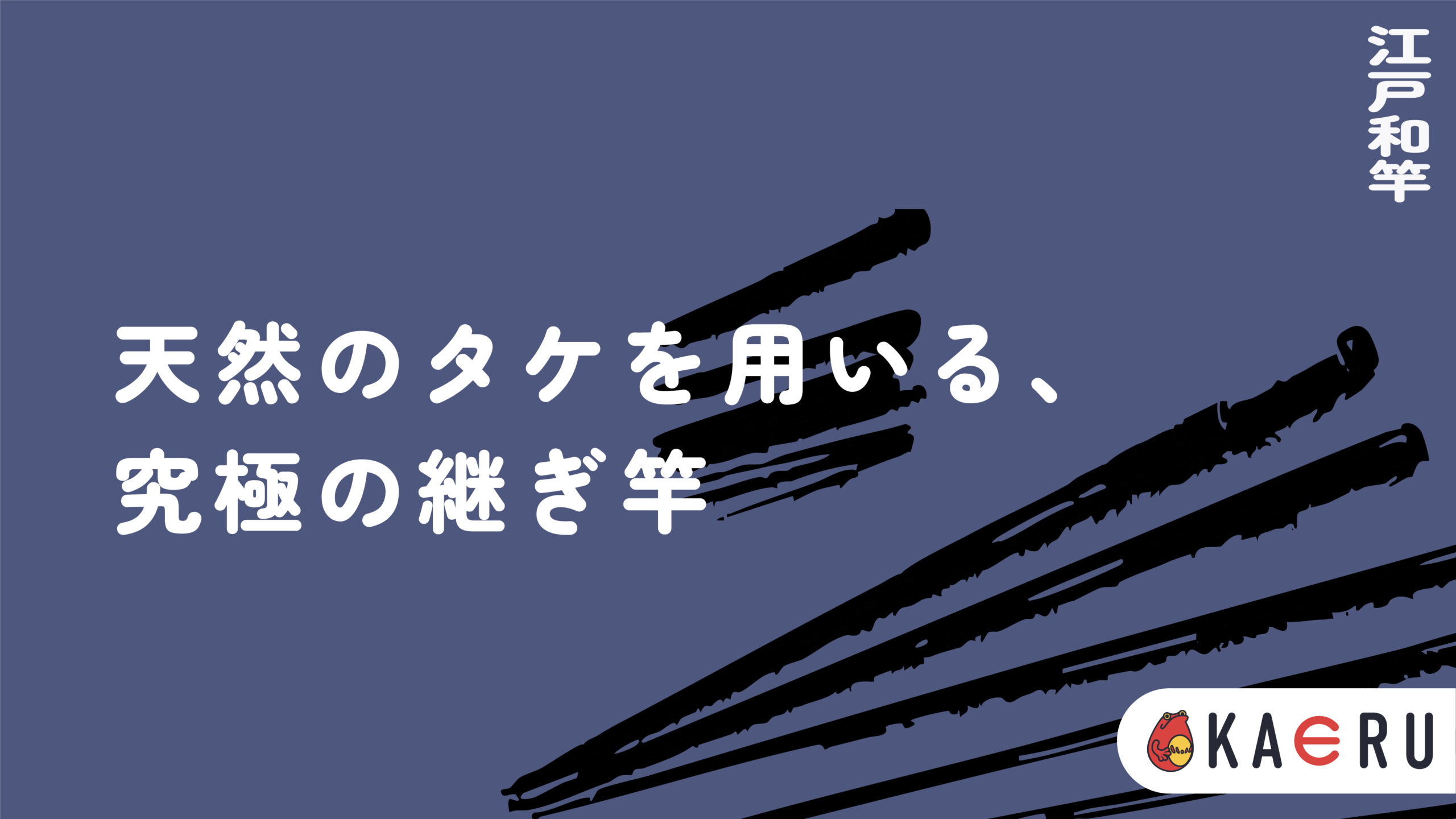江戸和竿とは?
江戸和竿(えどわざお)は、東京都を中心に作られる竹製の伝統的工芸品で、複数の竹をつないで仕立てる「継ぎ竿(つぎざお)」です。 ホテイチクやマダケなどの天然竹を用い、火入れや漆塗り、糸巻きなどの繊細な工程を経て、魚種や釣りの目的に応じて一本ずつ仕立てられます。
江戸時代から釣りを趣味とする町人文化の中で発展し、今では実用性と芸術性を兼ね備えた希少な竹工芸として高く評価されています。
| 品目名 | 江戸和竿(えどわざお) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 1991(平成3)年5月20日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |
| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

江戸和竿の産地
釣り文化と手仕事が交差する、東京下町のものづくり拠点

江戸和竿の主な産地は、東京都の台東区、葛飾区、荒川区といった東京の東部エリアです。これらの地域は、江戸時代から現在に至るまで多くの職人が暮らし、木工・竹細工・金工などの町人文化が色濃く残る場所として知られています。産地周辺には、隅田川や荒川、多摩川、さらに東京湾といった多彩な釣り場が広がっており、それぞれに適した釣り竿の需要が古くから存在していました。この環境が、魚種ごとに異なる特性を持つ江戸和竿の発展を後押ししてきたのです。
また、周辺の千葉県や埼玉県、神奈川県にも、ホテイチク、ヤダケ、マダケ、ダイミョウチクなどの良質な竹が採れる竹林が点在しており、原材料の安定供給が可能な地域環境が整っていました。
こうした自然資源と都市文化の融合が、江戸和竿の発展を支える土壌となり、今なお台東区などでは複数の竿師が工房を構え、技を受け継ぎながら日々竿づくりに取り組んでいます。
江戸和竿の歴史
江戸の釣り文化が育んだ継ぎ竿の美意識
江戸和竿の歴史は、江戸の町人が日常の楽しみとして釣りに親しむようになった江戸時代中期にさかのぼります。粋を重んじる江戸の気風の中で、竿にも機能性だけでなく美しさが求められ、工芸品として昇華していきました。
- 1716〜1736年(享保年間):江戸下谷稲荷町にて釣具店「泰地屋東作(たいちやとうさく)」が開業。和竿製作の祖とされる。
- 1789〜1818年(寛政〜文化年間):フナ竿やハゼ竿など、魚種ごとの専門竿が登場。町人文化と結びつきながら和竿文化が拡大。
- 1830〜1844年(天保年間):下町を中心に釣りが娯楽として庶民に広がり、竿師の数が増加。
- 1850年代〜(幕末):彫金や漆塗りなど装飾技法が加わり、美術工芸品としての価値が高まる。
- 1868〜1912年(明治時代):洋式の釣具が輸入される中で、和竿職人は独自の伝統を守り、愛好家に支えられ存続。
- 1955年頃(昭和30年代):高度経済成長期のレジャーブームにより、和竿の需要が再び高まる。
- 1991年(平成3年):江戸和竿が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現在:カーボン製ロッドが主流となる中でも、和竿は職人の技術と釣りの醍醐味を体現する逸品として根強い人気を保つ。
江戸和竿の特徴
実用性と芸術性を兼ね備えた、職人技の結晶
江戸和竿の最大の魅力は、魚種や釣り方、釣り人の好みに応じて一竿一竿オーダーメイドで仕立てられることです。最低でも3年以上寝かせた竹を使い、「切り組み」と呼ばれる工程で部位ごとに最適な竹を選び、複数本をつないで1本の竿に仕上げます。
この継ぎ竿構造により、竿のしなりや強度を細かく調整でき、釣り上げる魚の引きにも柔軟に対応。漆塗りや絹糸巻き、金属装飾などの装飾が施され、実用品でありながら芸術品としても鑑賞に堪える完成度を持ちます。竹は天然素材ゆえに、使用を重ねることで手になじみ、時間とともに味わい深さが増していくのも大きな魅力です。

江戸和竿の材料と道具
すべて自然素材、環境にもやさしい構成
江戸和竿づくりに用いられる素材と道具は、すべて国産の天然由来。職人の繊細な手仕事と、自然素材の個性が融合することで、唯一無二の釣竿が生まれます。
江戸和竿の主な材料類
- ホテイチク・ヤダケ・マダケ・ダイミョウチク:竿の芯材。しなり具合や強度に応じて使い分けられます。
- 絹糸:竿の補強や意匠装飾に使用。耐久性と美観の両立を実現します。
- 漆(うるし):塗装、防水、美観を兼ねた天然塗料。竹に深みのある艶と強さを与えます。
江戸和竿の主な道具類
- 鋸・小刀:竹の切断・成形に用います。
- 火入れ道具(炭火やガスバーナー):竹の曲がり矯正と強度調整に必須。
- 漆刷毛・乾燥棚:漆の塗布と乾燥に使用され、均一な仕上がりに欠かせません。
- 糸巻き機:絹糸を美しく、かつ適度な力で均等に巻くための装置。
江戸和竿の製作工程
すべて手作業で仕立てられる継ぎ竿の世界
江戸和竿の製作工程は、素材の選別から仕上げまで、熟練職人の手作業によって丁寧に行われます。竿の“しなり”や“節”、そして見た目の美しさを最大限に引き出すためのプロセスです。
- 竹の選定・乾燥
使用する竹材は、3年以上自然乾燥させたものを厳選。 - 切り組み
用途に応じて異なる性質の竹を部位ごとに切断・接合。 - 火入れ
竹に熱を加えて曲がりを矯正し、しなやかで強靭な竿に整形。 - すげ口・継ぎ加工
継ぎ目を緻密に削って隙間なく接合。 - 漆塗り・糸巻き
漆を塗布後、絹糸を巻いて装飾と補強を行う。 - 中矯め(なかため)
継ぎ竿全体の曲がり・調子を最終調整。 - 乾燥・仕上げ
全体を乾燥させ、磨きをかけて完成品とする。
江戸和竿は、単なる釣具ではなく、日本の釣り文化と職人技の融合が生んだ“用の美”の象徴です。一本一本に込められた職人のこだわりと技術は、現代においても色あせることなく、むしろデジタル時代の今だからこそ際立ちます。釣りを楽しむ道具でありながら、芸術品としても価値を持つ江戸和竿。その魅力にふれることで、あなたの釣りの時間がより豊かで粋なものになるでしょう。