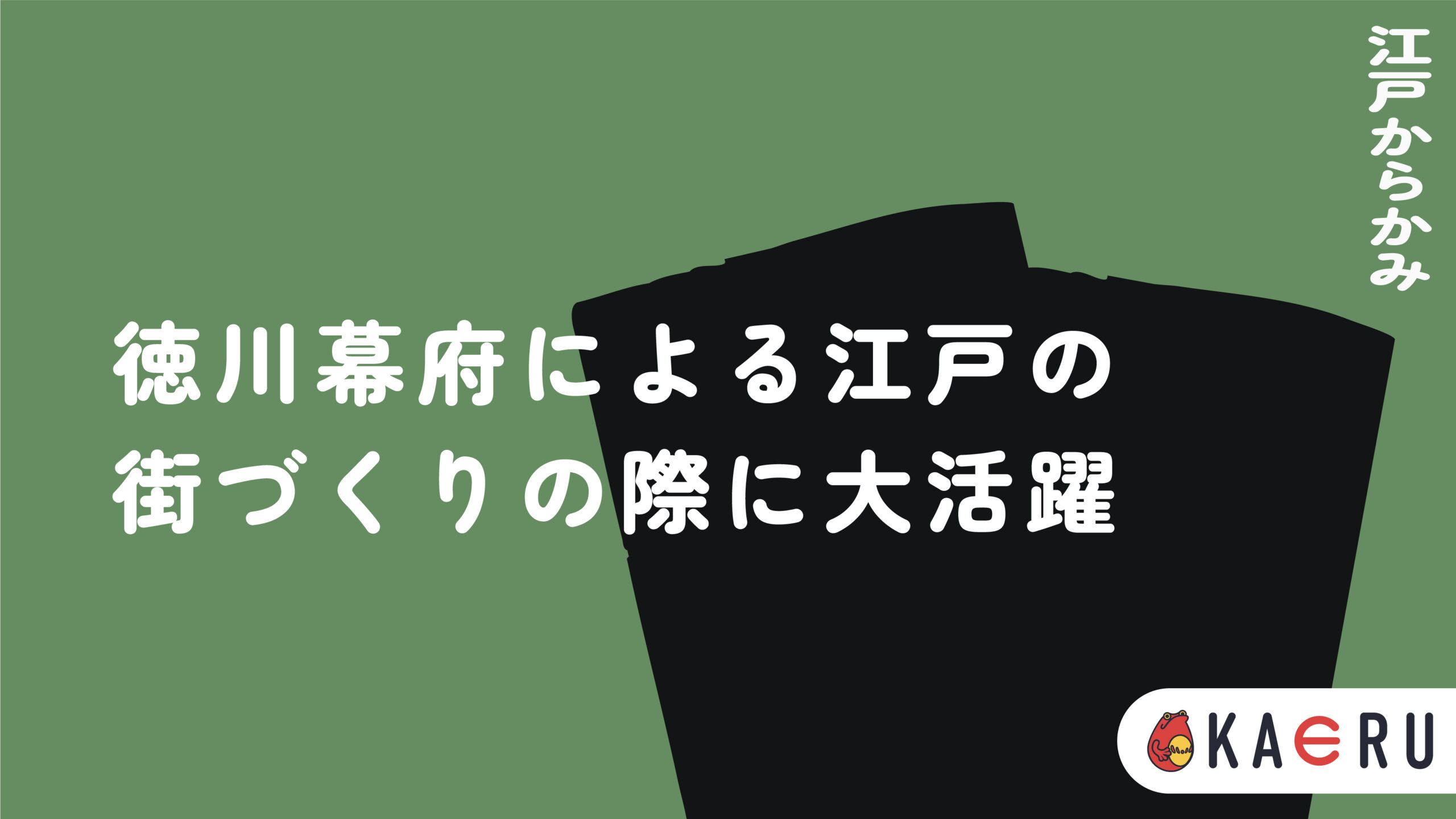江戸からかみとは?
江戸からかみ(えどからかみ)は、東京都江戸川区、練馬区、文京区などで製作される装飾紙で、ふすまや壁紙、文具などに使われる伝統工芸品です。その特徴は、木版手摺りや金銀箔を用いて文様を和紙に写す点にあります。草花や幾何学模様など多彩な意匠は、江戸時代に考案された伝統文様が今も受け継がれています。唐紙師、砂子師、更紗師といった職人が分業で製作に携わり、それぞれの技術が結集して江戸からかみを完成させます。
和紙の温かみと、手摺りならではの優しい風合いは、現代の空間でも落ち着きと趣を添え、伝統とモダンが融合した魅力ある工芸品となっています。
| 品目名 | 江戸からかみ(えどからかみ) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 分類 | その他の工芸品 |
| 指定年月日 | 1999(平成11)年5月13日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 6(11)名 |
| その他の東京都の伝統的工芸品 | 村山大島紬、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京染小紋、東京手描友禅、東京銀器、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

江戸からかみの産地
仏教文化と町人文化が交差した職人のまち

仏教文化と町人文化が交差した職人のまち 江戸からかみの産地である江戸川区や練馬区、文京区は、江戸時代から多くの職人が暮らす町として知られてきました。仏教の写経紙や和歌の料紙などに用いられた装飾紙が発展し、やがて襖や屏風など住宅内装へと応用されるようになります。
中でも江戸川区には紙関連の職人が多く集まり、型紙の保管や版木の管理、手摺りに適した環境が整えられてきました。また、町人文化が成熟した江戸では、草花や波などをモチーフとした洒脱な文様が生まれ、現代にも通じるデザイン性をもつ工芸品へと発展していきました。
江戸からかみの歴史
装飾紙から室内装飾へ、江戸の粋を映した紙の芸術
江戸からかみは、約400年前の江戸時代初期に誕生し、町人文化の広がりとともに発展してきました。江戸では武家・町人・職人が密集する都市空間が形成され、住宅内装の装飾性が高まり、独自の意匠文化が花開いたことが背景にあります。
- 17世紀初頭(江戸時代初期):中国から伝来した「唐紙」の技術が日本化し、仏教経典や和歌をしたためる装飾紙として広まる。
- 18世紀中頃(江戸時代中期):町人文化が成熟し、襖や屏風など住宅内装に文様を施す装飾紙として需要が増加。
- 19世紀前半(江戸時代後期):木版手摺りや砂子(すなご)、更紗といった技法が発展。江戸特有の大胆で洒落た意匠が確立される。
- 明治〜大正期:和紙の産地が全国に広がる中、江戸からかみは襖紙として高い品質を誇り、寺院や邸宅に広く用いられる。
- 1950〜70年代(昭和中期):高度経済成長により住宅事情が変化。需要が一時減少するも、装飾美を求める建築家や美術関係者に再評価される。
- 1999年(平成11年):江戸からかみが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
江戸からかみの特徴
分業で作り上げる、伝統文様の美
江戸からかみの最大の特徴は、手摺りによる文様表現と、それを支える職人たちの分業体制です。彫刻を施した版木を用いて和紙に摺り込む唐紙師、金箔や銀箔を施す砂子師、更紗文様を型紙で表現する更紗師が、それぞれの専門技術を発揮します。用いられる文様はすべて江戸時代に考案されたものに限られ、草花や流水、幾何学模様など多彩。これらを何百回もの手摺り工程で紙に写し、手仕事ならではの風合いを生み出します。
現代では、ふすま紙だけでなく壁紙や照明カバー、文房具などにも展開され、暮らしの中に江戸の美意識を取り入れるアイテムとして注目されています。加えて、ホテルや美術館の内装、建築家による商空間のデザインなどにも採用される事例が増えており、伝統工芸の新たな活用法として注目を集めています。
江戸からかみの材料と道具
和紙の質感と文様の再現力を支える素材と道具
江戸からかみの製作には、繊細な摺りの技法に適した素材と、長時間の作業に耐えうる道具類が不可欠です。特に和紙は顔料の吸収と保持に優れており、繰り返しの摺り作業にも耐える強度が求められます。道具もまた、摺りムラを抑えながら均一に顔料を定着させる性能が必要です。
江戸からかみの主な材料類
- 手漉き和紙:耐久性と吸湿性に優れ、摺りの風合いが際立つ。
- 金箔・銀箔・砂子:装飾効果として用いられ、豪華な印象を与える。
- 顔料:天然由来や鉱物系の素材を原料とすることが多く、色の定着性と発色の美しさが重視される。
江戸からかみの主な道具類
- 版木:文様を彫刻した木製の版で、摺りの基本。
- 刷毛:顔料を和紙に摺り込む際に使用。
- 型紙:更紗などの技法で文様を定着させるために使用。
- 箔刷り道具:箔や砂子を均一に押さえる専用器具。
職人は、気温や湿度、紙の状態に応じて摺り方を調整しながら作業を進めます。
江戸からかみの製作工程
職人の分業と繊細な手作業が織りなす文様表現
職人の分業と繊細な手作業が織りなす文様表現 江戸からかみの製作工程は、原紙となる和紙を準備するところから始まり、文様に応じた版木や型紙を用いた手摺り作業を経て完成します。摺りの回数や順序は文様の構成によって異なり、数十〜百回を超えることもあります。
- 和紙準備
漉き上がった和紙を天日干しで乾燥させ、摺り作業に適した状態に調整する。 - 文様選定・版木準備
使用する文様に応じて、保存されている版木や型紙を準備する。 - 手摺り
唐紙師が顔料を刷毛で和紙に摺り込み、文様を写す。多色の場合は色ごとに繰り返す。 - 箔押し・砂子作業
砂子師が箔や砂子で装飾を加える。 - 更紗摺り
更紗師が型紙を用いて繊細な文様を追加する。 - 乾燥・仕上げ
乾燥後、紙の状態を確認しながら必要に応じて補整や裁断を行い、完成品とする。
こうした緻密な手作業によって、江戸の粋を現代に伝える装飾紙が生み出されているのです。江戸からかみは、日本家屋の美意識と職人技の結晶です。襖や壁紙としてだけでなく、現代の空間にも自然に調和する意匠と質感は、多くの人の心を惹きつけてやみません。