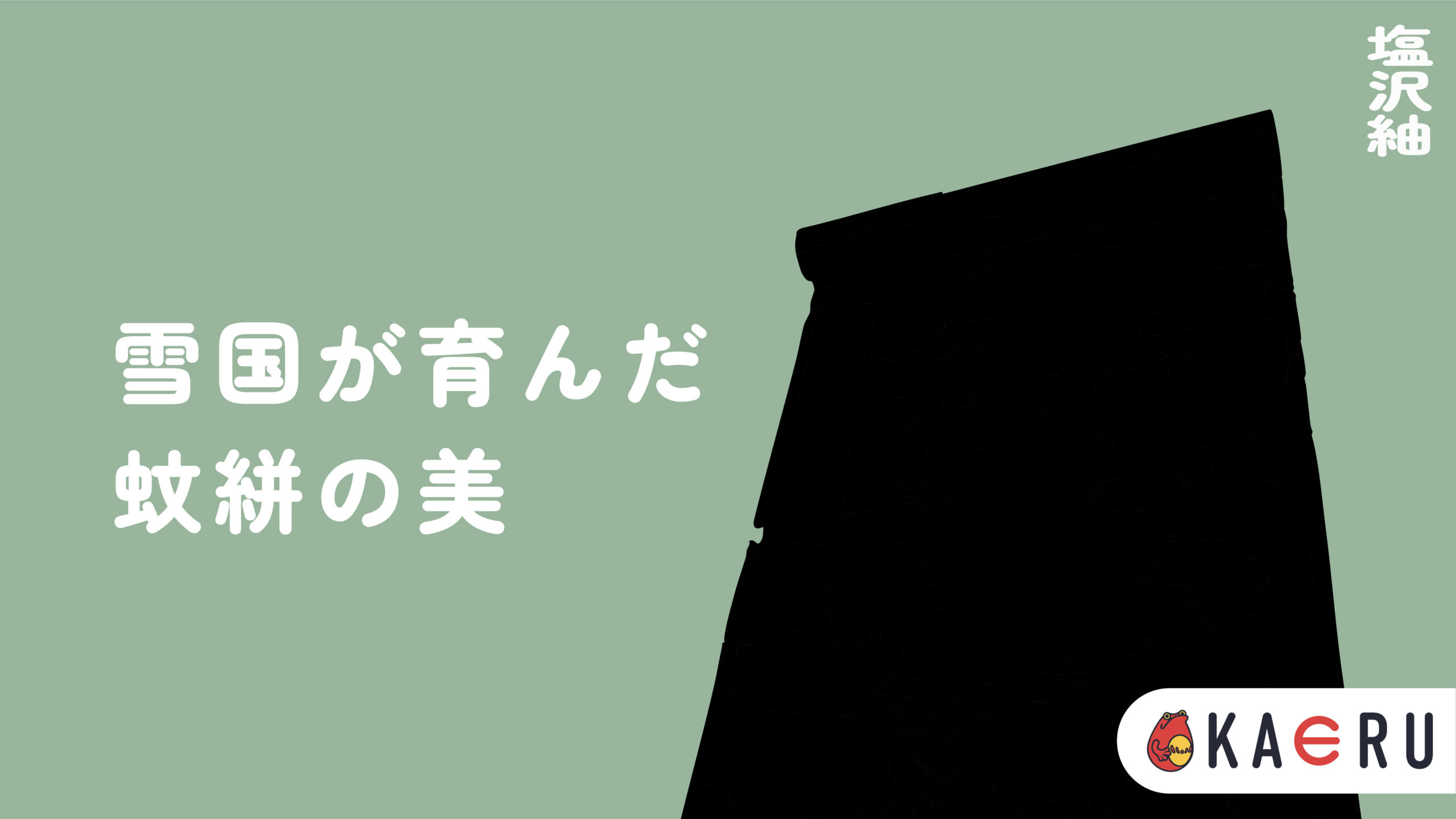塩沢紬とは?
塩沢紬(しおざわつむぎ)は、新潟県南魚沼市で生産される絹織物で、同地の伝統麻織物「越後上布」の技術を母体として、18世紀後半に生まれました。特に、極めて細やかな絣模様「蚊絣(かがすり)」で知られ、その精緻な文様と落ち着いた色調は、上品さと風格を兼ね備えた着物地として広く親しまれています。
原料には真綿から手紡ぎされた紬糸が用いられ、柔らかくふっくらとした肌触りが特徴。雪深い気候がもたらす清らかな水と湿度、そして雪晒しなどの雪国特有の技法が、その美しい風合いを支えています。
| 品目名 | 塩沢紬(しおざわつむぎ) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(34)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

塩沢紬の産地
雪国の知恵と美意識が育んだ、蚊絣のふるさと

主要製造地域
塩沢紬の主産地は、新潟県南魚沼市の塩沢地域。冬には3メートル以上の積雪があるこの地域では、豊かな雪解け水と湿潤な空気が織物づくりに最適な環境をもたらし、古くから越後上布や小千谷縮といった高級織物の産地として知られてきました。
とくに、江戸時代から受け継がれる絣織の技術と、雪国ならではの「雪晒し」「湯もみ」といった加工技術が、塩沢紬の風合いや色調に大きく寄与しています。また、冬場の農閑期を活かした副業として、各家庭で機を織る文化が根づいていたことも、伝統の継承を支えてきました。
加えて、塩沢は江戸時代には北陸道の宿場町として栄え、京都や江戸との文化的・経済的交流が盛んだったことから、早くから上質な絹織物の需要と供給のネットワークが形成されていました。厳しい冬の寒さと雪は繊維の加工に適し、絹糸の染色や保管にも良好な条件をもたらします。こうした気候・風土・歴史・文化の重なりが、塩沢紬の産地としての礎を築いてきたのです。
塩沢紬の歴史
麻から絹へ、越後の技が織りなす蚊絣の発展
塩沢紬の起源は、古代から続く越後の麻織物文化にあります。なかでも「越後上布」は、雪晒しによる美しい白さと、極細の絣模様で知られる伝統的な麻織物。その技術が江戸時代中期に絹へと応用され、塩沢紬として新たな展開を見せました。
- 奈良時代:越後地方では麻織物の産地として知られ、布づくりの文化が根づいていた。
- 平安〜鎌倉時代:朝廷や武家への上納品として麻布が評価される。
- 18世紀後半(江戸時代中期):越後上布の技術をもとに、絹素材で蚊絣の塩沢紬が誕生。
- 明治時代:製織技術の改良と市場拡大により、塩沢紬が各地で流通。蚊絣の精緻さが高評価を受ける。
- 昭和初期:草木染や手織による美術工芸品としての価値が認められ、全国で注目を集める。
- 1975年(昭和50年):塩沢紬が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
塩沢紬の特徴
真綿のぬくもりと、絣の芸術が織りなす美
塩沢紬の魅力は、織物全体に宿る静かな上品さと、絣(かすり)文様の精緻さにあります。とくに蚊絣と呼ばれる微細な点状の模様は、熟練した職人が数百本もの経緯糸を緻密に計算して染め、織り合わせることで初めて成り立つもので、その手間と技術はまさに工芸の粋です。
また、真綿から紡がれた紬糸の持つふんわりとした柔らかさが、肌になじむような優しい着心地を生み出します。色合いは落ち着いた茶系・灰系を基調とし、染色には自然由来の植物染料も多用されています。

塩沢紬の材料と道具
自然の恵みと繊細な技を支える道具たち
塩沢紬の織りに使われる材料や道具は、自然環境との調和の中で受け継がれてきました。繭から糸を取り出し、草木で染め、手作業で織るという一連の工程を支える道具の数々は、職人の手仕事と雪国の暮らしに根ざしています。
塩沢紬の主な材料類
- 真綿:蚕の繭を手で広げたもので、紬糸の原料。
- 紬糸(手紡ぎ糸):真綿から紡がれた糸。織物に独特の風合いを生む。
- 草木染原料:栗、藍、ヤマモモなどの植物染料が使われる。
塩沢紬の主な道具類
- 座繰り器:繭から糸を引くための装置。
- 地機:体重を使って織る手織り機。
- 箱枠・綜絖(そうこう):整経や織りの際に使用される糸道具。
- 筬(おさ):織りの密度を調整するための道具。
これらの素材と道具は、塩沢の風土と生活に根ざした文化の結晶です。
塩沢紬の製作工程
雪の恵みに支えられた、丹念な織りの技法
塩沢紬の製作には、原料準備から織り、仕上げまで多くの手作業が関わり、ひと織りひと織りが職人の技術と時間の集積です。
- 真綿づくり
繭を蒸して乾燥させ、手で広げて真綿をつくる。 - 糸紡ぎ
真綿から糸を引き出し、撚りをかけて紬糸にする。 - 染色
植物染料などで糸を染める。防染や多段階染めを行う場合もある。 - 絣括り
模様をつくる部分を防染する。絣模様の精度を決める工程。 - 整経・機仕掛け
染めた糸を整えて織機にかける。 - 手織り
地機を使って、手仕事で一反一反丁寧に織り上げる。
塩沢紬はその落ち着きある風合いと絣の美しさを備えた織物として仕上がります。