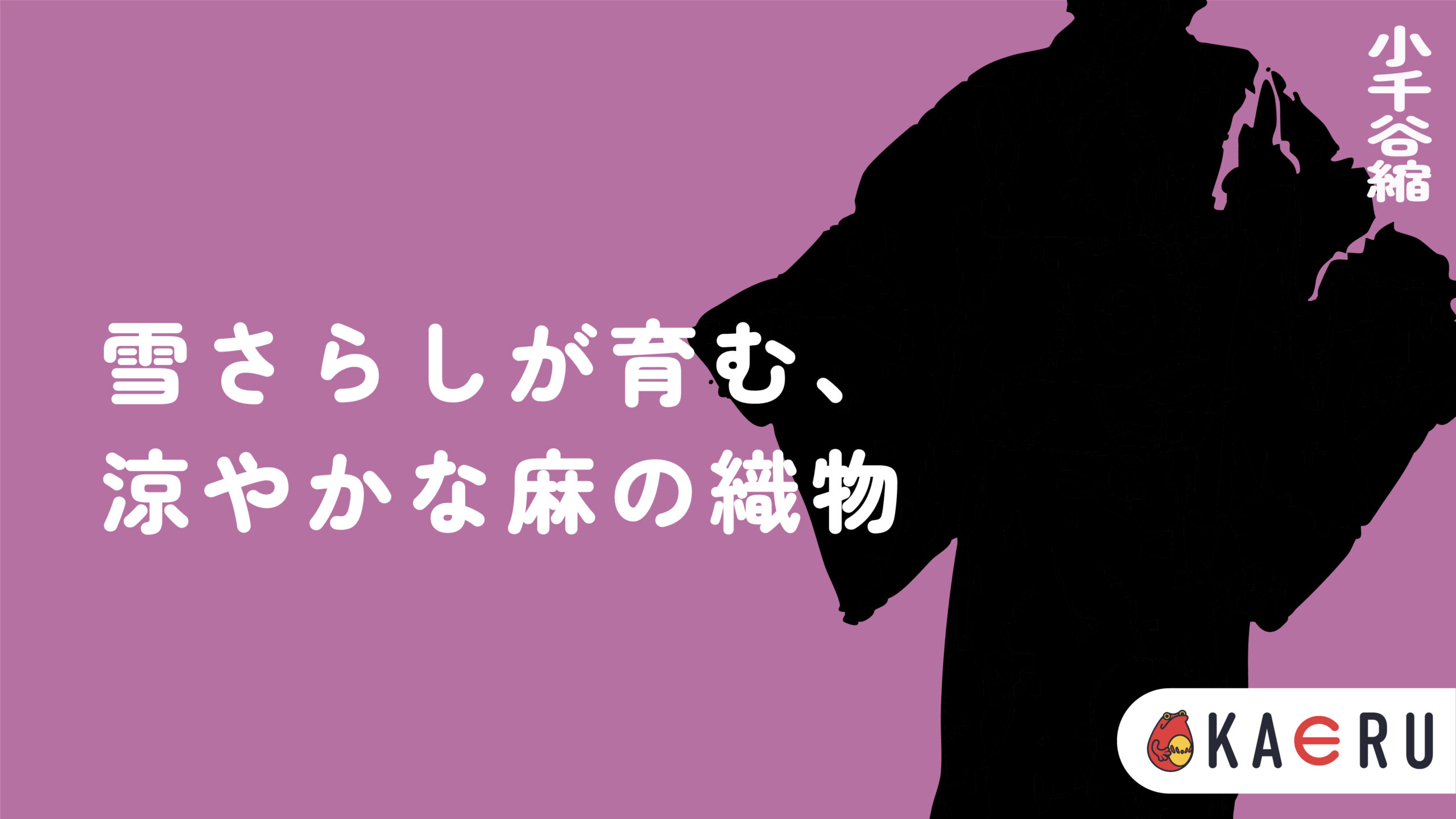小千谷縮とは?
小千谷縮(おぢやちぢみ)は、新潟県小千谷市を中心に生産される高級麻織物で、苧麻(ちょま)を原料とし、強撚の緯糸による独特の「しぼ(しわ)」と「雪さらし」による風合いが特徴です。古くは日常着や肌着として、現在は夏用の着物やインテリア素材として親しまれています。
江戸時代初期に、播磨国(現在の兵庫県)から伝えられた縮織技法により、越後の麻布は技術革新を遂げ、上質な「小千谷縮」へと進化しました。その完成度と希少性の高さから、2009年には「越後上布」とともにユネスコ無形文化遺産にも登録されています。
| 品目名 | 小千谷縮(おぢやちぢみ) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年9月4日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(14)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

小千谷縮の産地
縄文から現代へ、雪と共に生きる織物の里・小千谷

主要製造地域
小千谷縮のふるさと、新潟県小千谷市は、信濃川中流域に位置する豪雪地帯です。古くは縄文時代の遺跡から布目の土器が出土しており、布文化の痕跡が残っています。平安時代には朝廷への上納布として、鎌倉〜室町時代には民間の衣料として、越後の麻織物は長く日本人の生活とともにありました。
冬に3メートル近い積雪があるこの地では、農閑期の副業として織物づくりが根づき、女性たちの手によって家内制工業として発展しました。高い湿度は麻糸を扱いやすくし、清らかな雪解け水は染色や精練に適しています。
また、雪国独自の「雪さらし」は、小千谷縮の象徴的工程。積雪の白と太陽光を利用して自然に漂白するこの技術は、雪国ならではの知恵であり、地域に根づく文化そのものです。
小千谷縮の歴史
越後縮から世界遺産へ、麻と技術が育んだ縮織の系譜
小千谷縮の歴史は、単なる織物技術の伝承にとどまらず、気候と暮らしと改良精神の積み重ねから生まれた文化遺産です。
- 〜前1000年頃(縄文時代):布目のついた土器が小千谷地域の遺跡から出土。
- 8世紀(奈良時代):越後の麻布が朝廷に上納された記録が残る。
- 9〜13世紀(平安〜鎌倉時代):貴族や武家への贈答品・日常衣料として定着。
- 14〜16世紀(室町時代):農村部で麻布づくりが副業として拡大。
- 17世紀前半(江戸時代初期):播磨国明石藩の武士・堀次郎将俊が、強撚糸と湯もみを活用した縮織技法を小千谷に伝える。
- 18世紀後半〜幕末:越後縮の名で全国に流通し、夏着物の最高級品とされる。
- 1868〜1912年(明治時代):鉄道網と商業展開により、販路が広がる。
- 1975年(昭和50年):小千谷縮が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 2009年(平成21年):越後上布とともに「小千谷縮」がユネスコ無形文化遺産に登録。
小千谷縮の特徴
清涼感と上品な張りを備えた、夏の高級麻織物
小千谷縮の特徴は、緯糸に強い撚りをかけて織り上げた後、湯もみによって自然に「しぼ(しわ)」を生じさせる技法にあります。これにより布と肌の間に空気層が生まれ、さらりとした感触と清涼感が得られます。
さらに、吸水性・速乾性に優れているため、汗をかいても肌に張りつきにくく、夏物の着尺地として理想的です。染色には藍を中心とした草木染が用いられ、絣模様との組み合わせにより、伝統美と涼感が同居する布地が生まれます。
また、雪国ならではの「雪ざらし」によって、白地部分が美しく冴え、自然の漂白作用が見た目にも清らかな印象を与えます。

小千谷縮の材料と道具
苧麻と手仕事が生む、雪国の織物美
小千谷縮は、植物繊維である苧麻(ちょま)を主原料とし、繊維の取り出しから撚りかけ、織り、湯もみ、雪さらしまで一連の工程を支える道具は、地域の暮らしの中で受け継がれてきました。
小千谷縮の主な材料類
- 苧麻(ちょま):天然の麻繊維。通気性・速乾性・張りがあり、夏着物に適している。
- 草木染原料:藍を中心に、自然由来の染料が使われる。
小千谷縮の主な道具類
- 撚り機:緯糸に強い撚りをかけるための装置。
- 地機(じばた):手織り用の伝統的な織機。
- 湯もみ用桶・台:織布を手でもんで縮ませ、しぼを生む工程に使用。
- 雪ざらし台:冬の雪原で布を広げるための布干し用器具。
これらの道具と素材が、雪国の知恵と調和しながら、独自の美意識を織り成しています。
小千谷縮の製作工程
自然の力を生かした、涼やかな布づくり
小千谷縮は、職人の手業と雪国の自然環境を生かして作られます。各工程に高度な技術と丁寧な仕事が求められます。
- 糸づくり
苧麻の繊維を手で紡ぎ、経糸・緯糸に整える。緯糸には強い撚りをかける。 - かすり作り
図案に沿って、防染・染色を行い、絣模様をつくる。 - 機巻・機織
経糸・緯糸を整経し、地機を用いて手織りする。 - 湯もみ
織り上がった布をぬるま湯に入れて手でもみ、しぼを出す。 - 雪ざらし
冬の晴天時、雪原に布を広げ、太陽光と雪の反射で自然漂白する。 - 仕上げ
汚れを除去し、布幅を整えて検反し、完成させる。
小千谷縮は、雪国の知恵と麻の伝統が融合した夏の高級織物。しぼと雪さらしが生む涼感と美しさは、今も世界に誇る日本の工芸文化です。