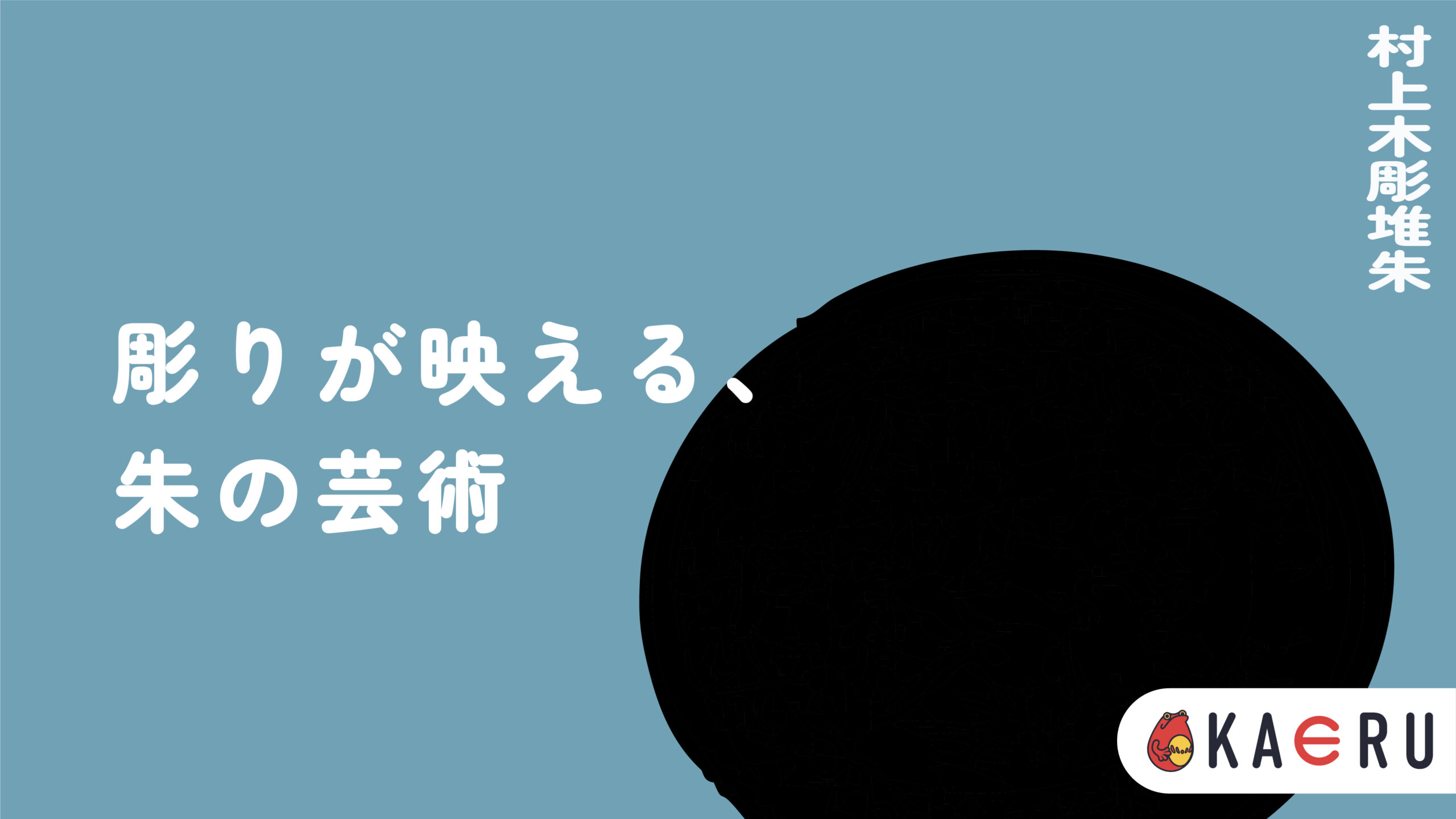村上木彫堆朱とは?
村上木彫堆朱(むらかみきぼりついしゅ)は、新潟県村上市で受け継がれている彫刻と漆塗りを融合させた伝統漆芸です。中国から伝来した「堆朱(ついしゅ)」の技法に、日本独自の木彫の美意識を掛け合わせて成立したもので、江戸時代に村上藩の武士たちが江戸彫刻の技法を持ち帰ったことにより、その基盤が築かれました。
他の漆芸と異なり、漆を塗ってから彫るのではなく、まず木を彫ってから漆を塗るというユニークな手法が特徴。この逆転の発想により、漆の無駄が少なく、立体的で深みのある文様が生まれます。赤みを帯びた落ち着いた朱色の仕上がりは、まさに彫刻と塗りの結晶といえるでしょう。
| 品目名 | 村上木彫堆朱(むらかみきぼりついしゅ) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年2月26日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 15(31)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

村上木彫堆朱の産地
越後の城下町が育んだ、木と漆の文化
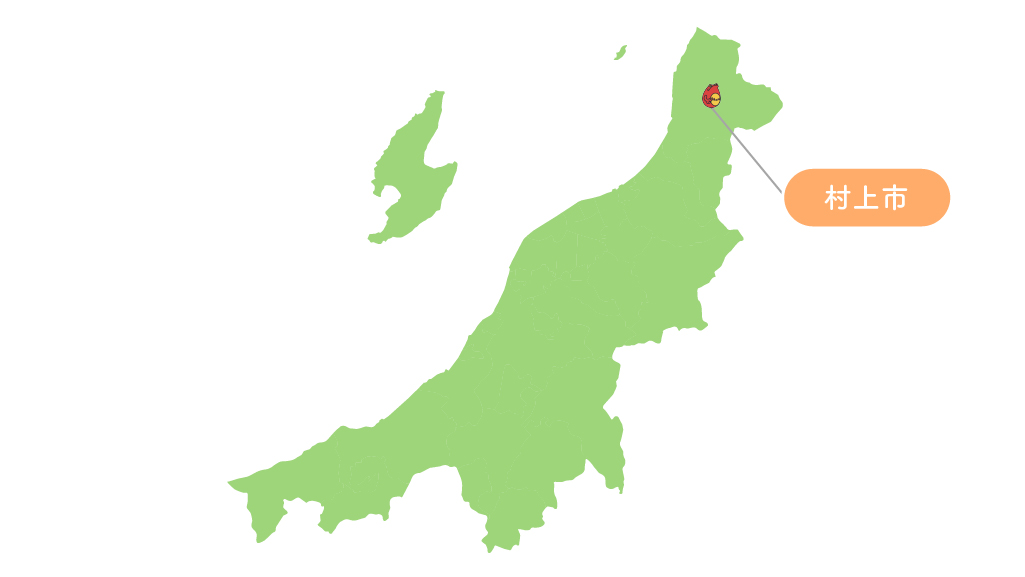
主要製造地域
村上木彫堆朱の主産地である新潟県村上市は、県北に位置する日本海沿いの歴史ある城下町です。周囲には、漆の木や、木地に用いられるホオノキ・トチノキ・カツラなどが自生し、漆器づくりに適した自然環境が整っていました。
また、日本海から吹き込む湿潤な気候は、漆を硬化させるうえでも理想的。村上は古くから漆の産地として知られ、平安時代からその名が記録に残っています。室町時代には寺院建立とともに多くの職人がこの地に入り、京都から来た塗師が漆器づくりを広めたと伝えられています。
こうした歴史と風土に支えられ、村上では木工・彫刻・漆塗りが融合し、独自の工芸文化が花開いていきました。
村上木彫堆朱の歴史
武士の嗜みから生まれた、江戸由来の漆芸
村上木彫堆朱の成り立ちは、越後・村上の漆文化と江戸彫刻の融合にあります。
- 平安時代:村上は漆の産地として記録される。天然漆が採取され、漆器づくりが行われていた。
- 室町時代:寺院の建立とともに、京都の塗師が移住し、漆器文化が根づく。
- 江戸時代前期:村上藩が漆器生産を奨励し、漆奉行を設置。漆の管理・栽培が制度化され、他地域へも出荷される。
- 江戸時代中期:江戸詰の武士が江戸彫刻と堆朱技法を習得し、村上へ持ち帰る。
- 明治時代:漆器が民間にも広まり、日常使いの器や装飾品として普及。地域全体で技法の保存・継承が進む。
- 1976年(昭和51年):村上木彫堆朱が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
江戸から伝わった技法に、越後の自然と美意識が加わり、村上木彫堆朱は独自の発展を遂げていきました。
村上木彫堆朱の特徴
彫りの陰影と艶消しの朱が織りなす、静謐の美
村上木彫堆朱の最大の魅力は、繊細な彫刻と、それを際立たせる朱漆の組み合わせです。あらかじめ木地を彫ってから塗りを施すため、模様の凹凸が鮮やかに浮かび上がり、まるで文様が浮かび上がるような立体感が生まれます。
なかでも「指頭ぬり」と呼ばれる技法では、彫刻を潰さないよう指の腹で漆を丁寧に塗り込み、仕上げには「つや消し」と呼ばれる炭研ぎが施されます。最終的に「毛彫り」で葉脈や羽根など細部の表現が加えられ、柔らかな陰影と重厚な美しさが共存する逸品に仕上がります。
さらに、「堆朱」「堆黒」「朱溜塗」「色漆塗」「金磨塗」「三彩彫」など、6種の技法があり、色彩や仕上げのバリエーションも豊か。茶托や箸、菓子器、装身具まで、実用品としても現代の生活に馴染む作品が多く生まれています。

村上木彫堆朱の材料と道具
越後の木々と漆が支える、手しごとの道具たち
村上木彫堆朱の製作には、地元の自然素材と、長年使い込まれた道具が欠かせません。木地の彫刻から漆塗り、仕上げまで、それぞれの工程に特化した職人と道具があります。
村上木彫堆朱の主な材料類
- ホオノキ・トチノキ・カツラ:木地に用いる。柔らかく彫刻に適した材。
- 生漆(きうるし):天然のウルシ。地元産が理想とされる。
- 砥の粉:漆に混ぜて下地処理に使う岩石粉末。
村上木彫堆朱の主な道具類
- 彫刻刀(うらじろ・毛彫り):模様の粗彫りや仕上げ彫りに使用。
- ハケ・筆:木がためや塗りに使う。
- 紙やすり/とくさ:木地の磨きに用いる。
- 炭・砥石:艶消しや中塗りの磨きに使用。
これらの素材と道具が、村上の風土と職人の手技を支え、静かな存在感を放つ漆芸品へと昇華させています。
村上木彫堆朱の製作工程
木を彫り、漆を塗り重ね、陰影を生む丁寧な仕事
村上木彫堆朱の製作工程は、木工と漆芸の技術が融合した、精緻で根気のいる手仕事です。
- 木地づくり
木地師が木材を切削・くり抜き・成形して、器や台の形を作る。 - 下絵かき
彫師が木地に花鳥風月や山水文様を描く。 - 木ぼり
下絵に従い、彫刻刀で立体的に彫る。 - とくさがけ
表面をとくさや紙やすりでなめらかに整える。 - 木がため
生漆を全面に塗って木地を保護する。 - さびつけ・さびとぎ
砥の粉を混ぜた漆を塗り、砥石で磨く。 - 中ぬり・中ぬりとぎ
彫りがつぶれないように中塗りし、再度磨きあげる。 - 上ぬり
朱漆を塗布し、作品全体を彩る。 - つや消し
炭や炭粉で研ぎ出し、落ち着いた艶を表現。 - 毛ぼり
細部の文様を細い彫刻刀で彫り出す。 - 上すりこみ
生漆を全体にすり込み、深みのある質感を仕上げる。
この緻密な工程を経て、村上木彫堆朱は他に類を見ない風格と存在感を備えた漆器となるのです。