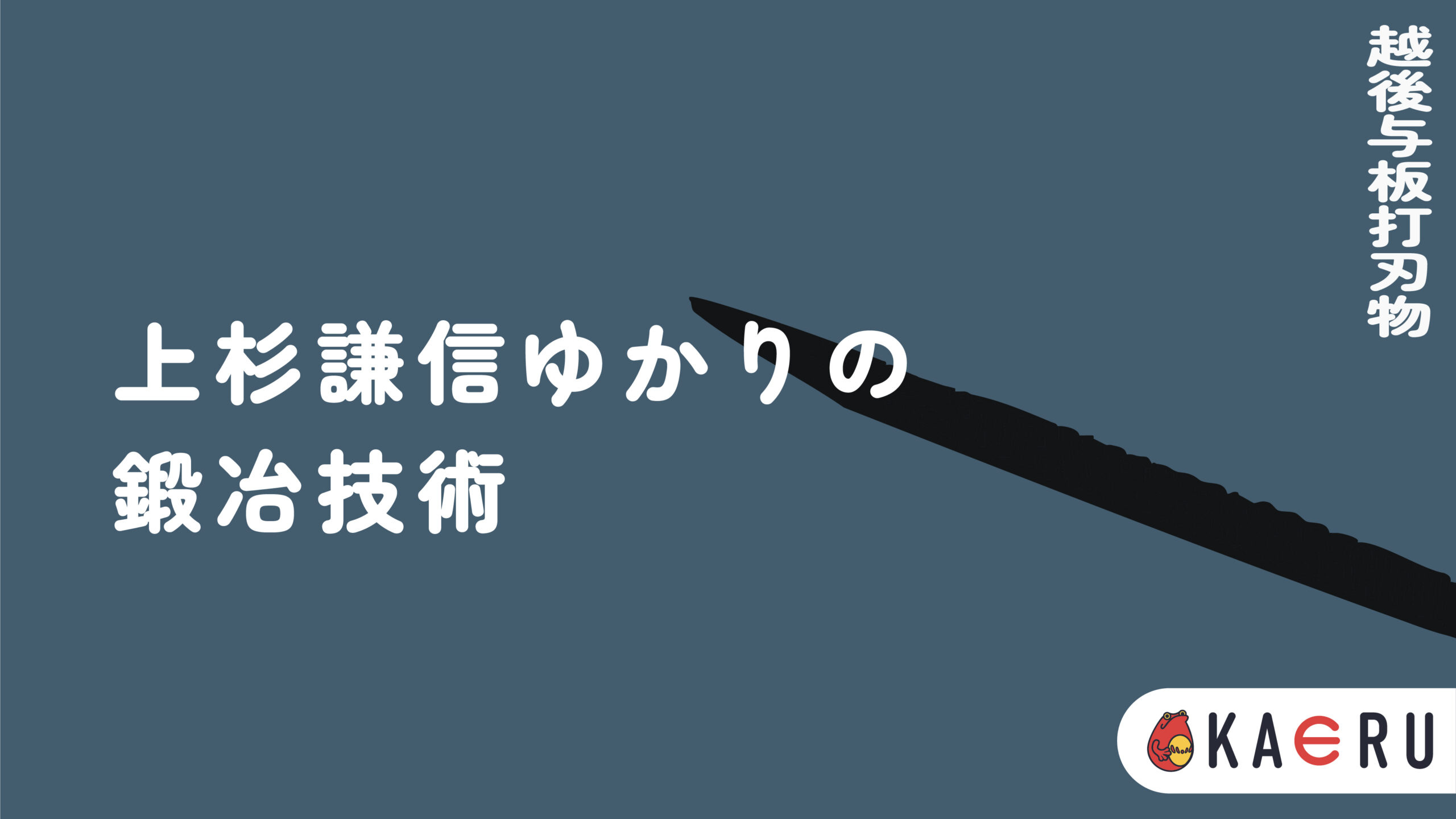越後与板打刃物とは?
越後与板打刃物(えちごよいたうちはもの)は、新潟県長岡市与板地域で製作される伝統的な刃物工芸品です。戦国時代に始まる刀剣鍛造の技術を礎に、江戸時代には大工道具の名産地として名を馳せ、現在ではかんな・のみ・ちょうな・まさかりなど多彩な打刃物が製造されています。
与板の刃物は、火造りによる鍛造法を用い、鉄と鋼を鍛接して何度も打ち鍛えることで、鋭い切れ味と耐久性を兼ね備えた逸品に仕上がります。現代においても、職人の手作業による精緻な仕上げと、用途に応じた機能性が評価され、多くの木工職人や建築関係者に支持されています。
| 品目名 | 越後与板打刃物(えちごよいたうちはもの) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 金工品 |
| 指定年月日 | 1986(昭和61)年3月12日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(16)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

越後与板打刃物の産地
雪国・越後に息づく鍛冶と職人のまち、与板
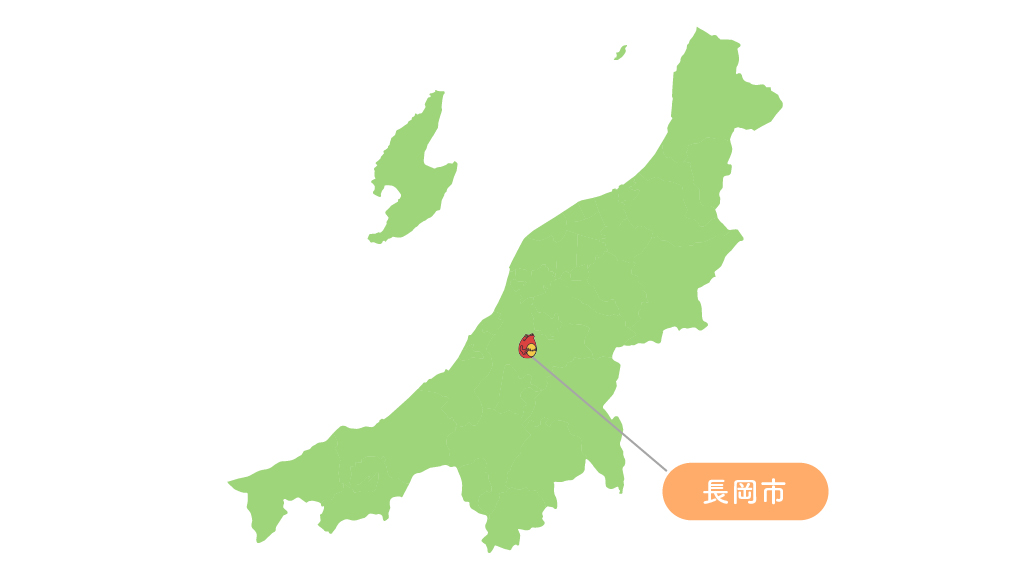
主要製造地域
越後与板打刃物の産地である新潟県長岡市与板地域は、信濃川と刈谷田川に挟まれた肥沃な地に広がる、自然と共に生きる町です。古くから水運に恵まれた交通の要衝として栄え、周辺の山間部からは良質な木材が集まり、木工や建築の需要が高い地域でした。そうした背景の中で、刃物の供給拠点として発展する素地が整っていたのです。
とくに注目すべきは、戦国時代にこの地を治めた名将・上杉謙信の存在です。彼の家臣が戦用の刀剣製造を目的として刀鍛冶を与板に招いたことが、この地に鍛冶文化が根づく端緒となりました。以来、武家の技術と農村の手仕事が融合するかたちで、実用的で高品質な刃物づくりが発展していきます。
また、与板は江戸期には長岡藩領として武具や農具の製造も盛んであり、冬季の農閑期を活かした鍛冶仕事が各家庭に広がりました。気候面でも、厳しい積雪と湿潤な空気が鉄材の保管や加工に適しており、焼入れや研磨の工程にも好影響を与えています。
越後与板打刃物の歴史
戦国の刀剣から大工道具へ
越後与板打刃物の歴史は、戦国武将・上杉謙信の時代に始まります。謙信の家臣である直江実綱(なおえさねつな)が、1578年に春日山から刀鍛冶を与板に招いたことが起源とされ、当初は武具製造の拠点として栄えました。その後、時代の変遷とともに刀剣から農具・大工道具へと展開し、火造り鍛造の高度な技術は現代まで脈々と受け継がれています。
- 16世紀後半(戦国時代):上杉謙信の家臣・直江実綱が、春日山から刀鍛冶を与板に招く。
- 17世紀(江戸初期):上杉家が米沢へ転封された後も職人たちは残り、農具や民具の製作へと技術が応用される。
- 18世紀(江戸中期):火造り鍛造の技術が成熟し、「土肥のみ」「兵部のみ」など名工の大工道具が全国に名を広める。
- 幕末〜明治初期:武士階級の廃止とともに刀剣の需要が急減し、建築用・木工用の刃物製造へと転換。
- 1880年代(明治20年代):木造建築の需要増加を背景に「かんな(鉋)」や「のみ」などの道具製造が活発化。
- 1986年(昭和61年):越後与板打刃物が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
越後与板打刃物の特徴
火造りが生む、鍛冶刃物の真価
越後与板打刃物の大きな特徴は、刀鍛冶の流れをくむ“火造り鍛造”にあります。高温に熱した鋼材を何度も打ち鍛え、硬さ・粘り・切れ味のバランスを職人の勘で調整するこの技法は、現代でも手作業で行われています。製品はすべて用途に応じた設計で、木工職人向けの「かんな」や「のみ」はもちろん、左利き用や特注形状も対応可能。美術工芸品のような佇まいを持ちながら、あくまで“使える道具”としての本質を貫いています。
また、刃先の研ぎやすさ、長時間の使用に耐える柄の設計など、実用面での配慮も評価が高く、道具にこだわるプロフェッショナルからも信頼を集めています。
越後与板打刃物の材料と道具
火と鉄を操る、職人の手と五感を支える道具たち
越後与板打刃物は、原材料の選定から鍛造、研磨にいたるまで、ひとつひとつの工程で熟練の技が要求されます。
越後与板打刃物の主な材料類
- 炭素鋼(白紙鋼・青紙鋼など):切れ味と研ぎやすさに優れた高炭素鋼。
- 軟鉄:芯材との鍛接に用いることで、粘りとしなやかさを補う。
- 柄材(ケヤキ・樫など):手に馴染み、長時間の使用にも耐える堅牢な木材。
越後与板打刃物の主な道具類
- 鍛造炉:鋼を高温で加熱し鍛造可能な状態にする。
- 金床(かなとこ):鋼材を打ち付けて成形するための鉄製台。
- 手槌(てづち):鋼材を打ち鍛えるためのハンマー。
- 鑢(やすり)・砥石:成形後の研磨や仕上げに使用。
これらの材料と道具が、与板の自然環境と歴史に根ざした鍛冶文化の中で今も生き続けています。
越後与板打刃物の製作工程
火花と汗が刻む、鍛造の技と工程
越後与板打刃物の製作工程は、刃物一本一本に職人の技術と魂が込められた手仕事の積み重ねです。
- 材料準備
用途に応じて鋼と軟鉄を選定し、適切な長さ・厚さに切断。 - 鍛接(たんせつ)
鋼と軟鉄を高温で熱し、打ち叩いて接合。 - 鍛造・成形
鍛接した素材を金床の上で何度も打ち、目的の形状に整える。 - 焼入れ・焼戻し
刃先を硬くするために急冷し、適切な硬度と粘りを調整。 - 研磨荒研ぎから仕上げまで数段階に分けて行い、切れ味と美しさを追求。
- 柄付け・最終調整
適した柄を選び、取り付けたのち、切れ味やバランスを確認して完成。
越後与板打刃物は一本ずつ丁寧に仕上げられていきます。そこには、400年以上にわたって受け継がれてきた鍛冶の伝統と、現代の暮らしに寄り添う実用性への深い配慮が息づいています。火と鉄と人の技が織りなす、与板ならではの手仕事の結晶は、使う人の手に確かな力とぬくもりを届けてくれます。