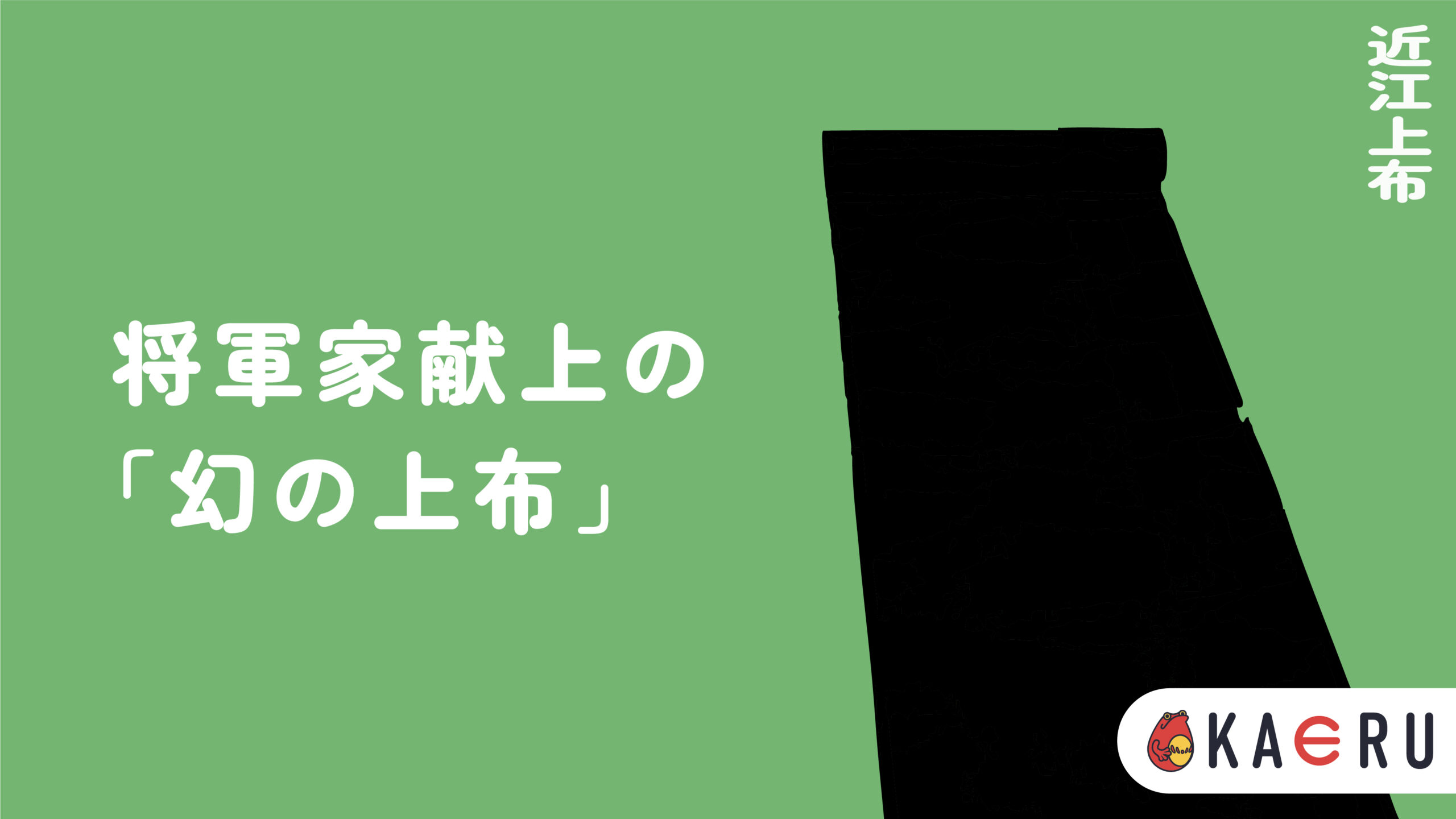近江上布とは?
近江上布(おうみじょうふ)は、滋賀県湖東地域で古くから織られてきた高級麻織物です。苧麻(ちょま)や大麻(おおあさ)といった天然繊維を使い、一本一本を手で績んだ糸から生まれるその布は、独特の光沢と軽やかな着心地を持ち、「幻の上布」とも称されてきました。
細く繊細な糸を用い、伝統的な「地機(じばた)」で織り上げられる近江上布は、手仕事の粋が凝縮された織物芸術です。特に、江戸時代には将軍家への献上品として珍重され、現代でもその希少性と美しさから高い評価を得ています。
| 品目名 | 近江上布(おうみじょうふ) |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1977(昭和52)年3月30日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 11(30)名 |
| その他の滋賀県の伝統的工芸品 | 信楽焼、彦根仏壇(全3品目) |
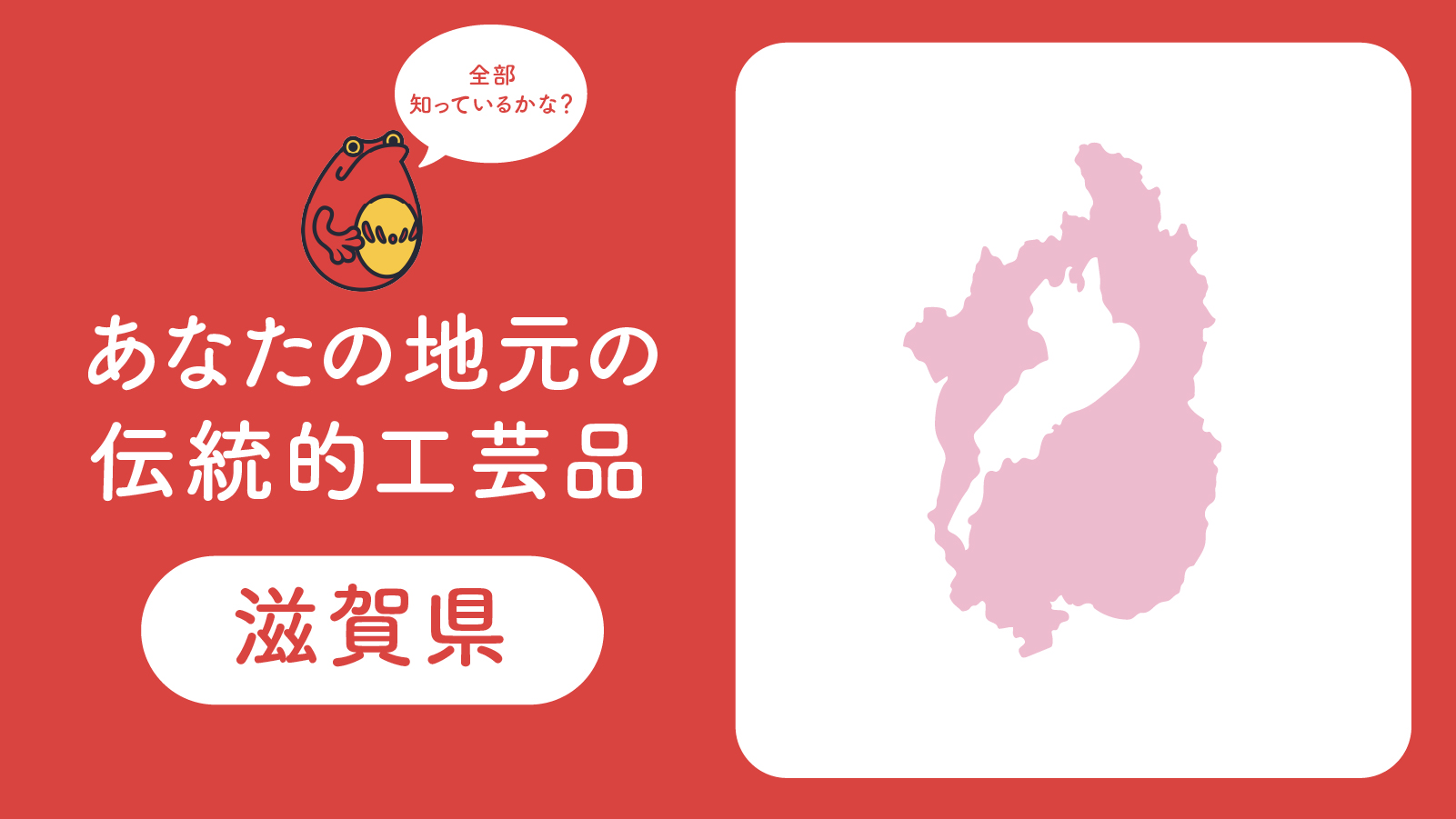
近江上布の産地
琵琶湖の恵みと暮らしの知恵が育んだ、麻織物の里

主要製造地域
近江上布の主産地は、滋賀県の湖東地域。特に愛知郡愛荘町、東近江市、彦根市、近江八幡市などが中心です。この一帯は、古くから「湖東麻布」と呼ばれる麻織物の一大産地として知られ、豊かな自然と文化が技術の継承を支えてきました。湖東地域は中世以降、農民が副業として麻布を織る地場産業が根付いた地域であり、江戸時代には彦根藩が保護政策をとることで技術と生産が一層活性化しました。また、近江商人の発展により他地域への流通網が構築され、麻布の名声が全国に広まっていきました。
仏教文化や武家文化の影響を受けた土地柄であり、質素で実用的ながらも品位を重んじる美意識が生活に根付いています。上布の「控えめな絣模様」や「繊細な手仕事」は、そうした文化的背景と深く結びついています。
また、琵琶湖の水蒸気がもたらす高湿度と、山間からの冷涼な風が、麻糸の取り扱いに最適な環境を生み出しています。麻は乾燥に弱く、糸が切れやすいため、湿度の高い気候は織作業において大きな利点となります。また、豊富な湧き水も染色や仕上げ工程に欠かせない資源として活用されてきました。
このように、自然・歴史・文化が織り合わさるなかで、近江上布は単なる織物ではなく、風土に根ざした生活文化の表現として発展してきたのです。
近江上布の歴史
献上布から暮らしの装いへ、六百年の技と意匠の変遷
近江上布は、室町時代に始まり、幾度もの革新を経ながら現在まで脈々と受け継がれてきた麻織物です。
- 14世紀後半(南北朝期):湖東地域で農家の副業として麻布の生産が始まる。自家用の衣類や蚊帳地として活用される。
- 1575年(天正3年):織田信長が近江一帯を支配。戦国大名の庇護下で、特産品としての麻布生産が安定化。
- 1603年(慶長8年):江戸幕府成立。彦根藩が麻布の産業保護を開始し、職人の技術指導や販路整備を行う。
- 1688年〜1704年(元禄期):染色技術が発展し、絣(かすり)模様の意匠が導入されはじめる。庶民の夏衣料として需要拡大。
- 1716年(享保元年):将軍家への献上品に指定。「近江上布」の名が文書に登場する最古の記録とされる。
- 1800年代前半(文化・文政期):絣の柄が多様化し、縞・格子に加え花草文様や流水文様なども織られるように。
- 1868年〜(明治期):化学染料の登場とともに一時的に伝統技法が衰退するが、地機による製法は継続される。
- 1950年代(昭和中期):化学繊維の普及により麻布の需要が減少。職人の数も激減する。
- 1977年(昭和52年):近江上布が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:涼感・天然素材へのニーズの高まりから、浴衣やファッション小物として再注目される。ワークショップや後継者育成も進む。
近江上布の特徴
麻がまとう涼と品、手仕事が紡ぐ幻の一反
近江上布の魅力は、なんといってもその風合いと模様にあります。麻糸が持つ自然の光沢と通気性、そして手績みによるやわらかな質感は、夏の衣類として理想的な素材です。派手さを抑えた素朴な絣文様は、縞、格子、十字柄のほか、流水や植物など自然のモチーフが多く用いられています。柄合わせには高度な技術が必要で、ずれのない整然とした模様は織手の腕の見せどころです。
苧麻・大麻ともに糸を手で績むため、1日あたり10gほどしか生産できません。1反分を織るには数ヶ月を要するため、大量生産ができず、結果として「幻」と呼ばれるほど希少性が高くなりました。
地機は腰に巻いた布を体で引っ張りながら織るため、織り手の感覚がそのまま布に伝わります。結果として肌にしなやかに沿う、柔らかくて馴染みやすい着心地が生まれます。大量生産の機械織りでは決して得られない“布の呼吸”がここにあります。

近江上布の材料と道具
手で績み、体で織る。自然と技が生む麻布の質感
近江上布は、素材選びから織りまでのすべての工程において、手作業と自然環境が密接に関わっています。特に繊維の細さや強度を見極める感覚と、織り機を「体の一部」として使う技術が求められます。
近江上布の主な材料類
- 苧麻(ちょま):経糸に使用される高品質の天然繊維。強度と光沢に優れる。
- 大麻(おおあさ):緯糸に使用。手績みにより柔らかさと通気性が生まれる。
- 天然染料:藍、刈安、クルミなど、自然由来の色で絣模様を染め出す。
近江上布の主な道具類
- 地機(じばた):腰に巻いて体の重みを使う手織り機。織手と布が一体化する。
- 絣括り具:文様部分の染め残しを作るために糸を括る道具。
- 杼(ひ):緯糸を通すための投げ杼(なげひ)。
- 手績み道具:麻繊維を撚り合わせて糸にするための道具一式。
こうした材料と道具が一体となって、近江上布の繊細な風合いが生まれます。
近江上布の製作工程
一糸一糸に思いを込めて織り上げる、伝統の手仕事
近江上布の製作工程は、すべて手作業で丁寧に行われ、完成までに長い時間と熟練の技術を要します。
- 原料の処理
苧麻や大麻の繊維を水に浸して柔らかくし、手で裂いて細かくする。 - 手績み(てうみ)
繊維を撚り合わせて糸にする。1日わずか10グラム程度の根気のいる作業。 - 絣括り
模様部分に防染のための括り(くくり)を施す。意匠に応じて何千回も括ることもある。 - 染色
天然染料で糸を染め上げる。染めムラが出ないよう天候や水温にも注意。 - 整経・地機設置
経糸を揃え、地機に掛けて準備する。 - 織り
腰機(こしかた)とも呼ばれる地機で、体全体を使いながら布を織っていく。 - 仕上げ
織り上がった布を湯通しし、天日に干して自然な風合いを整える。
このように、自然と対話しながら糸と布を育てていく過程が、近江上布の唯一無二の存在感を形づくっています。
近江上布は、滋賀の風土と人々の手仕事が織り上げた、日本を代表する麻織物です。湖東地域の自然環境、歴史的背景、文化的美意識のすべてが織り込まれた一反には、実用性と芸術性が共存しています。今もなお、伝統を守りながら現代の暮らしに寄り添い続ける近江上布は、涼やかな季節の装いに、静かな誇りと美しさを添えてくれる存在です。