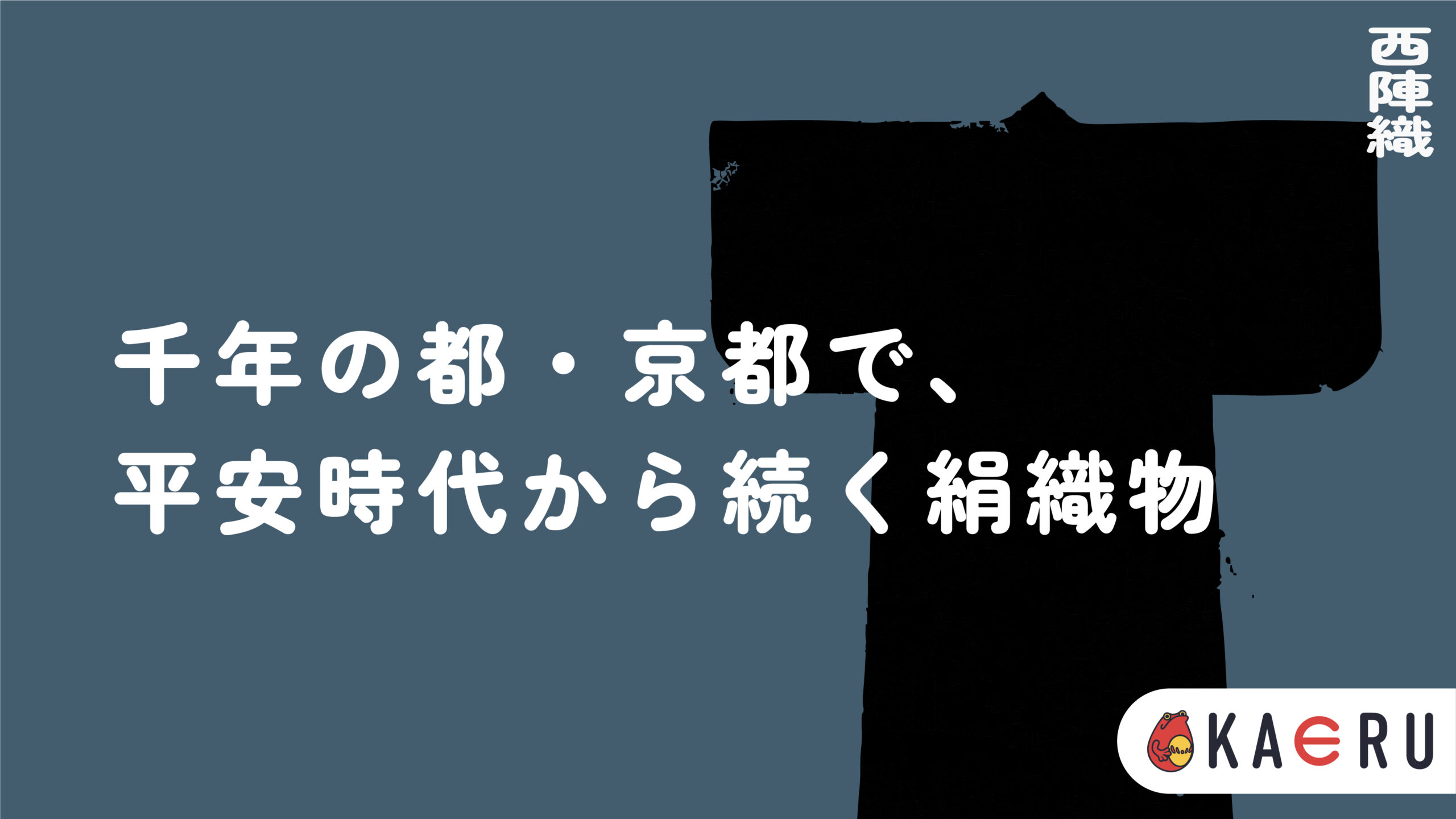西陣織とは?
西陣織(にしじんおり)は、京都市北西部で生まれ、千年以上にわたり受け継がれてきた高級絹織物です。色とりどりに染め分けられた絹糸を用い、織りだけで模様を浮かび上がらせる「先染め紋織物」として、世界でも類を見ない精緻な意匠を実現しています。
その技術と美意識は、雅やかな王朝文化や武家文化と深く結びつき、能装束・打掛・帯などの晴れ着に用いられてきました。織りの種類は多岐にわたり、「緞子」「綴」「紹巴」「錦」など十数種を数える複雑な技法体系と、数百に及ぶ分業体制が特徴です。
| 品目名 | 西陣織(にしじんおり) |
| 都道府県 | 京都府 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年2月26日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 214(556)名 |
| その他の京都府の伝統的工芸品 | 京漆器、京友禅、京うちわ、京指物、京繍、京くみひも、京仏具、京小紋、京鹿の子絞、京仏壇、京黒紋付染、京石工芸品、京焼・清水焼、京扇子、京人形、京表具(全17品目) |

西陣織の産地
洛中洛外の文脈に息づく、都の織物文化

主要製造地域
西陣織の産地は、京都市上京区・北区を中心とする地域です。なかでも「西陣」という呼称は、応仁の乱(1467〜1477年)の際に西軍の本陣が置かれたことに由来しており、戦後に戻った職人たちが再びこの地で機を織り始めたことで定着しました。
平安京の建都(794年)以来、京都は常に政治・文化・宗教の中心地であり、貴族や皇室の衣装、寺院の装飾用織物などの需要が絶えなかったことが、西陣織の発展を支えてきました。中世以降も、天皇家や公家、武家階級、町衆文化など、多様な階層の美意識に応える高度な織物が生産されてきたのです。
また、西陣界隈には美術工芸、茶道、華道、能楽、仏教美術といったあらゆる伝統文化が交差しており、それらが西陣織の意匠や色彩に多大な影響を与えてきました。能装束に見られる幾何学文様や、茶人の美意識を映す淡色の織物などには、京都文化特有の繊細さと静けさが表現されています。
京都盆地は四季が明瞭で、特に夏は高温多湿、冬は底冷えする内陸性の気候です。この環境は、絹糸の乾燥や染色、保管に一定の配慮を要する反面、職人にとっては素材や工程への深い理解を促す要素ともなってきました。また、鴨川・賀茂川の豊富な水資源は、糸染めや湯のしなどの水作業を支える重要な条件となっています。
西陣織の歴史
千年の都が育んだ、織の系譜と美意識
西陣織は、渡来技術に始まり、王朝文化や戦乱、分業体制の確立を経て現在に至るまで、幾度もの変革を経ながら織の文化を育んできました。
- 5世紀後半: 応神天皇時代に、渡来人・秦氏が絹織物技術を伝来。山背国(のちの京都)に拠点を置く。
- 794年(平安遷都): 京都が日本の都となり、貴族階級の装束や調度品として絹織物の需要が急増。
- 11世紀(平安中期): 「綴(つづれ)」や「錦織」など、装飾性の高い織物技法が確立。
- 1467年(応仁の乱): 京都市街が戦火で荒廃。織物職人たちは各地に避難。
- 1477年: 応仁の乱終結後、織師たちが西軍の旧陣地に戻り、機業を再開。地名「西陣」が生まれる。
- 17世紀(江戸初期): 西陣が幕府公認の織物産地として繁栄。分業体制が整う。
- 18世紀中頃: 能装束や帯などの高級品に特化。独自の色彩と意匠が確立。
- 1872年(明治5年): 西陣にジャカード機が導入され、自動化と複雑紋様の量産が進む。
- 昭和初期: 高級帯の需要が高まり、「手機」と「動力織機」の併用体制が確立。
- 1976年(昭和51年):西陣織が 経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
西陣織の特徴
糸と技が織り成す、絹の芸術
西陣織の最大の特徴は、先染めの絹糸を用いた織り模様にあります。染められた糸を数百本単位で設計し、その配置と織り構造の組み合わせだけで、立体的かつ色彩豊かな意匠を織り出す点は、世界の織物のなかでも極めて独自性が高いものです。
織物の種類も多彩で、緞子(どんす)や綴(つづれ)、緯錦(ぬきにしき)、紹巴(しょうは)、朱珍(しゅちん)など、用途や表現に応じて十数種類の技法が用いられています。とくに綴織では、織手が爪を鋸のように削って使い、一本一本の糸を爪でかき寄せながら丁寧に文様を織り上げるという、非常に高度で根気の要る作業が続けられています。
1本の帯を仕上げるまでに数万本の糸を使用し、手機で織る場合には一ヶ月以上かかることも珍しくありません。糸の種類や織り方の違いによって、同じ文様でも質感や陰影がまったく異なる印象を与えるという点も、西陣織ならではの奥深さと言えます。

西陣織の材料と道具
糸に命を吹き込む、職人と分業の匠の連携
西陣織の製作には、多くの工程と専門職が関わります。素材の選定と道具の精緻さが、その品質を支えています。
西陣織の主な材料類
- 生糸(絹糸):主に国産または中国産の高級糸を使用。光沢と強度を併せ持つ。
- 金糸・銀糸:帯や礼装用の意匠に用いられる装飾糸。
- 染料:天然染料から合成染料まで用途によって使い分ける。
西陣織の主な道具類
- 手織機(手機):高級織物に使われる伝統的な機織り機。
- ジャカード装置:紋様の複雑な制御を可能にする装置。
- 紋紙:紋様を制御するための厚紙。設計図のような役割。
- 織杼(しょくひ):緯糸を通すための舟形の道具。
こうした素材と道具に加え、図案作成・染め・整経・製織などの分業体制が西陣織の技術を支えています。
西陣織の製作工程
多彩な意匠を実現する、分業と熟練の連携プロセス
西陣織は、数十にもおよぶ工程を経て完成します。それぞれの工程に専門の職人が関わり、精緻な織物が生まれます。
- 図案制作
使用目的(帯・着物など)に応じて意匠を設計。伝統文様から現代柄まで多様。 - 紋紙作成
図案に基づき織り機を制御するための「紋紙」を作成。手作業で穴を空けていく。 - 原糸準備・染色
絹糸を用途に応じて染め分け。高度な色管理が必要。 - 整経(せいけい)
経糸を機にかけるために本数・張力を揃えて並べる。 - 織り(製織)
手織機またはジャカード機で、緻密な模様を織り上げる。 - 仕上げ
湯のし・検反・整理などで最終調整。光沢や風合いを整える。
完成した西陣織は、技と感性が響き合う絹の芸術作品。長い工程を経て、絹糸が“意匠”へと昇華する瞬間を物語っています。
西陣織は、京都の歴史と文化、そして職人たちの高度な技が織り重なって生まれる絹の芸術です。緻密な分業と多様な織技法によって、一本の糸が美しい意匠へと昇華するプロセスは、まさに日本の美意識の結晶。未来に受け継ぐべき、世界に誇る伝統工芸です。