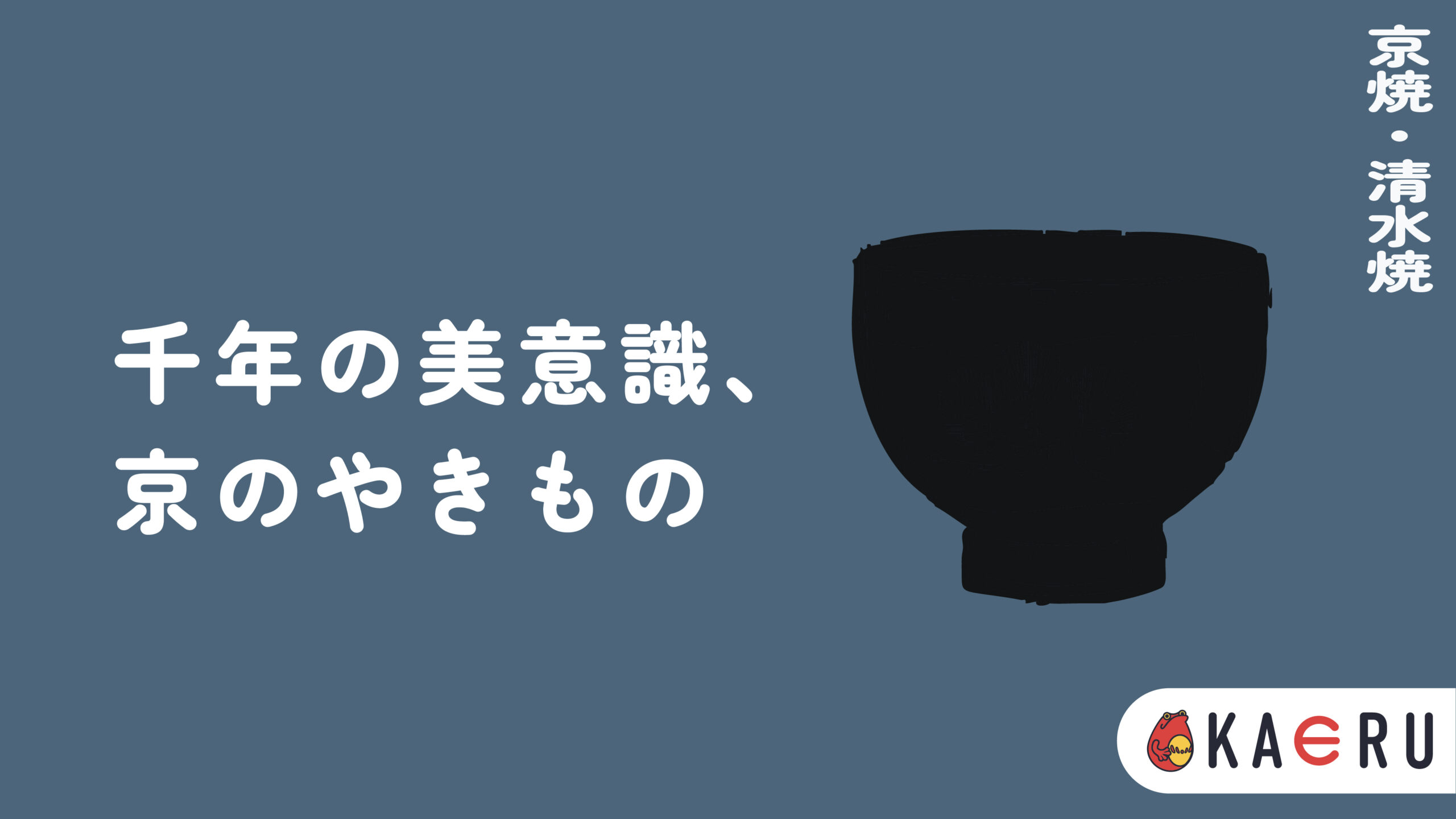京焼・清水焼とは?
京焼・清水焼(きょうやき・きよみずやき)は、京都市を中心に生産されている陶磁器で、日本の陶芸文化の粋とも言える存在です。一つの流派や様式にとらわれず、多種多様な技法や表現が並立する点が大きな特徴で、時代とともに茶の湯・華道・料理文化などと密接に関わりながら進化を遂げてきました。
特に江戸時代以降、東山・清水寺界隈の窯で生産された陶器を「清水焼」と称するようになり、これが総称として定着しました。
| 品目名 | 京焼・清水焼(きょうやき・きよみずやき) |
| 都道府県 | 京都府 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1977(昭和52)年3月20日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 57(137)名 |
| その他の京都府の伝統的工芸品 | 西陣織、京漆器、京友禅、京うちわ、京指物、京繍、京くみひも、京仏具、京小紋、京鹿の子絞、京仏壇、京黒紋付染、京石工芸品、京扇子、京人形、京表具(全17品目) |

京焼・清水焼の産地
千年の都が育んだ、美意識と匠の技が交差する陶の街

主要製造地域
京焼・清水焼の主産地は京都市内、とくに東山区・山科区・伏見区などに集中しています。とりわけ東山・清水寺界隈は「五条坂」や「茶わん坂」の通称でも知られ、焼き物の町として古くから多くの陶工が工房を構えてきました。
京都は平安時代から都として栄え、貴族・武家・僧侶らが器物に高い審美眼を持ち、茶道や香道、懐石料理などの文化とともに器への需要と洗練が進みました。江戸期には町人文化も加わり、注文主の多様な美意識に応えることで、京焼は“型にはまらない焼き物”として独自の進化を遂げたのです。
また、絵画・染織・建築・書などの諸芸術と常に近い距離にあり、陶芸もまたその一翼を担ってきました。狩野派の流れを汲んだ絵付け、琳派の意匠、唐物写し、さらには仏教美術や建築装飾との連関など、京都に息づく総合芸術のひとつとして発展してきました。
京焼・清水焼の歴史
茶の湯とともに進化した、器文化の変遷
京焼・清水焼の歴史は平安時代に遡りますが、工芸品としての確立は桃山時代以降の茶陶の隆盛によって加速しました。
- 794〜1185年(平安時代):京都で土師器・須恵器が盛んに作られ、日用品としての器文化が根付く。
- 1185〜1333年(鎌倉時代):禅宗の広まりにより、宋から伝わった唐物陶磁が茶人に珍重され、舶来陶磁への憧れが高まる。
- 1336〜1573年(室町時代):東山文化の隆盛とともに茶道が普及し、東山・南禅寺周辺に陶工が集まり茶陶制作が本格化。
- 1573〜1603年(桃山時代):千利休の茶の湯文化を背景に、登り窯が導入され、侘び寂びを備えた手づくりの茶陶が多数生み出される。
- 1603〜1650年(江戸前期):野々村仁清が仁和寺門前に窯を築き、色絵技法を確立。京焼に華やかな意匠と高い装飾性をもたらす 。
- 1650〜1750年(江戸中期):元禄文化の中で尾形乾山が絵画性豊かな陶芸作品を発表。弟・光琳との協働で新たな様式美を確立 。
- 1750〜1868年(江戸後期):清水寺門前の五条坂で窯元が急増し、「清水焼」の名が広まり京都の代表的な焼物として定着 。
- 1868〜1912年(明治時代):万国博覧会への出品を契機に輸出が盛んになり、洋風意匠や写し物の制作も増加。近代化と融合が進む。
- 1977年(昭和52年):京焼・清水焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:日常器から茶陶、アート作品まで多岐にわたる展開で、国内外のファンを魅了し続けている。
京焼・清水焼の特徴
多様性こそが最大の個性、“京らしさ”がにじむ美のバリエーション
京焼・清水焼の最大の特徴は、流派や型に縛られない圧倒的な自由度にあります。一つの窯元で複数の技法やスタイルを同時に展開するのは、全国的に見ても非常に珍しく、京都ならではの芸術文化の懐の深さを物語っています。
野々村仁清が確立した色絵技法では、白地に鮮やかな赤や緑、金彩を組み合わせた華やかな意匠が用いられ、現代でも祝いの席を彩る器として親しまれています。また、尾形乾山の流れを汲む絵画的な装飾では、手びねりによる不均一な造形の中に、筆で描いた草花文様が自然に溶け込み、まるで一幅の絵画のような趣を醸し出します。
技術面では、器の表面を削って模様を浮かび上がらせる透かし彫りや、複数の色土を重ねて断面模様を見せる練り込みなど、立体的で視覚的な演出を得意とする作品もあります。こうした造形力の高さは、彫刻や染織など他の工芸分野との影響を受け合いながら磨かれてきたものであり、京焼ならではの総合的な美の結晶と言えるでしょう。
また、特徴的なのが“写し物”の文化です。これは古伊万里や唐物など、他地域や中国・朝鮮の名陶を研究し、写実的に再現する技術で、写しでありながらもどこかに京風の品格が漂う点に京都職人の美意識が垣間見えます。
さらに、京焼・清水焼は「季節を映す器」とも称され、春には桜や若芽、夏には流水や朝顔、秋には紅葉、冬には雪輪や椿といった意匠が、器の形や絵付けの中に織り込まれています。こうした四季の表現を器に託す感性は、料理や空間演出の一部として、使い手の心を和ませる大きな魅力となっています。

京焼・清水焼の材料と道具
多種多様な表現を支える、選ばれし素材と精緻な道具
京焼・清水焼の製作には、釉薬・土・顔料・絵付け筆など、用途に応じた選定が求められます。
京焼・清水焼の主な材料類
- 陶土(信楽土・天草陶石など):器の基礎となる。各作風に応じてブレンドされる。
- 釉薬(青磁釉、飴釉、灰釉、織部釉など):表面の発色や質感を決定する。調合に独自性あり。
- 顔料:鉄、銅、コバルトなどを含む顔料で絵付けを施す。
京焼・清水焼の主な道具類
- ロクロ:成形に使用。電動・蹴りロクロなど用途に応じて使い分け。
- カンナ:高台や表面を削るための刃物。
- 絵付け筆:極細の線や塗り面を描き分けるための専用筆。
- 型(石膏型など):練り込み成形や複製に使われる。
- 焼成窯(電気窯・ガス窯・登り窯など):作品により焼成温度や方法が異なる。
素材と道具の自由度が高いことこそが、京焼・清水焼の際立つ個性。芸術性と機能性の両立を支える礎として、唯一無二の表現を実現しています。
京焼・清水焼の製作工程
多彩な技法が織りなす、手業と火の競演
京焼・清水焼の魅力は、職人の自由な発想と確かな技術が積み重なる工程そのものに宿ります。
- 土練り・調合
粘土を適切な柔らかさに練り、気泡を抜く。作品によっては他地域の陶土とブレンドされる。 - 成形
ロクロ成形・手びねり・型押し・鋳込みなど、用途や作風に応じて技法を選ぶ。 - 乾燥
ゆっくりと時間をかけて乾燥させ、ヒビや歪みを防ぐ。特に季節や湿度の影響を受けやすい工程。 - 素焼き
700~900℃で素焼きすることで、強度を持たせ、釉薬や絵付けを受け入れる下地を作る。 - 絵付け・釉掛け
鉄絵・呉須による下絵や、色絵・金彩などの上絵を施し、透明釉・色釉をかけて焼成準備をする。 - 本焼き
1300℃前後の高温で焼成。電気窯・ガス窯・登り窯などがあり、窯の種類や炎の性質で仕上がりが変化。 - 仕上げ・検品
底を削って整え、欠けや割れを確認。金継ぎや追加の上絵焼成を行うこともある。 - 箱詰め・完成
桐箱や紙箱に収納し、落款や銘を添えて完成。高級品では「しおり」や証紙も添えられる。
京焼・清水焼は、京都の歴史と美意識、職人の自由な発想が融合した日本有数の陶磁器です。多彩な技法と用途を持ち、使うたびに新しい発見がある“日常に寄り添う芸術品”。現代の暮らしにも調和する美のかたちとして、今なお進化を続けています。