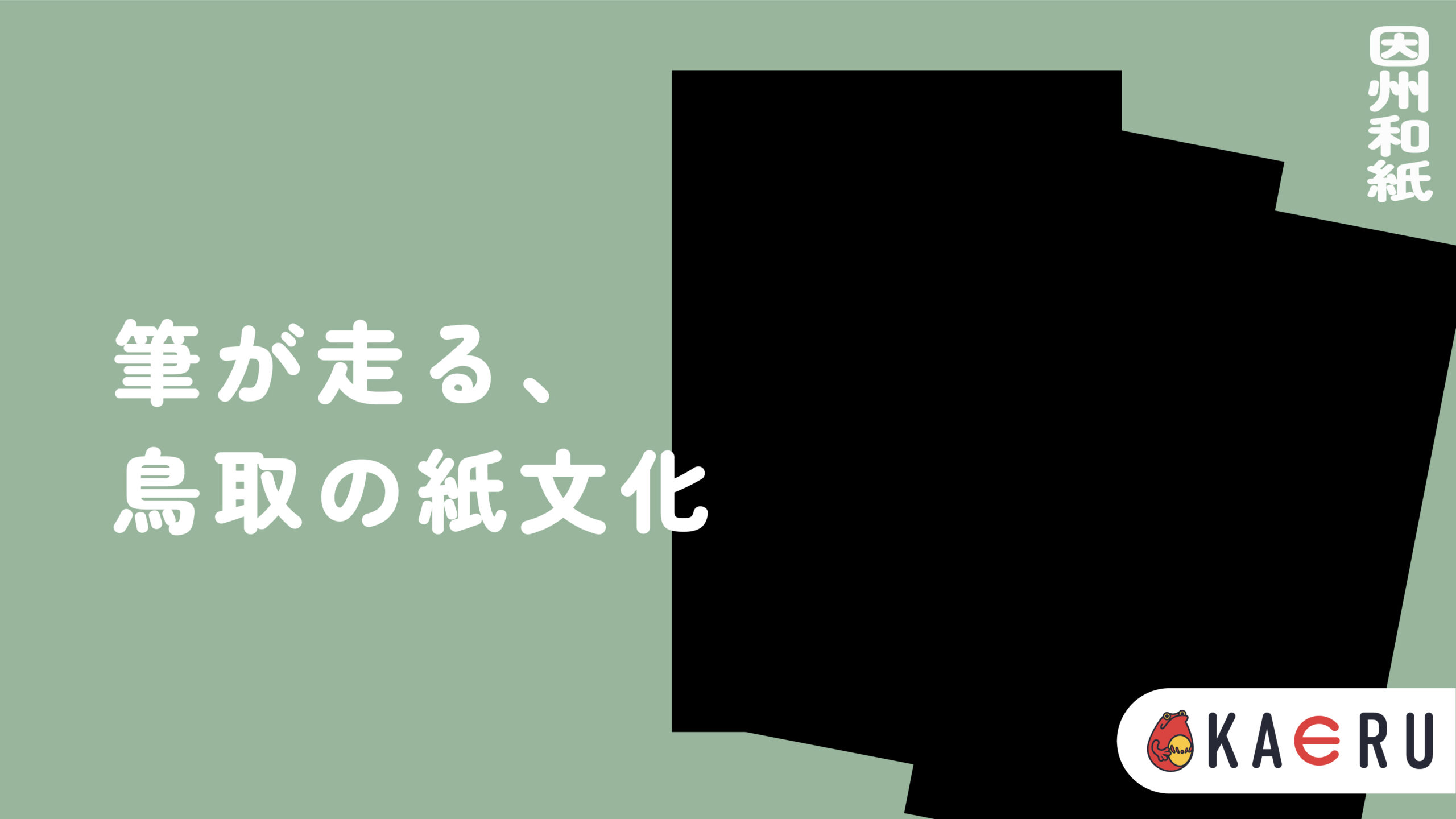因州和紙とは?
因州和紙(いんしゅうわし)は、鳥取県東部に位置する青谷町・佐治町を中心に作られている伝統的な和紙です。1300年を超えるとされるその歴史の中で、書道用紙としての評価を高め、「因州筆切れず」と称されるほど筆運びに優れた品質を守り続けてきました。
その魅力は、コウゾ・ミツマタ・ガンピなどの天然繊維を手間ひまかけて紙に漉き上げる伝統的な製法にあります。特に書道用の画仙紙は全国生産量の6〜7割を占め、国内トップシェアを誇る書のための紙文化として知られています。滑らかな書き味、墨のにじみやかすれの美しさ、しなやかな強さ。そのすべてが、因州和紙の丁寧な手仕事の賜物なのです。
| 品目名 | 因州和紙(いんしゅうわし) |
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 分類 | 和紙 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 4(26)名 |
| その他の鳥取県の伝統的工芸品 | 弓浜絣、出雲石燈ろう(全3品目) |

因州和紙の産地
山紫水明の地に息づく、書の紙文化のふるさと
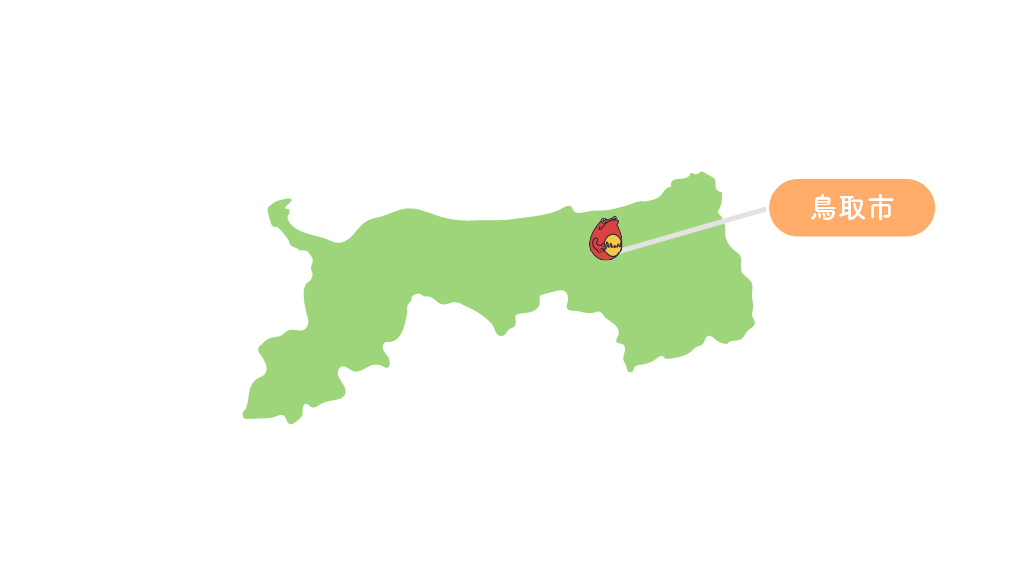
主要製造地域
因州和紙の主産地は、鳥取県鳥取市の青谷町と佐治町。中国山地の支脈が織りなす山あいの地であり、そこを流れる清流・勝部川や佐治川の水は、紙漉きに最適な透明度と冷たさを誇ります。この地は古くからコウゾ・ミツマタの栽培に適しており、さらに竹・麻などの素材も豊富。和紙の原料・水・気候の三拍子がそろったこの環境こそが、良質な手漉き和紙の継続的な生産を可能にしてきました。
特に佐治町は「紙のふるさと」とも呼ばれ、地域ぐるみで和紙の伝統を守り、後継者の育成にも取り組んでいます。現代では書道用紙だけでなく、工芸紙やインテリア用途、機能性和紙など、新たな展開も生まれています。
因州和紙の歴史
朝廷献上の記録から現代アートへ。1300年続く紙の系譜
因州和紙の起源は定かではありませんが、平安時代の法典『延喜式』には、因幡国(現在の鳥取県東部)から紙が献上されたとの記録が見られます。これは因州和紙が少なくとも1000年以上前から存在していたことを示しています。
- 8世紀(奈良時代):正倉院に残された文書に、因幡産とみられる和紙が含まれる。
- 927年(延長5年):『延喜式』に、因幡国から朝廷へ紙を献上した記録が記載。
- 1600年代(江戸初期):鳥取藩が和紙の品質を重視し、御用紙制度が確立。
- 1596〜1615年(慶長年間):因州紙が海外にも輸出されるようになる。
- 18世紀中頃:町人層による生活用紙の需要が拡大。帳簿用紙・包装紙などが流通。
- 1880年代(明治20年代):ミツマタの大規模栽培が始まり、和紙原料の安定供給へ。
- 1920年代(大正末期):機械技術の導入と販路の拡大で生産量がピークに。
- 1950〜60年代(昭和30年代):書道用の画仙紙が本格的に生産開始。品質の高さが評価される。
- 1975年(昭和50年):因州和紙が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:機能性和紙・アート用途の紙など多様な商品開発が進行中。
因州和紙の特徴
筆に寄り添う、繊維のきめ細やかさと墨のにじみの妙
因州和紙の最大の魅力は、その「筆運びの良さ」です。繊維が均一に絡み合い、表面がなめらかなため、筆先がスッと紙に吸い込まれるような感覚で書くことができます。こうした特性から「因州筆切れず」と称され、書道家や篆刻家、さらには書写教育現場でも広く用いられています。
特筆すべきは、墨のにじみやかすれの美しさ。これはトロロアオイの粘液を加えた流し漉き技法と、紙質に応じた原料の調整によって実現されています。たとえば、ミツマタを多めに配合すれば光沢が増して筆の滑りがよくなり、細字や仮名書きに最適。ガンピを加えると墨の濃淡がくっきり出て、墨絵や水墨画に向いた紙が生まれます。また、酸化防止処理を施した高保存性の和紙は、展覧用や長期保管にも適しています。
さらに知っておきたいのが、“紙粉(しふん)”の出にくさ。因州和紙は、原料繊維の長さが揃っているため筆先に繊維が絡まず、紙面に粉が出にくいという利点があります。作品の保存性を高めるうえで、この特徴は見逃せません。
そして、もう一つの魅力は「音」。因州和紙の紙漉きに使われる簀桁(すけた)が立てる“さらさら”“じゃぶじゃぶ”という音は、1996年に「日本音風景100選」にも選定されました。自然と職人の手技が織りなす音そのものが、文化財として評価されているのです。

因州和紙の材料と道具
紙の繊維を見極める、自然と向き合う手仕事の世界
因州和紙の製作では、原料の選定から乾燥まで、すべてが人の手で行われます。素材の良し悪しが、書き心地や墨の映え方を大きく左右するため、職人の目利きと経験が不可欠です。
因州和紙の主な材料類
- コウゾ:繊維が長く、強靭でにじみにくい。和紙の基本素材。
- ミツマタ:柔軟性と光沢に優れ、書道紙や奉書紙に最適。
- ガンピ:高級和紙に使用。繊細で艶のある仕上がり。
- トロロアオイ:粘液質を加えることで繊維を均一に分散させる。
- 麻・竹:にじみの表現に幅を持たせるための補助素材。
因州和紙の主な道具類
- 簀桁(すけた):竹や桜の皮で作られる紙漉き用の枠道具。
- 包丁:樹皮から黒皮をそぎ落とす際に用いる。
- 叩き棒:繊維を叩いて細かくし、漉きやすくする道具。
- 刷毛・乾燥板:紙を平滑に伸ばして乾燥させるための器具。
素材を調和させる調合技術と、紙を漉く「手のリズム」が、因州和紙のしなやかさと美しさを生み出します。
因州和紙の製作工程
水と繊維が織りなす、一枚の紙に宿る時間と技
因州和紙の製作工程は、およそ7〜8の工程に分かれ、すべてが手作業で丁寧に進められます。
- 皮剥ぎ
原料となるコウゾやミツマタを水に浸けて柔らかくし、包丁で黒皮を取り除く。 - 煮る
木灰や石灰を加えながら煮ることで、不純物を取り除き、繊維を分解。 - さらす
川の清水に晒してアク抜きし、ゴミや硬い繊維を手作業で取り除く。 - 叩く
木槌などで繊維を均一な長さに整える。手加減ひとつで紙質が変化する。 - 紙漉き
水に溶かした繊維にトロロアオイの粘液を加え、簀桁で均等に漉く。 - 脱水
漉いた紙を積み重ね、圧をかけて余分な水分を取り除く。 - 乾燥
刷毛でしわを伸ばし、乾燥板に一枚ずつ貼って自然または機械で乾かす。 - 裁断
完成した和紙を用途に応じたサイズ(画仙紙・半紙等)に切り分ける。
1枚の紙に込められた工程は、すべてが手と目と感性によるもの。自然と職人の呼吸が調和して初めて、因州和紙のしなやかな強さと美しさが生まれます。
因州和紙は、鳥取の自然と文化に育まれた“書のための和紙”です。1300年続く伝統と職人技が生み出すその紙は、書き心地の滑らかさと美しいにじみで、多くの書道家を魅了してきました。伝統技法を守りながらも新たな用途へ挑む因州和紙は、今も進化を続ける日本の紙文化の結晶です。