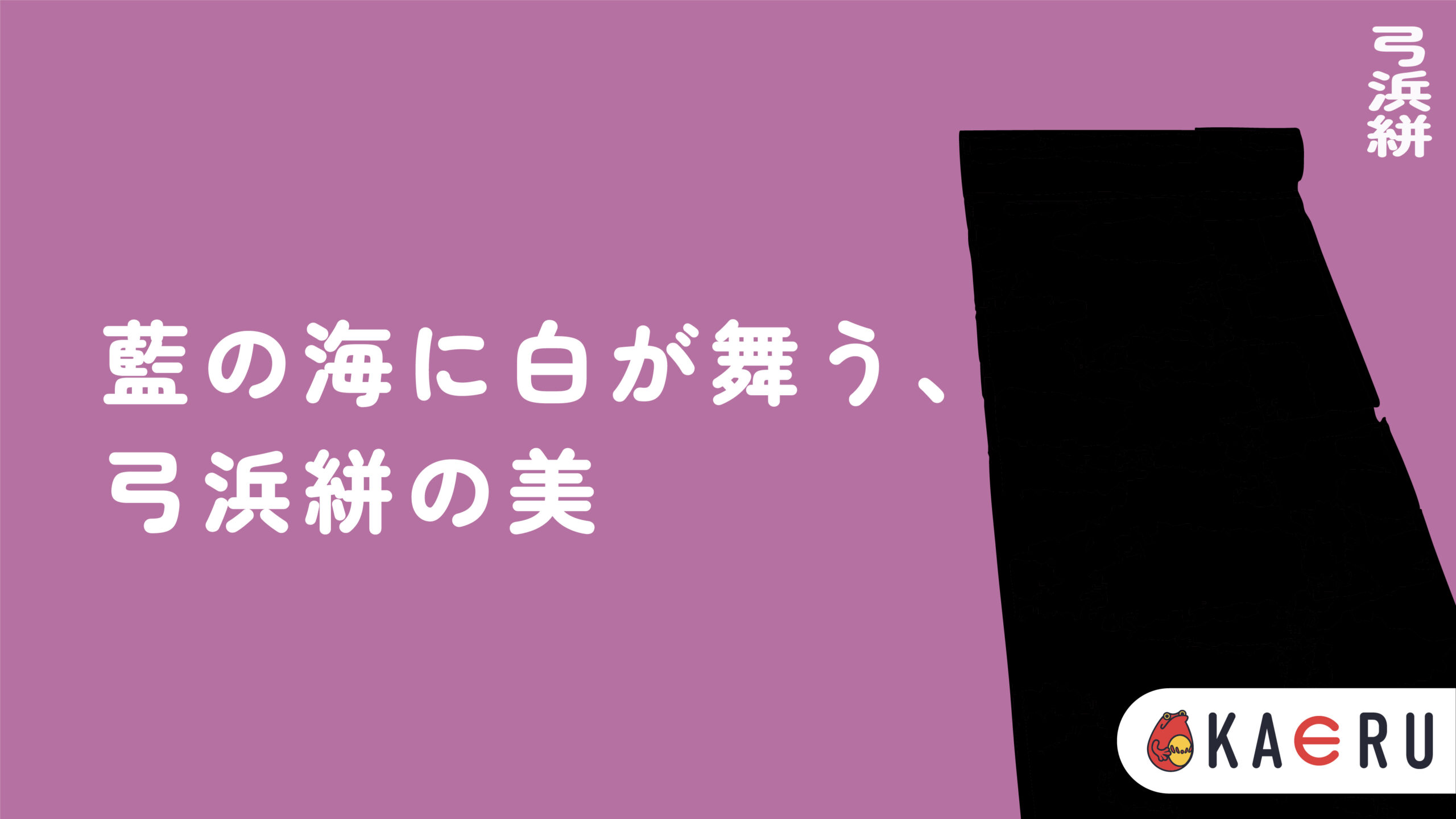弓浜絣とは?

弓浜絣(ゆみはまがすり)は、鳥取県西部の弓ヶ浜地域(米子市・境港市)で生まれた綿織物です。藍で染めた深い青の地に、白く浮かび上がる鶴や亀、松竹梅といった吉祥文様を絣(かすり)技法で織り出すのが特徴で、かつては嫁入り道具や普段着として人々の暮らしに根付いてきました。
木綿産地であった弓ヶ浜の自然と暮らしが育んだ弓浜絣は、「実用の中の美」を体現する生活工芸。模様を糸にあらかじめ括り染めして織るという複雑な工程を経ながらも、どこか素朴で温かな風合いが魅力です。現在では衣類だけでなく、バッグやインテリアなど新たな形でも注目を集めています。
| 品目名 | 弓浜絣(ゆみはまがすり) |
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年9月4日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(14)名 |
| その他の鳥取県の伝統的工芸品 | 因州和紙、出雲石燈ろう(全3品目) |

弓浜絣の産地
白砂青松の風景が育む、実用と美の布文化

主要製造地域
弓浜絣の主産地は、鳥取県の弓ヶ浜地域、米子市から境港市にかけて日本海に弓なりに広がる浜辺一帯です。この地域は中海・日野川・日本海に囲まれ、豊かな水資源と肥沃な砂地土壌を活かして古くから綿作が行われてきました。
江戸時代、この地域の農家では自家用の木綿織物が盛んに作られ、特に女性の副業として絣織が普及しました。藍染と括りによる模様表現は、嫁入り道具や晴れ着、祝い布として地域文化に深く根ざしました。また、幕末から明治にかけては、年貢制度の緩和により自由な物資流通が可能となり、農家の間で技術の交流も進みました。
弓浜地域には素朴な中にも祈りを込めた文様文化があり、生活と信仰が織物に反映されています。鶴亀・宝尽くし・唐草模様などは家内安全や豊作祈願の意味を持ち、絣布は単なる衣料ではなく“幸せを織る布”として大切にされてきました。特に婚礼用の反物や襦袢(じゅばん)は、母から娘へと継がれる家族の証でもありました。
弓浜絣の歴史
暮らしに息づく文様、絣が語る地域の記憶
弓浜絣の起源は江戸中期とされ、農村の副業として定着した後、時代の変化とともに芸術性と社会的価値を高めてきました。
- 18世紀中頃(江戸中期):農家の副業として綿作と手織りが広がる。白地に藍模様の単純な織物が中心。
- 1804〜1830年(文化・文政期):絣の技術が地域内で洗練され、模様表現が複雑化。縞模様に加え、幾何学的・植物文様が登場。
- 1830〜1844年(天保年間):婚礼用の反物として吉祥文様(鶴、亀、宝尽くし)が定着し始める。
- 1877年前後(明治10年代):機織り技術の改良により生産性が向上。市場流通も活発化。
- 1912〜1935年(大正〜昭和初期):農家の女性による内職需要が拡大。柳宗悦らの民藝運動により再評価される。
- 1955〜1965年(昭和30年代):化学繊維の台頭により一時衰退。伝統保持の危機に直面。
- 1975年(昭和50年):弓浜絣が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:小物・インテリア・アパレル商品などに展開。地域ブランドとしての再認知が進む。
弓浜絣の特徴
藍と白が織りなす吉祥文様、暮らしに宿る美意識
弓浜絣の最大の魅力は、藍一色の地に白く浮かび上がる絣模様の美しさにあります。この布に描かれる文様は、すべて織る前の糸に手作業で括りを施し、藍で染めることで生まれるもの。あらかじめ設計された図案通りに、模様部分だけを括って染め残すという非常に手間のかかる工程を経て、ようやく布の上に姿を現します。
絣の模様には、長寿を象徴する鶴や亀、家内安全を祈る松竹梅、金運や繁栄を願う宝尽くしなど、古くから縁起物とされる吉祥文様が多く用いられています。こうした意匠は、かつて嫁入り道具や晴れ着として織られた弓浜絣に、母から娘への祈りや願いを込めて表現されたものであり、地域の暮らしと深く結びついた精神文化を感じさせます。
模様の輪郭がほんのりとにじむように見える「絣足(かすりあし)」は、括り染め特有の表情であり、手織りによる温かさを感じさせる要素のひとつです。この“にじみ”は、職人の微細な括り加減と染め具合によって左右されるため、同じ模様でも一点ごとに風合いが異なります。

弓浜絣の材料と道具
藍と綿が語る、素朴で力強い素材の美
弓浜絣の製作は、綿糸の準備から括り・染め・織りまで一貫して手作業で行われます。使われる材料や道具にも、土地の気候や風土が息づいています。
弓浜絣の主な材料類
- 綿糸:地元で育てられた綿を使用。柔らかく吸湿性に優れる。
- 藍染料:天然藍を用い、深い藍色に染め上げる。
- 括り糸:文様を表現するため、染める前に部分的に縛る糸。
弓浜絣の主な道具類
- 絣括り台:模様部分を括るための台。図案に応じて糸を丁寧に縛る。
- 織機(地機・高機):木製の手織り機。足踏み式で経糸と緯糸を操る。
- 染桶:藍染を行うための桶。発酵建ての藍が使われる。
- 綛巻き(かせまき):染色後の糸を整え、織りに備えるための道具。
こうした素材と道具を使いこなす手仕事の積み重ねが、弓浜絣の柔らかな風合いと文様美を生み出しています。
弓浜絣の製作工程
一本の糸に込められた、文様と祈りの手仕事
弓浜絣の製作工程は、すべてが手作業で行われます。糸に文様を描くための括りから、藍染、織りまで、気の遠くなるような緻密な作業が続きます。
- 整経(せいけい)
織りの幅・長さに合わせて経糸を整える。 - 図案設計
文様を図案化し、どこに括るかを設計。 - 括り(くくり)
図案に沿って緯糸を括り、白く残す部分を決める。 - 藍染め
括った糸を藍甕に浸け、数回染め重ねて濃い藍色に。 - 解き・干し
括り糸を外し、染めムラが出ないよう天日干し。 - 機織り
手織り機で一本一本模様を合わせながら織り進める。 - 仕上げ
洗浄・乾燥し、布目を整えて完成。
熟練の職人による高度な絣合わせが必要とされ、ほんの数センチの布を織るのに数時間を要することも珍しくありません。弓浜絣は、暮らしと祈りを織り込んだ“日々の美”を伝える布芸術なのです。