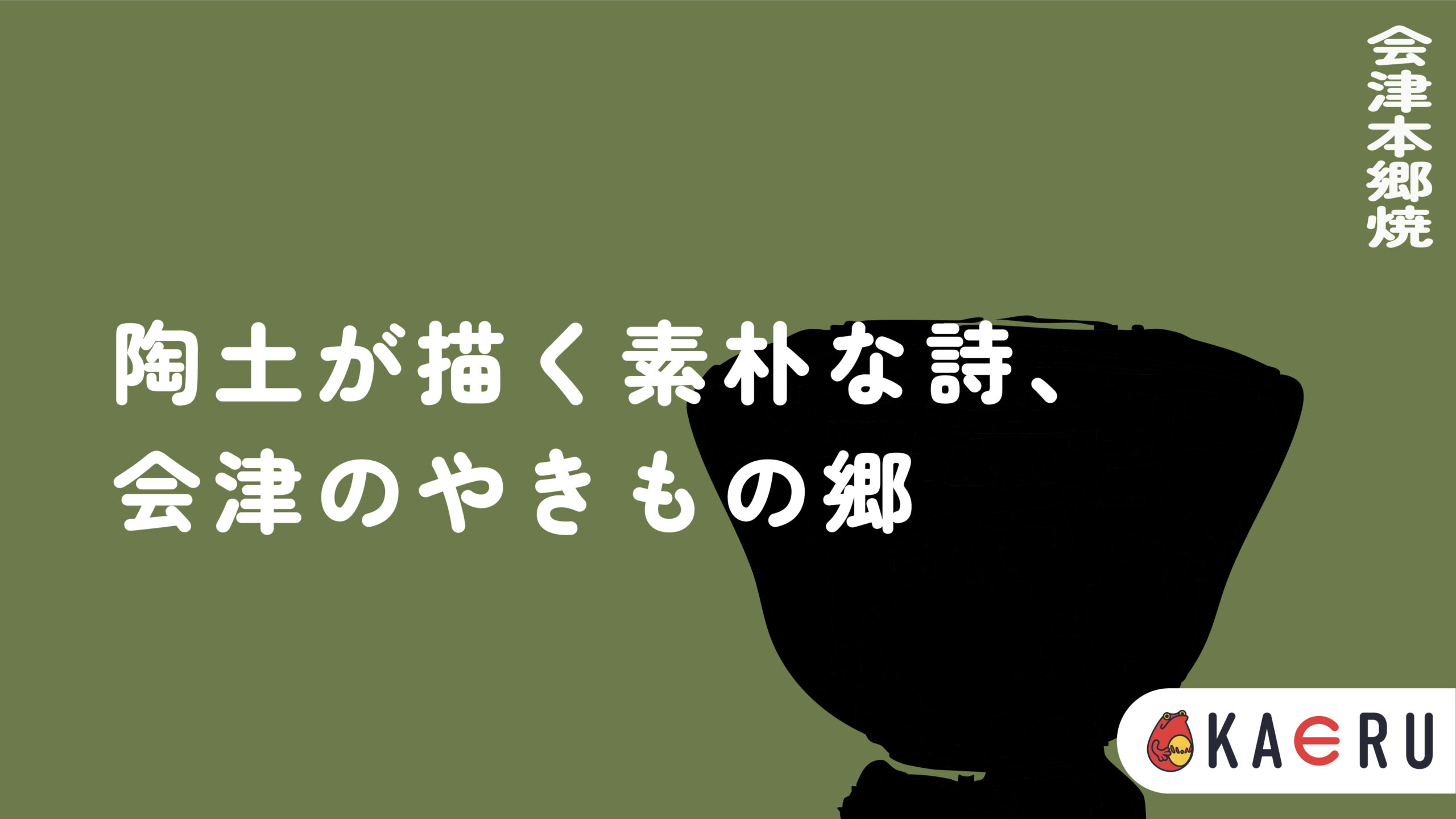会津本郷焼とは?

会津本郷焼(あいづほんごうやき)は、福島県会津美里町を中心に作られている陶磁器です。およそ400年以上の歴史をもち、日本で最も古いやきもの産地のひとつとされています。
その魅力は、会津の自然が育んだ陶土の素朴な風合いと、日常使いに適した堅牢さにあります。美術品というよりは、暮らしの中で親しまれてきた実用品としての系譜をもち、器や壺、火鉢、徳利など多様な製品が生み出されてきました。
近年では伝統的な風合いに加え、現代の感性を取り入れた作品も登場し、工芸とアートの融合が進んでいます。
| 品目名 | 会津本郷焼(あいづほんごうやき) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1993(平成5)年7月2日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(13)名 |
| その他の福島県の伝統的工芸品 | 大堀相馬焼、会津塗、奥会津昭和からむし織、奥会津編み組細工(全5品目) |

会津本郷焼の産地
豊かな風土と歴史に育まれた、東北随一のやきものの里
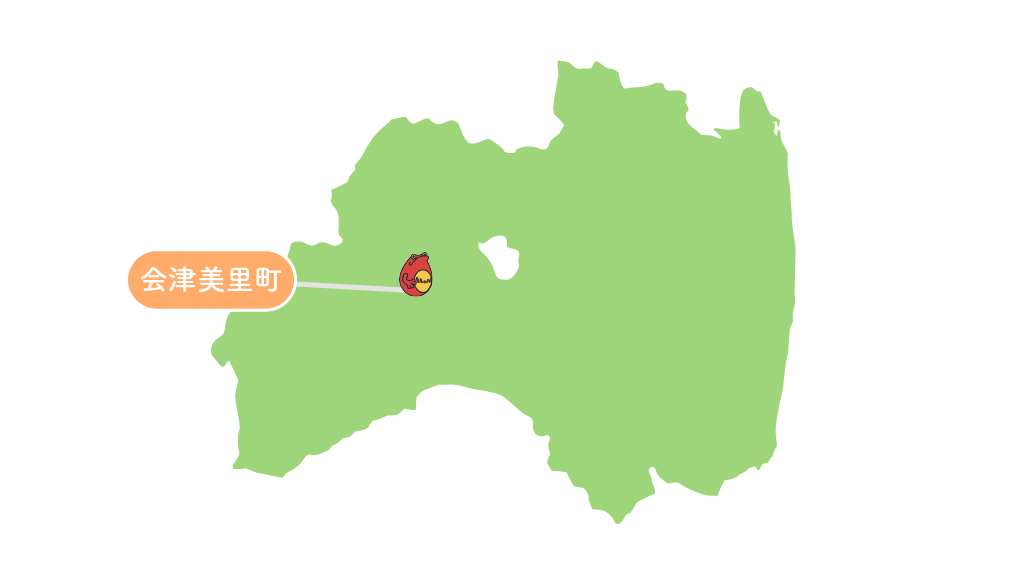
会津本郷焼の産地・会津美里町は、会津盆地の南西に位置し、阿賀川水系と宮川の流域に広がる自然豊かな地域です。古くから良質な陶土や陶石が採取でき、やきもの作りに最適な立地として知られてきました。
文禄年間に加藤景正が開窯して以降、江戸時代には会津藩の庇護のもとで藩窯として発展。藩主の命により技術者が招聘され、技術が磨かれていきました。明治以降は民間の手で再興され、輸出用陶磁器や火鉢の一大産地として名を馳せました。
また、会津塗や赤べこなど多彩な工芸文化が共存する土地柄であり、会津武士の質実剛健な気質と、雪国ならではの丁寧な暮らしが器のかたちに反映されています。冬は厳しく長い雪に覆われる地域であるため、屋内でのものづくりが根付いた風土がありました。乾燥や焼成の工程にも繊細な配慮が求められ、そうした自然との共生が、温もりある器の風合いを育んでいるのです。
会津本郷焼の歴史
400年の歩みを刻む、会津やきものの年表
会津本郷焼は、日本でも有数の長い歴史を誇る陶磁器の産地です。戦国末期の築窯から、藩政時代の発展、明治の民営化、現代の再評価まで。その歩みは時代ごとの変化とともに形を変えながら、脈々と受け継がれてきました。
- 1593年(文禄2年):豊臣秀吉の朝鮮出兵から帰国した加藤景正が、本郷地区に築窯。これが会津本郷焼の始まりとされる。
- 1645年(正保2年):会津藩主・保科正之が尾張から陶工を招き、本格的な製陶技術の導入を進める。
- 1670年代(寛文年間):藩内需要の増加に伴い、本郷周辺に複数の窯元が誕生。生活雑器の供給地としての役割を確立。
- 1740年代(寛保年間):中国陶磁の意匠が導入され、呉須絵付けなどを用いた磁器の製作が始まる。
- 1804年(文化元年):御用窯として藩の管理下に置かれ、技術水準と品質が安定。上級武士への献上品や贈答用にも用いられる。
- 1868年(明治元年):戊辰戦争で会津地域が戦火に見舞われる。多くの窯が一時焼失し、衰退の危機を迎える。
- 1877年(明治10年):会津本郷地区に残った陶工たちが民営窯として再出発。再興運動が始まる。
- 1915年(大正4年):大火により窯元の多くが被災するも、地域ぐるみで復興し、輸出用火鉢の大量生産が始まる。
- 1925〜30年代(昭和初期):輸出向け色絵火鉢・徳利などが欧米市場で人気を博し、産地としての名声を高める。
- 1976年(昭和51年):地域文化の見直しが進み、「陶祖祭」が復活。技術保存と地域一体の文化継承が始まる。
- 1993年(平成5年):会津本郷焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 2000年代以降:若手作家による現代的な器づくりが盛んに。個人窯がアートと日用品の橋渡しを担うように。
会津本郷焼の特徴
素朴のなかに宿る、手仕事の温もりと強さ
会津本郷焼の魅力は、なんといってもその「実直さ」と「やさしさ」です。器としての実用性を重視しながらも、手に取るとほっとするような素朴な美しさが宿っています。会津産の陶土は鉄分を多く含み、焼成後に生まれる赤みがかった色味が特徴です。釉薬には灰釉や透明釉が使われ、土の風合いを活かしたシンプルな仕上がりが多く見られます。磁器製品では会津陶石の白さが際立ち、藍や呉須を用いた絵付けが映えるのも魅力のひとつです。
明治期に全国へ出荷された「火鉢」は、会津本郷焼の名を全国に広めた立役者でした。冬の寒さが厳しい土地で生まれた実用品だからこそ、丈夫で割れにくく、保温性にも優れていたのです。
また現代では、作家によって「二重掛け」や「刷毛目」、「焼き締め」などの技法が多様化し、同じ会津本郷焼でも窯元ごとに個性の違いを楽しめるのも醍醐味です。日常に寄り添う器でありながら、使うほどに味わいが深まる「暮らしの道具」として、幅広い世代に愛されています。

会津本郷焼の材料と道具
会津の土と釉薬が生む、あたたかな質感
会津本郷焼の製作には、地元で採れる土と釉薬を中心に、伝統的な陶芸道具が使われます。
会津本郷焼の主な材料類
- 会津産の陶土:鉄分を含む赤褐色の粘土。陶器に使用。
- 会津陶石:磁器用の白い陶石。滑らかで焼成後の強度が高い。
- 灰釉・透明釉:薪灰や長石を用いた、落ち着いた釉調の釉薬。
- 草木灰:独特の景色を作る伝統的釉薬成分。
会津本郷焼の主な工具類
- 轆轤(ろくろ):手びねりまたは蹴ろくろで成形。
- へら・こて:成形や削り出しに使用。
- 焼成窯:登り窯や電気窯など多様。現在はガス窯も普及。
- 筆・型:絵付けや加飾に使う道具。
こうした自然素材と伝統的工具の組み合わせが、手仕事ならではの温もりある器を生み出しています。
会津本郷焼の工程
土から器へ。会津の暮らしに寄り添うやきものづくり
会津本郷焼の製作は、自然素材と向き合いながら、繊細かつ確かな工程を積み重ねて完成します。
- 土練り
陶土や陶石を水で練り、気泡を抜いて滑らかにする。 - 成形
轆轤や手びねりで形を作る。器ごとに厚みや重さを調整。 - 乾燥
日陰でゆっくりと乾燥。急激な乾燥は割れの原因となる。 - 素焼き
600〜800℃程度で素焼きを行い、強度をもたせる。 - 釉薬掛け
器に釉薬を施す。浸し掛けや刷毛塗りなど。 - 本焼き
1200〜1300℃で本焼き。釉薬が溶けて独特の艶が出る。 - 加飾・絵付け
磁器には絵付けを行う場合もあり、文様や文字を描く。 - 検品・仕上げ
高台や縁を整え、完成。
会津本郷焼は、会津の自然が育んだ土と火、そして職人の手によって育まれてきた、日常に寄り添うやきものです。400年以上の伝統を礎にしながら、現代の感性を取り入れた器も数多く生まれ、今なお進化を続けています。素朴であたたかく、使うほどに暮らしに馴染む器です。