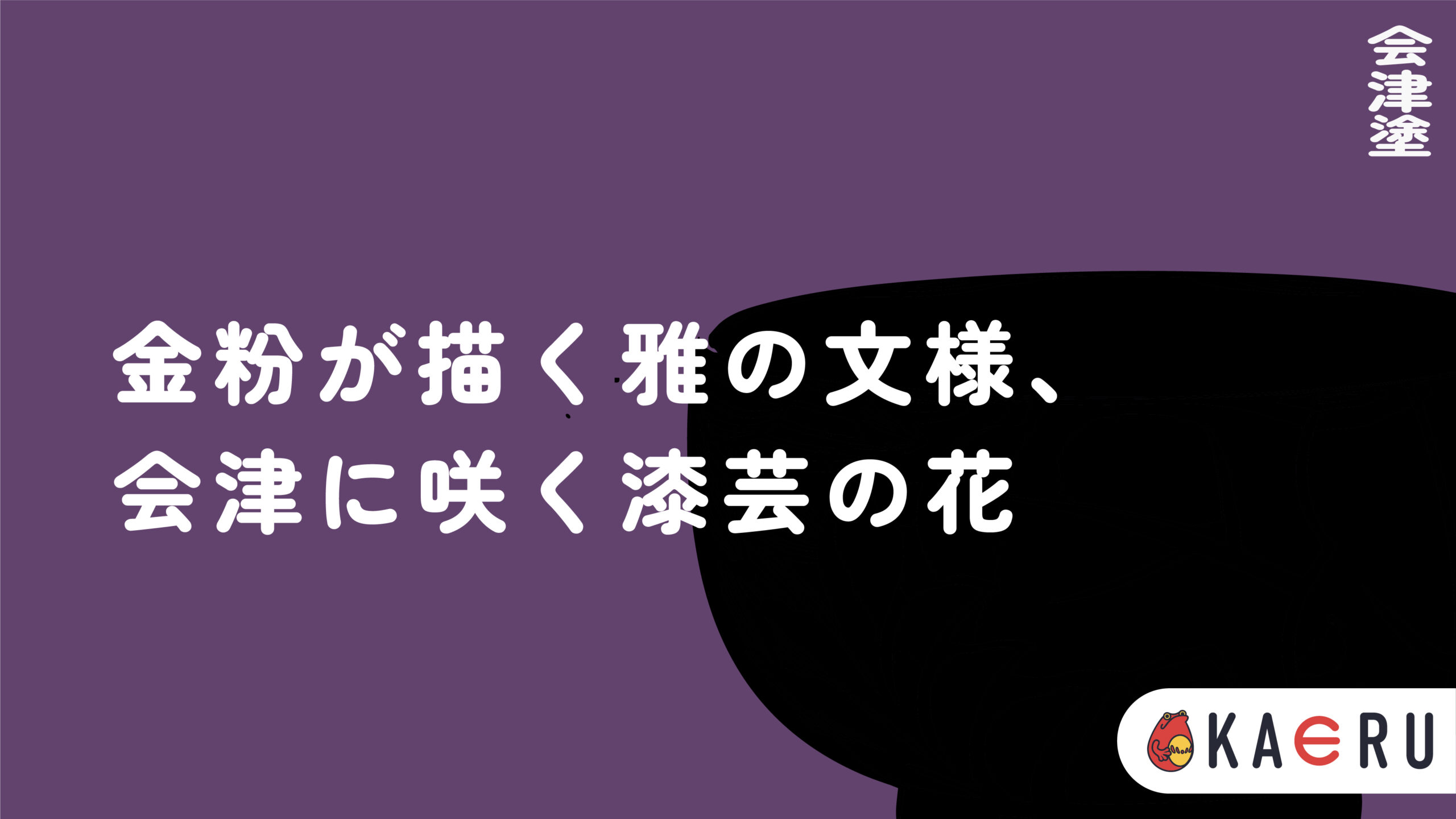会津塗とは?
会津塗(あいづぬり)は、福島県会津地方で約500年の歴史をもつ伝統的な漆器です。椀や盆などの「丸物(まるもの)」と、重箱や角盆などの「板物(いたもの)」では職人の分業体制が確立しており、木地・塗り・加飾の各工程に高い専門性が求められます。
中でも特徴的なのが、蒔絵・沈金・朱磨き・鉄錆塗・会津絵など多彩な加飾技法。漆の黒に浮かぶ金粉や朱の文様は、祝いや慶事を彩る品として古くから親しまれ、格式高い贈答品や海外輸出品としても重宝されてきました。
| 品目名 | 会津塗(あいづぬり) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 25(84)名 |
| その他の福島県の伝統的工芸品 | 奥会津昭和からむし織、大堀相馬焼、会津本郷焼、奥会津編み組細工(全5品目) |

会津塗の産地
自然と文化が漆芸を育んだ、会津の風土

会津塗の主産地は、福島県西部に位置する会津若松市を中心とした会津地方一帯です。周囲を磐梯山・飯豊山などの山々に囲まれた内陸盆地にあり、夏は高温多湿、冬は積雪に覆われる独特の気候風土が特徴です。漆器づくりには湿度が欠かせないため、この地の気候はまさに理想的な環境といえます。
また、地元には漆の木のほか、ホオ・トチ・ケヤキ・センといった木地に適した広葉樹が多く自生しており、自然素材を自給できる点も大きな利点です。漆の生産についても、古くから会津地方では植樹・採取が行われ、国内屈指の国産漆の産地としての歴史があります。
また、かつて城下町として栄えた会津若松を中心に、武家文化や茶道文化が浸透していたことも、漆器需要の拡大に寄与しました。武家の婚礼道具、茶の湯道具、正月の重箱など、漆器は暮らしの格式を支える存在として定着していったのです。こうした自然・文化・気候の三要素が融合し、会津塗という伝統産業を根づかせていきました。
会津塗の歴史
500年にわたって受け継がれる、漆と人の物語
会津塗の歴史は、室町時代末期に始まり、武将たちの保護政策と職人たちの研鑽によって発展してきました。
- 16世紀後半(室町時代末期): 会津を支配した葦名氏が、漆の植樹を奨励。地場産業としての漆器作りが始まる。
- 1590年(天正18年): 蒲生氏郷が豊臣秀吉の命により会津へ移封。近江から漆器職人を招き、産業振興を本格化。
- 17世紀前半: 蒲生氏の後を継いだ加藤氏・保科氏のもとでも保護政策が継続され、技術基盤が定着。
- 18世紀(江戸時代中期): 京都から蒔絵や沈金などの装飾技術が導入され、加飾の洗練が進む。
- 18世紀後半: 海外への輸出も始まり、会津塗は国際的な需要を獲得。
- 19世紀中頃: 会津藩の公式産業として制度化され、職人の数が飛躍的に増加。
- 1868年(明治元年): 戊辰戦争により会津地方が焦土と化し、漆器産業も大打撃を受ける。
- 明治20年代: 地元有志によって再興が進み、再び国内需要に応じた生産体制が整う。
- 1975年(昭和50年):会津塗が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代: 伝統技術とデザイン性を融合させた新作の開発や、修理・修復ニーズにも対応。観光やギフト産業としても注目を集めている。
こうした歴史を経て、会津塗は今なお全国有数の漆器産地として高い評価を受け続けています。
会津塗の特徴
加飾が語る縁起と格式、漆が紡ぐ美の深み
会津塗は、木地師・塗師・蒔絵師・沈金師といった専門職が連携し、それぞれの卓越した技を持ち寄ることで、一つひとつの作品に高い完成度がもたらされます。
加飾技法の豊富さも特筆すべき点です。「金虫くい塗」は、漆を塗った上に籾殻を撒いて模様を作り、銀粉をまいて研ぎ出すことで独特の立体感を生み出す技法です。「花塗」は油を加えた漆でムラなく塗る仕上げ技で、職人の熟練度が試されます。木目を透かす「木地呂塗」は、時間とともに木目が美しく浮かび上がり、使い込むほどに深みが増すのが特徴です。
さらに、蒔絵や沈金、鉄錆塗、朱磨き、漆絵など多彩な装飾が展開され、特に松竹梅や破魔矢などの縁起物をあしらった「会津絵」は、晴れの席や贈答用に高い人気を誇ります。会津絵の破魔矢文様は「災いを払う」「福を射止める」とされ、婚礼や出産祝いの漆器に多用されます。
こうした技法の多様性と意味づけの豊かさこそが、会津塗を単なる器以上の「語る道具」へと高めているのです。

会津塗の材料と道具
素材と分業が支える、精緻な漆芸の基盤
会津塗には、豊かな自然が育んだ地元産の木材や漆、そして用途に応じた多様な道具が使われます。
会津塗の主な材料類
- ホオ・トチ・ケヤキ・セン: 木地の素材。丸物・板物に応じて選定される。
- ウルシ: 会津地方でも採取される透明度の高い国産漆。
- 金粉・銀粉・朱顔料: 加飾用素材として、蒔絵や朱磨きに用いられる。
会津塗の主な工具類
- ろくろ: 丸物木地師が碗や椀を成形する旋回機具。
- 鉋・鑿: 板物の形状加工や表面仕上げに用いられる。
- 刷毛: 漆を塗る際に使用。毛先の扱いで仕上がりが変わる。
- 蒔絵筆・沈金刀: 加飾工程において精密な模様を描くための道具。
こうした素材と道具を、専門職人が連携して使いこなすことが、会津塗の美と機能性を生み出しているのです。
会津塗の製作工程
分業で紡ぐ、漆芸の調和と洗練
会津塗の製作工程は以下のように進みます。各工程で異なる職人が関与し、高度な連携によって一つの作品が完成します。
- 木地づくり
丸物はろくろで成形、板物は鉋などで切削。木材は十分に乾燥させて使用。 - 下地づくり
木地を固め、必要に応じて布を貼り、錆漆(砥の粉+漆)を施す。全体を研磨して平滑に整える。 - 中塗り・上塗り
中塗りで漆を均一に重ねた後、上塗りには花塗や木地呂塗などの技法を使い分ける。 - 加飾
蒔絵や沈金、朱磨き、会津絵などの装飾を、専門職人がそれぞれの技法で施す。 - 乾燥・検品・仕上げ
乾燥室(室)で自然乾燥。仕上げを施して検品し、完成品として世に送り出される。
会津塗は、分業制によって高度な技術を集約し、漆と加飾の美を極めた日本有数の漆器です。500年の歴史を受け継ぎながら、今も職人の手で丁寧に作られています。日常使いから贈答品まで幅広く活躍し、暮らしに品格と華やぎを添える伝統工芸の逸品です。