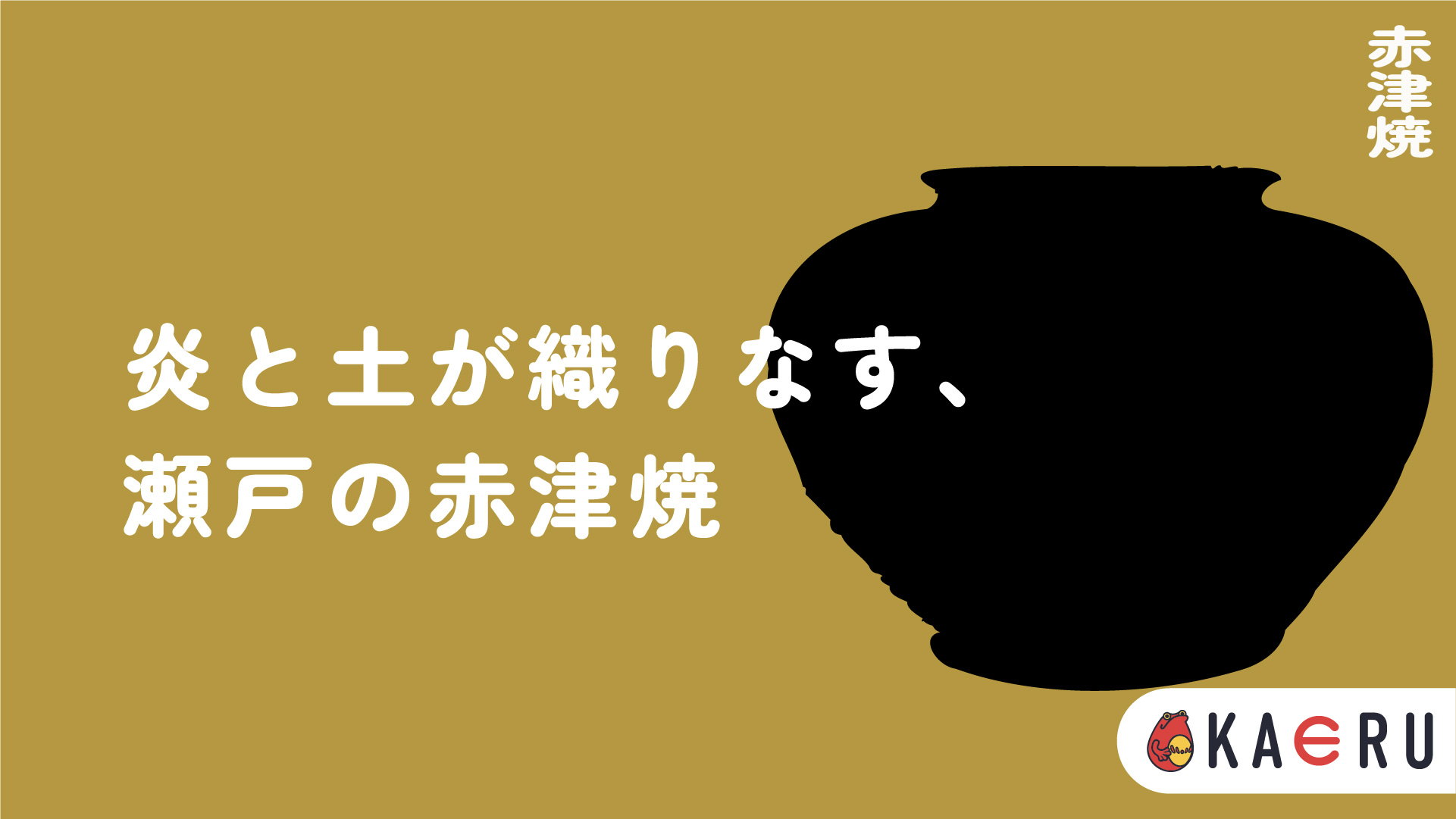赤津焼とは?
赤津焼(あかづやき)は、愛知県瀬戸市赤津町を中心に生産される陶器で、日本六古窯の一つ「瀬戸焼」の源流をなす存在です。その起源は奈良時代の須恵器にまでさかのぼり、千年以上の時を経て、現代まで連綿と受け継がれてきました。
赤津焼の真骨頂は、多彩な釉薬と実用性の高さにあります。鉄釉・織部・黄瀬戸・志野などの伝統釉を駆使し、器に豊かな表情を与えながらも、日常生活に根ざした「用の美」を追求してきました。
| 品目名 | 赤津焼(あかづやき) |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1977(昭和52)年3月30日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(17)名 |
| その他の愛知県の伝統的工芸品 | 名古屋友禅、名古屋黒紋付染、有松・鳴海絞、三州鬼瓦工芸品、常滑焼、瀬戸染付焼、名古屋桐簞笥、尾張仏具、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、岡崎石工品、尾張七宝、名古屋節句飾(全15品目) |

赤津焼の産地
窯の里・赤津に宿る千年の炎と風土の記憶

主要製造地域
赤津焼の産地である愛知県瀬戸市赤津町は、日本六古窯に数えられる「瀬戸焼」の発祥地の一つであり、陶磁器の一大生産地として知られています。赤津は古くから粘土質の土壌に恵まれ、周辺には良質な陶土が豊富に採取できる地層が広がっていました。この自然条件が、古代より焼き物の生産を可能にし、やがて瀬戸全域の窯業文化を育む基盤となったのです。
また、赤津地区は古くから東山道や中山道といった幹線交通に近く、物流の要衝でもありました。中世以降は、美濃や尾張との文化交流の中で茶道具や日用器としての需要が高まり、地域の窯元が技法を磨きながら独自の陶芸文化を発展させていきました。
文化的には、室町〜桃山期にかけて隆盛を誇った茶の湯文化と密接な関係があり、織部・志野・黄瀬戸といった個性ある釉薬が生み出された背景には、茶人との交流や美意識の影響が色濃く見られます。茶陶の制作は単なる器作りではなく、美術工芸としての完成度を求められるものであり、赤津焼の表現力と造形力がこの時代に大きく飛躍したことがうかがえます。
赤津焼の歴史
須恵器の流れを汲む、瀬戸陶芸の源流
赤津焼の歴史は千年以上におよび、各時代の需要と文化を反映しながら、技法と表現を進化させてきました。
- 8世紀後半(奈良時代):赤津地区にて須恵器の生産が始まる。登窯(のぼりがま)による焼成技術が伝来。
- 10世紀後半(平安時代末期):生活雑器の生産が盛んになり、赤津窯が形成される。山腹に築かれた窯が複数稼働。
- 12世紀〜13世紀初頭(鎌倉時代):鉄釉や灰釉などの施釉技術が定着。瀬戸地域全体の陶業基盤が強化される。
- 14世紀(南北朝期):古瀬戸様式が完成。茶器・壺などに本格的な釉薬が施され始める。
- 15世紀(室町時代):「瀬戸七釉」の原型が形成。美濃地方と並び茶道具の名産地となる。
- 16世紀末(桃山時代):織部焼や志野焼など、個性豊かな釉陶が誕生し、茶人の注目を集める。
- 17世紀前半(江戸初期):本格的な分業体制が整い、窯の種類や釉薬の専業化が進行。
- 19世紀中頃(幕末期):近代化の波とともに窯業の生産性向上が図られる一方、赤津の伝統技法は縮小。
- 20世紀初頭(明治後期):一部窯元が復興に取り組み、赤津焼の技法保存と伝統釉の復活が始まる。
- 1977年(昭和52年):赤津焼が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:若手作家やデザイナーとの協業が進み、現代の食卓に合う意匠や形状が開発されている。
赤津焼の特徴
七つの釉が織りなす、豊穣な表情と実用美
赤津焼の魅力は、見た目の多彩さと使い心地の良さ、その両立にあります。特に特徴的なのが、「瀬戸七釉」と呼ばれる7種類の伝統釉薬を駆使した、釉調の豊かさです。深みのある緑が美しい織部、黄味がかったやわらかな発色の黄瀬戸、白濁釉に素朴な筆致が映える志野など、それぞれが焼きあがる度に異なる表情を見せ、同じ釉でも温度や灰の量によって模様や色合いが微妙に変化します。
織部釉は酸化焼成によって渋い緑に仕上がり、鉄釉との併用で輪郭を際立たせるといった技法が用いられます。また、黄瀬戸には「練込模様」と呼ばれる文様が入れられることがあり、まるで絹地のような滑らかさと風合いを醸し出します。こうした釉薬の使い分けは、単なる装飾ではなく、食器や茶道具の用途に応じた意味づけも込められています。
赤津焼の器の多くには「畳付き」と呼ばれる高台(こうだい:器の底部)があり、茶碗などではここが滑らかに磨かれていることが良品の証とされます。また、釉薬が流れた跡や焼きのムラを“景色”として愛でる感性も、赤津焼ならではの楽しみ方です。実用品でありながら、手に取るたびに新しい表情を発見できるのが、赤津焼の大きな魅力といえるでしょう。

赤津焼の材料と道具
土と釉薬を操る、焼き物の五感
赤津焼は、赤津特有の陶土と多種多様な釉薬を駆使して作られます。その製作は土の選別から釉掛け、焼成に至るまで、職人の経験と感性が大きくものをいいます。
赤津焼の主な材料類
- 赤津陶土:鉄分を適度に含み、可塑性に優れる。焼成後の発色も良好。
- 瀬戸釉(七釉):織部釉、黄瀬戸釉、志野釉、鉄釉、御深井釉、古瀬戸釉、灰釉など。
- 木灰・藁灰:釉薬の原料として使用される。
赤津焼の主な道具類
- 轆轤(ろくろ):成形の基本道具。電動・手回しともに用いられる。
- ヘラ・コテ:形を整えるための手道具。
- 筆:釉薬の加飾や文様描きに使用。
- 窯:主にガス窯や電気窯のほか、登窯も一部で用いられる。
こうした素材と道具を自在に操ることで、赤津焼はその独特の表情と質感を生み出しています。
赤津焼の製作工程
炎と手が織りなす、やきものの時間
赤津焼の製作は、土から器へと生まれ変わる一連の工程を通じて、職人の技と感性が形になります。
- 土練り(ねり)
粘土に水を含ませ、空気を抜きながら均質な土に仕上げる。 - 成形
轆轤成形、型打ち、手びねりなどで器の形を作る。用途に応じて厚みや口縁の形状も工夫。 - 乾燥
自然乾燥で数日〜数週間寝かせ、歪みや割れを防ぐ。 - 素焼き
約800℃で焼成し、釉薬を乗せるための下地をつくる。 - 釉掛け
浸し掛け・掛け分け・筆描きなどで釉薬を施す。絵付けを行うものも。 - 本焼き
1300℃前後で焼成し、釉が溶けてガラス質に変化する。窯の中の温度変化も意匠の一部となる。 - 仕上げ・検品
高台の整え、釉の流れ具合などを最終チェックし、必要に応じて磨きを施す。
完成した赤津焼は、生活空間に彩りと機能をもたらす器として、静かに佇みます。
赤津焼は、瀬戸焼の源流に位置し、千年以上にわたる陶芸文化を受け継ぐ存在です。多彩な釉薬表現と高い実用性を兼ね備え、現代の暮らしに自然に馴染む焼き物として注目されています。伝統と革新が息づく赤津焼は、器としての美しさと使いやすさの理想形といえるでしょう。