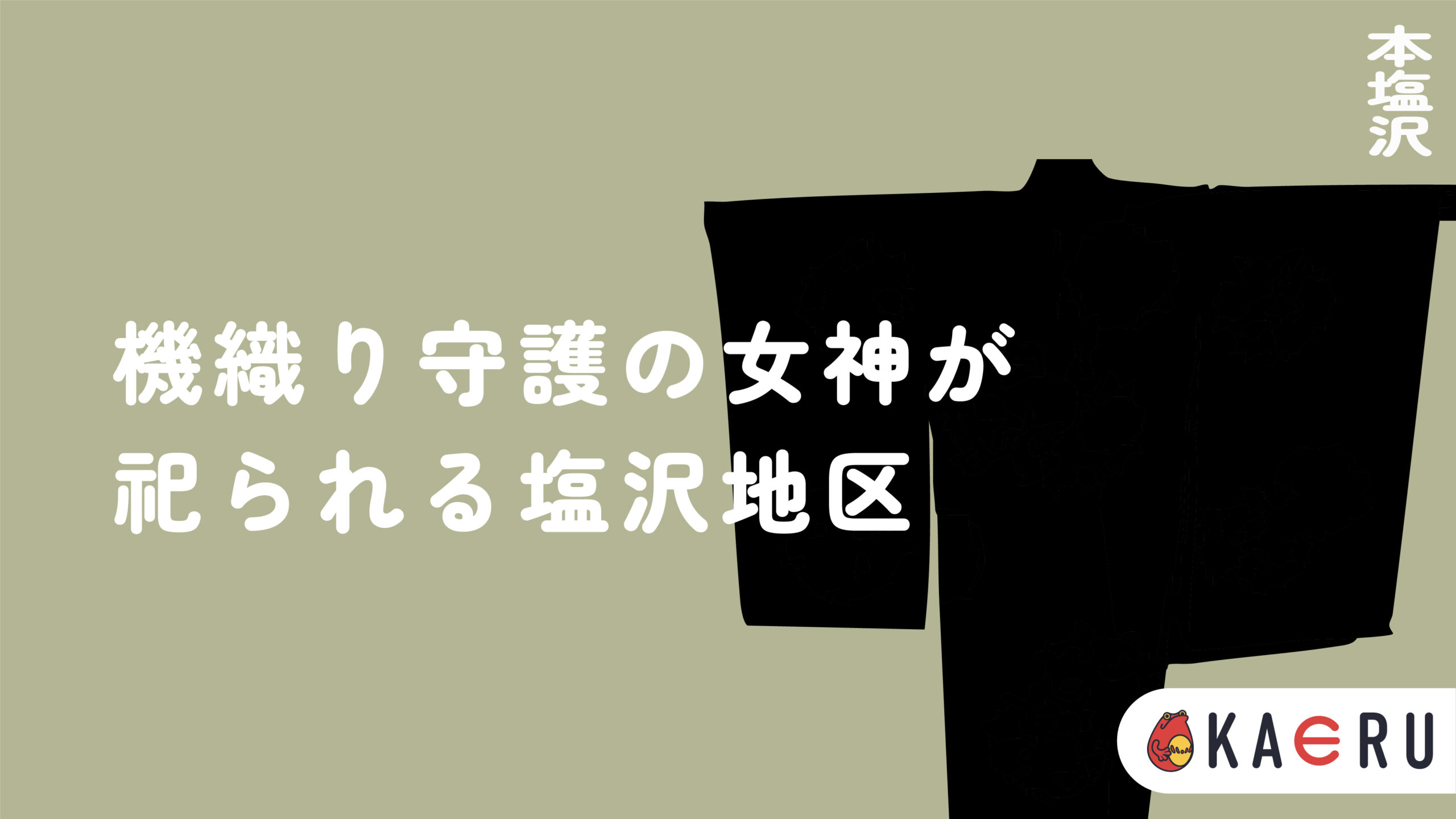本塩沢とは?
本塩沢(ほんしおざわ)は、新潟県南魚沼市の塩沢地域で生産される高級絹織物で、越後上布の技術を母体とし、17世紀中期から発展してきました。蚊絣で知られる塩沢紬と並び称される本塩沢は、「塩沢お召し」とも呼ばれ、しなやかな風合いと絣文様の上品さで多くの愛好家に親しまれています。
最大の特徴は、緯糸に強い撚りをかけることで生まれる「シボ立ち」と呼ばれる独特の地風。この技法は麻織物の小千谷縮に由来し、絹のしなやかさの中に適度な張りと立体感をもたらします。十字絣や亀甲絣といった精緻な模様が、品格ある意匠を形作り、晴れ着や略礼装にも適した織物として高く評価されています。
| 品目名 | 本塩沢(ほんしおざわ) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 14(28)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

本塩沢の産地
雪国の文化と技術が根づく、絹織物の町

主要製造地域
本塩沢の主産地は、新潟県南魚沼市の塩沢地域。越後三山から流れる清らかな雪解け水と、湿潤で安定した気候が、精緻な絣織物に理想的な環境を提供しています。この地は古くから越後上布や小千谷縮などの高級織物の産地として栄えてきました。
雪国ならではの「雪晒し」「湯もみ」などの技法に加え、冬場の農閑期を利用して家々で機を織る生活文化が、長年にわたる技術継承を支えてきました。江戸時代には宿場町として栄えた塩沢は、京都や江戸の上流文化と接点を持ち、需要の高い絹織物の生産と流通が盛んに行われました。
また、塩沢地域では古くから機織りの女神「栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)」が巻機大権現として信仰されており、織物に携わる人々の心の拠りどころとして親しまれてきました。
本塩沢の歴史
越後上布から発展した、塩沢お召しの系譜
本塩沢の歴史は、雪国越後に根づく麻織物文化の延長線上にあります。とくに越後上布の製織技術を基盤として、17世紀には絹織物への応用が進み、独自の風合いをもつ本塩沢が確立されました。
- 8世紀(奈良時代):越後地域では麻織物の生産が盛んで、都への貢納品としても用いられていた。
- 14〜16世紀(室町時代):越後上布が高級麻織物として地位を確立。雪晒しなどの技法が洗練される。
- 17世紀前半(江戸時代初期):播磨国明石藩の武士・堀次郎将俊が、強撚糸と湯もみを活用した縮織技法を小千谷に伝える。
- 17世紀中頃(江戸時代中期):塩沢で越後上布の技術を応用し、絹糸による織物「塩沢お召し(のちの本塩沢)」が誕生。シボの技術は小千谷縮から転用された。
- 18〜19世紀(江戸時代後期):十字絣・亀甲絣などの文様技術が向上し、礼装向けとして定着。
- 19世紀後半(明治時代):織機の改良とともに生産が拡大し、東京や大阪の呉服店で流通が進む。
- 20世紀前半(昭和初期):草木染と手織による高品質織物として評価が高まり、美術工芸品としての価値が広まる。
- 1976年(昭和51年):本塩沢が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 2009年(平成21年):越後上布がユネスコ無形文化遺産に登録される。
本塩沢の特徴
シボの地風と絣の美が融合した、気品あふれる織物
本塩沢の最大の特徴は、シボ立ちの独特な風合いと、十字絣・亀甲絣に代表される精緻な模様にあります。緯糸に強い撚りをかけてから織ることで、布面に凹凸が生まれ、さらりとした肌触りと涼感、さらには優れた吸湿性と軽さを実現しています。絣模様は、熟練の職人が緻密な設計に基づいて防染・染色を施し、絣合わせの精度は織物の完成度を左右する重要な要素です。とくに十字絣の繊細な連なりや、亀甲絣の幾何学的な美しさは、本塩沢ならではの上品な趣を醸し出しています。
色調は白・黒・灰・茶などの落ち着いた色味が中心で、控えめながら洗練された印象を与えるため、現代の装いにも合わせやすく、着物としてだけでなく帯地や和装小物としても人気があります。

本塩沢の材料と道具
自然と手業に育まれた、絹織物のための道具たち
本塩沢の製作には、厳選された素材と、代々受け継がれてきた道具が欠かせません。素材の選定から織り上げまで、多くの工程に熟練の技術が求められます。
本塩沢の主な材料類
- 生糸:主に国産の蚕から得られる絹糸を使用。しなやかで張りのある織物に適する。
- 草木染原料:栗、藍、ヤマモモなど。自然な発色と色持ちを実現。
- 精練剤・撚糸用油分:絹糸の表面処理と撚りに必要。
本塩沢の主な道具類
- 座繰り器:繭から生糸を取り出す際に使用。
- 高機(たかばた):本塩沢の織りに使われる足踏み式の織機。
- 筬(おさ)・綜絖(そうこう):糸の整経・織り密度の調整に用いる。
- 糸車:撚糸や経糸準備の際に使用。
こうした素材と道具が、本塩沢の静謐で洗練された風合いを支えています。
本塩沢の製作工程
絹のしなやかさを活かした、緻密な製織技法
本塩沢の製作工程は、糸づくりから絣染め、織り、仕上げまで、多くの手間と時間をかけて丁寧に行われます。
- 糸づくり(精練・撚糸)
蚕の繭から生糸を取り出し、必要に応じて精練し、緯糸には強い撚りをかけてシボを出す準備をする。 - 絣括り
模様となる部分の糸に防染を施し、絣模様の設計に従って括る。 - 染色
草木染料などを用いて、括った糸を染める。多段階染めが必要な場合もある。 - 整経・機仕掛け
縦糸・横糸を準備し、織機にかける。絣の位置を丁寧に合わせる。 - 手織り
高機を用いて、熟練の技で一反一反織り上げる。撚りをかけた緯糸により、織りながらシボが生まれる。 - 湯通し・仕上げ
織り上げた反物を湯通しし、柔らかさと風合いを整えて完成。
これらの緻密な工程を経て、本塩沢はその軽やかさと品格を兼ね備えた絹織物として仕上がります。