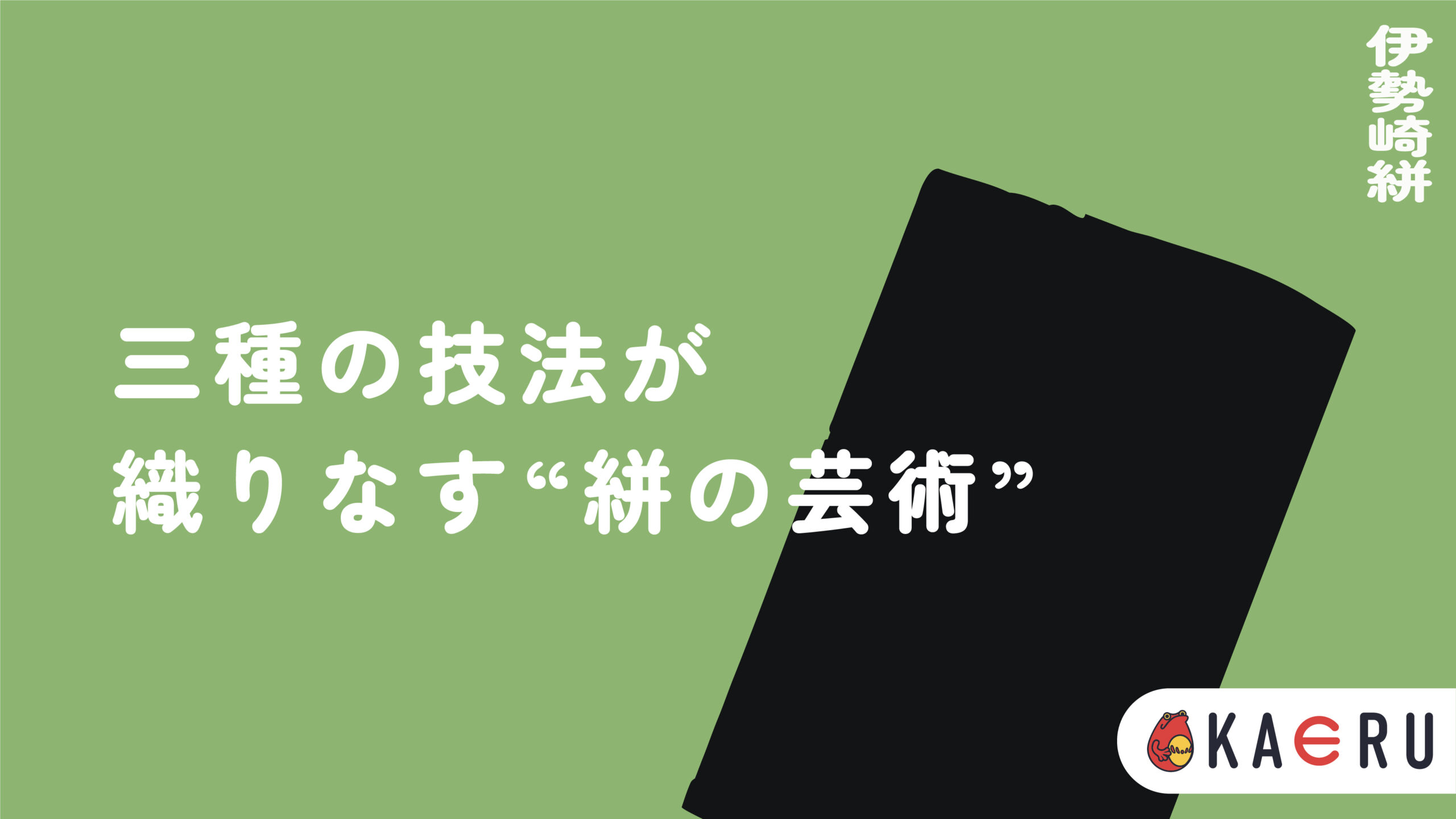伊勢崎絣とは?
-1024x683.jpg)
伊勢崎絣(いせさきがすり)は、群馬県伊勢崎市を中心に受け継がれてきた絹織物です。その起源は江戸時代の厚手の「太織(ふとおり)」にあり、のちに「伊勢崎銘仙」として全国に名を馳せました。かすり糸に独自の染色技法を施し、平織で織り上げるこの織物は、色鮮やかで多彩な柄が特徴です。
伝統的な括り絣・板締め絣・型紙捺染という三種の染技法を用いながら、設計から染色、織りまでのほとんどを手作業で行う、非常に手間のかかる技術の集積でもあります。絹のしなやかさと丈夫さ、そして繊細な意匠が融合した伊勢崎絣は、現在も着物やファッション小物など幅広い製品に姿を変え、多くの人々を魅了し続けています。
| 品目名 | 伊勢崎絣(いせさきがすり) |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年5月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(38)名 |
| その他の群馬県の伝統的工芸品 | 桐生織(全2品目) |

伊勢崎絣の産地
養蚕文化の息づく絹のまち

伊勢崎市は、群馬県の南部に位置し、赤城山や利根川の恵みを受けた肥沃な土地です。この地域では古くから養蚕が盛んに行われており、良質な生糸の生産地として知られてきました。こうした背景のなかで、自家用の織物として発展してきたのが伊勢崎絣の前身「太織」です。
近代以降も、絹糸や染料を支える自然環境と人々の技術が絶妙に調和し、今日の伊勢崎絣のものづくりを支える土壌となっています。
伊勢崎絣の歴史
太織から銘仙、そして絣へ
伊勢崎絣の起源は、江戸時代の「太織」と呼ばれる厚手の織物にさかのぼります。当初は農家が自家用に織っていたものでしたが、江戸後期に入り商品化が進み、「伊勢崎太織」として流通するようになります。
- 江戸後期: 太織の商品化が始まり、伊勢崎太織として生産。
- 明治時代: 伊勢崎太織会社が設立され、「伊勢崎銘仙」の名称で広く普及。
- 大正〜昭和初期: 全国生産量の半数を占めるまでに発展。軽くて丈夫、美しい絣模様が人気を集める。
- 戦後: 洋装化の波により需要が減少。伝統技法の継承に課題が生じる。
- 1975年(昭和50年): 伊勢崎絣が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。
伝統的工芸品の名称が「伊勢崎絣」となったのは、国への登録時に「絣」の名称で届出が行われたためです。中身としては、かつての伊勢崎銘仙と地続きの技術と文化を受け継いでいます。
伊勢崎絣の特徴
三種の染め技法が織りなす多彩な絣模様
伊勢崎絣の最大の特徴は、三種類の染色技法を組み合わせて絣糸をつくり出す点にあります。括り絣、板締め絣、型紙捺染という技法は、それぞれ異なる表情を糸に与え、織り上げられた布地に独特の奥行きと色彩を生み出します。
織りには、たて糸とよこ糸が交互に現れる平織が用いられ、模様を構成するかすり糸の染め分けと、織りのタイミングを絶妙に合わせることで、緻密な図柄を実現しています。
すべての工程において手作業が重視され、設計から染色、絣合わせ、織りに至るまで、職人の繊細な感覚がものを言う織物です。光沢のある絹の質感と、軽やかな風合いは、見る者の目と肌にやさしく訴えかけてきます。

伊勢崎絣の材料と道具
絹と手仕事の調和が生む風合い
伊勢崎絣の製作には、国産の生糸をはじめとした自然素材が用いられ、工程のほとんどが手作業で進められます。伝統の道具や技術が、絹ならではの風合いと色彩を最大限に引き出すのです。
伊勢崎絣の主な材料類
- 生糸:国産の絹糸を使用。つやと軽さが魅力。
- 染料:化学染料を主体としながらも、伝統的な色味や堅牢度を重視。
- テープ:括り工程で使う専用テープ。防染用。
伊勢崎絣の主な工具類
- 糸枠・整経台:糸を巻き取り、縦糸の長さを整える。
- 板締め器具:板に挟んで染色模様をつける。
- 捺染用型紙:図案を再現するための型。
- 高機(たかはた):腰掛けて織るタイプの織機。手織りに適している。
- 絣合わせ道具:柄合わせを補助する器具。
これらの材料と道具の活用により、伊勢崎絣は伝統の美と実用性を両立させる織物として、今日まで多くの人に愛され続けています。
伊勢崎絣の製作工程
緻密な意匠と手間が支える手織りの美
括り絣の製作工程を例に、その手仕事の精緻さを紹介します。
- 意匠設計
絣模様の図案を描き、設計図を作成。 - 糸の準備
生糸を煮沸・洗浄し、のりづけして乾燥。 - 糸繰り・整経・経玉づくり
糸枠に巻き取り、縦糸を整え、玉状にまとめる。 - 染色準備
設計図に沿って染め分けの印を糸に付ける。 - 摺込捺染
目印に沿って染料をすり込む。 - 括り
染色した部分を専用テープで括り、防染処理を施す。 - 浸染・絣合わせ
地色を染め、乾燥しながら絣模様を丁寧に揃える。 - 経巻・引込
縦糸を織機に整経し、絣合わせを確認。 - 製織
高機で手織りし、生地に仕上げる。 - 整理加工・検査
のり抜き・蒸気仕上げを行い、完成。
こうして一反の伊勢崎絣が完成するまでには、数十にもおよぶ工程と長い時間が必要とされますが、そのすべてが美しく丈夫な織物としての価値を形づくっています。
伊勢崎絣の未来は、こうした伝統技術の継承にかかっています。着物だけでなく、テーブルクロスやバッグ、ネクタイといった現代の生活に寄り添う製品としても展開され、その可能性はさらに広がっています。手作業でしか生まれない、絹の輝きと絣の芸術。それが、伊勢崎絣の真髄なのです。