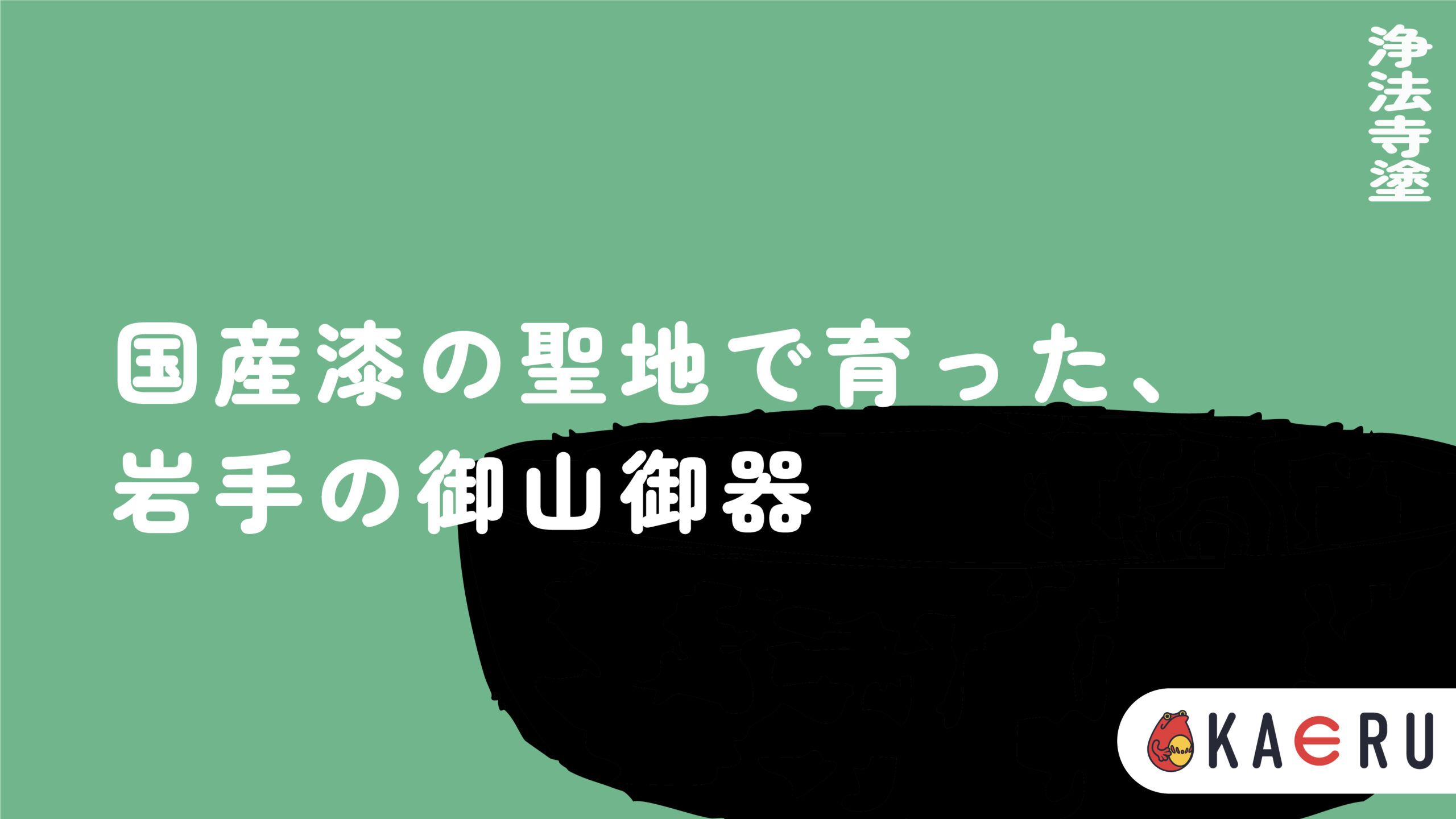浄法寺塗とは?
浄法寺塗(じょうぼうじぬり)は、岩手県二戸市浄法寺町を中心に作られる漆器で、素朴な中にも確かな機能美を宿した伝統的工芸品です。その最大の特徴は、国内生産量がわずか1割以下とされる希少な「国産漆」をふんだんに使い、堅牢な塗り重ねによって仕上げられる点にあります。
起源は奈良時代に遡り、天台宗の古刹・天台寺において修行僧が自らの食器を漆で作ったのが始まりとされています。のちに「御山御器(おやまごき)」と呼ばれるようになったこれらの器は、地元の人々の暮らしに根づき、今もなお“日常使いの漆器”として愛され続けています。
| 品目名 | 浄法寺塗(じょうぼうじぬり) |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1985(昭和60)年5月22日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(12)名 |
| その他の岩手県の伝統的工芸品 | 秀衡塗、岩谷堂簞笥、南部鉄器(全4品目) |

浄法寺塗の産地
御山の漆が育んだ、祈りと暮らしの器文化

浄法寺塗の主産地は、岩手県北部の二戸市浄法寺町です。天台宗の古刹・天台寺の門前町として知られ、古来より「御山(おやま)」と呼ばれる信仰の地でもあります。奈良時代から続く漆器づくりの文化が今も脈々と息づく、まさに“漆の里”です。
この地では修行僧たちが自らのために漆器を作るという自給自足の精神が礎となり、やがて参拝客にも器を分け与える習慣が定着しました。それが「御山御器(おやまごき)」として地域に浸透し、飾り気のない実用的な漆器文化が育まれていきました。
また、浄法寺町は近世から続く「漆掻き(うるしかき)」の技術を代々継承してきた土地であり、ウルシの植栽・採取から精製・塗りまでを一体で担う全国でも稀有な産地です。民藝運動の流れもあり、「用の美」に価値を見出す文化が地域全体に根づいています。
寒冷かつ湿潤な気候が漆の乾燥と育成の両方に適しており、標高差のある地形が良質なウルシ栽培を支えています。さらに、豊かな山林資源に恵まれており、漆器の素地となるミズメザクラやトチノキなどの広葉樹も自生しています。
こうした歴史・文化・自然環境が重なり合い、浄法寺塗は「漆と共に暮らす文化」を体現する唯一無二の漆器として今日に至っています。
浄法寺塗の歴史
天台寺から広がった、1300年の漆器文化
浄法寺塗の歴史は非常に古く、1300年もの時をかけて発展してきました。
- 8世紀中頃(奈良時代):天台寺の僧侶が、自給自足のため自らの食器を漆で製作。漆掻きと塗りの文化の起点。
- 9世紀(平安時代):寺を訪れる参詣者に器を授ける風習が生まれ、「御山御器」として地域に流通。
- 15世紀(室町時代):周辺地域でも漆器づくりが盛んに。日常生活の器として普及。
- 17世紀前半(江戸時代前期):南部藩が漆栽培と塗師の育成を奨励。産業的な基盤が整う。
- 18世紀(江戸時代後期):質素で堅牢な器が主流となり、飾らない実用性が地域文化として定着。
- 1880年代(明治時代中期):輸入漆や合成樹脂の台頭により衰退の危機を迎える。
- 1930年代(昭和初期):柳宗悦らによる民藝運動の影響で、浄法寺塗の価値が再認識される。
- 1985年(昭和60年):浄法寺塗が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 2000年代以降(平成〜令和):浄法寺産漆が文化財修復に不可欠とされ、産地としての重要性が国際的にも評価される。
浄法寺塗の特徴
重ね塗りが映す、漆とともに生きる美意識
浄法寺塗の魅力は、見た目の華やかさではなく、使い込むほどに味わいが深まる“育つ美”にあります。素地にはミズメザクラやトチノキなどを用い、麻布や砥の粉による下地を施したうえで、地元産の漆を何度も塗り重ねて仕上げます。
色彩は、黒、朱、溜(ため)の三色が基本で、光沢は控えめ。とりわけ溜塗は、半透明の漆を通して下地がほのかに透けて見えることで、深みと奥行きのある表情が生まれます。朱塗りの器も、使い込むうちにやや色が沈み、年月を経て独特の渋みが加わるのが特徴です。
また、漆は天然樹脂でありながら抗菌性や耐酸性にも優れ、食器として非常に衛生的。軽くて割れにくく、断熱性もあるため、日常使いにぴったりの道具です。特に、熱い汁物でも器が熱くなりすぎず、口当たりも柔らかく、漆器ならではの実用性が際立ちます。
日本国内で使用される漆のうち、国産漆はわずか約3%にとどまりますが、その7割近く(※約2%)が岩手県二戸市浄法寺町で生産されています。浄法寺漆は高品質で知られ、国宝・重要文化財の文化財修復にも広く用いられてきました。

浄法寺塗の材料と道具
漆と木が支える、実用性と美の両立
浄法寺塗の製作には、地元の自然資源を活かした素材と、専門性の高い漆芸道具が欠かせません。
浄法寺塗の主な材料類
- 浄法寺漆:国内漆の7割を占める希少な天然漆。高い粘度と乾きの良さが特徴。
- ミズメザクラ・トチノキ:器の素地に用いられる堅牢な木材。
- 地の粉・砥粉(とのこ):下地に用いる天然鉱物。
- 麻布・和紙:素地の補強に用いられる。
浄法寺塗の主な工具類
- 漆刷毛:塗りの工程で用いる。人毛を素材とする繊細な道具。
- ヘラ(地塗り・中塗り用):漆や下地材を均一に塗るために使用。
- ヤスリ・木賊(とくさ):表面の研磨に使われる。
- 蒔絵筆(まきえふで):簡素な加飾を施す際に使われる場合も。
地元の自然とともに歩んできた浄法寺塗は、素材も技術もすべて“土に還る”循環型のものづくりを体現しています。
浄法寺塗の製作工程
漆を育て、幾重にも塗り重ねる熟練の技
浄法寺塗の製作は、「育てるように塗る」とも表現されるほど、手間と時間を要する工程です。
- 木地づくり
ミズメザクラなどの広葉樹を使用し、ロクロや刳り物で器の形を作る。 - 布着せ
木地の強度を増すため、布を貼り、漆と下地材で密着させる。 - 下地塗り
砥の粉と漆を混ぜたペーストで表面を何度も塗り重ね、乾燥・研磨を繰り返す。 - 中塗り
漆を複数回に分けて均一に塗布し、厚みを出していく。 - 上塗り(仕上げ)
黒・朱・溜などの色漆を丁寧に塗り、光沢と深みを調整。 - 乾燥・仕上げ研磨
漆室(むろ)と呼ばれる湿度管理された空間で自然乾燥。研磨や検品を経て完成。
すべての工程において、「塗っては乾かし、また塗る」という繰り返しがあり、完成までに数週間から数ヶ月を要します。まさに、手と時間で育てる漆器なのです。
浄法寺塗は、国産漆の聖地・岩手県浄法寺町で生まれた、素朴で堅牢な漆器です。奈良時代から続く信仰と暮らしの文化が育んだ器は、使うほどに美しさを増し、現代の食卓にも静かな存在感を放ちます。自然とともにあるものづくりの原点が、ここにあります。