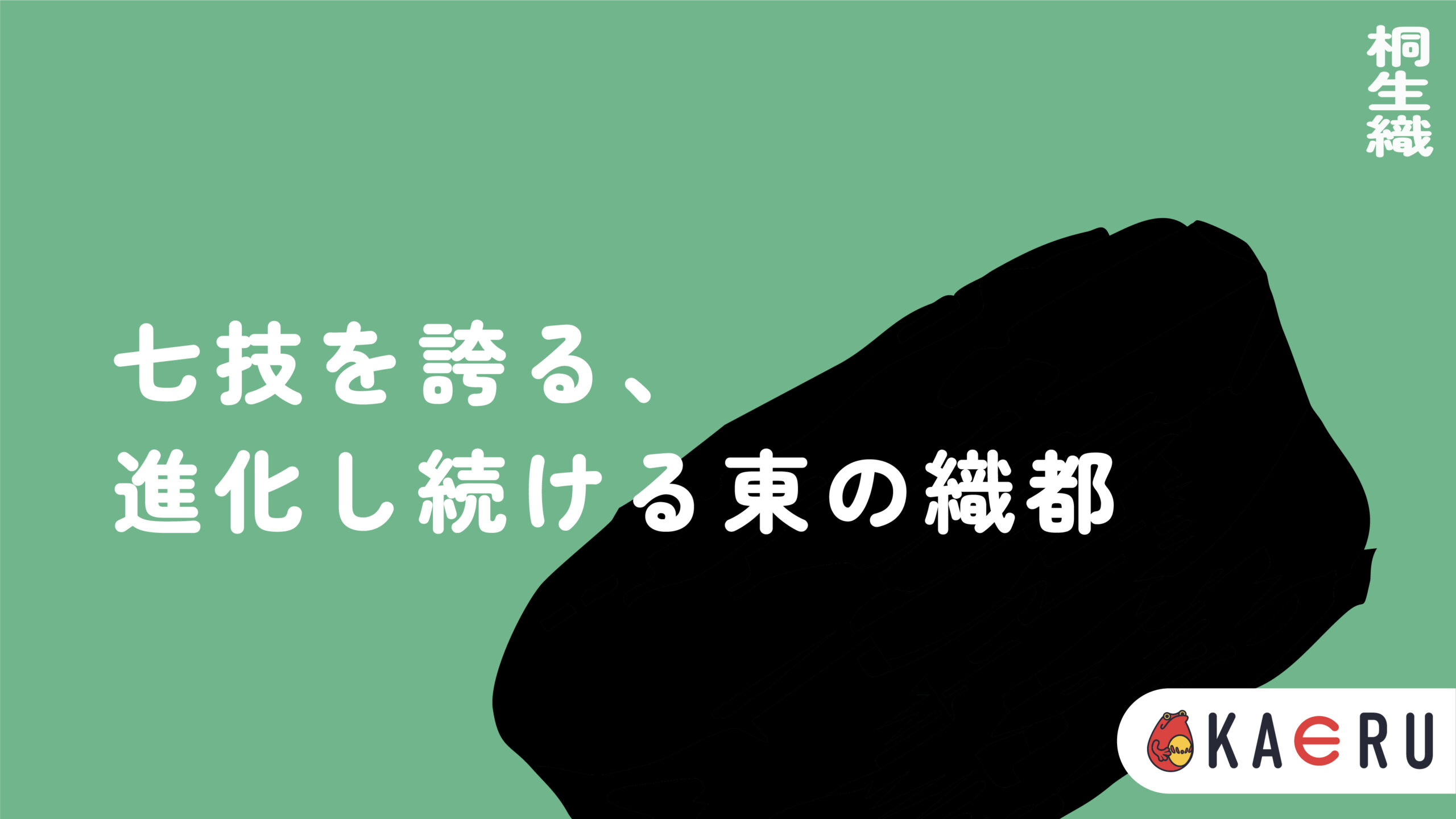桐生織とは?
桐生織(きりゅうおり)は、群馬県桐生市を中心とした地域で受け継がれてきた高級絹織物です。その起源は奈良時代にまでさかのぼり、『続日本紀』にも記録が残るほどの長い歴史を誇ります。京都・西陣と並び称されるほどの技術をもち、「西の西陣、東の桐生」と呼ばれてきました。
七種類にもおよぶ多彩な織技法を今に伝え、しなやかで光沢のある布地を生み出す桐生織は、和装からインテリア・現代ファッションにまで幅広く活用されています。歴史と革新が織りなす桐生織は、まさに「進化する伝統」の象徴といえるでしょう。
| 品目名 | 桐生織(きりゅうおり) |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1977(昭和52)年10月14日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 16(73)名 |
| その他の群馬県の伝統的工芸品 | 伊勢崎絣(全2品目) |

桐生織の産地
機の音が響く、織物のまち・桐生

群馬県の東部に位置する桐生市は、古くから織物のまちとして栄えてきました。赤城山系の清流と、利根川や渡良瀬川の豊富な水資源に恵まれ、製糸・染色に適した土地として発展。古墳時代には朝鮮半島から伝わった織技術が定着し、奈良時代にはすでに朝廷への献上品として織物が届けられていたとされます。
近代以降は、ジャカード織機やドビー織機といった先進技術を積極的に取り入れ、伝統を保ちながらも進化を続ける“織都”として知られています。
桐生織の歴史
朝廷への献上から、近代織物の最前線へ
桐生織の歴史は、今からおよそ1300年前、奈良時代にさかのぼります。『続日本紀』には、下毛野国(しもつけのくに)から織物が朝廷に献上されたとの記録があり、これが桐生における織物の最古の文献とされています。
- 奈良時代:山背の御織部の技術が桐生へ伝来。
- 室町時代:西陣織と技術交流。高級織物としての基盤が整う。
- 江戸時代:幕府献上品としての地位を確立。「西の西陣、東の桐生」と称される。
- 明治時代:富岡製糸場との連携により、製糸・染色・織布の一大拠点になる。
- 大正〜昭和期:近代織機を導入しながらも、手織りの伝統を保持。
- 1977年(昭和52年):桐生織が経済産業省より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:高度なジャカード技術を継承しつつ、アパレルやインテリア分野への応用も進む
こうして桐生は、高度な技術力と感性を備えた織物産地として、1300年以上にわたる歴史を現在に伝えています。
桐生織の特徴
七技が生み出す、立体的で華やかな織の表現
桐生織の特徴は、なんといってもその「織りの多彩さ」にあります。代表的な七種の技法には以下のようなものがあります。
- お召織:細かいシボをもたせたしなやかな織り。高級着物地に多用。
- 緯錦織(ぬきにしきおり):横糸で模様を織り出す錦織技法。
- 経錦織(たてにしきおり):縦糸の配置で文様を構成する高度な技法。
- 風通織(ふうつうおり):表と裏で異なる文様が現れる二重織り。
- 浮経織(うきたており):経糸を浮かせて模様を出す表情豊かな織り。
- 経絣紋織:絣染めの経糸に紋様を重ねる、染と織の融合。
- 捩り織(もじりおり):経糸と緯糸を交差させ、透け感のある布を織る技法。
これらの技術を自在に組み合わせることで、桐生織は見た目にも手触りにも奥行きをもたせ、見る角度によって表情を変えるような織物が生まれます。まさに「織の芸術」とも呼ぶべき奥深さが、この織物には宿っているのです。

桐生織の材料と道具
絹と機が織りなす精緻な世界
桐生織では、主に国産の絹糸が用いられ、その特性を最大限に引き出すために、伝統的な道具と現代的な機械が併用されます。
桐生織の主な材料類
- 絹糸:国産の生糸を中心に使用。なめらかで光沢に優れる。
- 染料:化学染料・天然染料を使い分け、深みある色彩を表現。
桐生織の主な工具類
- ジャカード織機:細かい文様を織る高性能機械。
- ドビー織機:中規模の複雑な模様に対応。
- 高機:伝統的な手織り機で、一部製品に使用。
- 紋紙:図案をパンチカードにして織機に読み込ませる。
- 管巻き機・緯入れ具:糸の調整と管理に使用。
精緻な意匠と実用性を両立する桐生織は、こうした素材と道具の融合によって支えられています。
桐生織の製作工程
設計から仕上げまで、一貫した美の連なり
桐生織の製作は、設計から仕上げまで一貫して職人の技によって支えられています。ここでは代表的な工程を紹介します。
- 意匠設計
織物の図案を設計し、紋紙またはデジタルデータとして準備。 - 糸の準備
絹糸を精練・染色し、必要に応じて経糸・緯糸を整える。 - 整経・糸張り
織機にあわせて経糸の本数や長さを揃えて張る。 - 装置準備
ジャカード織機やドビー織機に紋紙やデータをセット。 - 製織
手織りまたは機械織りにより、設計通りに文様を織り出す。 - 検反・整理加工
織り上がった布地を検査し、蒸し・湯のし・縮絨などの仕上げを施す。
一反の布が完成するまでには数十にも及ぶ工程があり、そのすべてに熟練の技と判断力が求められます。桐生織は、1300年にわたる歴史の中で、常に時代の変化を受け入れながら進化してきました。現代では、伝統的な和装に加え、ネクタイ・ストール・バッグ・インテリアファブリックなど、日常生活に寄り添う製品へと展開が広がっています。
また、若手デザイナーやアーティストとのコラボレーションも活発に行われ、伝統技術をベースにした新しい表現が次々と生まれています。織の芸術として、そして未来へつなぐ文化として、桐生織は今なお織り続けられているのです。