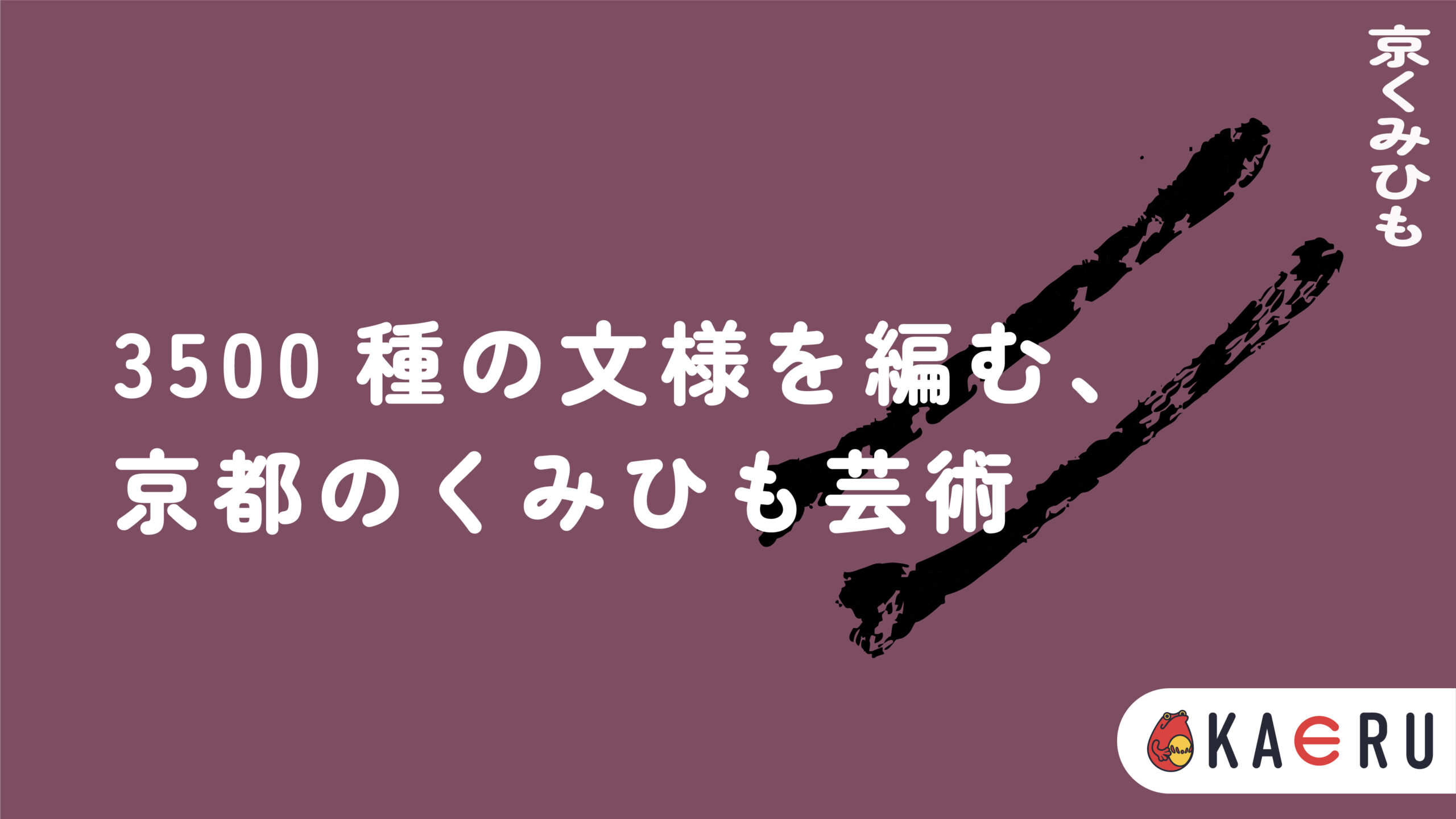京くみひもとは?
京くみひも(きょうくみひも)は、京都市および宇治市を中心に製作されている伝統的な組紐工芸です。染め上げた絹糸を専用の組台で繊細に編み上げていく技法は、平安時代に確立され、仏具や神具、宮中装束、武具、さらに現代では和装小物やアクセサリーにまで多彩に展開しています。
「組む」ことで立体的な文様や構造を表現する京くみひもは、結び目ひとつに意味を込め、色の配列や紐の撚りに京都の美意識が息づく、日本独自の装飾文化です。
| 品目名 | 京くみひも(きょうくみひも) |
| 都道府県 | 京都府 |
| 分類 | その他繊維製品 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 14(36)名 |
| その他の京都府の伝統的工芸品 | 西陣織、京漆器、京友禅、京うちわ、京指物、京繍、京仏具、京小紋、京鹿の子絞、京仏壇、京黒紋付染、京石工芸品、京焼・清水焼、京扇子、京人形、京表具(全17品目) |

京くみひもの産地
王朝文化と信仰が育んだ、装飾紐の美と機能

主要製造地域
京くみひもの主産地は、京都市および宇治市を中心とした京都府南部です。千年以上にわたり都として栄えた京都は、政治・宗教・芸術の中心地であり、その暮らしの中で京くみひもは実用と美の両面から発展を遂げてきました。
平安時代に公家社会の装束や調度品の飾り紐として組紐文化が定着し、さらに中世には武士の武具として用途が広がるなど、用途の変遷とともに技術も洗練されていきました。近世に入ると町人文化の成熟と共に、帯締めや羽織紐として日常に浸透し、くみひもは装飾工芸としての価値を高めていきました。
また、京都特有の洗練された色彩感覚と繊細な装飾美が、くみひもにおける文様や配色の多様性を支えています。また、西陣織や京友禅など染織文化との共鳴も深く、素材選びや染色技術の高度化にも影響を与えてきました。
京くみひもの歴史
貴族文化から武具・装身具へ、用途と技の広がり
京くみひもは、1000年以上の歴史を誇る日本有数の組紐技術として、各時代の社会と密接に関わりながら発展してきました。
- 8世紀(奈良時代):朝鮮半島より組紐技法が伝来。仏具・経巻の結束紐として用いられる。
- 794年(平安遷都):宮廷文化の装束や調度品に組紐が多用され、雅な文様が発展。
- 13世紀(鎌倉時代):武士の台頭により、甲冑の緒や刀の下緒として実用品としての需要が拡大。
- 16世紀(安土桃山時代):南蛮文化と交わり、装飾性の高い結びや意匠が加わる。
- 17世紀(江戸初期):羽織紐・帯締めとして庶民にも普及。需要増加により生産体制が整備される。
- 19世紀(幕末〜明治初期):洋装との共存により、新たな装身具や贈答品としての用途が増加。
- 1976年(昭和51年):京くみひもが経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:伝統の技を活かした現代アートやファッションとの融合が進む。
京くみひもの特徴
3500種におよぶ組み方が生む、無限の表現と文様の美
京くみひもの特徴は、絹糸の光沢と滑らかな手触り、そして組み方の多様性にあります。基本的な組み方だけでも約40種類、応用や用途に応じた文様を含めると3500種類以上にのぼるとされ、まさに無限の可能性を秘めた工芸です。
帯締めや羽織紐に使われるだけでなく、結納飾りや神仏具、現代ではストラップやネックレス、茶道具の飾り紐など、幅広い場面で用いられています。文様には、吉祥を表す「松竹梅」や「亀甲」、五色を配した縁起色などがあり、結び方にも「叶結び」「宝結び」などの意味が込められています。色彩の調和、糸の撚り加減、組目の密度といった細部に、職人の美意識と熟練が宿ります。
京くみひもの材料と道具
糸の表情を操る、絹と台と職人の三位一体
京くみひもの製作は、糸の選定・染色・組み立てに至るまで、すべてが高度な手作業で行われます。素材の美と技の融合が、品格ある風合いを生み出します。
京くみひもの主な材料類
- 絹糸:発色と光沢に優れ、滑らかな手触りを持つ。
- 染料:手作業で調合し、図案に応じて美しく染色される。
京くみひもの主な道具類
- 組台:高台・丸台・角台・綾竹台・籠打台・内記台・重打台などがあり、用途により使い分ける。
- 糸くり機:染色後の糸を巻き取るための装置。
- 経尺(へいしゃく):糸の長さや太さを整えるための大枠。
- 転がし台:組み上げた紐の目を整える仕上げ台。
これらの道具と糸に、職人の熟練した手業が加わることで、上品で優美な一本の紐が生まれるのです。
京くみひもの製作工程
絹糸が舞う、組みの妙技が紡ぐ工程美
京くみひもの製作は、色糸の準備から房の仕上げまで、すべてが繊細で丁寧な手仕事によって行われます。
- 糸割り
組む長さや太さに応じて、絹糸を必要本数に分ける。 - 染色
図案に基づき、職人が手作業で均一に糸を染め上げる。 - 糸くり・経尺
染めた糸を糸くり機で巻き取り、大きな枠に整えて経尺する。 - 糸合わせ・よりかけ
複数の細糸を撚り合わせて、適切な太さに調整。 - 組み
目的に応じた組台を使い、リズムよく糸を交差させながら組んでいく。 - 房づくり
組み上げた両端の糸をほぐして房を整え、結びを施す。 - 湯のし・転がし
全体を蒸して形を整え、転がし台で組目を均一にして完成。
京くみひもは、視覚・触覚・感性のすべてに訴える工芸です。組まれた一本の紐の中に、職人の技と京都の美意識が凝縮されています。
京くみひもは、千年の都・京都で磨かれてきた絹糸の芸術です。仏具や装飾品から現代のファッションまで幅広く活躍し、組みの多様性と優美な色彩が織りなす文様は、職人の感性と技の結晶です。伝統を守りつつ、新たな表現へと進化を続けています。