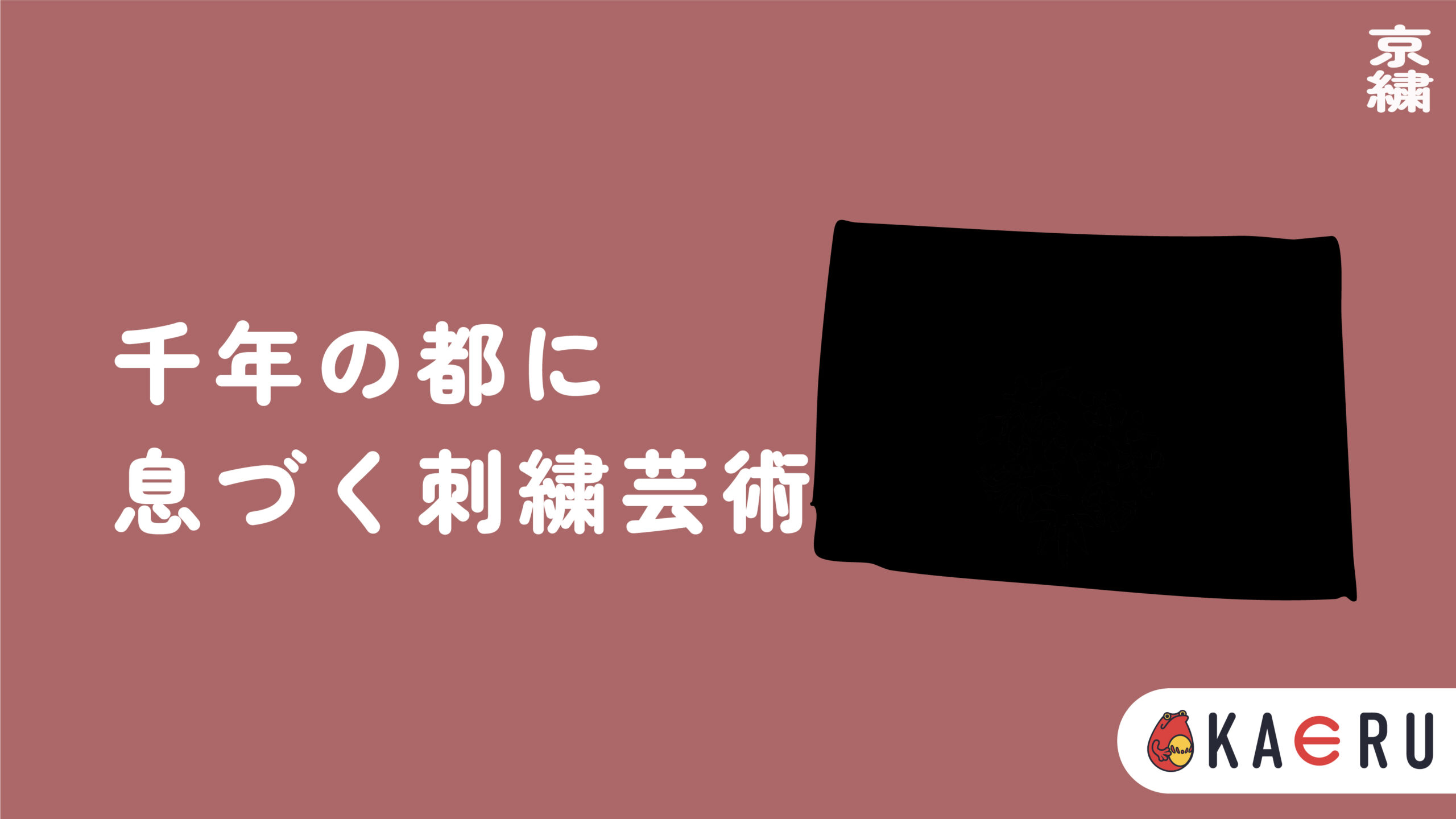京繍とは?
京繍(きょうぬい)は、京都府内で作られている伝統的な刺繍工芸品です。絹や麻の織物に、色とりどりの絹糸などを用いて模様を刺し表すその手法は、「糸で描く絵画」とも称されるほどに精緻で華麗。
平安時代の宮廷文化を源流とし、能装束や仏教美術、さらには京友禅などの衣装にも装飾として取り入れられてきました。伝統的な技法は30種以上、指定技法だけでも15種を数え、細部まで神経の行き届いた手仕事によって、その品格と美しさが現代にも受け継がれています。
| 品目名 | 京繍(きょうぬい) |
| 都道府県 | 京都府 |
| 分類 | その他繊維製品 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 38(64)名 |
| その他の京都府の伝統的工芸品 | 西陣織、京漆器、京友禅、京うちわ、京指物、京くみひも、京仏具、京小紋、京鹿の子絞、京仏壇、京黒紋付染、京石工芸品、京焼・清水焼、京扇子、京人形、京表具(全17品目) |

京繍の産地
王朝文化を支えた、刺繍芸術のふるさと・京都

主要製造地域
京繍の主産地は、京都市を中心とする京都府内です。794年の平安京遷都以来、京都は約1000年にわたり日本の首都として文化と芸術の中核を担ってきました。宮廷文化のもとでは、衣装や調度品の装飾美が重視され、その流れの中で京繍は刺繍芸術として発展してきました。
また、京都の伝統産業の特徴として「分業制」があります。京繍も例外ではなく、図案描き、配色、繍加工など各工程を専門職が担い、相互に連携することで高度な仕上がりを実現しています。この分業体制は江戸時代以降に確立され、技術継承を支える仕組みとなりました。
さらに、京都の気候も刺繍製作に適しています。夏の高温多湿は糸の発色や生地の伸縮に影響を与える一方で、四季の移ろいが色彩や図案の着想に豊かさをもたらしました。また、冬の乾燥期は糸の扱いがしやすく、繍作業の仕上げに向いています。こうした文化的・地理的・気候的条件が重なり合うことで、京繍という芸術が育まれてきたのです。
京繍の歴史
平安の宮廷に始まる、糸の芸術の系譜
京繍の歴史は、平安京の誕生とともに幕を開けます。宮廷文化や武家文化、そして宗教美術の隆盛を背景に、その技は長きにわたって磨かれてきました。
- 794年(平安時代初頭):平安遷都と同時に、刺繍専門の官職「縫部司(ぬいべのつかさ)」が設置される。宮廷衣装や調度品に刺繍が施されるようになる。
- 11世紀(藤原時代):公家装束に精緻な刺繍が施される。御所文化における優美な装飾の象徴に。
- 1185年(鎌倉時代):武士の直垂・銅服に刺繍が使われるようになり、実用性と装飾性を併せ持つ存在に。
- 1336年(南北朝・室町時代):能楽の隆盛とともに、能装束に華やかな刺繍が用いられ、芸術性が高まる。
- 1600年代(江戸時代初期):町人文化の広がりとともに、一般階層の婚礼衣装や祭礼衣装にも京繍が用いられる。
- 1700年代後半:京友禅との併用が始まり、図案との融合で複雑な装飾表現が発達。
- 明治時代:文明開化により洋装化が進む中でも、晴れ着や婚礼衣装としての京繍の地位が確立。
- 1976年(昭和51年):京繍が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
京繍の特徴
一針一針が紡ぐ、静謐で絢爛たる美の世界
京繍の魅力は、繊細かつ華やかな刺繍表現にあります。糸を“描く”ように縫い込むことで、花鳥風月や吉祥文様などを立体的に、かつ豊かな質感で表現します。絹糸に撚りをかけるか否か、太さを変える、刺す角度や重ね方を調整するなど、一つのモチーフに対して多様な刺し方が用いられるのが京繍の奥深さです。
また、まつい繍や霧押え繍、刺し繍などの技法によって、陰影やぼかしを巧みに表現し、糸の重なりで空気感すら描き出します。こうした技法の積み重ねが、「糸で描く絵画」と称される京繍独自の芸術性を生み出しているのです。
京繍の材料と道具
絹の光沢と、職人の目利きが織りなす刺繍の世界
京繍の製作には、刺繍専用の絹糸や生地、繊細な針や枠など、多様な素材と道具が用いられます。それらを使いこなす職人の繊細な技が、美しい刺繍表現を支えています。
京繍の主な材料類
- 絹糸:染色された高品質な絹糸。光沢と発色が美しく、撚りの有無で質感を調整。
- 絹や麻の生地:模様を刺すための台布。繊細な繍加工に適したものが用いられる。
- 青花・胡粉:図案写しに使用される顔料。生地に描くため水溶性のものが選ばれる。
京繍の主な道具類
- 針(約15種):用途に応じて使い分ける。全て手作りで、太さ・長さ・しなりに特徴あり。
- 樋棒・台帳・台枠:生地を張る専用の枠や棒。大きさや図柄に応じて使い分ける。
- 照明台:図案を透かして下絵を写すために用いられる。
- 糸切りばさみ・糸通し・ピンセット:細部の処理や糸の取り扱いに欠かせない。
こうした素材と道具を駆使しながら、刺繍の構図、質感、立体感を一針ずつ仕上げていきます。
京繍の製作工程
糸に魂を込める、繊細な手仕事の連なり
京繍の製作は、図案から配色、刺繍加工、仕上げに至るまで、すべての工程に高度な技と集中力が求められます。
- 図柄の作成
鉛筆や筆を用いて原画を作成。モチーフは自然風景や吉祥文様など。 - 下絵かき
照明台の上で原画を透かし、青花や胡粉で生地に写す。 - 配色
糸の色・太さ・撚りなどを調整しながら、図柄に合わせて刺繍糸を決定。 - 生地はり
生地を歪まないように台帳や台枠に固定。樋棒を使う場合も。 - 繍加工
伝統技法を駆使し、一針一針丁寧に模様を刺していく。技法の選択が完成度を左右。 - 仕上げ
裏面に糊をつけて乾燥させ、糸を固定しつつ全体の張りを整える。
完成した京繍は、衣装や装飾品として用いられるだけでなく、空間や時間に静かな彩りを添える芸術品として、多くの人々に感動を与えています。
千年を超える時の中で、京繍は刺繍を超えた“糸の絵画”として昇華されてきました。絹糸の一本一本に心を込め、一針一針が織りなす優雅な美しさは、今なお京都の静かな工房から世界に向けて発信され続けています。伝統と革新が共に息づく京繍は、日本が誇る装飾芸術の極みといえるでしょう。