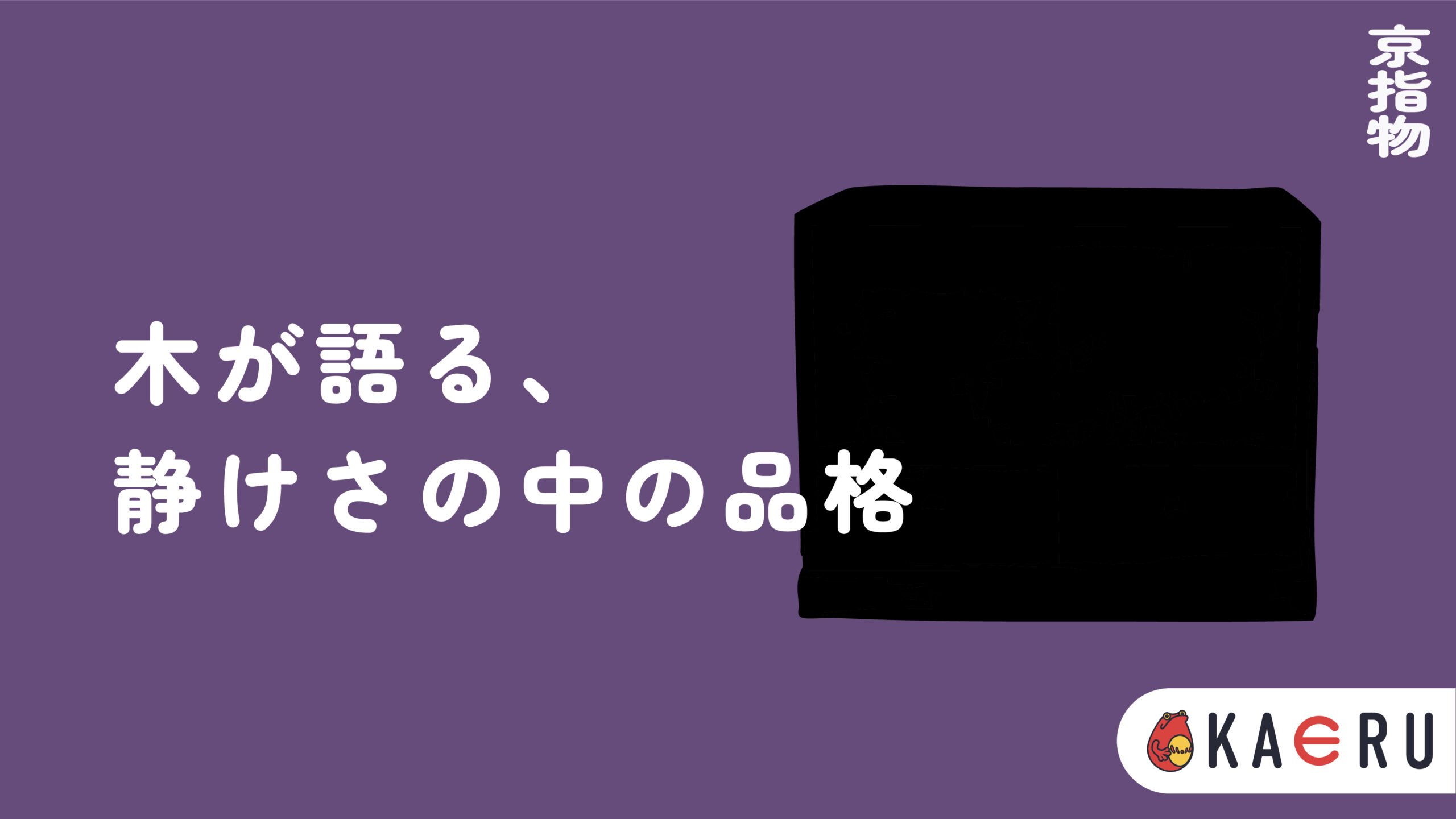京指物とは?
京指物(きょうさしもの)は、京都市内で作られている伝統的な木工品です。最大の特徴は、釘や金具を一切使わず、精緻な組手・継手によって木と木をつなぎ合わせる構造にあります。平安時代の御所調度に始まり、茶道具・数寄屋建築・書院家具など、静かで端正な美を求められる空間の中で発展してきました。
特に、茶の湯文化と結びついた棚物や香合、炉縁といった道具は、用と美の両立を求められる日本独自の造形意識の象徴とされます。京指物は、単なる木工品ではなく、“空間と調和する木の詩”として、暮らしと文化の中に根を下ろしてきたのです。
| 品目名 | 京指物(きょうさしもの) |
| 都道府県 | 京都府 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 14(29)名 |
| その他の京都府の伝統的工芸品 | 西陣織、京漆器、京友禅、京うちわ、京繍、京くみひも、京仏具、京小紋、京鹿の子絞、京仏壇、京黒紋付染、京石工芸品、京焼・清水焼、京扇子、京人形、京表具(全17品目) |

京指物の産地
茶の湯文化とともに育まれた木工の美意識
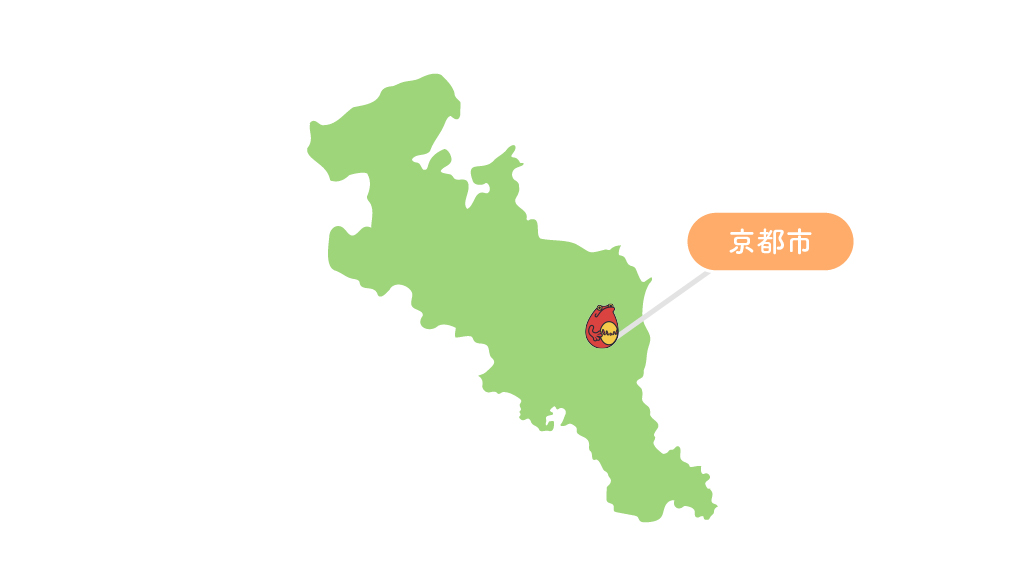
主要製造地域
京指物の主産地は京都市内で、中京区・東山区・北区などの歴史的町並みを残す地域を中心に製作が行われています。京都は千年以上にわたり日本の文化と美意識を牽引してきた都であり、御所文化、寺院建築、町人文化が共存する独自の美意識を育んできました。
特に茶の湯文化の影響は大きく、書院造や数寄屋造といった空間様式に合わせた調度品として京指物が発展しました。茶室の棚や炉縁、香合や道具箱などは、形状だけでなく素材や木目、寸法にも厳密な基準が求められ、工芸と精神性が深く結びついています。
また、京都は盆地特有の気候で湿度差が大きく、木材が反りやすい環境にあるため、寸法精度と木組みの技術が特に重視されてきました。こうした気候への対応と、住まいに品格を求める文化的背景が、京指物を高度な木工芸術へと育て上げたのです。
京指物の歴史
御所調度から数寄の道具へ、静かに継がれた木工の系譜
京指物の歴史は、都とともに歩んできた工芸の系譜そのものです。道具を“道”と捉える日本独自の文化の中で、その姿を磨き続けてきました。
- 794年(平安京遷都):貴族文化とともに、御所の調度品として指物技法が登場。
- 1100年代(院政期):寺院建築における仏具棚などで釘を使わない木工技術が用いられる。
- 1336年(室町幕府成立):書院造の台頭とともに、家具調度に京指物の原型が定着。
- 1480年代(村田珠光の活動期):わび茶思想が広まり、茶室用指物に簡素な意匠が求められる。
- 1580年代(千利休の時代):茶道具としての指物が洗練され、棚物・香合・道具箱などが発展。
- 1700年代(江戸中期):町人文化が隆盛し、町家で使う箪笥・棚類の需要が拡大。
- 1868年(明治維新):宮廷文化の衰退とともに需要は一時減少するが、茶人や文化人が継承。
- 1930年代(昭和初期):京数寄屋建築の復興とともに、棚や建具などの指物需要が再燃。
- 1945年(戦後復興期):建築需要の高まりとともに、寺社・茶室建具としての需要が回復。
- 1976年(昭和51年):京指物が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
京指物の特徴
一切の無駄を削ぎ落とした木組み
京指物の最大の特徴は、接合に釘や金具を使わない「組手(くで)」「継手(つぎて)」の技術にあります。榫(ほぞ)やほぞ穴を組み合わせ、木材そのものの力でしっかりと組み上げる手法は、造形的な美しさと構造的な強さを両立させています。
家具や茶道具などは、いずれも直線的で凛とした姿をもちながら、木地の柔らかさや繊維の方向を考慮して加工されており、空間に品格と調和を与えます。
なかでも「手鉋仕上げ」による面取りや、「差し込み棚」「釘隠し継手」といった技巧は、目に見えない部分にまで意匠が宿る、京ならではの美意識を感じさせます。
また、杉や桐、ヒノキなどの木目を活かしたシンプルな造形は、使い手の暮らしに静かに寄り添い、長く愛される「用の美」の真髄を体現しています。

京指物の材料と道具
繊細な木地と真っ直ぐな線を生む、京の道具立て
京指物の製作では、湿度の変化に強く、加工しやすい国産材が主に使われます。木目の美しさや木肌の素直さが求められるため、材料の選別には熟練の目利きが不可欠です。
京指物の主な材料類
- 桐(キリ):軽くて狂いが少なく、茶道具などに最適。
- 杉(スギ):柔らかく、滑らかな木肌で家具にも用いられる。
- 檜(ヒノキ):香り高く、精度の高い加工が可能。
- 欅(ケヤキ):堅牢で高級感ある木目が特徴。
京指物の主な道具類
- 墨差し・墨壺:正確な墨付けのための基本工具。
- 鉋(かんな):微細な面調整や仕上げに使用。
- 鋸(のこぎり):直線・細部切断に。指物専用の薄刃鋸も使う。
- 錐(きり):下穴あけや仕込み用。
- 治具(じぐ):精密な位置決めのために自作されることも多い。
こうした材料と道具を使いこなし、ミリ単位の精度で木を組み上げる技術が、京指物の品質を支えています。
京指物の製作工程
釘を使わずに組み上げる、精緻な木工の流れ
京指物の製作は、図面設計から木取り・仕上げに至るまで、一貫して手作業で行われます。各工程には高い精度と美意識が求められます。
- 設計・図面作成
用途や空間に応じた図面を引き、木材寸法や継手の位置を決定。 - 木取り・面取り
木目・方向を見極めて部材を切り出し、鉋で表面を整える。 - 継手・組手加工
ほぞや凹凸の形状を細かく刻み、接合部を成形。 - 仮組み・調整
全体を仮組みし、歪みや隙間を微調整。 - 本組み・仕上げ
接合し、鉋で最終仕上げ。必要に応じて蝋引きや拭き漆などの仕上げを施す。
完成した京指物は、釘を一本も使わずに木だけで組み上げられた、精密で端正な工芸品。美と実用が結晶した、京都の暮らしを支えてきた静かな名品です。
京指物は、釘を使わずに木を組み上げる高度な技術によって生まれる、京都を代表する伝統木工品です。平安期から受け継がれる繊細な意匠と茶の湯文化に根ざした美意識が、静けさの中に気品を宿らせます。今も数寄屋建築や茶室空間に求められ、京の暮らしと文化を支え続けています。