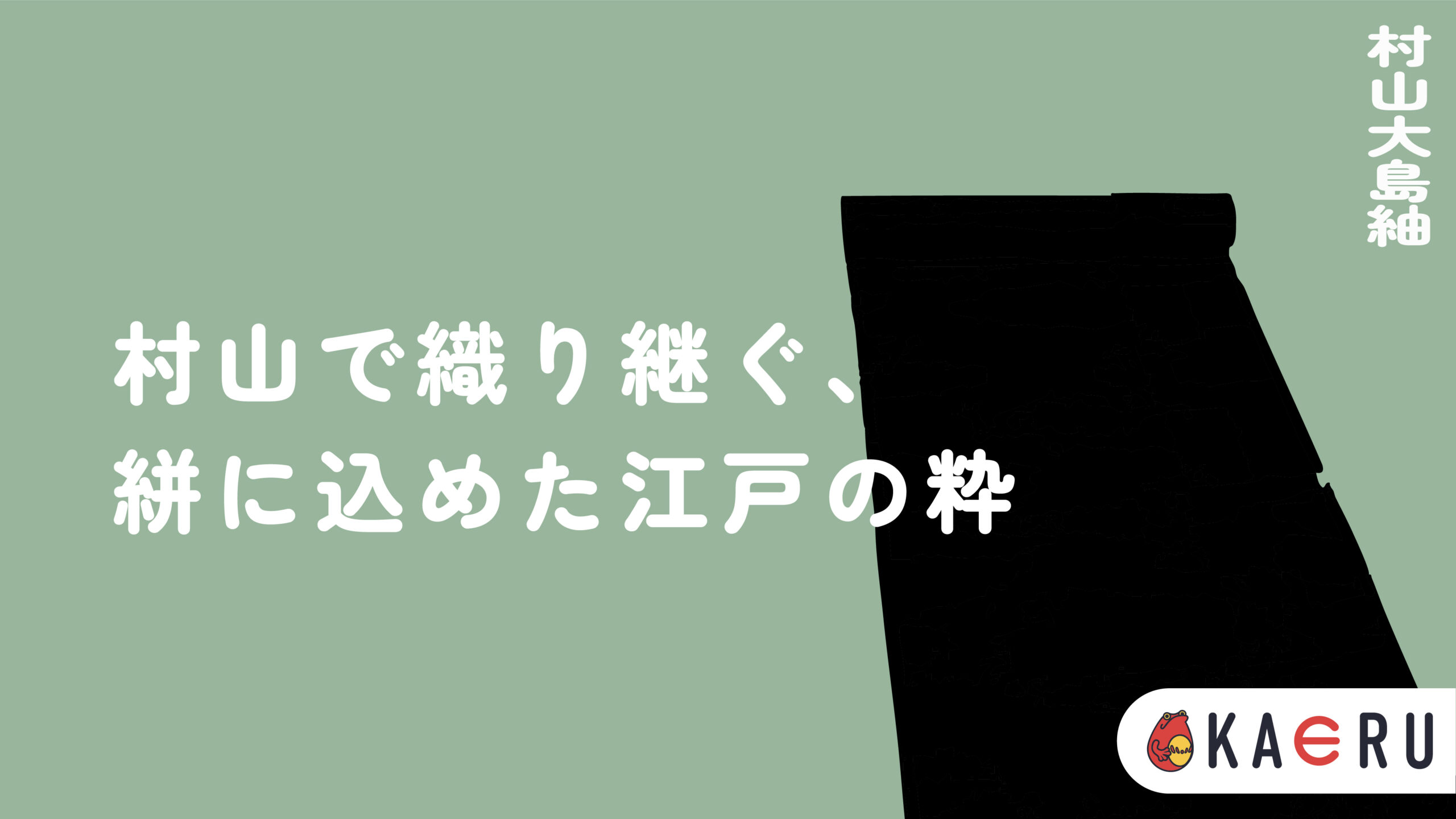村山大島紬とは?
村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ)は、東京都武蔵村山市周辺で生産される絹織物で、精緻な絣模様が特徴の伝統的工芸品です。名称に「大島紬」とありますが、奄美大島のそれとは異なり、東京の地場産業として独自の発展を遂げてきました。
村山大島紬では、大島紬と同じく生糸を用いながらも、板締め染色法やすり込み捺染といった技法により、精巧で美しい絣柄を効率的に生み出しています。滑らかな肌ざわりと軽やかさから、長時間着ていても疲れにくく、通好みの「普段着の逸品」として親しまれてきました。
| 品目名 | 村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 11(36)名 |
| その他の東京都の伝統的工芸品 | 東京染小紋、本場黄八丈、江戸木目込人形、東京銀器、東京手描友禅、多摩織、江戸和竿、江戸指物、江戸からかみ、江戸切子、江戸節句人形、江戸木版画、江戸硝子、江戸べっ甲、東京アンチモ二ー工芸品、東京無地染、江戸押絵、東京三味線、東京琴、江戸表具、東京本染注染(全22品目) |

村山大島紬の産地
東京の西北、武蔵村山の地場技術

村山大島紬の産地は、東京都多摩地域北部に位置する武蔵村山市およびその周辺地域です。江戸時代より桑の栽培と養蚕が盛んで、地場産業として織物文化が根付いてきました。
都市化が進む現代においても、この地域では手仕事による伝統的な製織技法が継承されており、村山大島紬は東京が誇る数少ない織物文化の一つとして評価されています。
村山大島紬の歴史
江戸の養蚕文化とともに育まれた絣の普及品
村山大島紬は、江戸時代の農村部での養蚕と機織りの技術をもとに発展し、奄美大島の大島紬の影響を受けつつ、独自の板締め絣技術で確立されました。
- 18世紀末〜19世紀初頭(江戸時代後期):養蚕が盛んだった多摩地域で、農家の副業として機織りが普及。材の製造が始まり、東京に出荷。地元でのうちわづくりの土壌が形成される。
- 19世紀後半(明治時代):奄美大島の大島紬の技術が伝わり、これを参考にした板締め絣染色法が確立される。より手軽に生産できる絣織物として「村山大島紬」の名称が使われるように。
- 20世紀前半(大正〜昭和初期):村山大島紬は、丈夫で軽く着やすい日常着として広く普及。男性用には遠目に無地に見える細かい絣柄が好まれた。
- 1980年(昭和55年):村山大島紬が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:高度な絣合わせ技術を誇る織物として、着物愛好家の間で根強い人気を保ち、後継者育成と販路拡大が進められている。
村山大島紬の特徴
絣が語る、江戸の美意識
村山大島紬の最大の魅力は、細やかで緻密な絣模様にあります。絣とは、あらかじめ染め分けた経糸と緯糸を正確に柄合わせして織り上げる技法であり、織り手の高度な技術が求められます。
村山大島紬では、板締め注入染色法とよばれる独自技法を用いて絣糸を染色。その後「すり込み捺染」によって部分的に多色染めを施すこともあります。これにより、あたたかみのある絣模様が生まれ、素朴でありながらも気品ある風合いが特徴となっています。
また、絹特有の光沢と、肌ざわりの良さ、軽さは長時間の着用でも疲れにくく、普段着からおしゃれ着まで幅広い用途で親しまれてきました。

村山大島紬の材料と道具
絹と木板が織りなす技法
村山大島紬の製作には、伝統的な天然素材と職人技が欠かせません。
村山大島紬の主な材料類
- 生糸(絹糸):経糸・緯糸ともに使用。絹の光沢としなやかさが特徴。
- 染料:植物染料などの草木染による天然の色合い。
- 板(絣板):みずめ桜の大木を使って製作される、絣染め用の木板。
村山大島紬の主な道具類
- 地機:経糸と緯糸を手動で織る織機。
- 絣板固定具:絣板を圧着させる際に使うボルト等。
- 竹べら:すり込み捺染に用いられる染料を糸に染み込ませる道具。
- 湯舟・染舟:染色工程で使用する槽。
素材と道具、そしてそれを扱う職人の熟練が一体となることで、村山大島紬の上質な風合いが生み出されています。
村山大島紬の製作工程
絣を染め、織り上げる精緻な手仕事
村山大島紬は、絣糸の染めから織り上げまで、すべての工程を職人の手で丁寧に仕上げていく織物です。板締め染色やすり込み捺染といった独自技法を駆使し、緻密な絣模様を生み出す過程には、長年培われた技術と経験が息づいています。
- 絣板の製作
絣模様ごとに異なる絣板を、70〜100年以上の歳月を経たみずめ桜で製作します。 - 絣染色(板締め注入染色)
経糸・緯糸を絣板に挟み、10〜15t/㎡の圧力で締めてから、湯と染料を注いで染色します。 - すり込み捺染
必要に応じて、染め上げた絣糸に絵柄をすり込み、部分的に異なる色を加えます。 - 括りと防染
染めた絣糸を束ねて括り、模様のズレやにじみを防ぎます。 - 整経と糸準備
染め終わった糸を経糸・緯糸に整え、織機にかけられるように調整します。 - 製織
手織りの地機で、経糸と緯糸を絣模様がずれないように丁寧に合わせながら織り進めます。 - 検品と証紙貼付
長さ・重さ・傷の有無など28項目にわたる厳格な検査に合格した反物にのみ、証紙が貼られます。
すべての工程には職人の緻密な作業と経験が求められ、一本の反物を織り上げるまでに1週間以上の時間がかかります。
村山大島紬は、江戸の粋と庶民の暮らしに根ざした美意識が息づく伝統的工芸品です。精巧な絣柄と軽やかな着心地は、普段使いの着物としても格式を持つ場でも活躍します。