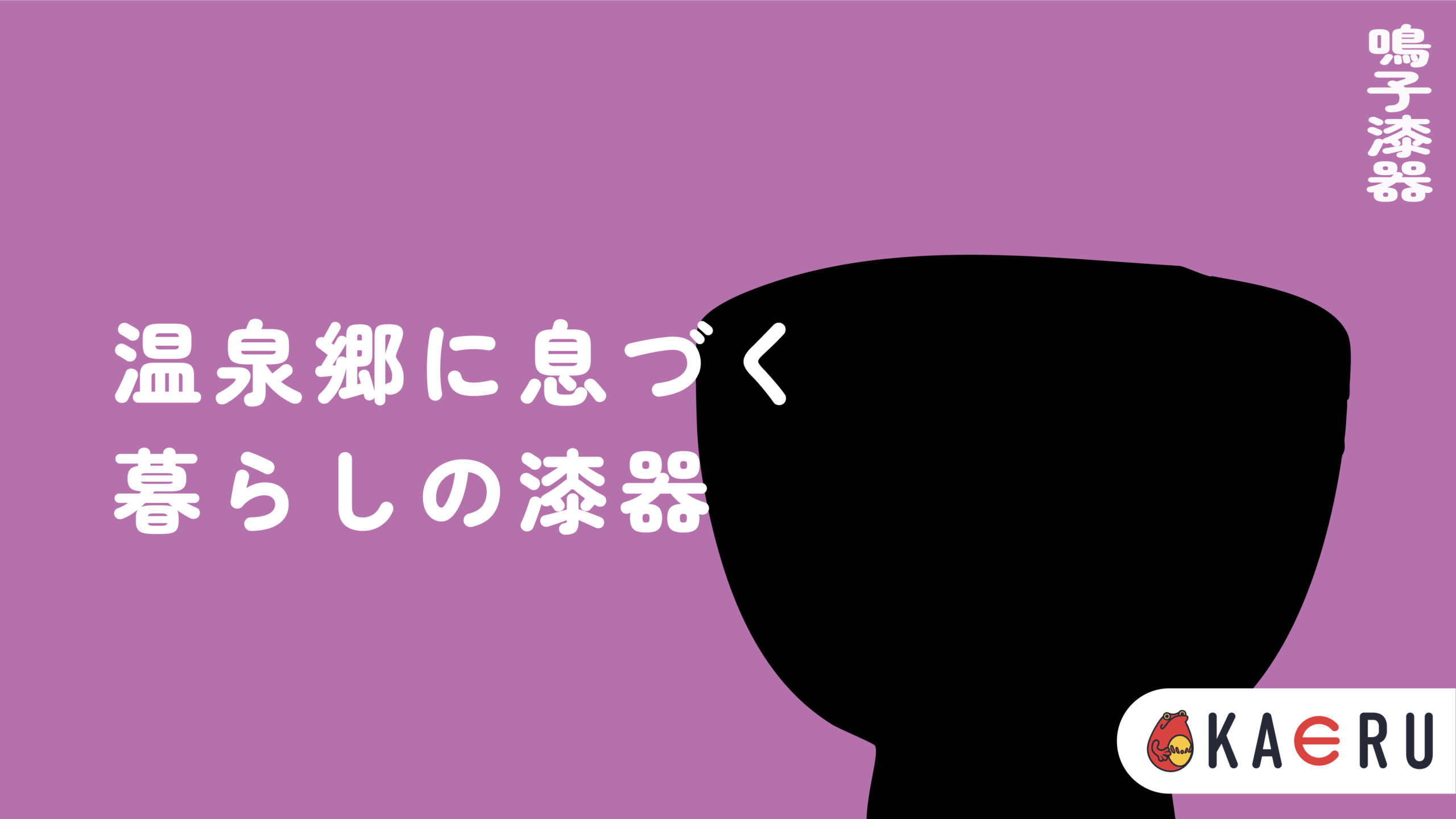鳴子漆器とは?

鳴子漆器(なるこしっき)は、宮城県大崎市の鳴子温泉郷で作られる伝統的な漆器です。江戸時代初期に伊達家がこの地を治めていた頃、足軽たちの手仕事として始まりました。温泉街とともに発展し、旅館での日用品や贈答品として多くの人々の暮らしに寄り添ってきた工芸です。
その大きな魅力は、透き通る漆を幾度も塗り重ねて木目を浮かび上がらせる「木地呂塗り」や、墨を流したような独特の模様が現れる「龍文塗」といった、鳴子ならではの仕上げ技法にあります。実用性と装飾性を兼ね備えたこの漆器は、今もなお地域の暮らしと美意識の象徴として息づいています。
| 品目名 | 鳴子漆器(なるこしっき) |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 分類 | 漆器 |
| 指定年月日 | 1991(平成3)年5月20日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 1(7)名 |
| その他の宮城県の伝統的工芸品 | 雄勝硯、仙台箪笥、宮城伝統こけし(全4品目) |

鳴子漆器の産地
山と湯が育んだ、木と漆の手仕事のまち

鳴子漆器の産地である宮城県大崎市鳴子温泉郷は、奥羽山脈の懐に抱かれた自然豊かな温泉地です。古くから湯治場として全国に名を馳せ、街道沿いには旅館や土産店、工芸の工房が軒を連ね、土地の文化と密接に結びついた暮らしが営まれてきました。
江戸時代初期に伊達家の岩出山藩が戦のなくなった足軽たちに屋敷を与え、この地に新たな産業として漆器作りを奨励したことが鳴子漆器の始まりとされます。温泉街の一角に残る「新屋敷」という地名は、まさにこの由来を今に伝えています。
また、湯治客をもてなす器や道具への美意識が根づき、旅館で使用される茶びつ・湯桶・飯びつなど、実用品としての漆器が発展しました。また、こけしや土産物文化との親和性も高く、実用性と芸術性を兼ね備えた民芸のまちとして知られています。
気候的にも、鳴子は漆器づくりに適した条件が揃っています。冷涼で湿度が安定した気候は、漆の乾燥を緩やかに進めるには理想的であり、季節ごとの気温・湿度を読みながら塗りや乾燥を調整する技術が長年の経験によって培われてきました。加えて、周辺山林から得られるケヤキやトチといった良質な広葉樹の供給も、漆器産業の土台を支えてきた要素です。
山の恵みと温泉文化、そして武家と町人が織りなす歴史が交差する鳴子という土地が、鳴子漆器という独自の工芸を育んできたのです。
鳴子漆器の歴史
湯治とともに歩んだ、400年の漆器史
鳴子漆器は、江戸初期に端を発する実用工芸のひとつです。その歩みは、土地の政治・文化・産業の変遷とともに歩んできました。
- 1608年(慶長13年):伊達政宗の転封により、岩出山藩がこの地域を治める。戦がなくなった足軽たちに屋敷を与え、漆器づくりを推奨。
- 1615年(元和元年)頃:「新屋敷」の地名が成立。漆器製作が本格化し、武士の内職から地域の産業へ。
- 1680〜1700年代:湯治文化の定着により、旅館需要が拡大。漆塗りの茶びつ・湯桶などの実用品が製造されるようになる。
- 1800年代前半:「木地呂塗り」「龍文塗」が誕生。木目を生かした意匠性の高い塗りが定着。
- 1877年(明治10年):鳴子駅が開業し、観光地としての発展が加速。土産物としての漆器需要も増加。
- 1920〜1930年代(昭和初期):漆器産業が最盛期を迎え、20軒以上の工房が存在。手仕事と分業による生産体制が確立。
- 1945年以降(戦後):戦中に一時停滞するも、戦後復興とともに再興。生活用品から贈答品・観光商品へと展開。
- 1991年(平成3年):鳴子漆器が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 2000年代以降:若手職人の活動や海外への発信が活発化。修理対応やカフェ・ホテル向け器など現代的用途も増加。
鳴子漆器の特徴
使うことで深まる美、木と漆の調和が織りなす表情
鳴子漆器の最大の魅力は、木材そのものの美しさを生かした塗りの表現にあります。なかでも「木地呂塗り」は、透明感のある漆を何層にもわたって塗り重ね、丹念に磨き上げることで木目を透かし出す技法。ケヤキの赤褐色の木肌やトチの白木の柔らかさが、光を受けて深く艶やかな表情を浮かべます。
もうひとつの特徴的な技法「龍文塗(りゅうもんぬり)」は、漆の表面に水墨画のような流れ模様が生まれる、全国でも鳴子にしかない独自技法です。墨を流したようなマーブル模様は、塗布直後の漆の動きによって生じるもので、狙って同じ模様を再現することは不可能とされます。その偶然性ゆえ、同じ器が二つと存在しないという個性が魅力です。
また、鳴子漆器は見た目の美しさに加え、驚くほど軽く、手に取ると木の温もりがしっとりと伝わるのも特徴。表面はしっとりとした艶を湛え、使い込むほどに光沢が増し、風合いが深まっていきます。まさに“育てる器”と言えるでしょう。
鳴子では古くから漆器を「塗物(ぬりもの)」と呼び、冠婚葬祭や節句の際にも重箱や屠蘇器が重宝されてきました。世代を超えて受け継がれる生活の道具として、実用性と美しさが一体となった工芸なのです。

鳴子漆器の材料と道具
木と漆、その素材に寄り添うための繊細な道具たち
鳴子漆器の製作には、木の目を読み、漆の性質を見極めながら仕上げる繊細な感覚が必要です。使用される素材と道具は、長年の経験と知恵によって受け継がれてきました。
鳴子漆器の主な材料類
- ケヤキ:硬く丈夫で、木目が美しい。木地呂塗りに最適。
- トチノキ:柔らかく加工しやすい。白っぽい木肌と緻密な木目が特徴。
- 漆(うるし):精製された生漆を用い、透漆や黒漆、朱漆などを使い分ける。
鳴子漆器の主な工具類
- 刷毛:漆を均一に塗布するための専用刷毛。
- 研磨道具(砥の粉・炭・木くず):塗膜を整えるための道具。
- 布・綿:拭き漆や磨きの際に用いる。
- 木地加工用刃物(小刀・彫刻刀など):木材の整形や加飾に使用。
漆と木、そして職人の手が一体となることで、鳴子漆器の奥深い表情が形作られていきます。
鳴子漆器の製作工程
手数を重ねて育てる、木と漆の語り合い
鳴子漆器は、木地と塗り、そして磨きの工程が繊細に積み重ねられ、一つの器として完成します。時間をかけて育てるように、職人は木と漆に向き合います。
- 木地加工
ケヤキやトチを十分に乾燥させ、用途に応じた形状に木地を削り出す。木目の出方もこの段階で決まる。 - 下地塗り
木地の凹凸を整えるために下地を塗布し、乾燥後に研磨。漆の乗りを安定させる役割。 - 中塗り・研磨
漆を塗り重ね、層を整えながら何度も磨き上げることで、深みのある表情を作る。 - 上塗り(木地呂塗り・龍文塗など)
最終仕上げとなる透明漆や模様漆を塗布。塗膜の均一性が美しさを左右する。 - 磨き・仕上げ
炭や木くずなどで塗面を磨き、光沢を引き出す。最後に器の縁や裏面なども整えて完成。
こうして完成した器は、温泉郷の暮らしとともに育まれた、使い手の日常に寄り添う“用の美”を体現します。
鳴子漆器は、奥羽の山あいで育まれた温泉文化と手仕事が融合した、実用と美の結晶です。木地呂塗りや龍文塗に象徴される意匠性の高さに加え、使い込むほどに魅力が深まるその漆器は、暮らしに静かな感動を与えてくれます。今もなお、地域とともに息づく工芸として、その価値を静かに広げ続けています。