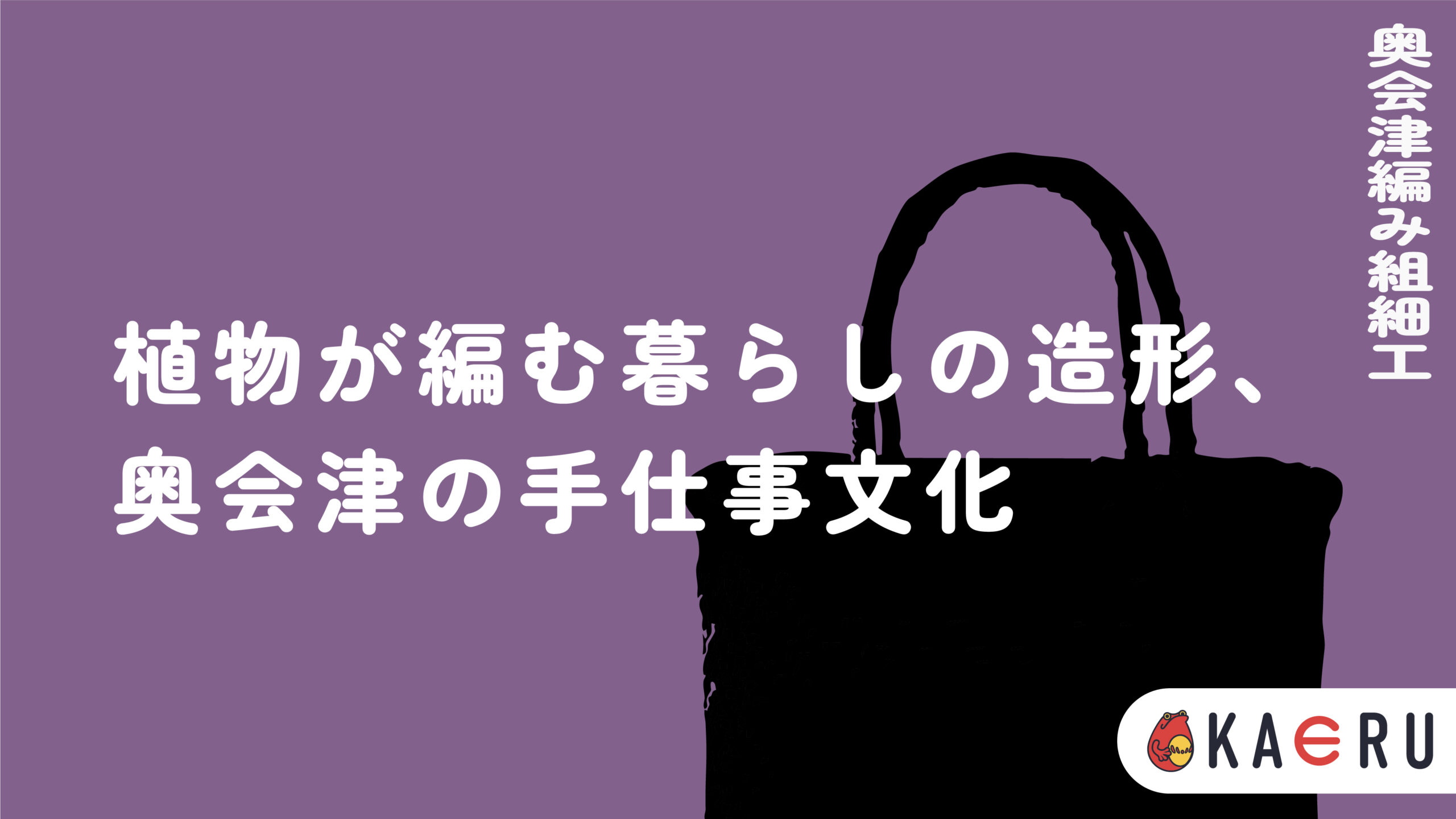奥会津編み組細工とは?
奥会津編み組細工(おくあいづあみくみざいく)は、福島県会津地方の山間部、三島町を中心につくられている伝統的な手工芸品です。ヒロロ(スゲの一種)や山ブドウの樹皮、マタタビのつるといった天然の植物素材を編み上げて、かごやざる、バッグなどの日用品を仕立てる技術が伝えられてきました。
厳しい冬のあいだ、雪に閉ざされる奥会津の暮らしのなかで、自然素材を使ったものづくりは生活の知恵でもあり、美意識の結晶でもありました。今では100人以上のつくり手が活動し、現代の暮らしに調和する民芸として、全国的にも注目を集めています。
| 品目名 | 奥会津編み組細工(おくあいづあみくみざいく) |
| 都道府県 | 福島県 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 2003(平成15)年9月10日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 7(12)名 |
| その他の福島県の伝統的工芸品 | 大堀相馬焼、会津塗、奥会津昭和からむし織、会津本郷焼(全5品目) |

奥会津編み組細工の産地
自然と共生する、山の手仕事文化の継承地

奥会津編み組細工の主な産地は、福島県西部の三島町。新潟県との県境に位置し、只見川と山々に囲まれたこの地は、まさに“日本の原風景”とも言える山村地域です。町の約85%を森林が占め、古くから林業とともに生きる暮らしが根付いてきました。こうした自然環境が、編み組細工の原材料となるヒロロやマタタビ、山ブドウといった植物の宝庫となっています。
三島町は縄文時代から人が住み、自然素材を用いた道具作りが営まれてきた地域です。町内の「荒屋敷遺跡」から出土した植物製のかごの一部は、2400年以上前のものであり、現代の編み組細工と技法的な共通点を持つ点でも注目されます。このことは、奥会津の人々が太古の昔から自然と共に手仕事を続けてきた証です。
気候的にも奥会津は年間を通して積雪が多く、寒冷な環境が人々を家の中での仕事へと導きました。冬の間に手を動かし、春には使える道具が生まれるというサイクルは、自然のリズムに寄り添った暮らしそのものです。また、雪解け水にさらして素材を乾燥させる「寒ざらし」といった独自の風土的手法も、この地域ならではの技です。
奥会津編み組細工の歴史
縄文の記憶から現代へ、暮らしとともに紡がれた伝統
奥会津編み組細工は、古代から現代へと受け継がれてきた貴重な手工芸です。
- 紀元前400年頃(縄文晩期): 三島町・荒屋敷遺跡にて、植物製のかごの破片が出土。現代の編み組細工と類似する編み方が確認される。
- 1600年代(江戸初期): 山村における農閑期の手仕事として、ヒロロ・マタタビ・山ブドウの素材を使ったざるやかごが一般家庭で普及。
- 1800年代中頃(江戸後期〜幕末): 林業の発展に伴い、山仕事と編み組細工の両立が一般化。商品として他村に持ち出されるようになる。
- 1890年代(明治30年代): 商業流通により、奥会津編み組細工が福島県内外の市場に出荷されるようになる。
- 1960〜1970年代(昭和40年代): 高齢化とプラスチック製品の普及により、担い手が急減。技術継承が危機に瀕する。
- 1970年代後半: 三島町が「生活工芸運動」を開始。地域住民への技術指導や研修会を開催し、編み組文化の復興を図る。
- 2003年(平成15年): 経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代: 若手作家や後継者の活動が活発化。都市部との交流、体験イベントも盛んに。
こうして、奥会津編み組細工は生活工芸としての実用性と、芸術性を併せ持つ伝統文化として、再評価と発展を遂げています。
奥会津編み組細工の特徴
素材と向き合い、手で編むからこそ宿る“暮らしの美”
奥会津編み組細工の大きな魅力は、素材の個性に寄り添いながら、用と美を両立させてきた点にあります。一つとして同じかたちがなく、同じ表情もない。それは素材が天然の植物であり、すべてが人の手で仕立てられるからです。
ヒロロ細工は、細い繊維を何本も束ねて編むことで、美しい光沢と軽やかな風合いが生まれます。触れると驚くほどなめらかで、和装小物や手提げかごなどに愛用されています。その見た目の繊細さとは裏腹に、丈夫で長持ちする点も特筆されます。
山ブドウ細工は、樹皮の厚み・色合い・年輪模様を活かした編みで、使用するほどに飴色へと変化し、艶が深まります。愛用者の間では「10年育てるかご」とも呼ばれ、持ち主の暮らしとともに味わいを増していくのです。
マタタビ細工は、水気に強く、濡れると柔らかくなり乾くと固まるという性質を持つため、ざるや盛りかご、米とぎざるなど、日用品として重宝されてきました。「水切れの良さはマタタビに限る」と言われるほど、生活の中に根付いた素材です。
また、編み方も多彩で、「矢羽編み」「二本飛び網代編み」「四つ目編み」など、目的や素材によって編み方を変えています。図案があるわけではなく、手の感覚と経験により美しい模様が生まれる点は、まさに職人技と言えるでしょう。

奥会津編み組細工の材料と道具
山が育む素材と、手が編む伝統の技
奥会津編み組細工は、自然から採取した植物素材と、それを生かす道具・技術によって生まれます。
奥会津編み組細工の主な材料類
- ヒロロ(スゲの一種): 細くてしなやか。レース編みのような細工に最適。
- 山ブドウの皮: 堅牢で光沢がある。梅雨時の採取が最良。
- マタタビのつる: 吸水性と復元力が高く、水回り製品に適す。
奥会津編み組細工の主な工具類
- ナイフ・小刀類: 皮はぎや芯取り、幅の調整などに使用。
- 計量具・定規: 幅や長さを揃えるための基本道具。
- 木枠・押さえ具: 編みの張力を一定に保つ補助道具。
素材を無駄にせず、自然に感謝しながら編む、こうした精神が、奥会津の工芸には息づいています。
奥会津編み組細工の製作工程
自然と調和する、丁寧なものづくり
ここでは代表的なマタタビ細工のざる製作工程を紹介します。
- 採取(11〜12月)
雪が降る前に山に入り、マタタビのつるを採る。同じ場所から翌年も採れるように節度を守って採取。 - 皮はぎ・さき割り
つるの表皮をはぎ、縦に4〜5本に割く。まっすぐに割ることで、編みやすく整った材料になる。 - 芯とり
小刀で芯の硬い部分を取り除き、柔らかな皮だけを残す。手指の感覚が求められる工程。 - 底編み
一定の幅に整えた皮を放射状に並べ、中央から編み上げて底面を成形。 - 横編み
底面から立ち上がるように側面を編んでいく。編み模様は用途によって異なる。 - ふちどめ・補強
ふちに堅牢なつるを巻いて固定し、変形を防ぐ。技術の差が仕上がりに現れる。 - 乾燥(寒ざらし)
軒下などで風と雪の反射光に当てて自然乾燥させる。素材の色合いが白く冴え、強度も増す。
これらの工程には、自然素材を見極める目と、手の感覚が何より重要です。無理に整えず、素材の特性に寄り添うことが美しい仕上がりにつながります。
奥会津編み組細工は、福島・三島町を中心に自然素材と人の手が織りなす、暮らしに寄り添う伝統工芸です。縄文時代からの編み技術を受け継ぎ、ヒロロ・山ブドウ・マタタビといった地域資源を生かして、かごやざるが丁寧に編み上げられます。自然と共生する精神と、美と実用を兼ね備えた工芸の魅力は、今なお新たな世代に受け継がれています。