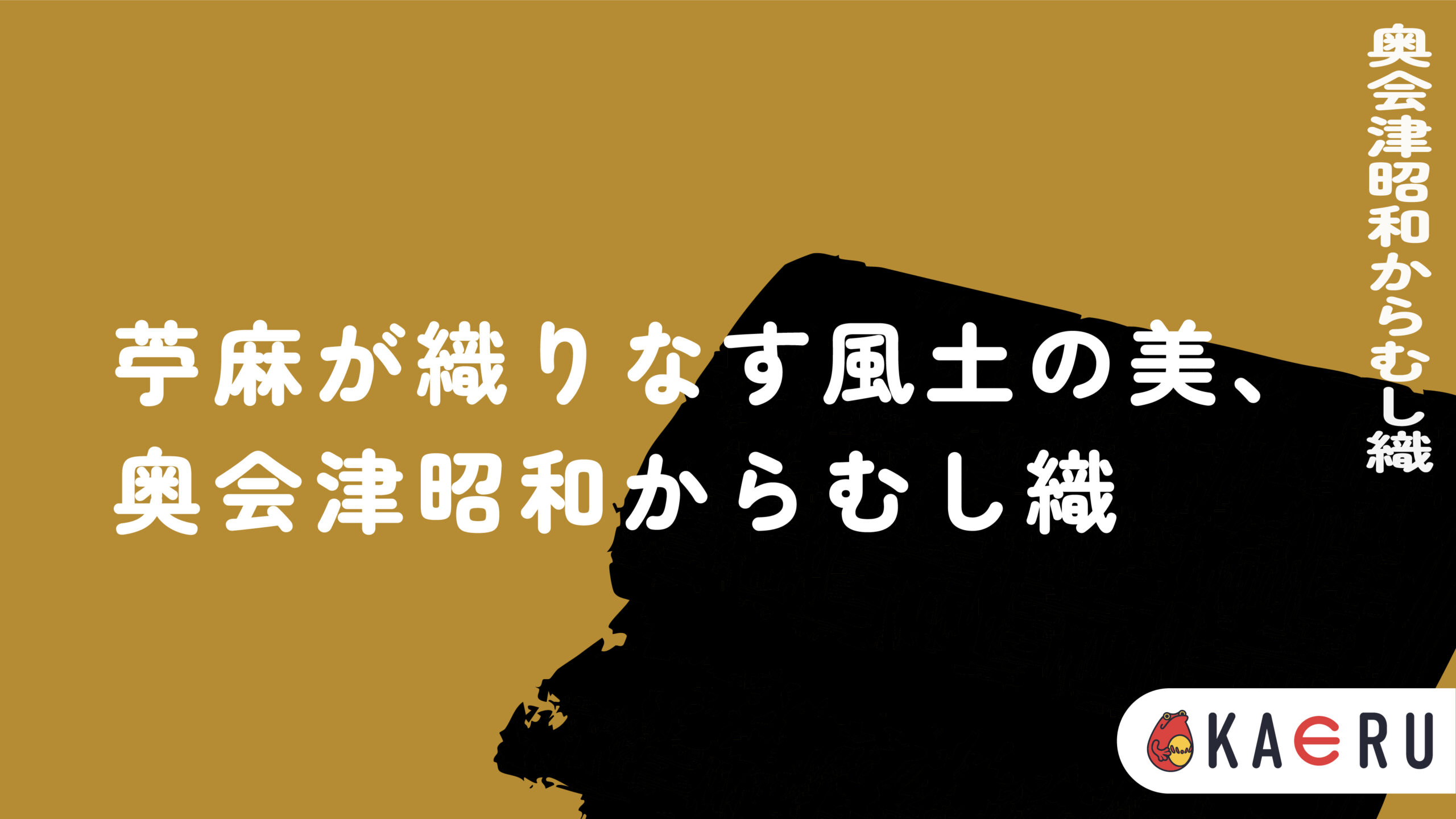奥会津昭和からむし織とは?
奥会津昭和からむし織(おくあいづしょうわからむしおり)は、福島県大沼郡昭和村で織られる苧麻(からむし)の織物です。からむしはイラクサ科の多年草で、古代から日本の衣料文化を支えてきた植物繊維。その繊維を糸に績(う)み、地機(じばた)で織り上げた布は、軽くて強く、さらりとした風合いを持つ夏用の高級織物として知られています。
特筆すべきは、栽培・収穫・繊維の加工・糸づくり・織りのすべてを地域住民の手仕事で行う点にあります。これは全国的にも極めて稀な伝統継承のかたちであり、「山の暮らし」と「工芸」の境界が曖昧な、昭和村独自の文化です。苧麻の生命力、山里の風土、そして人の営みが織りなす、静かで力強い布。それが奥会津昭和からむし織の真髄です。
| 品目名 | 奥会津昭和からむし織(おくあいづしょうわからむしおり |
| 都道府県 | 福島県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 2017(平成29)年11月30日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |
| その他の福島県の伝統的工芸品 | 大堀相馬焼、会津塗、会津本郷焼、奥会津編み組細工(全5品目) |

奥会津昭和からむし織の産地
苧麻に生かされる山里、昭和村という風土

奥会津昭和からむし織の産地・福島県昭和村は、標高500〜700メートルの山間地に位置し、村の9割以上を森林が占める自然豊かな土地です。会津盆地の南西に接し、冬には2メートルを超える積雪があり、夏は湿度が高く、日照時間にも恵まれています。こうした厳しくも豊かな自然環境は、苧麻の育成に最適な条件を備えています。
江戸時代から続く農村部の女性たちによる「家仕事」として、からむしの栽培・糸績み・機織りが代々受け継がれてきました。地域全体が一つの生産共同体となり、農業と工芸が切り離せない形で融合しているのが昭和村の大きな特徴です。
地理的には、古くから会津若松と越後(新潟)を結ぶ交易路の中継地に位置しており、織物や麻製品が近隣に流通しやすい立地にありました。また、山から湧き出る豊富な水源や冷涼な気候は、苧麻繊維の洗浄や製糸作業に適しており、品質の高い織物が生まれる条件が自然と揃っていたのです。
奥会津昭和からむし織の歴史
千年を超えて受け継がれる、苧麻織りの系譜
奥会津昭和からむし織の歴史は、単なる織物の歴史ではなく、日本の繊維文化そのものと深く重なります。
- 701年(大宝元年):『大宝律令』に「苧(からむし)」が記載され、租税の対象として栽培が奨励される。
- 927年(延長5年):『延喜式』に「布」としての苧麻が登場し、宮廷への貢納品として記録される。
- 1488年(長享2年):会津地方でからむし織が盛んだったことを示す古文書が残る(『会津旧事雑考』)。
- 1643年(寛永20年):会津藩、村々にからむし栽培を奨励し、女性の内職として普及。
- 1710年代(正徳年間):会津本郷や只見地方でも生産が確認され、商品流通が活発化。
- 1830年頃(天保元年頃):昭和村周辺で“自家用のからむし織”が一般化。祝い事の着物にも使われる。
- 1972年(昭和47年):地元住民と研究者により「からむし織復興会」が発足。
- 1984年(昭和59年):「昭和村からむし織技術保存協会」設立。
- 1991年(平成3年):昭和村の「からむし(苧麻)生産・苧引き」が国の選定保存技術に指定。
- 2017年(平成19年):奥会津昭和からむし織が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:和装以外にバッグやインテリア用途でも注目され、現代生活への応用が進む。
奥会津昭和からむし織の特徴
苧麻がもたらす、軽さ・強さ・涼やかさの三重奏
奥会津昭和からむし織の最大の魅力は、自然素材である苧麻が生み出す独特の風合いにあります。とりわけ夏向けの織物として、着る者に“涼”を届けるその肌離れの良さは、他の素材では得難いものです。繊維が短く、裂けやすい苧麻を丁寧に績み上げることで生まれる糸には、自然な節やムラがあり、そこに光が当たると独特の柔らかな反射を生み出します。
さらに、苧麻は綿や絹と比べても強度が高く、繰り返しの洗濯にも耐えうる耐久性を持っています。そのため、昭和村では嫁入り道具のひとつとして、からむし織の反物を持たせる風習もありました。
からむし織には“織り手の体の癖”が出るといわれています。地機で織る際、腰の高さ・糸の張り具合・足の力加減がそれぞれに異なるため、同じ意匠でも仕上がりが微妙に変わるのです。これは“機械では決して再現できない味わい”として、近年再評価されています。

奥会津昭和からむし織の材料と道具
苧麻を糸へ、糸を布へ。手の技が紡ぐ生命線
奥会津昭和からむし織は、苧麻の栽培から製品化まで、すべての工程に職人の手技と道具が欠かせません。
奥会津昭和からむし織の主な材料類
- 苧麻(からむし):昭和村で自家栽培される繊維植物。強くしなやかな繊維が特徴。
奥会津昭和からむし織の主な工具類
- 苧引き板:苧麻の表皮から繊維を剥ぐための木製道具。
- 糸績み台:繊維をより合わせて糸にするための道具。
- 地機(じばた):足踏み式の織機。体全体で布を織る。
- 櫛(くし)・筬(おさ):糸を整え、打ち込むための道具。
苧麻を育てる手間、繊維を取り出す技術、そして織りの感覚。それぞれが連関してはじめて、からむし織は布として成立します。
奥会津昭和からむし織の製作工程
苧麻に寄り添う、季節と人の織りなす仕事
奥会津昭和からむし織の制作は、自然のリズムに合わせて1年がかりで行われます。ひと織りの布に込められた手間と時間は、他に類を見ません。
- 苧麻の栽培(5〜8月)
春に苗を植え、夏に背丈ほどに伸びた苧麻を手作業で刈り取る。 - 苧引き(7〜9月)
皮を剥いで繊維を取り出す「苧引き板」の作業。繊維の質を左右する重要工程。 - 糸績み(通年)
乾燥させた繊維を水で柔らかくし、指先で撚りながら1本の糸にする。 - 整経・巻き取り(通年)
経糸を揃え、織機に張る準備をする。緻密な本数計算が必要。 - 織り(通年)
地機に座り、緯糸を通しながら布にしていく。力加減とリズムが命。 - 仕上げ(通年)
布を洗って柔らかくし、日陰干しして風合いを整える。
奥会津昭和からむし織は、自然の中で苧麻を育て、糸を績み、布を織るという手仕事の積み重ねによって生まれる織物です。暮らしとともに受け継がれたその技術と感性は、まさに日本の原風景ともいえる存在。風土に根ざしたこの布は、今も静かに、けれど力強く現代へ語りかけています。