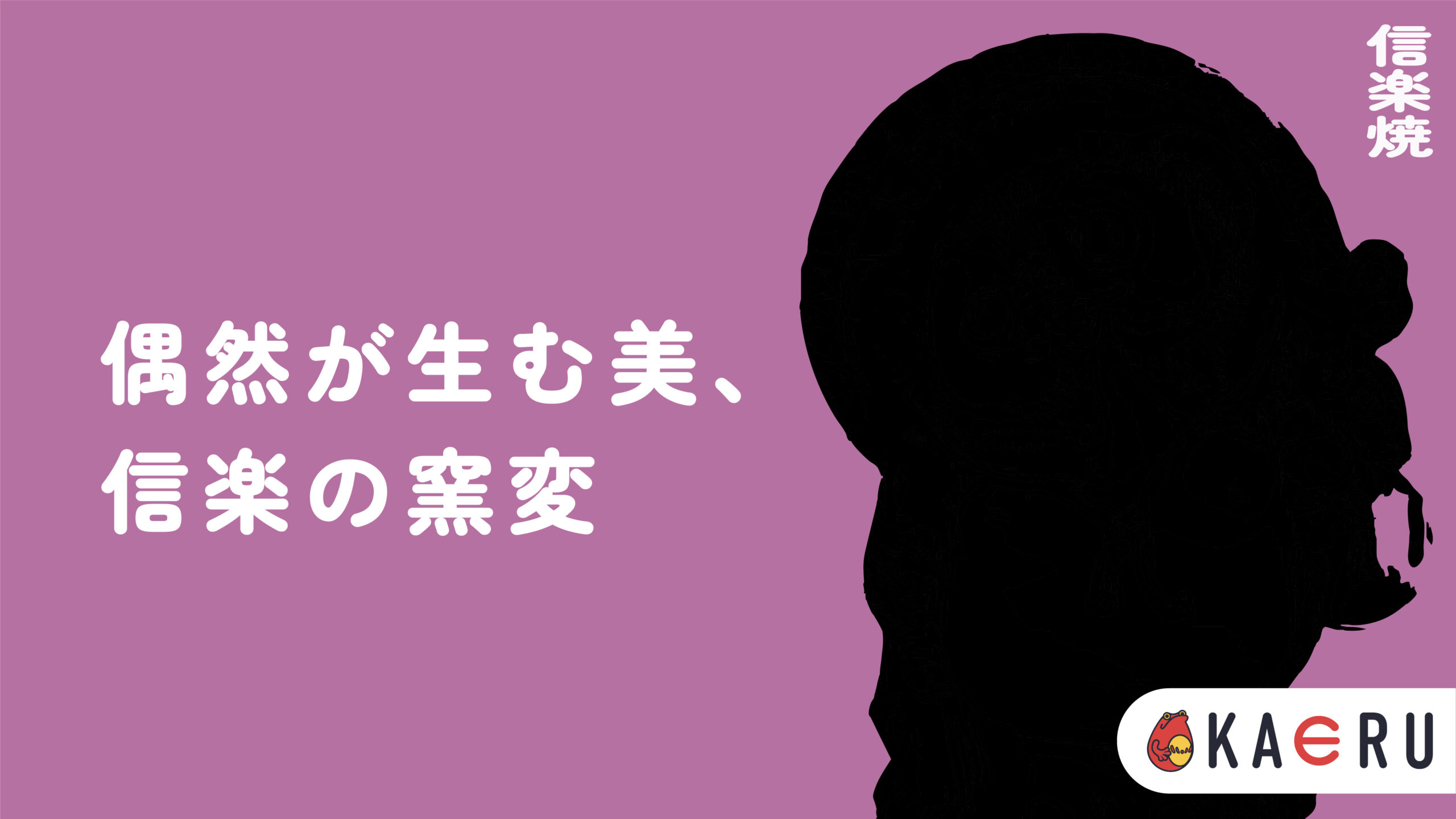信楽焼とは?
信楽焼(しがらきやき)は、滋賀県甲賀市信楽町を中心に作られている陶器で、日本六古窯の一つに数えられる由緒あるやきものです。釉薬を使わず、登り窯や穴窯で高温焼成することで、土と火と灰が偶然に描き出す「窯変(ようへん)」の美しさが生まれます。
赤みを帯びた「火色(ひいろ)」、ガラス質の「ビードロ釉」、黒く焼けた「こげ」、白い粒が浮かぶ「霰(あられ)」など、その表情は一点として同じものがありません。
素朴で温かみのある風合いは、時代を超えて多くの人々の暮らしに寄り添ってきました。
| 品目名 | 信楽焼(しがらきやき) |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 分類 | 陶磁器 |
| 指定年月日 | 1975(昭和50)年9月4日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 35(70)名 |
| その他の滋賀県の伝統的工芸品 | 彦根仏壇、近江上布(全3品目) |
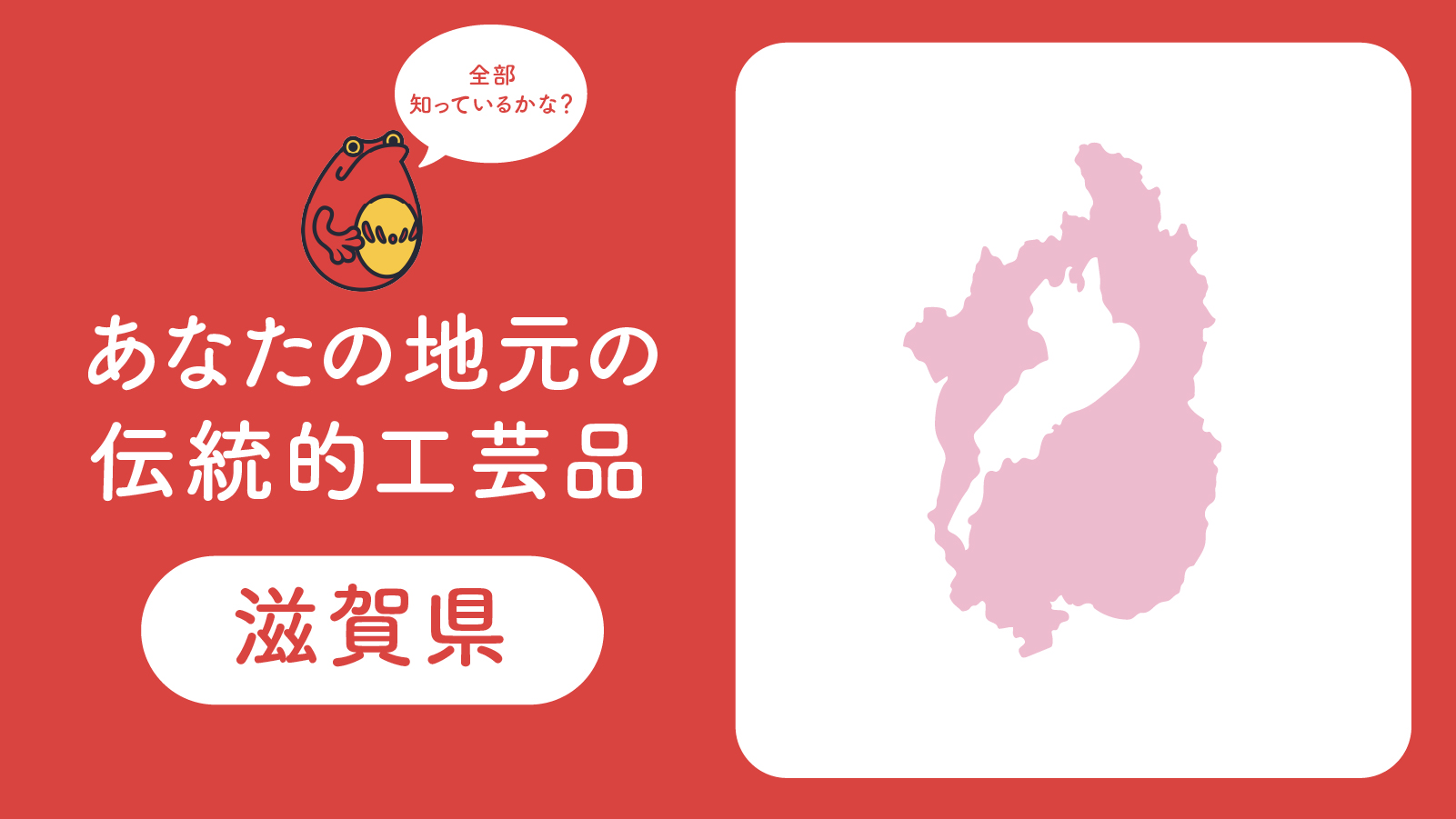
信楽焼の産地
古琵琶湖の地層に息づく、やきもの文化の原郷

主要製造地域
信楽焼の産地は、滋賀県南部の甲賀市信楽町。京都・奈良・三重に近接する山あいの地域で、古くから陶業が息づいてきました。この地がやきもの産地として発展した背景には、歴史的・地理的・文化的・気候的条件が絶妙に重なり合っていたことが挙げられます。
まず注目すべきは、約400万年前の「古琵琶湖層」と呼ばれる地層です。ここはかつて巨大な湖の底であり、長い年月の中で土砂や動植物の遺骸が堆積し、やきものに適した粘土層が形成されました。この粘土は粒子が粗くて粘りがあり、大型陶器の成形に向いており、信楽焼の素朴で力強い風合いを支えています。
信楽は奈良や京都に近く、宮廷文化や茶道文化の影響を受けやすい位置にありました。中世から近世にかけては茶陶としての需要が高まり、室町・桃山期には多くの名品が生まれました。また、江戸時代以降は大阪の都市文化圏にも近く、日用雑器や火鉢など大量生産品の供給地として機能しました。
さらに気候的側面では、周囲の山々に薪資源となるアカマツが豊富に自生していたことが、登り窯や穴窯による焼成技術を支えました。信楽の陶工たちは、炎と灰の動きを読み、自然の力を味方にする焼成技術を磨いていきました。窯の立地に適した地形や気象条件も、良質なやきもの作りには欠かせない要素でした。
こうした地質・文化・気候・流通の条件が整った土地の恵みと人の手が織りなす信楽焼は、まさに「風土が生んだ芸術」といえるでしょう。
信楽焼の歴史
千年を超えて受け継がれる、やきものの変遷
信楽焼は、日本列島の歴史と共に歩んできた陶器文化の系譜に連なります。
- 742年頃(奈良時代):聖武天皇が紫香楽宮(しがらきのみや)を造営。屋根瓦の製作に信楽の窯が使われた記録があり、これが信楽焼の起源とされることもある。
- 13世紀半ば(鎌倉時代中期):水がめや種壺など、生活に密着した日用陶器の焼成が始まる。釉薬を施さない素朴な焼き物が主流。
- 15世紀(室町時代):茶の湯の流行により、侘びの美を体現する茶陶として評価される。特に「信楽水指」などが茶人に珍重される。
- 1570年代〜(安土桃山時代):千利休らによる茶道の隆盛により、意図的に自然な窯変を引き出す技法が磨かれる。
- 17世紀(江戸前期):茶壺や徳利、皿などの食器類が量産されるようになり、京都・大阪の都市部へ広く出荷される。
- 18〜19世紀(江戸後期):梅壺、火鉢、土鍋などの大型日用品も多く製作され、庶民の暮らしに深く根付く。
- 1890年代(明治中期):火鉢の需要が急増。特に「信楽火鉢」は耐久性と保温性に優れ、全国的に人気を博す。
- 1930年代(昭和初期):信楽焼の産業化が進み、量産体制が確立。置物や傘立てなど、装飾品の需要も高まる。
- 1951年:昭和天皇が信楽を行幸。沿道に並んだたぬきの焼き物が話題となり、全国的に「信楽たぬき」が知られるきっかけに。
- 1975年(昭和50年):信楽焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:日常食器・インテリア・浴槽などに用途が多様化。現代作家とのコラボレーションやデジタル技術導入も進む。
信楽焼の特徴
炎が描く絵画、信楽焼という自然のキャンバス
信楽焼の特徴は、なんといっても“自然の力”がそのまま作品に表れる点にあります。人工的な装飾を控え、炎・灰・土の作用で偶然生まれる表情を大切にするのが信楽焼の美意識です。焼成中に作品表面が赤く変化する「火色(ひいろ)」は、薪窯で焼いた際に起きる酸化反応によるもの。これにより、どこかあたたかみのある赤みが器全体を包み込みます。
さらに、薪の灰が自然に作品に降り積もり、それが溶けて生まれるガラス質の「ビードロ釉」は、青緑色の透明感ある光沢となって作品に現れます。これは偶然の賜物であり、まさに“窯が描いた絵”と言える現象です。
また、焼成時に灰に埋もれた部分が黒っぽくなる「こげ」、長石の粒が白く浮かび上がる「霰(あられ)」なども、自然と炎のコラボレーションによる独自の模様。特に信楽焼は「どこに置いて焼かれたか」で色や質感が異なるため、同じ窯で焼いたものでも一つとして同じ表情の作品は存在しません。
加えて、「たぬきの置物」が有名なことも信楽焼の象徴です。これは昭和天皇の行幸をきっかけに広まったもので、商売繁盛や福を呼ぶ縁起物として日本各地に親しまれています。近年では、たぬきの姿も進化し、ピースサインをしたものやスマートフォンを持つ姿など、ユーモアあふれる現代的デザインも登場しています。

信楽焼の材料と道具
土と炎の声を聴く、感性と経験の技
信楽焼の製作は、地層が育んだ良質な陶土と、それを活かすための手道具に支えられています。
信楽焼の主な材料類
- 古琵琶湖層の粘土:粘りとコシがあり、成形性に優れる。
- 長石:自然釉や霰模様の要素となる鉱物。
- アカマツの薪:登り窯用の燃料。灰による窯変を生む。
信楽焼の主な道具類
- ろくろ:手回し・電動。成形の基本工具。
- 成形ヘラ・カンナ:形を整えるための手道具。
- 筆・ひしゃく:釉薬をかける道具。
- 温度計・窯道具:焼成を管理する装置類。
自然の力を借りながら、人の感性と経験でコントロールするのが信楽焼の魅力です。
信楽焼の製作工程
土と火が生む、やきものの生命
信楽焼は、一つひとつの工程に時間と手間をかけることで、その独特の美しさが生まれます。
- 成形
粘土を練り、ろくろや手びねりで形を整える。大型の壺や傘立てなども多く作られる。 - 乾燥
天日や室内で数日かけてゆっくりと乾かし、ひび割れを防ぐ。 - 素焼き
700〜800℃の温度で1日ほどかけて焼く。素地を安定させる工程。 - 釉薬かけ
自然釉や表現に応じて、筆やエアガンで釉薬をかける。無釉の場合も多い。 - 本焼き(焼成)
登り窯や穴窯、または現代の電気窯で、1200℃以上の高温で2〜3日かけて焼成。窯の位置や灰のかかり具合で表情が変化。
こうして完成した信楽焼は、同じ土と技法で作っても、すべて異なる風合いを持ちます。まさに“窯が描く芸術”ともいえる存在です。
信楽焼は、自然と共に生きる焼き物文化の結晶です。400万年前の地層から生まれた粘土と、炎が描く模様、職人の手わざが織りなす唯一無二の器たち。伝統を守りながらも、現代の暮らしに溶け込むかたちで進化を続けています。たぬきの置物からインテリアアートまで。信楽焼は、土の声を未来へと伝えるやきものです。