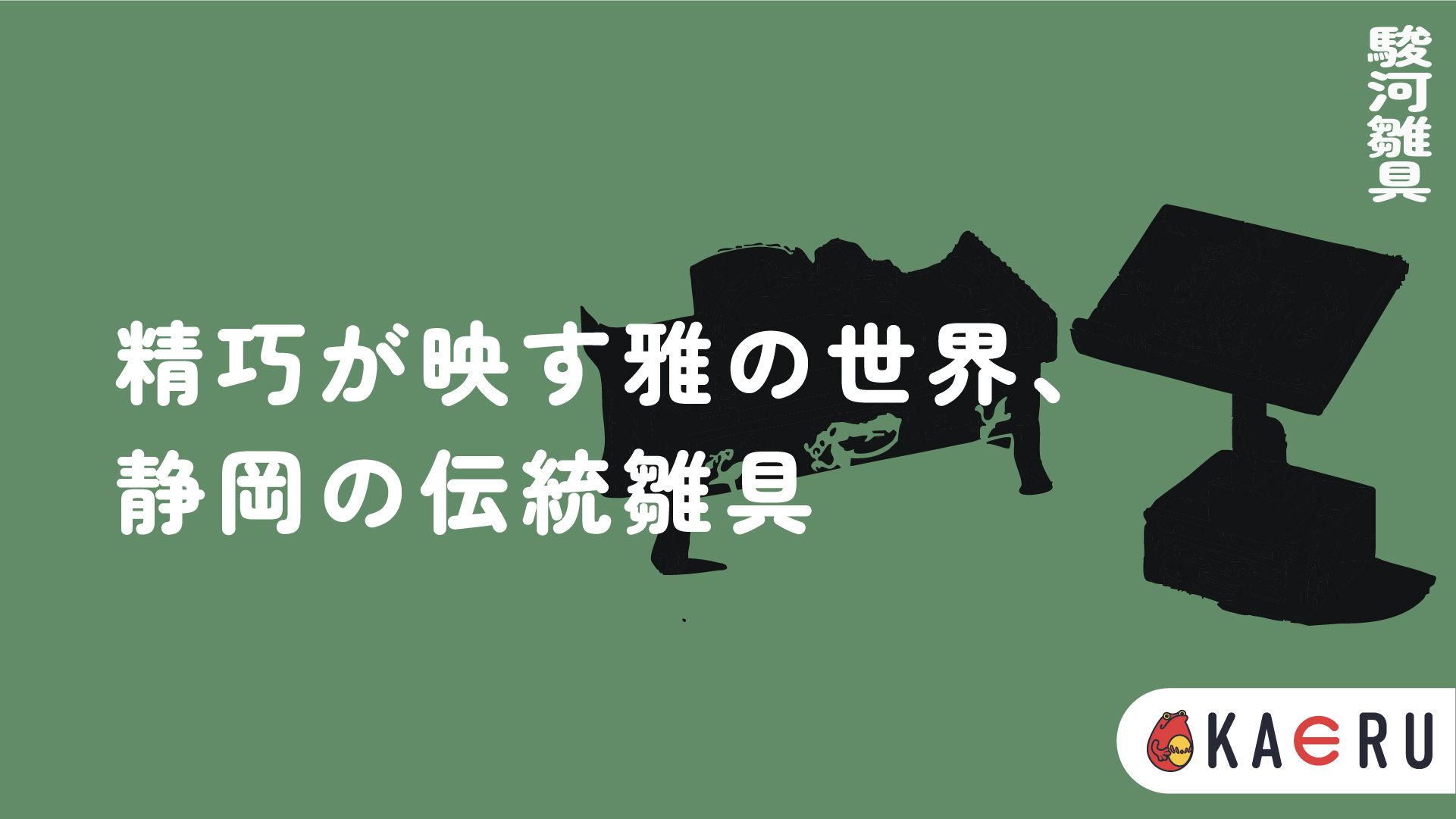駿河雛具とは?
駿河雛具(するがひなぐ)は、静岡県静岡市を中心に製作されている精密な雛道具の伝統工芸品です。雛人形の世界を彩る「箪笥」「長持」「鏡台」「蒔絵棚」などの小道具を、実物と同じ素材・技法で再現した精巧な工芸であり、その起源は16世紀まで遡ります。
特徴的なのは、木地から塗装、蒔絵、金具に至るまで、実際の家具や道具と同様の工程を経て製作されている点です。単なる装飾品ではなく、本物の技術が凝縮された“極小の工芸”とも言える存在で、静岡の工芸文化を象徴する逸品として知られています。
| 品目名 | 駿河雛具(するがひなぐ) |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 分類 | 人形・こけし |
| 指定年月日 | 1994(平成6)年4月4日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(26)名 |
| その他の静岡県の伝統的工芸品 | 駿河竹千筋細工、駿河雛人形(全3品目) |

駿河雛具の産地
全国屈指の職人文化が育んだ、雛道具づくりの聖地
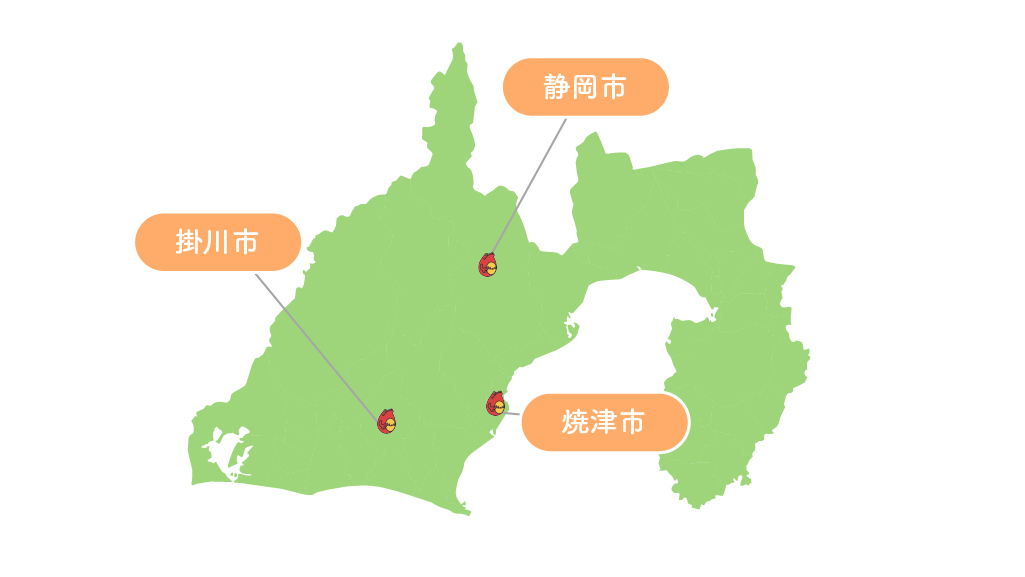
主要製造地域
駿河雛具の主な産地は、静岡市を中心とする駿河地方です。中でも、旧駿府城下町である静岡市葵区・駿河区は、古くから指物・蒔絵・漆工・金具製作の職人が集中する工芸の集積地として知られています。
1600年代初頭、徳川家康が駿府に隠居したことを契機に、全国から優れた職人たちが集められ、東照宮や浅間神社の造営に携わりました。これにより、江戸幕府の庇護のもとで高度な木工・漆芸・金工技術がこの地に根づきました。彼らの技術はやがて仏具や漆器、指物などの工芸品製作へと転用され、雛具製作の下地となっていきます。
また、静岡は江戸時代から交通の要衝であった東海道に面し、商人や武士階級の往来が盛んでした。これにより、武家の婚礼文化や節句文化が庶民にまで広がり、ひなまつり文化も根づいていきました。雛具は単なる子どもの飾りではなく、嫁入り道具の象徴や家庭の繁栄を願う品として、地域の暮らしに深く浸透しました。
駿河雛具の歴史
武家文化と職人技が融合した、五百年の精巧工芸史
駿河雛具の歴史は、16世紀に遡ります。
- 16世紀後半(安土桃山時代): 駿河地方で木工細工が盛んになり、嫁入り道具の一部として小型家具が作られ始める。
- 1607年(慶長12年): 徳川家康、駿府に隠居。東照宮や浅間神社の建立に全国から職人が集結。
- 1610年代: 城下町として発展した静岡で、蒔絵・金具・指物技術が定着。のちの雛具製作の技術的土台となる。
- 1750年代(江戸中期): 節句行事が庶民にも普及し、雛人形と共に雛具の需要が拡大。
- 1800年代初頭: 駿河人形(衣装着天神)と並行して、精巧な雛具の製作が始まる。
- 1870年代(明治初期): 分業体制が確立。漆塗りや金具などの専門職人による本格的な製作が定着。
- 1910〜20年代(大正期): 女児の誕生祝いとしての雛祭り文化が全国的に広まり、生産数が急増。
- 1950年代(戦後復興期): 手仕事による伝統技術が再評価され、全国の百貨店で駿河雛具が取り扱われるように。
- 1994年(平成6年): 駿河雛具が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代: ミニチュア工芸や和のインテリアとしての新たな需要が生まれ、海外のコレクターからも注目を集める。
駿河雛具の特徴
手のひらに宿る、“本物”の意匠と技術
駿河雛具の最大の特徴は、驚くほど小さなサイズでありながら、実物とまったく同じ工程で作られていることにあります。たとえば、3cmほどの箪笥の引き出しが実際に開閉できるのはもちろん、内部には木目や滑りの良さまで計算された細工が施されています。
使用される漆は天然の本漆であり、何度も塗り重ねて艶やかに仕上げられます。加飾には蒔絵が施され、金粉や銀粉を用いて桜や菊、鳳凰などの優雅な意匠が表現されます。金具もまた本物の金属素材から手作業で作られ、蝶番や取手、鍵受けまで緻密に再現されています。
こうした高度な完成度は、木地師・塗師・蒔絵師・金具師といった職人たちの分業によって支えられており、それぞれが専門技術を惜しみなく注ぎ込むことで、「手のひらの工芸美」が完成します。
駿河雛具の材料と道具
本物志向を支える、厳選された素材と専門道具
駿河雛具の製作では、実物の家具や漆器と同様の材料・道具が用いられ、精密さと芸術性を支える礎となっています。
駿河雛具の主な材料類
- キリ: 木肌が滑らかで軽く、精密な指物加工に適する。
- 漆: 天然漆を用いた本格的な塗装に使用。
- 金粉・銀粉: 蒔絵装飾に使われる。
- 金属素材(真鍮・銅など): 金具や蝶番の製作に使用。
- 和紙・絹: 一部の装飾や人形付属品にも利用。
駿河雛具の主な道具類
- 小型彫刻刀・ノミ: 繊細な木地加工に使用。
- 蒔絵筆: 細かな漆装飾を施すための極細筆。
- 金具製作用ヤットコ・鉄槌: 小型の金属部品の加工に使用。
- 朱漆・黒漆用刷毛: 漆塗り専用の細筆。
こうした本物の素材と道具により、雛具は“工芸のミニチュア”としての品格と完成度を誇ります。
駿河雛具の製作工程
分業の技と心が紡ぐ、縮小版・本格工芸の製作工程
駿河雛具は、小さいながらもすべての工程に専門的な技術が凝縮されています。
- 木取り・木地製作
キリ材などを用い、ミリ単位で木地を成形。引き出しや扉も実際に可動できるように調整。 - 下地塗り・本漆塗装
朱漆や黒漆を重ねて艶やかに仕上げる。工程は実物家具と同様に数回にわたる。 - 蒔絵装飾
金粉や銀粉を使い、桜や菊などの意匠を加飾。 - 金具製作・取付
小型の蝶番や取っ手を金属で製作し、手作業で丁寧に取り付ける。 - 最終検品・組み立て
可動部の確認や全体の仕上がりを最終確認し、完成。
この一連の工程を、専門職人たちが分業で行うことにより、高品質な製品を安定して生み出す体制が維持されているのです。
駿河雛具は、縮小された道具の中に本物の工芸技術を凝縮した静岡の誇る伝統工芸品です。指物・漆芸・蒔絵・金具といった多彩な職人技が分業で支え合い、まるで宝物のような逸品が生まれます。子どもの成長を願う文化の象徴であると同時に、現代に息づく「用の美」を映す芸術品でもあります。