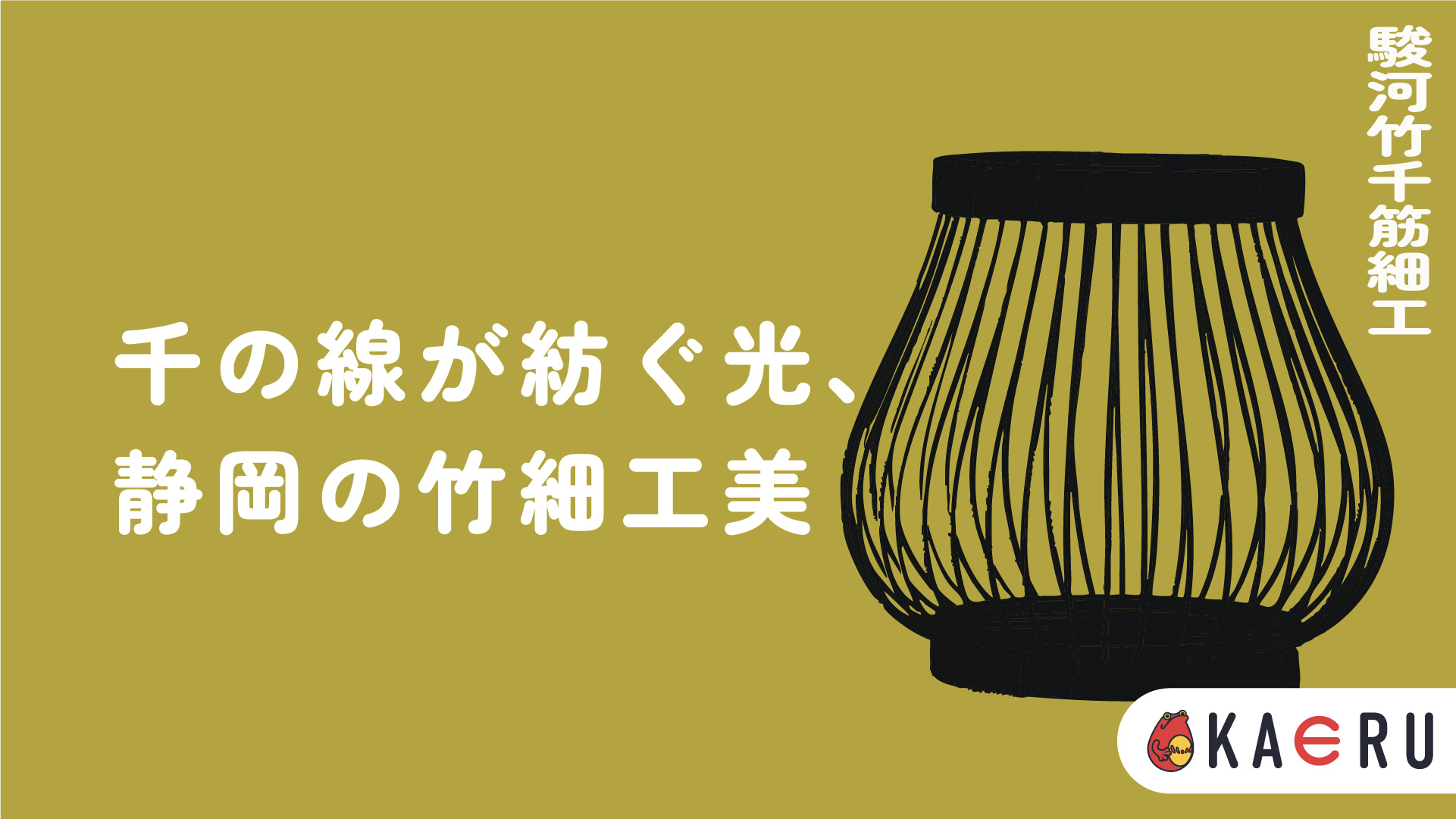駿河竹千筋細工とは?
駿河竹千筋細工(するがたけせんすじざいく)は、静岡県静岡市を中心に製作されている伝統的な竹工芸です。細く丸く削った竹ひごを千本近く使って組み上げる精緻な技法が特徴で、風鈴や花器、虫籠など、日本の暮らしに寄り添う優美な作品を生み出してきました。
この「千筋(せんすじ)」という名は、畳一枚分の幅(約90cm)に千本の竹ひごが並ぶほどの繊細さを誇ることに由来します。平ひごを使う他産地とは異なり、丸ひごを用いた細工は全国でも駿河独自の技とされ、静岡の竹文化を象徴する工芸品として発展してきました。
| 品目名 | 駿河竹千筋細工(するがたけせんすじざいく) |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 分類 | 木工品・竹工品 |
| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(13)名 |
| その他の静岡県の伝統的工芸品 | 駿河雛具、駿河雛人形(全3品目) |

駿河竹千筋細工の産地
東海道の宿場文化と竹林が育んだ精緻な技
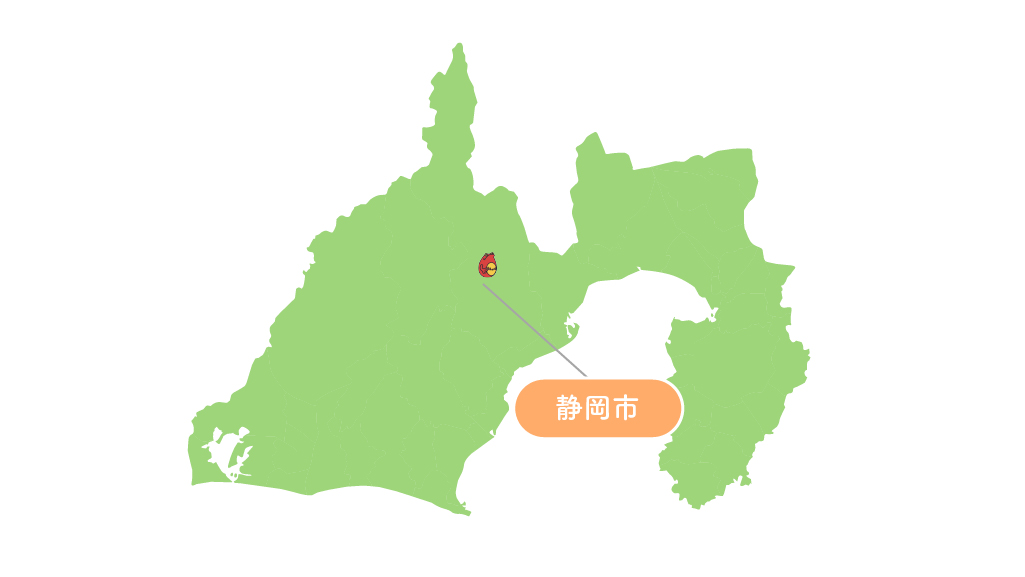
主要製造地域
駿河竹千筋細工の主な産地は、静岡県静岡市を中心とする駿河地方です。ここは古来より良質なマダケやモウソウチクの産地として知られ、竹資源に恵まれた土地柄が工芸の土壌を育みました。
江戸時代に東海道五十三次の宿場町として静岡が栄えたことが重要です。参勤交代の大名行列や旅人が頻繁に往来する中で、土産物や贈答品として竹細工が重宝され、産業として発展しました。また、地元では下級武士や町人が手内職として竹細工を行っており、身分を問わず生活の一部に竹工芸が根付いていました。
文化的観点では、静岡は茶の名産地としても知られ、茶道具や花器など、雅な道具類の需要が高く、竹工芸はその延長線上で発展していきました。さらに、明治・大正期には芸術的価値が評価され、美術工芸品としての地位も確立。近年ではデザイン性を生かした現代インテリアとしても見直されています。
気候的観点では、温暖で湿潤な気候により竹がよく育ち、冬場の乾燥した季節は竹の伐採・乾燥にも適しており、素材管理の面でも有利な環境です。海からの風が山に当たることで気流が生まれ、竹林の成長を促進する自然環境が整っています。
こうした地理・歴史・文化・気候が複合的に重なり合い、駿河独自の“千筋”という細工美を持つ竹工芸が静かに磨かれ、今日まで継承されてきたのです。
駿河竹千筋細工の歴史
旅人の土産から芸術へと昇華した竹の細工美
駿河竹千筋細工の歴史は、江戸時代末期に始まり、各時代の社会・文化とともに形を変えながら発展してきました。
- 1840年頃(天保年間):岡崎藩の武士・菅沼一我が静岡滞在中、宿の息子・清水猪兵衛に丸ひご技法を伝授。これが駿河竹千筋細工の起源とされる。
- 1850年代(安政年間):清水猪兵衛が門弟を育て、虫籠や花器などの精緻な細工を制作。旅人向けの土産として人気を集める。
- 1870年代(明治初期):文明開化の波とともに、芸術的な竹工芸として都市部の知識層に評価され始める。
- 1890年代(明治中期):商家や茶人の間で花器や煙草盆などの室内装飾としての需要が高まり、多品種化が進む。
- 1930年代(昭和初期):展示会出品などにより、工芸品としての評価が確立。一部の作品は東京や京都の美術館に収蔵される。
- 1976年(昭和51年):駿河竹千筋細工が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
- 現代:照明・現代インテリアなどの分野で再評価。若手デザイナーとのコラボや体験教室、海外展示などを通じて、新たな需要層を開拓中。
駿河竹千筋細工の特徴
丸ひごが描く静寂の美、光と影の交響
駿河竹千筋細工の魅力は、何と言ってもその繊細な丸ひご使いにあります。他産地の竹細工が平らな「平ひご」を使うのに対し、駿河では丸く削り出した「丸ひご」を用いるのが最大の特徴です。この丸ひごを一本一本、枠に開けられた穴に手で通して組み上げることで、まるで織物のような均整の取れた造形美が生まれます。光を受けることで、ひごの隙間から繊細な陰影模様が浮かび上がり、時間帯や照明によって異なる表情を見せてくれるのも魅力のひとつです。とくに夕刻にやさしい光が差し込むと、空間全体に詩的な影が映し出され、まるで“影を飾る工芸”とも言える趣が生まれます。
また、使用する竹は、皮に近い“外皮層”のみを使用しており、硬く強靭でしなやかさもある部分だけを活用する贅沢な構造。これが美しさと強度を両立させる理由でもあります。
現代では、風鈴、照明器具、アクセサリー、インテリアパネルなどにも応用されており、伝統とモダンが融合した“空間を彩る竹のアート”として新たな展開を見せています。

駿河竹千筋細工の材料と道具
竹の声を聴き、千の線に整える職人技
駿河竹千筋細工の制作には、自然素材である竹を細やかに加工するための高度な目利きと専用工具が用いられます。一本の竹が“千の線”に生まれ変わるまで、手仕事の積み重ねが必要です。
駿河竹千筋細工の主な材料類
- マダケ:主材。節が長く、加工しやすく美しい。
- モウソウチク:太く強靭で、特に大型作品に用いられる。
- 接着剤(にかわ等):伝統的なものから現代的接着剤まで用途に応じて使い分け。
駿河竹千筋細工の主な道具類
- なた・小刀:竹を割り、皮をへいでひご素材にするための基本工具。
- せん台:竹の厚さを一定に整えるための削り道具。
- ひご引き板:異なる穴サイズを持ち、丸ひごを成形するための鉄板。
- 胴乱(どうらん):加熱して竹を曲げ、輪を作る際に使う金属筒。
- ボール盤:枠に正確な穴をあけるための機械工具。
自然素材と向き合いながら、繊維のような美を生み出す道具たちが、駿河竹千筋細工の精緻な造形を支えています。
駿河竹千筋細工の製作工程
一本の竹が千の線になるまでの美の軌跡
駿河竹千筋細工の製作工程は、大きく10段階以上に分かれ、いずれも手作業による緻密な作業が求められます。
- 伐採
冬季にマダケやモウソウチクを採取し、一定の長さに切断。 - 油抜き・乾燥
湯煮によって油分を除去し、1ヶ月以上天日干し。 - 割り・へぎ・厚み決め
竹を縦に割り、皮に近い部分を選定。せん台で厚みを調整。 - 小割入れ・くじき
細かい切り込みを入れ、それをもとにひご状に割いていく。 - 先づけ・ひごびき
尖らせた竹材を荒・中・仕上げの順で鉄板に通し、滑らかな丸ひごに整形。 - 墨つけ・目盛り入れ
枠材に印をつけ、ひごの挿し込み位置を指定。 - 輪づくり・継ぎ手切り・つなぎ
胴乱で熱曲げし、接合部を切って接着。 - 枠穴あけ
ボール盤で正確に穴あけを行う。 - 組み立て
数百本の丸ひごを手で一本ずつ挿入・調整して仕上げる。
こうして完成した作品は、透かし細工のような軽やかさと構造体としての強度を兼ね備え、光と空気が宿る“静かな芸術品”となります。
駿河竹千筋細工は、静岡の自然と東海道文化が育んだ日本独自の竹工芸です。丸ひごによる精緻な構造と光が織りなす陰影の美は、工芸品の枠を超えた空間芸術としての価値を持ちます。一筋の竹が千の美を放つ。その静謐な手仕事は、今も職人の手によって丁寧に紡がれ続けています。