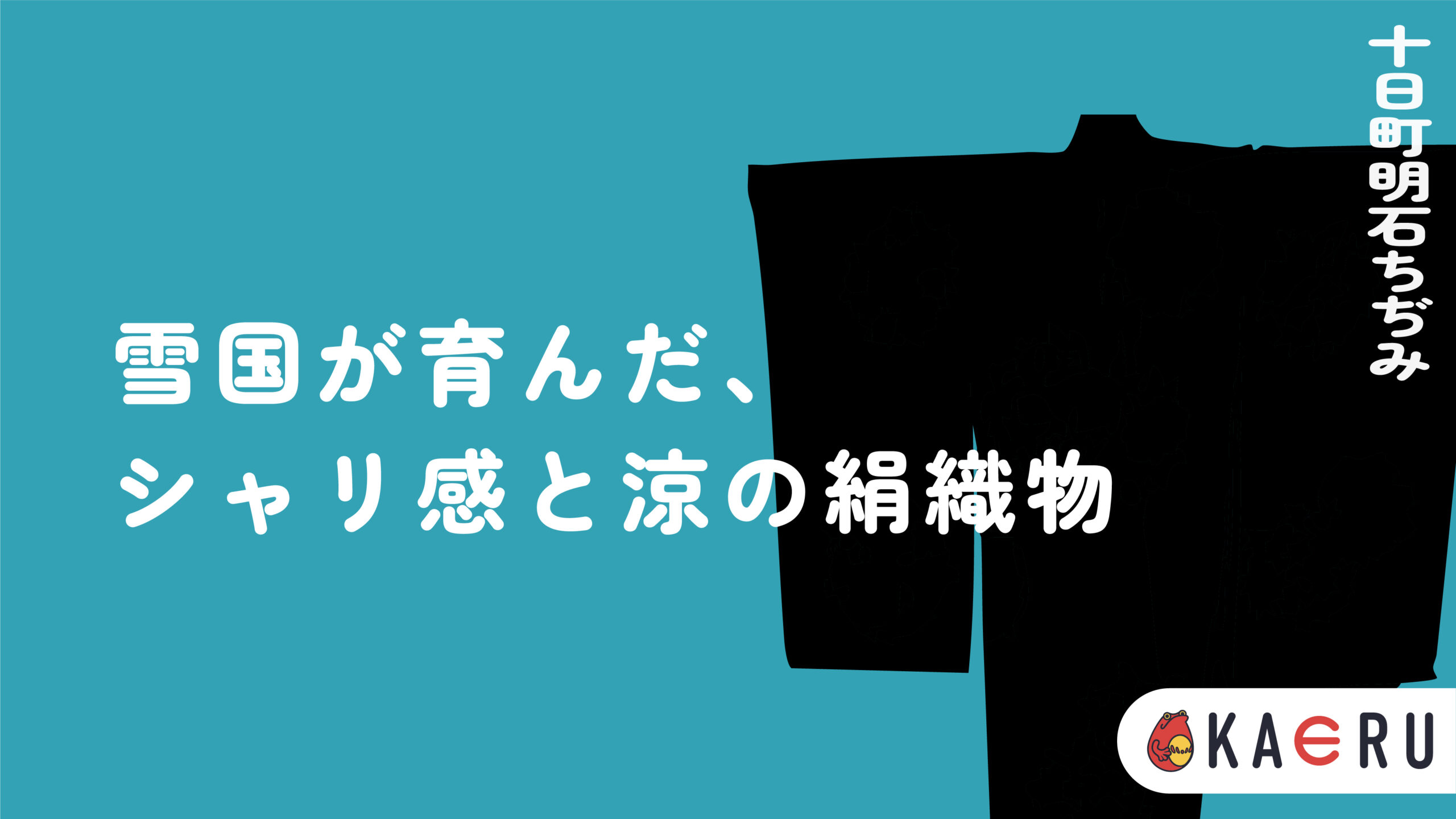十日町明石ちぢみとは?
十日町明石ちぢみ(とおかまちあかしちぢみ)は、新潟県十日町市で生産される伝統的な絹織物で、夏向けの高級着尺として知られています。19世紀初頭、麻織物「越後縮(えちごちぢみ)」の技法を絹に応用し、軽やかな透綾織(すきやおり)として生まれました。
緯糸に強撚糸(きょうねんし)を使い、仕上げに湯もみ加工を施すことで、シャリっとした張りと独特の「しぼ」が生まれます。この薄地で肌離れの良い質感は、蒸し暑い日本の夏に最適な織物として、多くの人々に親しまれています。
| 品目名 | 十日町明石ちぢみ(とおかまちあかしちぢみ) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1982(昭和57)年11月1日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 6(9)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、十日町絣、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

十日町明石ちぢみの産地
歴史と風土が織りなす、夏織物のふるさと・十日町

主要製造地域
十日町明石ちぢみの産地である新潟県十日町市は、豪雪地帯として知られ、冬には3メートルを超える積雪があります。この雪が春に豊かな雪解け水をもたらし、湿潤な気候は織物に適した環境を生み出します。空気中の適度な湿度は、絹糸の扱いや染色にとって非常に好条件であり、発色や仕上がりに繊細な違いをもたらします。
歴史的には、江戸時代から麻織物の産地として発展し、特に越後縮は全国的に名声を博しました。この伝統が絹織物に受け継がれた結果、十日町では明石ちぢみや十日町絣などの多彩な織物が発展。現在では、絣や友禅、無地染めなどと並んで、地域の代表的な工芸品となっています。
十日町明石ちぢみの歴史
越後縮の革新から生まれた、夏の絹織物
十日町明石ちぢみの歴史は、麻織物「越後縮」の技術を母体とし、それを絹に応用することで誕生した革新的な絹織物の系譜に連なります。
- 8世紀(奈良時代):越後地域で麻布が生産され、布文化の礎が築かれる。
- 13世紀(鎌倉時代):幕府や寺院に麻布が献納されるなど、産地としての地位が高まる。
- 17世紀〜(江戸時代):十日町で越後縮の生産が本格化。雪晒し・湯もみによる独自の加工法が確立。
- 1804〜1818年(文化年間):越後縮の技術を絹に応用し、透綾織による絹ちぢみの生産が始まる。
- 明治時代:意匠と染色の改良が進み、「明石ちぢみ」として全国的に評価される。
- 昭和30年代:新たな図案開発や機械化の導入により生産拡大。夏着物の定番として定着。
- 1982年(昭和57年):十日町明石ちぢみが経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
十日町明石ちぢみの特徴
涼感、軽さ、肌離れ、夏のための機能美が集結
十日町明石ちぢみの最大の魅力は、何といってもその涼やかな着心地と、視覚的にも感じられる軽やかさにあります。織物の内部に仕組まれた秘密の一つが、緯糸(よこいと)に使われる「強撚糸(きょうねんし)」です。これは、糸に通常よりも強く撚りをかけることで、織り上げた布地にシャリっとした独特の張りを持たせる技法で、これによって通気性と軽さが格段に向上します。
織り上がった反物には、さらに「湯もみ」と呼ばれる工程が施されます。高温の湯に反物を浸しながら揉むことで、布地表面に細かな凹凸が現れ、これが「しぼ」と呼ばれる質感を生み出します。このしぼは肌との接地面を減らして蒸れを防ぎ、汗ばむ夏でも快適に過ごせる工夫となっています。見た目にも波のような陰影が生まれ、視覚的な清涼感を演出してくれるのです。
模様には、細かな縞や格子が多く取り入れられ、色調も淡い藍や白、鼠色などが中心で、すっきりとした上品な印象を与えます。実用性と美しさが絶妙に調和したデザインは、盛夏の装いとして長く愛され続けてきました。

十日町明石ちぢみの材料と道具
撚糸と湯もみが紡ぐ、涼の伝統素材
十日町明石ちぢみの織りに使われる素材や道具には、長年の経験に裏打ちされた職人の目利きと、雪国ならではの知恵が息づいています。絹本来の美しさを引き出すために、一つひとつの工程に合った素材を選び、最適な道具を使い分けられています。
十日町明石ちぢみの主な材料類
- 生糸(絹糸):繊細な撚りや染色に耐えられる高品質な絹。
- 強撚糸:緯糸に使用され、シャリ感としぼをつくる要。
- 草木染原料:藍やヤマモモなどを用い、淡く透明感のある染色に用いられることも。
十日町明石ちぢみの主な道具類
- 高機(たかばた):図案ごとの正確な織り上げを行う大型の織機。
- 撚糸機:糸に適度な撚りを与える機械。
- 湯もみ道具:熱湯で反物をもみほぐし、しぼを形成するための桶や木槌など。
素材と道具の絶妙な組み合わせが、明石ちぢみ独特の質感を実現しています。
十日町明石ちぢみの製作工程
撚りと熱が生む、肌に涼しい美のプロセス
十日町明石ちぢみは、ひとつひとつの工程に職人の繊細な手仕事が込められ、いくつもの段階を経てようやく完成します。すべての工程が明石ちぢみ特有のしぼや涼感を生み出すために欠かせない役割を果たしています。
- 絹糸準備
生糸を経糸・緯糸用に選別・整理し、染色の準備をする。 - 撚糸加工
緯糸に強い撚りをかけ、シャリ感としぼのもととなる強撚糸を作る。 - 整経・製織
設計図に従い経糸と緯糸を整え、織機で織り上げる。模様に応じて縞や格子などを織る。 - 湯もみ加工
織り上がった反物を熱湯で揉み、「しぼ」を形成。力加減に熟練が必要。 - 天日干し・乾燥
自然光と風を利用しながら、反物の風合いを仕上げる。 - 検品・仕上げ
長さ・幅・しぼの均一性・染めの発色などを入念に確認し、製品として整える。
十日町明石ちぢみは、単なる工程の積み重ねではなく、一反一反に込められた「涼を織る」という思想の結晶です。