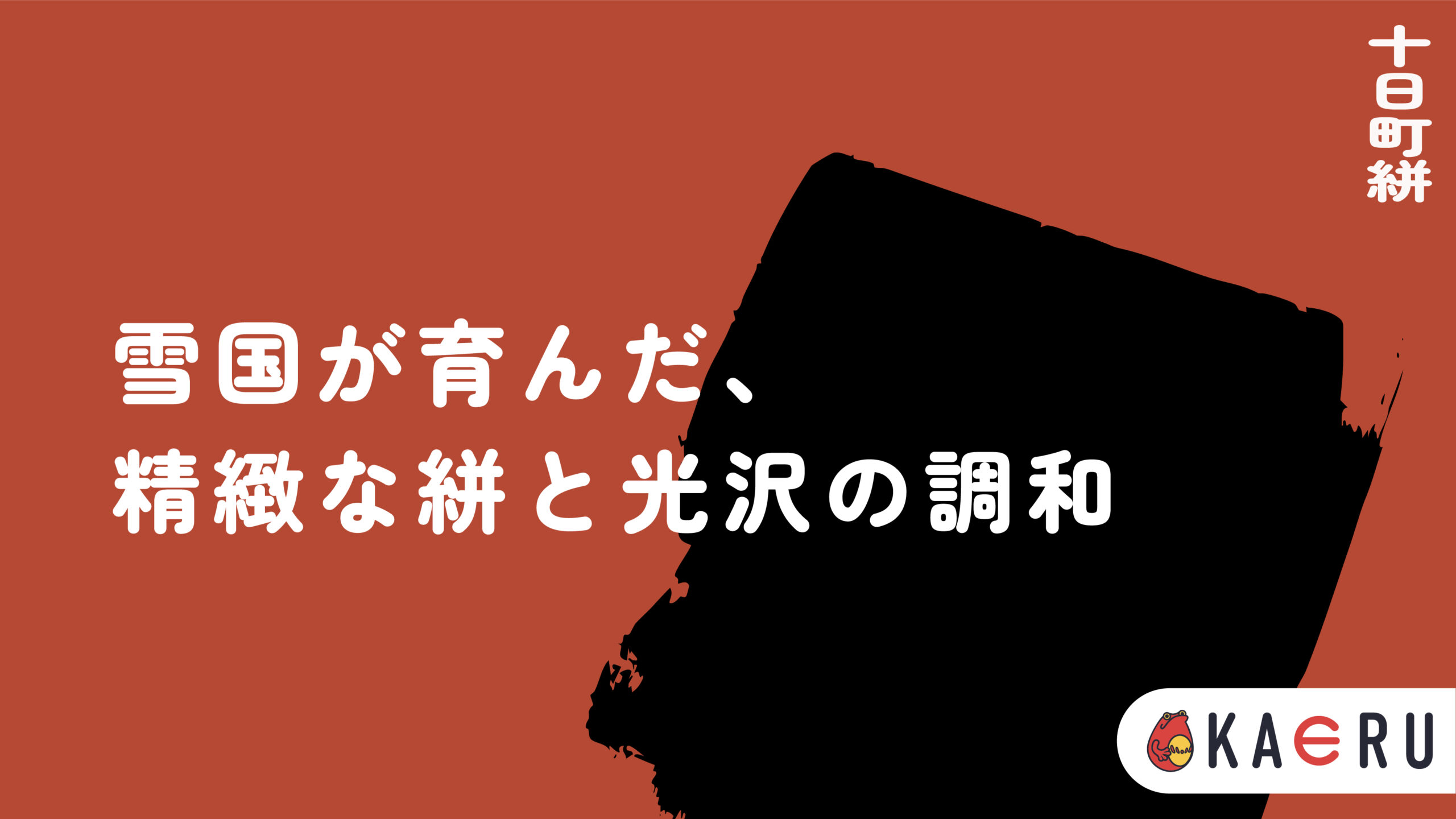十日町絣とは?
十日町絣(とおかまちかすり)は、新潟県十日町市および津南町を主産地とする伝統的な絹織物です。かつてこの地域に根づいていた麻織物「越後縮(えちごちぢみ)」の技術をもとに、19世紀中頃に絹素材での絣織物として誕生しました。
最大の特徴は、縦絣と横絣を組み合わせて表現される精緻な文様。先染めで染め分けた糸を織ることで、繊細で奥行きのある模様が生まれ、絹ならではの光沢とあいまって落ち着いた品格をまといます。現在では「十日町絣」「十日町明石ちぢみ」などの先染め織物に加え、「十日町友禅」に代表される後染め着物も生産されており、全国有数の“きもの総合産地”として発展を続けています。
| 品目名 | 十日町絣(とおかまちかすり) |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 分類 | 織物 |
| 指定年月日 | 1982(昭和57)年11月1日 |
| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 8(48)名 |
| その他の新潟県の伝統的工芸品 | 新潟漆器、塩沢紬、小千谷縮、小千谷紬、村上木彫堆朱、燕鎚起銅器、越後三条打刃物、越後与板打刃物、本塩沢、十日町明石ちぢみ、羽越しな布、三条仏壇、加茂桐箪笥、新潟・白根仏壇、長岡仏壇、佐渡無名異焼(全17品目) |

十日町絣の産地
雪国の知恵と文化が息づく、きもののまち・十日町

主要製造地域
新潟県十日町市と津南町は、日本有数の豪雪地帯として知られ、冬には2〜3メートルの積雪がある地域です。この豊富な雪がもたらす雪解け水と、冬季の安定した湿度は、染織にとって理想的な自然環境を生み出し、古くから織物産地として発展してきました。
とりわけ江戸時代には、農閑期の手内職として越後縮や麻織物が盛んに織られ、各家庭に機織り文化が根づいていました。さらに十日町は北国街道と三国街道の交差点に位置し、江戸と越後を結ぶ交通の要衝として機能していたことから、物資と情報の流通が活発で、織物技術や意匠が他地域からも流入しやすい土壌がありました。
明治以降は絹糸の導入と技術革新が進み、越後縮の技法を応用した絣織物が生産されるようになります。昭和に入ると十日町は地域独自の工場一貫体制を構築し、友禅染をはじめとする後染め製品の大量生産も可能に。先染めの十日町絣と後染めの十日町友禅という異なる技法が共存・発展するまちとして、全国有数の「きもの総合産地」としての地位を築きました。
十日町絣の歴史
越後縮の流れをくむ絣織物の誕生と発展
十日町絣は、古代から続く越後の織物文化を背景に、麻から絹への素材転換と技術継承の中で生まれました。
- 8世紀頃(奈良時代):越後地域で麻布の生産が行われ、朝廷への貢納布として納められる。
- 9〜12世紀(平安時代):麻織物が衣料として広く普及。越後は良質な麻織物の産地として知られるようになる。
- 17〜19世紀(江戸時代):農閑期に家庭内で越後縮の生産が盛んになる。織物技術が地域に定着し、絣模様の下地が形成される。
- 19世紀中頃(幕末):越後縮の技術を絹素材に応用し、十日町絣が誕生。先染めによる精緻な絣模様が特色となる。
- 1868〜1912年(明治時代):品質改良と市場流通が進み、十日町絣が新潟県内外へ出荷されるように。
- 1912〜1926年(大正時代):紬や縮の高級品化が進み、美術工芸品としての価値が高まる。
- 1960年代(昭和30年代後半):友禅染の導入により後染め商品が登場。産地独自の工場一貫生産体制が整う。
- 1982年(昭和57年):十日町絣が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。
十日町絣の特徴
絣文様の妙と絹の光沢が織りなす、十日町ならではの上品な着物地
十日町絣の最大の魅力は、縦糸と横糸の両方に模様を施す「縦絣」「横絣」の技法によって、布全体に緻密で表情豊かな柄を表現できる点にあります。特に、十字絣や亀甲絣のような伝統的な幾何文様から、自然の風景や草花をモチーフにした写実的な絣柄まで、意匠の幅広さが特徴です。こうした模様は、糸の段階で防染と染色を行い、織り上げたときに模様がぴたりと揃うよう精密に設計されており、熟練の職人技があってこそ成り立ちます。
さらに、絹素材ならではの光沢とやわらかさが、絣模様に奥行きを与え、着物全体に気品ある美しさをもたらします。なかでも、織りの揺らぎが生み出す“かすれ”や“にじみ”の風合いは、十日町絣ならではのあたたかみとして、多くの着物愛好家から高く評価されています。
また、通気性と軽やかさを兼ね備えた着心地の良さも特筆すべき点です。越後縮の技法を受け継いだ織り構造によって、単衣や夏物としても快適に着用できるため、実用性と美しさを両立する織物として親しまれています。

十日町絣の材料と道具
先染め絣の技を支える、自然素材と伝統の道具
十日町絣の織りに使われる材料と道具は、すべてが自然と手仕事に根ざしたものです。繊細な文様を表現するために、染色や防染、織りにおいて高精度が求められます。
十日町絣の主な材料類
- 生糸(絹糸):光沢としなやかさを持つ、織物の主素材
- 草木染原料:藍、ログウッド、栗などの植物染料を使用することもある
- 防染糸:絣括りの際に模様部分を守るために用いられる
十日町絣の主な道具類
- 絣括り器具:模様に応じて糸を縛るための専用道具
- 整経台:糸を織機にかける前に長さ・順序を整えるための台
- 手織機:一反ずつ丁寧に模様を合わせながら織るための伝統的な織機
- 筬(おさ)・綜絖(そうこう):糸の密度や柄の配置を制御する機構部品
どの工程にも、職人の経験と緻密な作業が求められ、長年培われた技術と道具の連携が、絣の美を支えています。
十日町絣の製作工程
計算と感性が織り成す、十日町絣の繊細な製作工程
十日町絣の製作工程は、糸づくりから織りまで複雑かつ精緻。特に模様の設計と再現には、高度な知識と職人技が必要とされます。
- 製糸・糸準備
蚕から生糸を取り出し、染色に適した糸を選定 - 絣括り
模様設計図に基づいて、糸の模様部分を防染 - 染色
草木や合成染料で糸を染め分け、模様の色を表現 - 整経・織機準備
染めた糸を順序通り整え、織機にかける - 手織り
絣模様が揃うよう慎重に織り進め、一反の布に仕上げる - 仕上げ加工
湯通しや湯のしで、光沢と風合いを整える
これらの工程を経て完成した十日町絣は、見た目の美しさだけでなく、着る人の身体に寄り添う優しさを備えた、雪国の知恵と技術の結晶です。